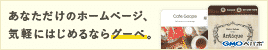教行証文類(全)下
2019/02/14[4−16]
親鸞さんはここまでに、「真仏土」は「光明」で具体的には「智慧」で、その智慧の徳がこの「涅槃の徳」で、「涅槃の徳」は「遍満してる」から「涅槃の徳」から「如来が垂迹(従果向因)」して利他を行じる「菩薩」になって現れるっていうのを「法蔵菩薩」に推定定義して、「法蔵菩薩」の「五念門五果門」を行じれば「利他」の「薗林遊戯地門」になりますねん。
っていう流れで、「真仏土の内容」をどんどん具体的定義して論を進めてきはりました。って、
前回書きましたけど、続いて。。ここで。。
348ページの【16】に、迦葉菩薩が釈尊に尋ねるところから始まりますねんけど、
これは、343ページに「迦葉菩薩」が「涅槃と仏性と決定と如来が同じ意味で異なる表現なら、どうしてわざわざ三帰依するのか?」って尋ねてるところを「涅槃の徳」を挟んで続くかたちで、
《迦葉菩薩の問い》がここでまた起こされているようです。
前回につづいて、「迦葉菩薩」は、釈尊に「世尊さま、仏性は常住で虚空のようであるというてはったのに、なんで如来はこれらを《未来のこと》として説いてますのん?」って尋ねてはります。
また、仏道を求める気持ちがない「一闡提(いっせんだい)」のものは「善法」がないっていうけど、
同学や同師。。なんかに「愛心が起こらないっていははりますのん?」「もし一闡提でもそういう人々に対して愛心が起これば、それは「善」っていうてええんと違いますのん?」って。。
①「涅槃と仏性と決定と如来が同じ意味で異なる表現」って言うてはった以上、「衆生が菩薩の行を行じるまでもなく、すでにそのまま仏性である」って言うてもいいんと違いますか?
②「一闡提にも善はあるんやないですか?」
っていうことを尋ねてはりますねんけど。
これについて「仏(世尊)は、いい質問ですねぇ」って感じで答えはります。
「仏性は虚空のようなもので、過去でも、未来でも、現在でもないんです」
「それは、一切衆生には、過去と未来と現在の三種の身があるんだけど、未来に荘厳清浄の身を得て、仏性を見ることになるでしょう。」
「だから、仏性未来っていったんです。」って答えてはります。
ここでポイントにすべきは、ここの時間軸が「大経」の「過去、未来、現在」と同じなってることです。
この時間軸は、「現在」は「過去法と未来法の間の刹那(接点)」にあって、「現在法っていうのは、現実的には存在しないってことです」これは「刹那滅前提」ですから「過去法と未来法」しか存在を規定できません。
「いま」っていうた瞬間「いま」が過去になるんです。
つまり、迦葉菩薩は多分「このことがわかっていなかった」んでしょう。
だから、ここで「因果論」について説明しはります。
「因から果」に向けて説く時と、「果が決定してる時は、果から説く時がある」っていうてて、
「命という果が食という因」によって成り立ってるというてみたり、「存在っていう果を触っていう因」でいうてみたりするんです。
だからこのケースもこれと同じで「未来に必ず「浄」の身を得る」から「仏性」っていうてるんです。
迦葉菩薩さんはここでさらに突っ込みます。
「いうてはることはわかりますねんけど、そしたらなんでいまから《一切衆生悉有仏性》っていいますのん?」っていうてはります。
世尊は懲りずに「一切衆生悉有仏性っていうたのは、《衆生に仏性が見えてない》から「無い」ように思うかも知れへんけど、《虚空》のような状態の性質は「無」のように思えても、現在、虚空の中に居るんだから「無い」とは言えへんでしょ。」
「一切衆生自体は《無常》の《状態変化の中に居る》けれど、その存在はどう変化しようとも《仏性は変化しない》だから、《衆生の仏性は衆生の内にあるとも外にあるとも言えへん》から虚空のようなものである」って説いてるんです」って。。
☆これは、「一切衆生が変化すること自体が仏性」ってことです。
☆「無常は常住である」という「常」でいえば、「一切衆生」は無常にあるってことが見えて、この真実を受け入れた時に「無常の《常》っていう仏性が見える」ってことやっていえます。
その上「内外は虚空のようだ」というても、「内と外」は「一」とも「常」とも言い難いんです。
「衆生の体内か体外に仏性があるか?」っていうても、どちらでも無い、「無常の法の《常》(無常の法は変化しない)」っていうことを仏性っていうてるんですから、「内外」という問題やないんです!
だから「内外」でいうたら「一切処有(一切衆生悉有)」とも言いにくいってなるんです。
しかし、「虚空っていう点で言えば、もろもろの衆生は虚空に包摂されているから、一切衆生にあるっていえるように、衆生の仏性もこのようなことなんです。」「だから先ほど《衆生の仏性は内でも外でも無い(非内非外)で、虚空のようである」っていうたんですよって回答されています。
まぁ結果「果」からいえば仏性があり、「因」でいうと見えて無いから「仏性未来」っていうたんですけど、「衆生の仏性は虚空のようにある」ってことです。
って結論を回答してはります。
ほんでね、「一闡提」についてはね、「一闡提」は「因果に従わず、仏を求めない」から「何をしても思っても」「邪業」ってしかいえへんから、「訶梨勒(かりろく)」っていう果樹のように「あらゆる部分が苦い」ようなものなんです。
つまりは「一闡提」は何をしても、思ってても「苦いことにしかならない」ってことなんです。
って、ここの問答は、「一切衆生悉有仏性」について説かれていて、これを引き出していくのが「利他」「薗林遊戯地門」だっていうてると確定できて。。
真仏土の「光明の智慧」は「如来が従果向因」して「法蔵菩薩」になり、私たちが「法蔵菩薩のように五念門を行じる菩薩」になれば、「仏性の身」になるってことを論じてはります。
続いて【17】には、「如来は衆生の諸根力を知る能力がある(知諸根力)」から、「どの衆生をどのように導けばいいか、よくわかってはるんです」だから「一切衆生」を「その衆生の状態に応じてさとりに導くんです」っていう内容につづきます。
つまり「真仏土」は、光明→智慧→涅槃の徳→如来→菩薩(法蔵)→利他(薗林遊戯地門)→一切衆生悉有仏性→如来は衆生の諸根力を知って導く。
っていう論の流れになっていて、これは全て「真実則」です。
2019/02/16[4−17]
「如来は、衆生の状態を正確に知ることができる」
この場合の「如来」は「釈迦を含めて」というよりも、直接的には「釈迦」のことで、
いわゆる「対機説法」「応病与薬」ってことで、「相手の状態を正確に知って、的確な薬を与える」っていうことです。350ページの【17】には、そのことが書いてあるんです。
「ある衆生のレベルが、上か、中か、下か」を知って。。
「下から上に登っていくものもあれば、下がっていくものもいる」
私たち「衆生」は、そのように「もともと不安定、不確定な存在である」ってことをいっています。
このように「不安定、不確定だから」いったん「善根を断じてしまうこと」があっても「再度善根が戻るものもある」っていう「不安定、不確定だからこそ」「下に落ちても上がれる可能性」「回復の見込み」があるってことです。
「もし」私たち衆生の「根性(本質的性質)」が「安定的に決定、確定している」なら、「善根が失われたら、二度と戻らない」ってことになるでしょう。
もし衆生の「根性」が「決定、確定的」なら「一闡提」(仏法を謗るもの)が、「地獄に堕ちて寿命が一劫(むちゃくちゃ長い間)である」ということもないでしょう。
つまり「一劫」すれば、「戻る可能性がある」ってことなんですから。。
だから、「如来は、一切の法には《定相》(定まって変化しないこと)はない」(衆生を含めて「無常」)だって説いてるんですよ。
って迦葉菩薩に「仏が説いたところで。。」迦葉菩薩が「質問」します。
☆ここが「おもしろいところ」です。(仏教がいかに世俗の価値と異なるかってことが明確です)
「世尊さん、そういうことを如来であるあなたがわかってて、なんで善星(釈迦の息子で”ラゴラ”ともいう)を出家させたんですか?」
☆ここには、興味深く深い話があるんです❗️
『釈迦が息子と嫁を捨てて出家して、のちに息子も嫁も”釈迦の弟子”になったのですが、この”息子”は、出家して《よこしまな心を起こして生きながら地獄に堕ちた》ってことなんです。』
《こういうことになりそうな「息子さん」を「なんで出家させたのか?」っていう質問です。》
これに対して「釈迦世尊は。。」「私(釈迦)が出家」して、「弟の難陀や、いとこの阿難や提婆達多(この人は阿闍世をそそのかして、父王を殺させるという大問題を犯した人)たちも出家しました。」
「そして息子の羅睺羅(ラゴラ)達も、みんな出家をしてちゃんと修行したんだけど、なんでそもそも息子の出家を許したかっていうと。。」
「釈迦族の王位を継ぐべき私が出家したら、次には息子が王位を継ぐでしょう。」
「そうなるとね。。息子が権力を持って、仏教を破壊する可能性があったからなんよ」
「とはいえ、息子が地獄に堕ちても、出家してからのことだし、出家してなかったら、マジマジ《善根を断って》もっとひどい状態になっていたかもしれません。
しかし《出家》している以上、戒律を守って、色々と供養や修行してきたから、とりあえず息子には《善因》が備わっているはずなので、いつかは《善法》を生むでしょう。
そうすればまた仏道を歩むようになる可能性は高くなるから出家させたんです。」
「もし私が、こういうことを見抜き考えていなければ、私は《如来具足十力》(十力は如来が衆生を救う十の力)と自称することはできません。」
(十力→Wiki https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E5%8A%9B)
「だから迦葉菩薩(善男子)さん。。《如来はよく衆生の、上中下の根を知る》から《具知根力》(明確に相手の性質を知る)とも称するんです。」
って、世尊が迦葉菩薩に回答したところで、また迦葉菩薩さんが「釈迦」に口をはさみます。
「世尊さん、如来はそういう知根力を持っていて、一切衆生の上中下の性質を知って、賢い劣ってるってこともわかり、《ひと、意(こころ)、時》を適切に見て、その適正にしたがっているから《如来知諸根力》って名づけるんですね。」
「だから《四重禁戒を犯したものも、五逆罪のものも、一闡提のものも》みんな《仏性がある》っていうてはるんですね❗️」って。。
ほんでここからはいちいち解説しませんけど、大まかにいうと。。
「如来は、いろんな国土(世界)、言語、人、衆根(それぞれの性質)のために。。」
「一つの《名》をいろんな《名》で表現したり、一つの意味(義)をいろんな名を使って表現します」
っていうこの辺からは、「如来がそれほどいろんな人の性質に応じて適切に判断して教えを説いているか」っていうことと、「説いている中身」が列挙されているので、「じっくり読み」してみてください。
☆そしてこの辺で明確なのは「さとらせる対象が”人”」になっていることです!
そしてここの結論は、「この講義で《真諦、俗諦》といってきたことを、《第一義諦と世俗諦》と表現して、「さとりを《衆生の性質》によって、いろんな言語表現で説いていることを明確にしてはります。」
なんでこんなにまたまためんどくさい細かいことを書いてはるのかっていう理由を先に言うと。。
「こういうことを通して親鸞さんがいいたいことは」。。
「真仏土文類」は、この先に書かれている【24】の
「正道の大慈悲は《出世の善根》から生まれて《荘厳功徳成就》って名づけられて、これは《法性にそむかず》→華厳経《宝王如来の性起》と同じように《法蔵菩薩の物語と四十八願》に説かれている」というところから。。
「真実則から方便則への転換」(→)を明確にしています。
そういうポイントから。。
☆☆☆
なぜ「法蔵菩薩の本願の教えで、荘厳功徳の教えで、阿弥陀如来の教え」なのかっていう理由を言うてはります。
そして、この論の流れは「真実則から【32】の方便則」っていう方向に向けて論じらていて、
【34】で「仏にしたがって《自然に帰す》」「無為法性身を証明して得る(さとりに入る)」っていう《真実則》でいう「究極目的」を明確にしてます。
結果【36】から終わりまでは「真の仏土」は、いずれも冒頭の「光明」であり「諸智土(あらゆる智慧の場)」であると定義して、それは「自然虚無之身無極之体」(真実則)で→かつ「如来浄華衆 正覚華化生」(方便則)と定義しています。
究極「真仏土文類」は「真実則(無常無我、空、法界縁起などの無為法)」から「方便則の阿弥陀仏の教え」が出てくるっていう「無碍光如来」から「阿弥陀如来」へというプロセスを明確にして、
「阿弥陀如来」という「方便則」の《出どころ》を明確にしてるってことと。。
「《衆生の性質を知る》から、《一切衆生》を《智慧の光明界(さとり)》に導く教えの《究極である》《善巧方便》は阿弥陀如来の教え」やっていうてはるんですねん❣️
☆☆☆
とりあえず、なぜ先のような[めんどくさいやりとり]が「迦葉菩薩」と「世尊」の間でされていて、そのあとの「チョーめんどくさい内容」で親鸞さんは結局「何を言わんとしてるのか」ってことを、まずいったんご理解いただくために。。
「ざっくり」「真仏土文類」のラストまでまとめましたが、次からも「真仏土文類」から、順次「重要な部分」を取り上げていきます。
2019/02/20[4−18]
さて、354ページの【18】の手前までに「如来世尊」の「教説」は「さとりをいろんな言説化(教えに)してあきらかにしていること」を書き綴って、そのラストに「真実の第一義諦」を説くことを「世諦」っていうって定義してますが、これはこの講義で「真諦」と「俗諦」っていうてることと同じです。
そして「世諦の法を説いて第一義諦とする」って書いてて、結果「いろんな言説(教え)があるけど全て《さとりへの誘導》言語化(ことばにする)」であるということを結論にしています。
【18】では、「第一義諦→道→菩提→涅槃」って書いてて、この「菩提の道を進むことが涅槃の楽への《菩薩道》です」って落とし込まれています。
つづいて【19】では、この「色も形もなくことばも絶えた第一義諦」を「言説」で「如来」などの《人格化表現》してる「善巧方便則化」の解釈について説明してます。
これは「法身」として「人格化展開」している「方便則の阿弥陀ストーリー」について、「身の理解」と、それは「真実が根本である」ってことを明確にするために、「法身論」を単純化して書いてはるんです。
そこで、法身について「生身」と「法身」に分けて、「生身」は「ほぼ釈尊」のことをいうてます。
だから「有為法」(縁起による仮の存在)やって書いてるんです。
そして「法身」を「常楽我浄の涅槃徳」っていうてて、「涅槃の徳」で書いてた「変わらない真理」に定義して、仏(釈尊)が世に出ようと出まいと変わらない「無為法」(さとりそのもの)って定義してます。
ほんでこれが「有為法の生身法身(釈尊)」の根本でもあることをサゼッションしてて、「釈尊を含むすべての法身」は「涅槃徳の無為法身」ですねんっていうてはります。
この部分でなぜ「無為法の法身」を論じてるのか「真仏土」の論の流れで見直すと。。
真仏土→光明→智慧→涅槃の徳→如来→菩薩(法蔵)→利他(薗林遊戯地門)→一切衆生悉有仏性→如来は衆生の諸根力を知って導く→第一義諦って論じてきて。。
ここまでは全て「真実則」で、この【19】の部分は、「釈尊は応身やし有為法の生身」
そして「法身」ていう「方便人格化」は「衆生の諸根力に応じるための言説」だから。。
「ホンマは無為法(さとりそのもの)です」っていうことをいうてはります。
そうなれば「さとりに住してる釈尊という《生身》の本質も法身や」ってことになります。
「善巧方便」も「ホンマは言説無為法」《さとりの言語化》だってことです。
だから。。
真仏土→光明→智慧→涅槃の徳→如来→菩薩(法蔵)→利他(薗林遊戯地門)→一切衆生悉有仏性→如来は衆生の諸根力を知って導く→諸根力に対する「さまざまな言説」→第一義諦→涅槃→「教説上の法身はすべて涅槃徳の無為法」っていう論の流れになっていて、すべてを「真実則」に定義してはるんです。
補足3の105の「高田派の仏壇」に書いた「仏壇の真ん中の絵像」は「方便法身」だけど、その本質は、向かって左の「帰命尽十方無碍光如来、南无不可思議光如来」で、そのことを、この真仏土文類のこの論で明確に説明してはるってことで、向かって右に「親鸞さんの絵像」があるって、「高田派の仏壇の荘厳は《方便則の背景は光明》それを《親鸞さんが教行証文類であきらかにした》っていう教義を背景に《荘厳されてる》ってスゴイ‼️」って感じたんです。。
☆とかく「絵像や仏像を対象物にする」っていうのは「偶像崇拝化」しやすいので、対象物に向かって礼拝するような「自我と仏」を分断しない方が、実際のところ「真実則」になります。
ですから「対象物としてではない《名字名号》」を受け入れて「自我名字と入れ換え」「五体投地礼拝し、讃嘆し。。」って行じること、対象物に対面するのではなく「真如一如」という前提で「具体的に法蔵菩薩の誓願と五念門行」を行じることを「真実則」と前提定義します。
そして、『私の煩悩を見せてくださる阿弥陀如来』に「あぁこれも煩悩でした南无阿弥陀仏」って感じで「自我の愚かさを見せてもらいながら《破我されるプロセス》を生きる」っていうのを、「仏壇の仏像という対象物に対面する形式」で行ないつつ生きることを「方便則」って前提定義してきました。
この「阿弥陀ストーリー」を《無疑の信心》で受け入れて「南无阿弥陀仏の称名」を生きる。
つまりは「《機と法の深信》の中で《阿弥陀如来》に《煩悩自我》を否定されながら《水の河(貪り)と火の河(怒り)》の間の白道を《群族悪獣》の誘惑にも振り向かず進み《破我されていく》プロセス」を「阿弥陀如来」と対面して生きる。
とにかくこのように「阿弥陀ストーリー」っていう「善巧方便」を「対象」にして、その「人格化されてる如来」に自我を任せて生きることを、ここまでに「方便則」って書いてきましたが、この「ストーリー」を生きることも、先に書いた、ストレートに「法蔵菩提の四十八願と讃嘆門中心の五念門行」を行じる「真実則」を歩むことも。
またはどっちも「究極同じである」っていう結論から、「称名一行に四十八願と五念門行を含めて行じ」「仏像を対象物としてではなく」「法蔵菩薩とともに至るゴールであり、真如に五体投地する意味で仏壇の如来に礼拝し、行によって至る果であるって、仏壇の荘厳を通してイメージして行じつつ生きる」《真実則と方便則を合わせて行じること》も。。
いずれにせよ結果「無常無我、空へ至る」中で「法楽を得ていく」のは同じなので、この「人格化した方便ストーリー」さえも「真実の言語化」だから「無為法身」であり「光明」であるってところに結論づけてはるんです。
【20】では、「この真実の言語化がいかにさまざまな諸根力のものに対応した方法であるか」っていうことを「具体的」に書いてはります。
ここの冒頭の「十二部経」っていうのは、「法を説く十二のパターン」のことですが、ここのラストでは、「一法のためのゆえに無量の法を説く」って書いてます。十二のパターンにこだわらないってことです!
とにかく、「真仏土」っていうのは、「光明」であって「さとりへの誘導の功徳」であるってことを、「法を身」であらわしたり「法をさまざまな言語化」で説いているってことを「細かく説明」してはるんです❣️
それほど「無碍光如来」の法は「あらゆる諸根力の者をさとりに誘導する法」であるってことをいうてはって、「法の人格化」である「善巧方便の阿弥陀如来」も「言説無為法」ですって、根拠を明確化してはるんです。
ここで特別重要なのは、「ここまでに《俗諦》と記述した《さとりそのものをストレートに言語化》している部分も、《方便則》と記述してきた《ストーリー部分》も、どっちも【さとりの言語化】だから、その言葉や表現そのものにとらわれると結果【自我行】(自性唯心)になるから注意が必要」ってことです。
「浄土は死後の往生です」とか「名号は絶対です」とかいうてると、【つかめないハズの真理をつかもうとすることになる】っていう「誤りに陥る危険がある」んです。
「現世は苦の世界」「来世は常楽の世界」なんていう「虚妄分別、分断思考」「自我行」に陥ってしまいます。
さまざまな言語化が指し示すのはあくまでも「さとりの法楽」→「虫も草木もすべてみんな仏性」って観えるようになっていくことです。
このことが【21】からの内容です❣️
2019/02/24[4−19]
真仏土文類は、
「真仏土→光明→智慧→涅槃の徳→如来→菩薩(法蔵)→利他(薗林遊戯地門)→一切衆生悉有仏性→如来は衆生の諸根力を知って導く→諸根力に対する「さまざまな言説」→第一義諦→涅槃→「教説上の法身はすべて涅槃徳の無為法」っていう風に流れてきています。
真仏土文類の内容を、おおまかに言えば、
☆☆☆
「真実の仏や浄土は《光明》で、それは《智慧》のことで、智慧っていうのは《涅槃の徳》にあらわされていて、《如来》っていうのはそこ(光明→涅槃の徳)から出ています。」って論じて、
「如来は《法蔵菩薩》のストーリーっていう形式で《利他》のためにあらわされた存在です」と定義して、
「その如来(すべての如来)は、《一切の衆生には悉く仏性がある》ということを基本にして、そのことに目覚めさせるための《言葉上の存在》で、人間の諸根力(各個人の能力や状態)に応じて、いろんな表現を駆使して、人間や衆生を《涅槃の徳》に導きます。」
「だから《すべての如来》は《言語上の存在》で無為法です」
って、【如来の本質と目的、そして《人や衆生をさとりに導く方法》】について論じてきています。☆☆☆
355ページの【21】からは、
その仏性に目覚めたもの(一切覚者)を「仏性そのもの」とする。
って定義してて、「十住(菩薩の20階位)の菩薩で、聞見して仏性を見ることができない」って、菩薩五十二位の中、下位から数えて第11番目から第20番目の位をいうてます。
せやから、いくら「菩薩」といってもこのように「仏性」を「聞見」することができないレベルの者もいる。
って書いてるんです。
🔻☆☆☆
ここで脚注には「菩薩の階位」について、本来「涅槃経」では「十住は十地」にあたるって書いてます。
しかしこれは微妙に意図的です。
本来の「十住の菩薩」は、『涅槃経』で菩薩の修行の階次を五十位に分けてて、「第四十一位より五十位」までを「十住」としてるっていうのが本来で、「十住毘婆沙論の華厳経十住品」ならば「十住を十地」としても、これは「階位」を表すということでもないようです。
そもそも「親鸞さん」は「涅槃経の四功徳」の「大我《如来我徳》」を抜いたり。。
「教行証文類」のあちこちに《本来とは違う読み替え》があったりというように、けっこうなイレギュラー部分がありますから、ここも素直に流れのまま「十住菩薩」って読んでいくほうがいいと思われます。
とにかく重要なのは「教行証文類」で論じたい「親鸞さんの意図」または「ここまでに定義されてきたこと」の論の流れによって読むことです。
そういう点でも、ここの「十住」はそのまま「十住と読む方が論がスムーズ」に通ります。
もし、これが「十地」ならば「初地、不退転地」であって、親鸞さんのうえでは、ほぼ「等覚同等」扱いですから、この時点で「仏性が見れない」ということは、「確定的」にありえないともいえます。
🔽🅿️
またまた申し訳ないんですけど、「脚注」は、時によって「本来はこう読むけれど、親鸞聖人はこう読んでいます」って書いてたり、この部分のように「十住は十地」です。「以上!」っていうような注釈の使い分けがあります。これは「とある学派の意図」からの解釈を立てているからだと思われます。
そもそも「龍樹」の「十住毘婆沙論」は「華厳経の十地品」の解釈から「十住を十地」としていますが、これは「阿毘跋致(あびばっち)《初地、不退転地、歓喜地》に至る《信方便の易行》」を論じているので、十住毘婆沙論の「十住」は「十界」ぐらいの意味でタイトルになってます。
そこが「十地毘婆沙論」ではない理由です。
また、この【21】の「十住」を「十地」って解釈すると後で出てくる「九地」の解釈に無理が出てきますから、そのまま「十住の階位」と読んでおくほうが論がスムーズになります。
🔺☆☆☆
だからここはいままでの論の流れのように、「十住の菩薩は阿耨菩提を得る」と知ってても「一切衆生悉有仏性」を知らない。しかし、356ページの「真ん中らへん」にあるように。。
「十住の菩薩は仏性を眼見、聞見することがある」
また続いて「一切衆生から九地までに仏性を聞見する」って書いてます。
けっきょくどちらにせよ「仏性を聞見する」って書いてて、そのポイントが「聞見」つまりは「因信心」によるということを書いています。
ここで逆方向から「菩薩がもし一切衆生悉有仏性と聞いて心に《信心》が生まれなければ《聞見》できていないってことになる」って書いています。
「菩薩道を歩むのに」。。「十住っていう20階位あたりから進んで、初地を経て九地まで」のプロセスで「仏性を観る」ってことになるんですけど、そのポイントが「因信心」ってことになるんです。
だからこの「十住」は「十住」のまま読みます。
つぎに「獅子吼菩薩摩訶薩さん」が世尊に「一切衆生は如来の心相を知ることができないので、どう観察したらそれを知ることができるのでしょう」って聞かはります。
ここに「如来の心相」ってありますのは、如来の「智慧と慈悲」といえば一般的ですが、それが結果「実相無相」に誘導することであることと言えます。
また、「すべては仏性」「草木国土悉皆成仏」という「存在のない存在であることだと知ることですべてが如来だと教えているということ」を意味しているであろうことは、論の全体の中で推察できます。
「如来」すらが「無相の存在」「言語上の存在」である以上、すべてがそういう「仮名人」であるとも言えます。(名前ということばで定義された存在)
証文類でいえば、「真如一如」への誘導ということになるのかもしれません。
さてここで世尊は回答で、まず「眼見」について述べて、つぎに「如来の口業(言葉)を聞いて観察するんです」って回答します。
そしてこれを「聞見」って定義して、この「聞見」によって「もし色貌(しきみょう)」を見れば、「一切衆生が如来」に観えます。って書いてて。。これを「眼見」って定義しはります。
そして「音声微妙最勝(おんじょうみみょうさいしょう)」を聞くなら、「衆生の音声」も「如来の音声」って聞こえます。って続いて定義しはります。
さらに、「こういう風に《すべて》を《如来》の姿や音声だと《観察》できるようになる」って明言しはります。
そして、聞見した者は「現実や生命を見る」時に「名誉や利益などの利己主義的な見方で《現実を見ない》ようになる」って書いてて、結論的に「他心智」つまり「他の生命の心を智慧で観る」ようになって「世の中や生命を利己的に見ない」ようになって「如来の荘厳功徳」が観えるようになる。って明言しはります。
これが、【20】までにある「如来が諸根力(個人の能力や状態)に応じて無量の教化をする」っていう中で【教化された者がどうなるか】ってことを書いているんです。
ここら辺を「現代語訳」で見ると、「如来」と「衆生」を分断して、「如来のおすがたはすべての衆生に超えすぐれている」とか、「聞見」によって如来の不可思議なはたらきを見たてまつり、それが衆生のためなのか、如来ご自身のためなのか、というとそれは衆生のためであり、ご自身のためではない」っていう書き方をしています。
しかし「如来」である以上「自分のためではない」なんて、「あったり前のこと」を書いているような部分から、現代語訳は「とある学派の意図」の上で「解釈してることが明確」な感じです。
特に、「色貌(しきみょう)」っていうような「重要な単語」を無視して現代語訳していて、かなり重要な単語を平気で無視するなんて、「意図的なのか、マジわかってないのか」
いつもながら本当にご無礼ながら、「かの学派」さんの解釈に偏りすぎています。
とにかく「真実則」において、「衆生と如来が分断される」のは「仏教と不相応」になります。
これは「関西風仏教解説」の「12、真如の誤解」にも書いたように、真如と衆生を分断すると「dhatu−vada」になってしまします。いわゆる「バラモン教」です。
ここで重要って書いた「色貌」は「存在を色で認識している」という「仏教学前提」で読めば、「色と貌」は「名色と形」ってなって、形は「存在の認識材料」ではないのが仏教の「前提」ですから、「そもそも一切の存在も、如来も原則《色も形もなくことばも絶えた》という存在」だということをあらわしています。
つまりは、『《色》で名づけて「存在」と見ている現実は、無明による「認識」だから、実は《貌》「形」なので、妄念による「誤認識」です』《実相無相を現実だと誤認識してる》って論じてるんです。
そして「すべて他心智」による「衆生のための行」として「生命を生きる」と、「現実」を「如来」の「功徳荘厳」って「観察」して「聞見」の中を生きられるっていうことを結論にしているんです。
「色も形もなくことばも絶えた状態をどのように観るか」という本質的な論点から、「すべてを如来の荘厳功徳と観る」という菩薩道であるということが、この論の背景になっていることを明確にしていなければ「真実則」をあきらかにしている「真仏土文類」の意味がなくなります。
とにかくこの部分は、「如来が諸根力(個人の能力や状態)に応じて無量の教化をする」という【20】からの結論を示してはります。この【21】は、「教化された者がどうなるか」ってことを書いてはるんです。
そしてここまでの「結論」として【22】に「浄土論」を引用して、「世尊我一心、帰命尽十方、無碍光如来、願生安楽国」の「無碍光」が「真仏土」の根拠であるって、「真仏土文類」の原点にいったんおさめてはります。
このなかに「かの世界の相を観ずるに迷いの道を過ぎて、究極のところ《虚空のようで辺際なし》」って書いてるのが、「真実則」を「観察する菩薩」になることをいうてはります。
ここまでに。。
真仏土文類は、
「真仏土→光明→智慧→涅槃の徳→如来→菩薩(法蔵)→利他(薗林遊戯地門)→一切衆生悉有仏性→如来は衆生の諸根力を知って導く→諸根力に対する「さまざまな言説」→第一義諦→涅槃→「教説上の法身はすべて涅槃徳の無為法」→「さまざまな言説」によって教化されたものがどうなるか→如来を観察するものになる→根拠は「無碍光」→虚空→【23】荘厳功徳成就って進みます。
2019/02/26[4−20]
ここまでの真仏土文類の論のポイントを書いてみます。
真仏土文類は、
「真仏土→光明→智慧→如来→菩薩(法蔵)→利他(薗林遊戯地門)→一切衆生悉有仏性→如来は衆生の諸根力を知って導く→諸根力に対する「さまざまな言説」→「教説上の法身はすべて涅槃徳の無為法」→「さまざまな言説」によって教化されたものがどうなるか→如来を観察するものになる→根拠は「無碍光」→虚空→【23】荘厳功徳成就って進みます。
ーーーー
このように、「光明の智慧」が「涅槃徳として如来という言説」になってあらわされ、それを「従果向因(果より因に向かう)」または「垂迹(本質から垂れてくる)」形態で「法蔵菩薩」としてストーリー化されて、「讃嘆門→薗林遊戯地門という利他」を行じることを勧めます。
そしてその利他は「一切衆生悉有仏性」を観ることによって「相手の諸根力」を見抜きながらさまざまな「言説」で「巧みに導く方便」の中で「いろいろな法身」とい形態で導くことを説いています。
しかしそれは「けっきょく無為法」という「色も形もなくことばも絶えた法そのものが根拠」であると「法身の根拠」を示しています。
そして、その「無為法から出たいろんな言説」によって「教化されたもの」は、「如来を観察するもの」になり、「荘厳功徳を観るものになる」けれど、その根拠はやはり「無碍光」であり「虚空」である。
ここまではこのような内容です。ーーーーー
そして【23】から、「論註」によって「荘厳功徳成就」について「彼の世界のすがたを観れば、迷いの(三界)を通り過ぎる」と書いてて、「凡夫、煩悩成就の者」が(現生にて)浄土に生ずることを得れば、「三界(迷界)」の「束縛に引っ張られることはありません」って書いてて。。
これこそ「煩悩を断たずとも涅槃を得る」っていう「不思議なこと」です。
って書いてて。。
【24】には、【23】の「荘厳功徳」から生まれる《正道の大慈悲は出世間の善根から生まれてくる》もので、「荘厳功徳成就」っていいます。って書かれてて、「荘厳功徳の根拠」を書いています。
ここで「性(しょう)」は。。って書いてて、もともとこの部分の根本の「性」について、この「荘厳功徳」つまり「浄土」の「本(根本)」は「法性」に背くものではなくて、じつは「法性にしたがったことで「法そのもの(法本)」です。って書かれてて、「華厳経」で「宝王如来」が「法性から生起」したことと同じように、
「積習(しゃくじゅう)して法性を成ず」って、「法性」が「智慧を積み重ねて(自然に)それが成就して」っていうのは「法の智慧が熟して」っていう意味で、法の智慧が熟して「法蔵菩薩」を出したんです。っていうことが書かれてて、ここで、その「性」は「聖種性」っていう「十地の菩薩」の位っていいます。
って「法蔵菩薩」がどういう背景で「法の言語化」として生まれて来たのかっていう根拠が書かれています。
このように、ここからは「法蔵菩薩」の「荘厳功徳」は「法性の智慧」が根拠となって、無為法から出て来たってことを書いてますが、これは「無為法」をさとった「釈尊」が発見した、または釈尊が積み重ねて来た「真理の智慧」から出て来た「言説」であるってことをいうてます。
だからこの先【25】から【28】までは、法蔵菩薩や四十八願という「俗諦(言説)」は、「法を根本としている」ということを説明しています。
そして【29】で、「南無阿弥陀仏」のストーリーを「無量寿経」の「智慧の光明」と定義して、光明を「無量寿経の十二光」によりつつ、さまざまな角度から定義し、362ページの後ろから3行目でまた「智慧光」に落とし込み、続いて「聞光力」って、「光(智慧)を聞く力」だから「心が断えることなく往生する」って、真仏土は「光明」であるっていう「根拠」に落とし込みつつ論を進めてはります。
363ページの3行目には「神光は相を離れてる」って書いてはって、「すがたを離れてるから《無称光(ことばで言い尽くせない智慧)》っていいます」って、けっきょく「すがたのない法性根拠」ですねんっていうことを「念押し」しながら論じてはるんです。
つづきに「光によって成仏したもう」って根拠は「光(智慧)」っていうて書いてるのも同じ「根拠の念押し」です。
ここまでは、真仏土は「光明」で「智慧」で、そこから利他の言説として「法蔵菩薩や四十八願」「南無阿弥陀仏」が出てるっていう根拠と、だから結果そういう「言説や善巧方便」は「法性無相の真如」やってことを言うてはるんです。
そして、「龍樹菩薩(摩訶薩)」は「末法の手前の像法の時代に生まれて、頹綱(たいこう)を理る」「邪扇(じゃせん)を関閉(かんぺい)」とかって書いてはるんは、「像法の時代」っていうのんは、「形ばかりのニセ(像)の時代になっていたから、いろんな間違った仏教を立て直した」っていうことです。
「閻浮提(えんぶだい)」っていうのは、倶舎論から当時でいう「世の中全体」をあらわすことばなんで、この龍樹さんが「ニセ(像)」を立て直して「世の中の一切に智慧の眼を与えた」っていうことです。
そしてそれが、「歓喜地」の「阿弥陀」による「安楽」に生まれるってことです。
って、もはや親鸞さんの「末法」以前の「像法の時代」から。。
「阿弥陀」の「言説」の「智慧」が「安楽を与える教え」ですねんっていうてはって、この「阿弥陀の言説」を十方の有縁に勧めてはるってことを述べてはります。
ほんで364ページに「十方三世の無量慧」「一如に乗じて正覚と号す」ってあって「二智円満」って書いてて。。
「実智(じっち)っていう真如、実相を知る智慧」と「権智(ごんち)っていう智慧による、さとりへの誘導である善巧方便や荘厳功徳を観る智慧」が「円満しますねん」っていうてはります。
【29】の終わりに、この智慧が「阿弥陀に言説化されてて、阿弥陀の浄土に帰依することは、諸仏の国に帰命することとおなじ」って「華厳経」の「一即一切原則」から、「われ一心をもって一仏を讃嘆する」って書いてて、願わくはそれが「十方無碍人に遍せん」って書いてるのを、脚注には「無碍人を諸仏」って書いてありますけど。。
この「一即一切原則」と「十方無量寿仏」って書いてますから「毘盧遮那仏」のように、「一仏即一切仏」をいうてて。。
しかも、真仏土文類のここまでに「一切衆生悉有仏性を観る」ってある論の流れからすると、この「無碍人」は、すべての「仏性」つまりは「衆生を含む生命の本質」に「あまねく光明(智慧)が行き渡る」っていう意味やと読み込めます。
これは「十方」→「無量寿仏」っていう「十方と無量寿仏」が連結されてることから、ここには「真実則で無量寿仏」が書かれてて、「西方無量寿仏」っていう「方便則」やないところと、この部分も「華厳経」に寄っていることから、この「智慧光」が「十方無碍人(十方衆生)に遍く行き渡ることを論じてはる」と推察できます。
2019/03/01[4−21]
けっきょく真仏土文類において。ポイントを拾っていけば、
「真仏土」→光明→智慧→涅槃の徳→如来→菩薩(法蔵)→利他(薗林遊戯地門)→一切衆生悉有仏性→如来は衆生の諸根力を知って導く→諸根力に対する「さまざまな言説」→第一義諦→涅槃→「さまざまな言説」によって教化されたものがどうなるか→如来を観察するものになる→根拠は「無碍光」→虚空→【23】荘厳功徳成就って進んできています。
これは、「光明の智慧」が「涅槃徳として如来という言説」になってあらわされ、「法蔵菩薩から阿弥陀仏になるってストーリー化」されて、「讃嘆門→薗林遊戯地門という利他」を行じることになるっていう風に進んできているんです。
これを「真実則」でいくなら「法蔵菩薩の行(五念門行)」を行じるっていうことになります。
「阿弥陀仏に託す」【31】っていう迂回をしなくてもいいってことです。
ただ、現代人といえど「すべてのひと」がそうはならないので「方便則」で、「阿弥陀ストーリー(韋堤希ストーリー)」があるってことをここでは論じます。
つまり、その利他は、世尊が「一切衆生悉有仏性」を観ることによって「相手の諸根力」を見抜きながらさまざまな「言説」で「巧みに導く方便」の中で「いろいろな法身」という形態で導くことを説いてきていて、「荘厳功徳」を観るってことが、「《無量寿仏》の中に《一切仏や無碍人》を観ること」になり、
これはすべて「智慧光」が「十方無量寿仏」「一切の無碍人」っていう《言説形態》によって「実際には《智慧》が普遍的に広まることをいうてるんです」っていうてはるんです。
そして、【30】に「善導さん」を引いて。。
この「言説」が「阿弥陀とその浄国」という「ストーリー」になってる内容は、「法蔵菩薩」の「願行の果」に報われた「報身、報土」が「阿弥陀と浄土」ですって定義して、「真実のさとりに導く仏身」ですっていうてます。
そして、これは人間のなかでも「上位クラスのひと(上品の三品)」を「報身の阿弥陀」が「化身仏」とともに、《現生に来て》「手を差し伸べる」って善導さんが書かれてますってことなんです。
ただ、ここは「来迎」するってことだから「死んだらお迎えにきはる」って感じですけど、「命終」って書いてるのを「心でいうか身でいうか」によって変わるので、いまここでは「現生」って書きましたけど、ここの文言そのものは「死後」原則でしょう。。
その上、ここは「人間の上位クラス」っていうことで定義しているので「限定的な話」です。
☆☆☆
しかも、365ページの後ろから3行目の問答から368ページまでには、『《さとり》もなにもかもが、じつは《幻》です』って書いてて、「新発意の菩薩」っていわれる「さとりに向かおうとするスタートラインにいる菩薩」が「ぜーんぶ幻(まぼろし)です」って聞いたら怖がるから、あえて「生滅するものはまぼろしで、不生不滅のものは《幻のようなものではない》っていうてるけど、じつは「ぜーんぶ《幻》」です。☆☆☆
っていうのが「実(ホント)のところ」だけど、「阿弥陀仏は、法蔵の願行に報われた《報身》です」って一応定義しておくんです。
って書いてて、でもこの「ぜーんぶ《幻》だけど、この教えがさとりに導く方便ってことは《智慧ある人》なら理解できることです」って明確に「《すべて幻》定義」してはります。
そして問答によって、「煩悩の垢」にまみれた凡夫が「阿弥陀仏の浄土を求めるなんてしないでしょ」っていう問いに、「だから仏願に託すことを強い縁にするように説かれていて、上位クラスだけではなくて、すべての凡夫が救われるようになってるんです」って答えてて。。
その強縁に託すことを【31】で「観経」に「最下位の韋堤希(いだいけ)のストーリーで、最下位のものがあえて《仏願に託す》っていうことを説いてるんです」っていう風に「如来が方便として韋堤希を差し向けて、仏願に託すことを示している」
って答えて、「真仏土の光明」→「智慧」→「諸根力に応じて言説化」→「俗諦」→「阿弥陀ストーリー」→「韋堤希ストーリー」においてすべてが救われる。
という流れをあきらかにしていますが、とにかく「さとりっていう言説を含めてぜーんぶまぼろし」っていう部分が重要で。。
【32】からはけっきょく「西方」の方便は「寂静無為」っていう風に「方便則」にある「真実則」を明確にしながら、「魔郷(迷界)」から「涅槃の城(みやこ)」に入るべきですっていうてはります。
【33】では、「真仏土文類」はそういう「如来(世尊)が《無常無我、空の状態》の《真如》を明らかにして、すべての凡夫人に《真如の法楽》を得させる為のあらゆる方便の究極が《阿弥陀の教え》」やってことを明らかにしてきて。。
【34】で、やはりそれは「自然に帰する」ことで、「無漏無生」「無為法性身」を「得ること」が目的であるって書いてます。
【35】でそれを「弥陀のさとり」が「無上涅槃」っていうことで、「阿弥陀の方便則」から得られる結果も同じです。っていうてはるんです。
そして【36】では、いろんな「言説や方便による」けれど、回り回って返って「光明」です。
ってところに落ち着くんです。
ここで「補足3−112」にも書きましたが、かなり「重要」なので、ここにも書きます。
🌟これは、「色も形もなくことばも絶えた」「《不確定》《無常無我、空》ということ」が「さとり」という【言語で定義された途端「さとり」ではなくなる】ってことです✴️
だから「空は非空で、非非空で、非非非空で。。」って果てしなく続きます。
円周率(3.14159265。。)とか「100➗3=33.333333。。」って感じです。
「浄土はさとりの世界です!」「阿弥陀如来は常住です」ってのも「幻(まぼろし)」なんです‼️
2019/03/04[4−22]
【36】までに、真仏土は、「さとり」をいろんな「言説や方便によって説き示すけど」回り回って、けっきょく「光明」です。ってところに落ち着きます。
そしてこの【36】の最後に、「身心柔軟の願(第三十三願)の致すところ」って書いてますが、願文は、触光柔軟の願(三十三) たとひわれ仏を得たらんに、十方無量不可思議の諸仏世界の衆生の類、わが光明を蒙りてその身に触れんもの、身心柔軟にして人・天に超過せん。もししからずは、正覚を取らじ。っていう内容です。
この三十三願が、教行証文類の「真実則」の根本になっているって解釈してる学説もあります。
また了慧ってひとの「論註略鈔」なんかでは、第十二願の「光明無量の願」の効力が、第三十三願だっていうてる説もあり、意外とこの三十三願って「重視」されてます。
☆☆☆
そして。。この願文のなかに「チョー重要なポイント」があります。
「十方無量不可思議の諸仏世界の衆生の類」この部分、普通にいうと「矛盾」してます。
それは、「諸仏世界」に「衆生の類」が存在してて、しかも「等価」になってるってことです。
「諸仏=衆生」が「無碍光に触れると人天を超える」って、そもそも「諸仏世界」に「人天が居てる」前提ってのも「矛盾」です。
けど、ここがこの願文の「重要」なところです。
親鸞さんは「真仏土文類」を「真実則」で書いてるので、当然のように「サラッ」と流してます。
つまり「光明」に出会って「観察門」で観れば「全てが仏ないしは化身仏」になるので、「観る側」が「俗世の見」で見れば「衆生」だったとしても、「智慧(観察門)」で観れば「諸仏」になるからです。
四十八願文の中にも意外と各所に「真実則と方便則」が混在してます。
この読み分けがないと「むちゃくちゃ」になりますし、もっともらしい「こじつけ(会通→えつう)」が必要になります。
☆☆☆
こういうことは教行証文類の「ここまでの論」を理解していれば、当然なことですから、「説明の必要がない」ということだと推定できます。だから、あえて「三十三願は真実則」と論じる「学説」があるんです。
【37】には、親鸞さんのことばで、「如来の真実の教説と各高僧の解釈を通して、安養浄刹は、法蔵菩薩の願行に報われて成り立った領域やってことが明確になりましたね」って書いてます。
ちなみに浄土を浄刹って書いてるのは「刹」は梵語 kṣetra (国土、世界)の音訳ってことで、「もともとサンスクリット語の音訳」を使って、浄土を「国土」という「エリアや領域的な意味」を強めてはります。
☆☆☆
そもそも無辺であるはずの《浄土》を《主がいる前提》の《領域》」っていう「国土」という表現はよく出てきます。
これって、「かなりな方便則」で「迷界」との違いを明確にする必要がある部分で使われる表現です。
この点、迷界について「国土」という表現はなくて、迷界に「主(あるじ)」はいません。
迷界についてここで「誘惑に染まる」って書いてます。☆☆☆
「誘惑に染まる(惑染の)衆生」って書いてますが、「この惑染」は「煩悩のことです」っていうと少しズレます。
「人間などの衆生」は、「誘惑の中で《煩悩》を動かされているってことです」
そういう意味では「広告宣伝」に動かされ、世間の「多数派の意見」に動かされ、動物的には「本能に誘惑が及べば」動かされているってことです。
つまり、迷界の主(あるじ)は「誘惑」ってことかもしれません。
いずれにせよ、「方便則」でいう「浄国」へ至らないと「仏性」は見えない。
そして「涅槃経」から「例の迦葉菩薩」が、「私は十住の菩薩ですけど《少し仏性が見えるようになってます》」って書いてる部分を、このままの流れで読むと「安楽仏国に到ればすなわちかならず仏性を顕す」っていう意味は、
☆☆☆
①教行証文類の論の流れで、現生で初地の「正定聚」になると、って読めば、「私」以外は全て「化身仏」って観えるようになる。
「唯識原則」でいうと「私という《自我名》が破られて《一如》を《さとりの荘厳功徳》って観える状態」になるから、「全てに仏性が見える」ってことになるし、「安養つまり法楽」になります。
このように「観られる」ようになると理論上【全てが成仏】することになります。
唯識論でいえば、「全てが《認識の産物》なのですから、理論上そうなります。
なお、「安養」ってのは「安楽、法楽」へ「養う」「利他世界」を意味します。
②ここを「完全方便則」で、ここには「誰が」「安楽仏国に到る」って「主語がない」ので、あくまでも「一般論」で、「とにかく浄国に到達すれば仏性が顕れるんです」っていうてはる。
☆☆☆
こんな風にここも「二通りの読み方」ができますが、とにかく「仏性を観るようになるのは」「本願力がそのように方向転換してくれるから」ってことで、「衆生、未来に清浄の身を備えて、荘厳して、仏性を観る」
ってあるのも、「この部分での《衆生》は、《まだ仏道を歩む前の衆生》(未来に)」について、書いてるので、
①の真実則でも読めるし、②の方便則でも読める書き方になっています。
だから【38】では、「完全真実則」で、「仏性を説くにしても、究極は《言説》や《念じる》ってことでは《不可能》です」っていう意味のことを書いてて、「さとりや仏性」っていう状態は「ことばや思いでつかもうとしても、掴めない《法則性》だから《随順》するしかない」
「つかもうとする思い(念)を離れて、《自然に随順して得入する》しかなくって」「随順して得入したら《真如三昧》」つまりは「虚妄分別」を離れて生きられて、さとりそのものに「従うものになる」んです。
って、「完全真実則」から「真如を行じる」ことを明確にしています。
ここの「念」を「仏を念じる」って読んでも同じです。
このことは「A」の経験からも、「自我の思いで生きる」と「ものごとがややこしくもつれる」
「しかし自然の智慧に任すと、自ずと《ものごと》が整然と整理される」っていう事実を経験してます。
つまり「自然に任せて生きると荘厳功徳世界になり、自我で生きるとカオス(混沌)になる」ってことです。
そしてこのように「思いを離れる」っていう状態は「完全滅度に至った《妙覚位》」のことで、
「了心っていう《心そのものの発生》の状態から、この《心の発生が煩悩が誘惑に染まって苦しめる》っていうことを知って〈初相を知る〉なら、この《心の思い(念)》を離れる《無念》に至る」ってことを書いてはります。
ほんで「この無念」っていう状態は、「十地の菩薩」でも「そこまでは知ることはできない」ぐらいの状態なのに、ましてや、「今の人」は「十信」っていう「入門位」にも居てへんのに「わからなくっても当然です」って書いてますけど。。
「今の人」ってのも「その時代時代の世俗の人」っていう意味と「過去法(過去の状態)」から「未来法(未来の状態がどうなるか)」を見ようとしない「今だけを見てる人」っていう意味合いがあります。
どっちにしても「世俗の人」です。
けどこの「世俗の人」が馬鳴大士(菩薩)のいうように「言説、教説」から「無説」に入って「ことばで言い切れない法則性の状態にいること」を知って、「仏を念じるってところから、究極は無念の《さとり》に入りますねん」って書いてはります。 そして【39】の「真仏土文類」の結論「光明」に入っていきます。
2019/03/06[4−23]
371ページラストの【39】に書かれていることは、
「報身、報土」について、「あくまでも如来の願海の結果だから《方便則》に《真実と仮の解釈》がある。」ってことを明らかにしてて、「選択本願」を「受け入れて《自我名字の転換(因信心)をする」という《正因》つまり異熟因ないしは能作因によって、「真仏土が成就される」って書かれてます。
ここは主語は如来になっていますが、「正因」を語る以上「無為法」では語れないので、「行者側」から読むとこうなります。
☆☆☆ここで「真仏」を「大経」によって「無辺光仏、無碍光仏」に論を進めて、結果、浄土論の「帰命尽十方無碍光如来」の「真実則」に戻して、「無量光明土」「諸智土」と規定して、「究竟して虚空の如し」「広大にして遍際なし」としています。
また、「皆受自然無極の体」という「真実則」と、「如来浄華正覚華化生」という「方便則」を並列して、「同一念仏無別道故」って書いてて、「どちらも同じ道」としています。
そして、これを「人知では考えられない、難思議往生」と定義しています。☆☆☆
そして、「仮の仏土」については「化身土文類」に記述しますって書かれてて、「これは《善巧方便》ではない、マジ《方便化身、化土》です。」っていうてて、真仮を知らないと「如来広大の恩徳を迷失しますからいまは、真仏、真土を顕わしたんです」と、「真実則」に基づく《報身、報土》っていう「善巧方便」をあきらかにして来た由来を明確にされています。あとは、「推して知るべし」でしょう。
続いて、ここまでに解析した「真実則」と「方便則」によって「信文類」の解析に戻っていきましょう。
2019/03/10[信文類を読む前に前提を解析]
真宗は「自力を廃して他力に依る」って言いますけど、これかて「真如実相」からいえば、「どちらもあるともないともいえます」
「無常無我、空」や「真如実相」なんかが「論理的にわかればそのまま《五念門》を行じたらいい」んです。
「それは自力行だ!」なんていうことそのものが「自力(はからい)」「分別」です。
そもそも「他力は縁起力」ですから、「自他分別のはからいを除く方向」で「法楽、真楽」を得ればいいんです。
仏教ってのは「権威や法」に《拘束する》ものではなく、「あらゆる拘束から解放される方法」です。
これが、「真理」に基づくので「法」を重視しますが、「法」は「無常無我、空」なので、《拘束》しません。
仏教に「ねばならない」はないんです。
仏教は「こう考えてこうしたらいい」っていう「論と方法」が「真理、真実」に基づくから、「あらゆる拘束を解放する」んです。
「論」がわかるなら「直(ちょく)」に「教→行→証」って進んだらいいんです。
だから「顕浄土真実《教行証》文類」なのだと思います。
けれど、「論」がわからないというひとの多い時代には、「信が必要になる」ってこと、また、重要なことは、そもそも「念仏でなぜさとりに至るか」っていうポイントを「解析して論じる」必要があったという理由で、
「信文類」を特別に分けた形で「書いてはる」んです。
「念仏でさとることができるのは、阿弥陀如来を受け入れて《破我》されるからだ!」
「それは、《信心》を通過するからだ!」って論じてはるんです。
だから「念仏」を「乃至十念」定義ではなく、「至心信楽」定義されているのだと言えます。
そういうことだから、「信文類」には「別に序文」があるんですって、これは「宗学上」でも言われています。
もちろん「現代でも」阿弥陀ストーリーの「方便則」でもいいんです。
「難しい仏教学」なんて「今さらわからん!」っていう方は、ありのまま「阿弥陀ストーリー」を受け入れる「信心」を通過した方がいいと思うのです。
つまりは「阿弥陀如来の真実心を疑蓋無雑(ぎがいむぞう)」っていう「無疑の一心」で受け入れて、ただ「自然を主」にして生きることです。
これも結果的には、ここまでの記述でいう「自我名字」を「南無阿弥陀仏名字」に入れ換えることで「名号という利他を行じること」になります。
つまり「自我」が「機の深信」で否定されて、「法の深信」で「願力に乗る」っていうことが同時(一体)ですから、「結果」⇒「破我」されて「自己の主客が入れ換わる」ことになるっていう構造です。
ですから、本来は「浄土真実教行証」でいいのですが、「信文類」を別に書き起こされたんです。
「行→証」ってスムーズにわからない、進めない人のために「信」が入るんです。
また、ほかの仏教者に「行には《信》が内在しているからさとりに至るんです」と論じているんです。
これは「事実上《行文類》の中に「信」が記述されている」ように、
「行→証」と進む人にも「起こっていること」ですが、スムーズに「行→証」と進むひとには、特に説明の必要がないことです。
また、サンスクリット語原典での「信」が「浄心(プラサーダ)」である以上、「自我」ではない。
仏教で「なにを行じる」にせよ「プラサーダ(浄心)」前提でなければ、「無我の法楽」にならないんです。
大げさにいえば「仏教である以上《プラサーダ》抜きでは仏教にならない」というメッセージでもあります。
これをスムーズに「行文類」で理解できる人と「そうでない人」があるから「信文類」があるんです。
「信」について「説明を要するひと」に向けた内容が「信文類」になるようです。
しかも「阿闍世」という「極悪人を持ち出して」まで、その対象者を「唯除」として説明されます。
「唯除」は例えると「親が」「お前は出て行け」と言わなければならないほど、どうしようもない「愚者」であり、かつ「心配な子」という「除は摂取の意味」という部分こそが、「第十八願(本願)の真意」であるっていう重要ポイントです。
(ここでは「わかりやすいように」あえて「親子」で例えました。)
以上のように「行」を「自力だの他力だの」と論じることに意味はありません。
結果「自我」であるか「無我や空に向かっているか」ってことです。
☆☆☆
しかし‼️「どちらのルートを進むにせよ《外せない》のは四十八願」ですから、ゴールは同じです。
☆☆☆
極論でいうなら
「法蔵菩薩コース」(真実則)で進むか、
「阿弥陀如来コース」(善巧方便則)で進むか
どっちでも「同じゴールです」ってことです。
とにかく真宗の教えを精査すると「自我=自力」「無我(破我)=他力」という意味で「自力他力」を使ってはるって解析できます。
これらのことを踏まえて「信文類」を読んでいきます。
【本題】🔴この前提のしたに「本文」を続けます。
[信文類を読む前に前提を解析]Plus‼️(3/22記)
真宗は「自力を廃して他力に依る」って言いますけど、これかて「真如実相」からいえば、「どちらもあるともないともいえます」
「無常無我、空」や「真如実相」なんかが「論理的にわかればそのまま《五念門》を行じたらいい」んです。
「それは自力行だ!」なんていうことそのものが「自力(はからい)」「分別」です。
そもそも「他力は縁起力」ですから、「自他分別のはからいを除く方向」で「法楽、真楽」を得ればいいんです。
仏教ってのは「権威や法」に《拘束する》ものではなく、「あらゆる拘束から解放される方法」です。
これが、「真理」に基づくので「法」を重視しますが、「法」は「無常無我、空」なので、《拘束》しません。
仏教に「ねばならない」はないんです。
仏教は「こう考えてこうしたらいい」っていう「論と方法」が「真理、真実」に基づくから、「あらゆる拘束を解放する」んです。
「論」がわかるなら「直(ちょく)」に「教→行→証」って進んだらいいんです。
だから「顕浄土真実《教行証》文類」なのだと思います。
けれど、「論」がわからないというひとの多い時代には、「信が必要になる」ってこと、
また、重要なことは、そもそも「念仏でなぜさとりに至るか」っていうポイントを「解析して論じる」必要があったという理由で、「信文類」を特別に分けた形で「書いてはる」んです。
「念仏でさとることができるのは、阿弥陀如来を受け入れて《破我》されるからだ!」
「それは、《信心》を通過するからだ!」って論じてはるんです。
だから「念仏」を「乃至十念」定義ではなく、「至心信楽」定義されているのだと言えます。
そういうことだから、「信文類」には「別に序文」があるんですって、これは「宗学上」でも言われています。
もちろん「現代でも」阿弥陀ストーリーの「方便則」でもいいんです。
「難しい仏教学」なんて「今さらわからん!」っていう方は、ありのまま「阿弥陀ストーリー」を受け入れる「信心」を通過した方がいいと思うのです。
つまりは「阿弥陀如来の真実心を疑蓋無雑(ぎがいむぞう)」っていう「無疑の一心」で受け入れて、ただ「自然を主」にして生きることです。
これも結果的には、ここまでの記述でいう「自我名字」を「南無阿弥陀仏名字」に入れ換えることで「名号という利他を行じること」になります。
つまり「自我」が「機の深信」で否定されて、「法の深信」で「願力に乗る」っていうことが同時(一体)ですから、「結果」⇒「破我」されて「自己の主客が入れ換わる」ことになるっていう構造です。
ですから、本来は「浄土真実教行証」でいいのですが、「信文類」を別に書き起こされたんです。
「行→証」ってスムーズにわからない、進めない人のために「信」が入るんです。
また、ほかの仏教者に「行には《信》が内在しているからさとりに至るんです」と論じているんです。
これは「事実上《行文類》の中に「信」が記述されている」ように、「行→証」と進む人にも「起こっていること」ですが、スムーズに「行→証」と進むひとには、特に説明の必要がないことです。
また、サンスクリット語原典での「信」が「浄心(プラサーダ)」である以上、「自我」ではない。
仏教で「なにを行じる」にせよ「プラサーダ(浄心)」前提でなければ、「無我の法楽」にならないんです。
大げさにいえば「仏教である以上《プラサーダ》抜きでは仏教にならない」というメッセージでもあります。
これをスムーズに「行文類」で理解できる人と「そうでない人」があるから「信文類」があるんです。
「信」について「説明を要するひと」に向けた内容が「信文類」になるようです。
しかも「阿闍世」という「極悪人を持ち出して」まで、その対象者を「唯除」として説明されます。
「唯除」は例えると「親が」「お前は出て行け」と言わなければならないほど、どうしようもない「愚者」であり、かつ「心配な子」という「除は摂取の意味」という部分こそが、「第十八願(本願)の真意」であるっていう重要ポイントです。
(ここでは「わかりやすいように」あえて「親子」で例えました。)
以上のように「行」を「自力だの他力だの」と論じることに意味はありません。
結果「自我」であるか「無我や空に向かっているか」ってことです。
☆☆☆しかし‼️「どちらのルートを進むにせよ《外せない》のは四十八願」ですから、ゴールは同じです。
☆☆☆
極論でいうなら
「法蔵菩薩モデルコース」(真実則)で進むか、「阿弥陀如来乗託コース」(善巧方便則)で進むか
どっちでも「同じゴールです」ってことです。
とにかく真宗の教えを精査すると「自我=自力」「無我(破我)=他力」という意味で「自力他力」の文言を使ってはるって解析できます。
🔴[5]の前提Plus
《名号大行と信心正因》の矛盾。
名号が「正因」にならないのは、基本的には「無為法」(色も形もない言葉も絶えた法そのもの)だからです。(無為法は因にならないが仏教の因果論原則です。)
だから「増上縁」の「縁」扱いです。「無為法は縁にはなる」原則だからです。
だからなのか、主流派では「信心正因」といいます。
これは「人間」という「有為法」でなければ「因」にならない原則だからでしょう。
ならば「大行」を「名号(法体)そのもの」とする場合。
「法蔵菩薩」という「ことばやストーリー」を設定して、その「法蔵菩薩」という「有為法に該当する存在」が《行じた》結果が「名号」だという流れがあらわすことを、「有為法が無為法になったという流れ」だと解釈する。
そうだとしても「名号を無為法」として扱うには問題があります。
なぜなら「名号」は「ことばが意味を持つ」という「性格である以上」さまざまな解釈が起こるから「無為法」にはなれません。
だから、「名号を独用の大行に定義する」と、このようなあいまいな「言語的存在」を「無為法」として扱うという「課題」を生みます。
つまり「名号」は「取り扱い方」によって、「阿弥陀さま」という「実体概念」になる「人格存在」になる「可能性」を持つからです。
わかりやすく言えば「十九願、二十願」という状態を生む可能性を持つ「存在の状態」を完全「無為法」とはいえません。
それを「受け取る側の問題」といいたくても、そもそも「行」は「有為法」がなければ成立しません。
「名号大行が、果位の上で《利他》を行じている」といえば「完全無為法」のように錯覚しますが、
「利他」を行じる以上、「利他られる迷界の存在がいなければ《利他》そのものが成立しません」
つまり、「迷いの存在」がいない以上「名号は存在できない」のです。
このように「有為法に依存」して「存在」する以上、「受け取る側の問題」ともいいきれないのです。
しかもその「迷いの存在」は、「名号を人格存在という実在化」いわゆる「阿弥陀さま」としてとらえる可能性が充分にありえます。
「成就文」の有無に関わらず、単独存在できないから「設我得仏〜不取正覚」のまま「言説有為法」というのが「真実」です。
「名号が出来ました」といっても「迷界の人間(衆生)」がいない場合には「存在」になれず、また「実体概念」になる可能性がある以上「有為法」扱いです。
結果「名号大行」は「名号単独では存在できない《矛盾した概念》」ということです。
「信心が正因」なのは「正因」は「人間の側」でしか言えないからというのは「理にかなって」います。「因は有為法」という「理」です。
しかし「行」も「受け入れる迷界の人間などの衆生(有為法)」が存在しないと成り立たない、しかも、「ことば」である以上「対象者」は現実的には「ほぼ人間限定」です。だから「人間を離れた《利他行》は無意味」になる。
つまり「大行」は「法体」で語れないから「讃嘆門」の「称無碍光如来名」という「人間」の側からしか語れません。
結果「名号大行」は成り立たないので、「讃嘆」(従来でいう略讃でいえば「称名」)でしか「定義」できません。
☆☆☆だから「法蔵菩薩のように行じる」が「真実則」で、「二種深信のように名号に破我される」が「方便則」になります。☆☆☆
⭕️この「二種深信」が必要なひとが「方便則」を行じるひとになるんです❣️
しかし、スタートから「仏教学」的に「無常無我、空」を理解できて、法蔵菩薩として「讃嘆行をメインに五念門、五果門」を行じて生きることが可能なひと。
⭕️「二種深信」を必要としないひとにとっては「信文類」はほぼ不要です。
しかし、難しいことはわからないという「方便則のひと」にとっては、二種深信というプロセスによって「南无阿弥陀仏」に破我されて、南无阿弥陀仏がわたしの「主体」であり、「世俗名」は客体であるという「破我」の歩み(二種深信)を生きるほうが適しています。
この「どっちをを歩むか」というのが「教行証文類」が言ってることです。
このポイントからいえば「称名報恩」は、「感謝」(ありがたい)ではなく、「報謝」(慚愧)だとしなければ、「自我の行信」になってしまいます。
(報謝の「報」は、教えに「応じる」っていう意味で、「謝」は、謝罪という内容を意味する「慚愧」ということです。)「恩徳讃は肉体(五蘊)を粉にしても、骨を砕いても、報謝せよ」っていう内容です。
いずれにしろ、共通するのは「受け入れる」→「信心」です。
これが「真実則」の人は「仏教学」を通して「スムーズ」なので、それほど「テーマ」になりません。
しかし「方便則」のひとにすれば「重要ポイント」だと「強調」しなければならないので、
「信文類」が別立てで「論じられている」といえます。
現代は「その両方のひと」が混在します。
むかしは「方便則」のひとが多かったということは「想像に難くありません」けれど、現代に「方便則」ばかりでは、逆に「受け入れないひと」が多くなっています。
そこで「内容」に戻ります。
2019/03/15[5−1]
205ページに、信文類の「序」があります。以前にも書きましたが、見直してみます。
信文類の「序」のはじめにいきなり「信楽」とでてきますが、この第十八願に出てくる信楽と、浄土論の「世尊我一心」の「一心」を同じであると論じられます。
これが、ストーリー性のある「方便則」の「信楽」が、「真実則」のいきなり功徳荘厳を行じる「一心」と同じであるってことを意味してるようです。
だから「阿弥陀如来」という「具体的な名字」は記述されておらず、どの如来なのか不明なまま、「《如来》選択の願心より発起す」とあって、「阿弥陀如来とも無碍光如来」ともいえる「真実則と方便則」が記述されています。
つまり「方便則」で読むと「阿弥陀如来」になって、「真実則」で読むと「如来全般」または「わたしを真如に導くすべてを如来とする」という風にも理解できます。
そして、ここで明らかにする内容について、「大聖(釈尊)矜哀の《善巧》より顕彰せり。」ってあって、「善巧」は「善巧方便」なので、この「信文類」は「善巧方便」前提です。ってことを明確にされています。
つまり、「色もない形もないことばも絶えた真如法性」に導く「方便」が「阿弥陀如来」やってことです。
ですから、「言説の念仏ストーリーは方便」前提だってことでもあります。
化身土文類に、「19、20願を方便」と論じてはるのんは、「善巧方便中の方便」ということです。
化身土文類で、「月を指す指」が「念仏の教え」(阿弥陀ストーリー)で、「指の形だの爪の色だの」ってことにこだわっているというのが「19、20願」なのです。つまりは「自我行」(救われたい自己がある前提の行)です。
ここで、教行証文類の難しさは「真如と方便が入り混じっている」ので、その見分けがつかないと、☆☆☆
「仏の世界(真如法性)などはわからなくてもいい」と方便に埋没して、結果「自性唯心」に沈んでしまうのです。実際そういう布教がほとんどだと感じます。☆☆☆
あくまでも「信文類」でいいたいのは、「世尊我《一心》」という「尽十方無碍光如来に帰命」する《一心》によって、「往還の二回向に生きることになる」ということと、「阿弥陀如来」本願の「至心」を「受け入れる」ってことが同じだというてはるんです。
親鸞はなぜそうなるのかというポイントについて、この《一心》を【三経】にあてはめて解釈しています。
例えば、大経の「本願(第十八願)」の《至心(真実心)》を「無疑」の《一心つまり信楽》で受け入れて《欲生我国》になっていくと書いてて、「観経や阿弥陀経」などからも「三心と一心」について解説されます。
この信文類の内容は、このような論によって、「方便則」から「真実則」の説明をするっていう逆方向からの証明っていう形式にもなっています。
それは《一心》が天親オリジナルではないことを典拠によって証明し、この《一心》において「わたしが真如化(如去・如来)すること」を論証しているのです。
そこで、本文3行目の「自性唯心」については、「補足47」に書いた通りです。
☆☆☆
ひとことで言えば「自分にとって都合のいい浄土の理解をしている人がふえている」ということです。仏教と相応しない浄土のあり方を信じている人がいることへの警告です。
「阿弥陀さまのお名号にお任せしていれば、何もしなくても思わなくても自然とお浄土に生まれさせていただけて、また会える世界があるんだよ」(会えると遇えるとこだわる必要もないほど根本からミスっています。)などと、おとぎ話かスピリチュアルかよくわからないものに貶めているのです。☆☆☆
「定散(じょうさん)の自心」というのも、定(観想)や散(善行)も「わたしが救われたい」という「自我」からの行ないだから、「迷ひて」と書かれています。
「金剛の真信」が「金剛」なのは「自我」がだんだんと「滅せられる」ことをいい、そもそも「迷う主体がなくなること」で「無為法」からの「自然の利他法」前提だからです。
簡潔に言えば、「如来の真実(真)を受け入れる(信)」ってことです。
ここに「論家、釈家」を脚注では、七高僧だと記述されていますが、ここでは「天親、曇鸞(論家)」がいっていることを、「道綽や善導などの解釈(釈家)」で宗義を開きあらわすと理解する方が、内容に符合しより鮮明になります。
そして三経の光明のなかで、「尽十方無碍光如来への帰命の一心」に含まれている「華厳(経)の文を開く」と読めば、「行文類」から論が一貫します。
そしてこの信文類の内容は、それこそ「如来の善巧方便がわからないひと」からすれば、「なにをいってるんだ」「人倫と違うじゃないか」といったことをいわれるであろうけれど、恥じる必要もなければ、「言い方をかえたりして理解を求めるにしても、決して謗るようなことにならないように注意してください」と記述しています。
実際、仏教は「一般的な道徳に合わない」内容も多いのです。
本来の「布施行」でも、あげた人は「あげたと思うべからず」、もらった人は「もらったと思うべからず」、そのAからBに移動したものの「良し悪しをいうべからず」という「三輪清浄」が基本ですから、「いただいたら感謝しましょう」なんていう世界ではありません。
ですから、釈尊は「チュンダの施し」を受けて「私に施されたのだから私が食べたら、土に埋めなさい」といって、「毒キノコだとわかっていながら食べたのです」ご存知のようにこれで釈尊は亡くなりました。
とにかく仏教は「時として非道徳的」な部分があります。
「無常なものごとにとらわれて、懸命に守ることすらナンセンス」だというのが基本の教えであり、「無我だから名字を入れ換えよ」といってみたり、「世間の常識や道徳ではわからない内容」が多いのです。
たとえば「無碍光如来に帰依する一心」で「浄土を観察して生きる」なんていうことも、《やりもしないで》に「難しい話しやなぁ」なんていう人も多いものです。
とにかくいろいろいう人があるけれど、「浄邦を欣ふ徒衆〜」は「謗り(そしり)」を生まないように注意して、この道を進みましょうと言われているのです。
さて、信文類の標挙(ひょうこ)には、「至心信楽の願」とあって、その内容は「正定聚の機」をあらわすとありますが、これは、本願(第十八願)は「正定聚」っていう「初地不退転地」に至る。
っていう「本願のストーリー」が、「初地不退転地」の「真実への道」であることを明確にしています。
ーーーーーーー(本日はここまでを改訂しておきます)
本文は211ページの【1】にはじまります。
ここに「往相回向」には「大信心がある」と記述し、この信心の「体」ではなく「讃」を挙げて「長生不死の神方」云々と数々の「讃」を列記されます。
このしょっぱなの「長生不死」は「脚注」にあるように《さとりの空性》のことですが、間違うと「お浄土で永遠に生きられる」と受け取ってしまいかねない《方便名》からはじめています。
しかし最終的に「真如一実の信海なり」と《さとり》に落とし込まれるのです。
これはほぼ親鸞の「方便と真実」をまぜつつ真実に誘導する論調(ロジック)です。
このように教行証文類は「真実と方便」が入り混じるので、読むときには念入りな仕分けができないと間違います。
わたしでも布教をするときに「色んな年代のひとが混在するケースでは、同じように混ぜるということをします」から「多分そういうことなんだろう」と思うのです。
たとえば、《Aパターン》で「釈尊は修行者であると同時に研究者だといえます。現代的にいえば釈尊の第1法則は《無常》の法則で、これは全てが常に変化する状態を言語化したものです」というようなことを、
ときには、《Bパターン》で砕いて、「すべてのものは常に変化する《無常》(真実)なものです。」
老病死というように(方便)移り変わっていきますよね。
お釈迦さんはこういうことを、「すべては変化し続ける」といわれているのですが、これを言葉にしないと人は意識しない(方便)ので、「無常」ということばにされた(真実)のです。」
というように対象によってAとBの言い方を使い分けます。
教行証文類も同じようなパターンを踏んでいると感じます。
さて戻って、「真如一実の信海なり。」と「真如」に落とし込むまで「讃」じられています。
そして、この往相回向の大信は、「念仏往生の願」から来るものだと、「法然」の《選択本願念仏集にある願名》をだし、あくまでも「念仏往生の願より出ているのである」と記述して、そのうえで、「往生」のところで「往相回向を案ずるに」と書き出されている「往相=往生」と、まずは第一段階を符合定義させています。
そして「この大願は。。」と進めつつ、そこで「選択本願と名づく」「本願三心の願と名づく」「至心信楽と名づく」という流れで、願の内容を「至心信楽」の「信心」に細分化していきつつ、最初の「往相の回向を案ずるに。。」から進めて「往相と信心」を再結合させて「念仏往生の願は至心信楽の願だ」と第二段階の定義をします。
そしてこの第十八願を「往相信心の願」と名づけるべきであるとして、第十八願は「信心の願だ」と最終的な定義をしています。
この辺は「法然」のいう「念仏往生の願」では、第十八願を「乃至十念」で定義しなければいけなくなり、「信心の根拠」にならないからだといえます。
続いて、しかるに「常没の凡愚〜が無上妙果を得られないわけじゃない」のだけれど「ただ真実の信楽を獲るのが難しいだけなんです」といっています。
なぜ難しいかというと「如来の増上縁のチカラによるものだから、わかりにくいでしょう」といった「まぁ普通に世間の常識を生きていると信じがたいですよ」と先手を打つロジックになっています。
とはいえ「たまたまにしろ縁あって《浄信》を得ることができれば、心が転倒することもなく、虚偽に生きることもなくなるのです」といって、信心を得れば「浄」になれることを明示し、
「だから極重悪人が大慶喜心を得て、諸々の聖尊の重愛を獲るんです」と《九条兼実や弁円などで実証された事実》に基づいて「聖尊」という「わかる人はわかっている」から、「重愛を獲られる」と記述して、「浄信」の典拠に移られます。
典拠の重要な部分が当然といえば当然の第十八願です。
ですから【2】に「至心信楽の願」として、《信心》を論じる上で重要な「本願の三心」をあらわす願名をあげて、第十八願を丸々記述されます。
次の【3】には「如来会」をひかれますが、これも四十八願経ですから同じ内容になるところがポイントです。
行文類の143ページの【9】【10】の二十四願経を引用すると、「蜎飛蠕動」まで入ってくるほか、「聞名」がポイントになり、信心に関する文言がないために、信心を論じるのには不適切だからだと推察できます。
そして【4】【5】に成就文を出されて、【4】でいえば「名号を聞く=信心歓喜=乃至一念=至心回向」と適切な文言が並び、「聞名=至心が回向されていること」という「信心の一念(信楽)は至心の回向による」としきりに「至心信楽」と言っている根拠を明確にするのです。 これが「如来会」の成就文も同じ構造になっています。
「聞名=一念=浄信=歓喜=所有の善根回向したまへる」というロジックです。
ここで「如来会」では「浄信」となっているのが、サンスクリット原典の「プラサーダ」に符合します。
如来の至心(真実心)が込められた信心なので「浄信」になるのですから「浄信」は「至心信楽」を包含した単語であり、ひとことで「至心信楽」をあらわすのです。
そして【6】において、「聞法不忘」「見敬得大慶」「即我善親友」になるから「発意せよ」と「聞く見る大慶、即我善親友」という結論を出して「信」を勧めています。
【7】においても、「この浄信に生きる人は大威徳の人で、たくさんある仏教の中から、よくこの浄土に生まれる世界に来たね」と「至心信楽」の「信心の人を讃じて」、信心の人になってくださいと勧めています。
【8】においては、「如来の功徳」「世尊の開示」「二乗を含めて他の及ばないところ」「諸有の有情、作仏する」「行は普賢を超える」「彼岸に登って一仏の功徳をひろめる【讃嘆】」「その時間はほぼ永遠である」と
今までの内容をまとめて讃じていますが、ここでポイントが出てきます。
「この中間において身は滅度すとも」とありますが、ここにも往生は「現生」とする根拠があります。
「有情作仏」して「彼岸に登って一仏の功徳を敷演せん」「時、多劫の不思議を超えん」とある時点で、すでに往生しているからです。
そして、「仏の勝慧はよく量ることなけん」という、《往生讃嘆》はすべて仏のすぐれた智慧によるからであるという理由を明記しています。
続いて、「信・聞によってもろもろの善親友の摂受を具足して」と「信と聞によって如来の願行が身につくこと」を述べて、聖尊の重愛を獲るのであるといっています。
そしてこのことは、「すべて如来の《勝智》が遍く虚空にあって、この如来の智慧の言葉《義言》はただ仏のみが悟ることだから、有情(凡夫)は《諸智土》を聞いて、如来会に説かれる教え、真如のことば(如実の言)を信ずべし」と記述されています。
ここに遍虚空の義言は「仏のみが悟る」とある部分をとらえて、「わたし達のような凡夫に仏の世界はわからない」としては間違います。
諸智土を聞いて、その言を聞信せよ。
という方便諸智土の意味をあらわす部分ですから、わからないのではなく、次の行にあるように「信慧多き時まさにいまし獲ん」とあるように、直接「遍虚空の義言はわからなくても」「諸智土を通して獲ることができる」とあるのです。
そしてこれを「信慧」としています。
次の行に「こういう妙法をすでに聴聞すれば諸仏も喜ぶ」と如来会の引用を結ばれていますから、親鸞は「一心→至心信楽→浄信→信慧」と「信に仏の智慧がそなわる」と定義づけているのです。
ですから【9】の「浄土論註」の引用で「如来のみ名を称し→光明智相の如く→名義の如く→如実修行相応」と論を進められて、「称名に光明智相がそなわり、如実修行と相応する」と明言されています。
続いて、この流れを「無碍光如来の名を称する」→仏の光明は智慧の相→光明十方に障礙なし→光明は十方衆生の無明を破る。
ゆえに無碍光如来の名号は「よく衆生の一切の無明を破り、一切の志願を満たす」のであると前提定義をしています。
この前提定義に基づいて、このようにならない人は、如実修行相応していないひとであるとされています。
そこで、如来は「真如から来生した《如実相(実相)》であること、この実相は物の為(衆生の為)の身であるとわかってない」と記述して、その理由を三不信にあらわします。
一つには「信心が淳くなく、信心があるような無いような状態だからである」といわれます。(ここで「淳」の文字の深い意味が出されていますので、味わってみてください。)
二つには「信心が一つに決定していないからである」といわれます。
三つには「信心が続かない(相続しない)からである」とされます。
そして、この三つを転がっている(三句展転する)から如実修行相応しないといっています。
これを、「信心淳からざる→決定なし→念相続しない→決定の信を得ない→心淳からざるべし」と論を通して、こうじゃないものを「如実修行相応」として「天親が《我一心》といった」のであると定義しています。
【10】には曇鸞の「讃阿弥陀仏偈」から、「阿弥陀仏の徳号を聞き、信心歓喜して聞くところを喜ばんこと、いまし一念におよぶまでせん。至心のひと回向したまへり。
《ここでいう「至心のひと」は如来の徳号(至心)を受け入れて(信心歓喜して)利他を行じているひと(聞くところを慶こぶ)》
生ぜんと願ずればみな往くことを得しむ。。。ゆえにわれ頂礼して往生を願ず」と引用しています。
この讃阿弥陀仏偈の引用が興味深いのは、これまでと違い、
「讃阿弥陀仏偈」にいはく、と記述してからあえて、「曇鸞和尚の造なり」と記述されていることです。
これは、文類として「このようにある」ではなく「曇鸞和尚も言っている」という主語を曇鸞和尚に定義して、 親鸞のいはく。。。
【9】の引用は、浄土論の解釈である論註によって「天親菩薩」のいう「無碍光如来のみ名を称する」から《三不信》を論じたのですが、なにも天親菩薩だけがいっているのではないのです。
これは、曇鸞和尚ご自身の見解も同じですから、念のために「曇鸞和尚独自の作」である「讃阿弥陀仏偈」を見てみましょう。
この通り、曇鸞和尚も「阿弥陀の徳号を聞く信心」が自利利他を行ずるかなめであるといっていますね!
ですから「信心」ということが、「すべての衆生が悟りを得るための重要なポイントだ」とわたし「親鸞」は定義するのです。といった論調です。
次からは善導によって論を展開しています。
2019/03/22[信文類を読む前に前提を解析]Plus‼️
真宗は「自力を廃して他力に依る」って言いますけど、これかて「真如実相」からいえば、「どちらもあるともないともいえます」
「無常無我、空」や「真如実相」なんかが「論理的にわかればそのまま《五念門》を行じたらいい」んです。
「それは自力行だ!」なんていうことそのものが「自力(はからい)」「分別」です。
そもそも「他力は縁起力」ですから、「自他分別のはからいを除く方向」で「法楽、真楽」を得ればいいんです。
仏教ってのは「権威や法」に《拘束する》ものではなく、「あらゆる拘束から解放される方法」です。
これが、「真理」に基づくので「法」を重視しますが、「法」は「無常無我、空」なので、《拘束》しません。
仏教に「ねばならない」はないんです。
仏教は「こう考えてこうしたらいい」っていう「論と方法」が「真理、真実」に基づくから、「あらゆる拘束を解放する」んです。
「論」がわかるなら「直(ちょく)」に「教→行→証」って進んだらいいんです。
だから「顕浄土真実《教行証》文類」なのだと思います。
けれど、「論」がわからないというひとの多い時代には、「信が必要になる」ってこと、また、重要なことは、そもそも「念仏でなぜさとりに至るか」っていうポイントを「解析して論じる」必要があったという理由で、
「信文類」を特別に分けた形で「書いてはる」んです。
「念仏でさとることができるのは、阿弥陀如来を受け入れて《破我》されるからだ!」
「それは、《信心》を通過するからだ!」って論じてはるんです。
だから「念仏」を「乃至十念」定義ではなく、「至心信楽」定義されているのだと言えます。
そういうことだから、「信文類」には「別に序文」があるんですって、これは「宗学上」でも言われています。
もちろん「現代でも」阿弥陀ストーリーの「方便則」でもいいんです。
「難しい仏教学」なんて「今さらわからん!」っていう方は、ありのまま「阿弥陀ストーリー」を受け入れる「信心」を通過した方がいいと思うのです。
つまりは「阿弥陀如来の真実心を疑蓋無雑(ぎがいむぞう)」っていう「無疑の一心」で受け入れて、ただ「自然を主」にして生きることです。
これも結果的には、ここまでの記述でいう「自我名字」を「南無阿弥陀仏名字」に入れ換えることで「名号という利他を行じること」になります。
つまり「自我」が「機の深信」で否定されて、「法の深信」で「願力に乗る」っていうことが同時(一体)ですから、「結果」⇒「破我」されて「自己の主客が入れ換わる」ことになるっていう構造です。
ですから、本来は「浄土真実教行証」でいいのですが、「信文類」を別に書き起こされたんです。
「行→証」ってスムーズにわからない、進めない人のために「信」が入るんです。
また、ほかの仏教者に「行には《信》が内在しているからさとりに至るんです」と論じているんです。
これは「事実上《行文類》の中に「信」が記述されている」ように、「行→証」と進む人にも「起こっていること」ですが、スムーズに「行→証」と進むひとには、特に説明の必要がないことです。
また、サンスクリット語原典での「信」が「浄心(プラサーダ)」である以上、「自我」ではない。
仏教で「なにを行じる」にせよ「プラサーダ(浄心)」前提でなければ、「無我の法楽」にならないんです。
大げさにいえば「仏教である以上《プラサーダ》抜きでは仏教にならない」というメッセージでもあります。
これをスムーズに「行文類」で理解できる人と「そうでない人」があるから「信文類」があるんです。
「信」について「説明を要するひと」に向けた内容が「信文類」になるようです。
しかも「阿闍世」という「極悪人を持ち出して」まで、その対象者を「唯除」として説明されます。
「唯除」は例えると「親が」「お前は出て行け」と言わなければならないほど、どうしようもない「愚者」であり、かつ「心配な子」という「除は摂取の意味」という部分こそが、「第十八願(本願)の真意」であるっていう重要ポイントです。
(ここでは「わかりやすいように」あえて「親子」で例えました。)
以上のように「行」を「自力だの他力だの」と論じることに意味はありません。
結果「自我」であるか「無我や空に向かっているか」ってことです。
☆☆☆
しかし‼️「どちらのルートを進むにせよ《外せない》のは四十八願」ですから、ゴールは同じです。
☆☆☆
極論でいうなら
「法蔵菩薩コース」(真実則)で進むか、「阿弥陀如来コース」(善巧方便則)で進むか
どっちでも「同じゴールです」ってことです。
とにかく真宗の教えを精査すると「自我=自力」「無我(破我)=他力」という意味で「自力他力」を使ってはるって解析できます。
🔴Plus3/22
《名号大行と信心正因》の矛盾。
名号が「正因」にならないのは、基本的には「無為法」(色も形もない言葉も絶えた法そのもの)だからです。
だから「増上縁」扱いです。無為法は縁にはなるからです。
しかし、主流派では「信心正因」といいます。
これは「人間」という「有為法」でなければ「因」にならない前提だからでしょう。
ならば「大行」を「名号そのもの」とする場合。
「法蔵菩薩」という「ことば、ストーリー」を設定して、その「法蔵菩薩」という「有為法に該当する存在」が《行じた》結果が「名号」だという流れが、「有為法が無為法になった」という流れだとするなら、「名号」は「ことばが意味を持つ」という「性格である以上」、「無為法」にはならないのに、これを「無為法」として扱うという「矛盾」を生みます。
つまり「名号」は「取り扱い方」によって、「阿弥陀さま」という「実体概念になる存在」としての「可能性」を持つからです。
わかりやすく言えば「十九願、二十願」という状態を生む可能性を持つ「存在の状態」を完全「無為法」とはいえません。
それを「受け取る側の問題」といいたくても、「行」は「有為法」がなければ成立しません。
「名号大行が、果位の上で《利他》を行じている」として「完全無為法」のように錯覚しますが、「利他」を行じる以上、「迷界の存在がいなければ《利他》そのものが成立しません」
つまり、「迷いの存在」がいない以上「名号は存在できない」のです。
「成就文」の有無に関わらず「設我得仏〜不取正覚」のままになります。
「名号が出来ました」といっても「迷界の人間(衆生)」がいない場合」には「存在」になれず、また「実体概念」になる可能性がある以上「有為法」扱いです。
結果「名号大行」は「名号単独では存在できない」ということです。
「信心が正因」なのは「正因」は「人間の側」でしか言えないからというのは「理にかなって」います。
しかし「行」も「受け入れる迷界の人間などの衆生」が存在しないと成り立たない、しかも、「ことば」である以上「対象者」は人間です。だから「人間を離れた《利他行》は無意味」になる。
つまり「大行」は「法体」で語れないから「讃嘆門」の「称無碍光如来名」という「人間」の側からしか語れません。
☆☆☆だから「法蔵菩薩のように行じる」が「真実則」で、「二種深信のように名号に破我される」が「方便則」になります。☆☆☆
スタートから「仏教学」的に「無常無我、空」を理解できて、法蔵菩薩として「讃嘆行をメインに五念門、五果門」を行じて生きる。
または、難しいことはわからないから、「南无阿弥陀仏」がわたしの主体であり、「世俗名」は客体であるという「破我」の歩みを生きる。
のどっちをを歩むかというのが「教行証文類」が言ってることです。
しかし、共通するのは「受け入れる」→「信心」です。
これが「真実則」の人は「仏教学」を通して「スムーズ」なので、それほど「テーマ」になりません。
しかし「方便則」のひとにすれば「重要ポイント」だと「強調」しなければならないので、「信文類」が別立てで「論じられている」といえます。
現代は「その両方のひと」が混在します。
むかしは「方便則」のひとが多かったということは「想像に難くありません」けれど、現代に「方便則」ばかりでは、逆に「受け入れないひと」が多くなっています。
そこで「内容」に戻ります。
ーーーここから下は書きかけです。(5−2になる予定です)
さて戻って、「真如一実の信海なり。」と「真如」に落とし込むまで「讃」じられています。
そして、この往相回向の大信は、「念仏往生の願」から来るものだと、「法然」の《選択本願念仏集にある願名》をだし、あくまでも「念仏往生の願より出ているのである」と記述して、そのうえで、
「往生」のところで「往相回向を案ずるに」と書き出されている「往相=往生」と、まずは第一段階を符合定義させています。
そして「この大願は。。」と進めつつ、そこで「選択本願と名づく」「本願三心の願と名づく」「至心信楽と名づく」という流れで、願の内容を「至心信楽」の「信心」に細分化していきつつ、最初の「往相の回向を案ずるに。。」から進めて「往相と信心」を再結合させて「念仏往生の願は至心信楽の願だ」と第二段階の定義をします。
そしてこの第十八願を「往相信心の願」と名づけるべきであるとして、第十八願は「信心の願だ」と最終的な定義をしています。
この辺は「法然」のいう「念仏往生の願」では、第十八願を「乃至十念」で定義しなければいけなくなり、「信心の根拠」にならないからだといえます。
続いて、しかるに「常没の凡愚〜が無上妙果を得られないわけじゃない」のだけれど「ただ真実の信楽を獲るのが難しいだけなんです」といっています。
なぜ難しいかというと「如来の増上縁のチカラによるものだから、わかりにくいでしょう」といった「まぁ普通に世間の常識を生きていると信じがたいですよ」と先手を打つロジックになっています。
とはいえ「たまたまにしろ縁あって《浄信》を得ることができれば、心が転倒することもなく、虚偽に生きることもなくなるのです」といって、信心を得れば「浄」になれることを明示し、
「だから極重悪人が大慶喜心を得て、諸々の聖尊の重愛を獲るんです」と《九条兼実や弁円などで実証された事実》に基づいて「聖尊」という「わかる人はわかっている」から、「重愛を獲られる」と記述して、「浄信」の典拠に移られます。
典拠の重要な部分が当然といえば当然の第十八願です。
ですから【2】に「至心信楽の願」として、《信心》を論じる上で重要な「本願の三心」をあらわす願名をあげて、第十八願を丸々記述されます。
次の【3】には「如来会」をひかれますが、これも四十八願経ですから同じ内容になるところがポイントです。
行文類の143ページの【9】【10】の二十四願経を引用すると、「蜎飛蠕動」まで入ってくるほか、「聞名」がポイントになり、信心に関する文言がないために、信心を論じるのには不適切だからだと推察できます。
そして【4】【5】に成就文を出されて、【4】でいえば「名号を聞く=信心歓喜=乃至一念=至心回向」と適切な文言が並び、「聞名=至心が回向されていること」という「信心の一念(信楽)は至心の回向による」としきりに「至心信楽」と言っている根拠を明確にするのです。
これが「如来会」の成就文も同じ構造になっています。
「聞名=一念=浄信=歓喜=所有の善根回向したまへる」というロジックです。
ここで「如来会」では「浄信」となっているのが、サンスクリット原典の「プラサーダ」に符合します。
如来の至心(真実心)が込められた信心なので「浄信」になるのですから「浄信」は「至心信楽」を包含した単語であり、ひとことで「至心信楽」をあらわすのです。
そして【6】において、「聞法不忘」「見敬得大慶」「即我善親友」になるから「発意せよ」と「聞く見る大慶、即我善親友」という結論を出して「信」を勧めています。
【7】においても、「この浄信に生きる人は大威徳の人で、たくさんある仏教の中から、よくこの浄土に生まれる世界に来たね」と「至心信楽」の「信心の人を讃じて」、信心の人になってくださいと勧めています。
【8】においては、「如来の功徳」「世尊の開示」「二乗を含めて他の及ばないところ」「諸有の有情、作仏する」「行は普賢を超える」「彼岸に登って一仏の功徳をひろめる【讃嘆】」「その時間はほぼ永遠である」と
今までの内容をまとめて讃じていますが、ここでポイントが出てきます。
「この中間において身は滅度すとも」とありますが、ここにも往生は「現生」とする根拠があります。
「有情作仏」して「彼岸に登って一仏の功徳を敷演せん」「時、多劫の不思議を超えん」とある時点で、すでに往生しているからです。
そして、「仏の勝慧はよく量ることなけん」という、《往生讃嘆》はすべて仏のすぐれた智慧によるからであるという理由を明記しています。
続いて、「信・聞によってもろもろの善親友の摂受を具足して」と「信と聞によって如来の願行が身につくこと」を述べて、聖尊の重愛を獲るのであるといっています。
そしてこのことは、「すべて如来の《勝智》が遍く虚空にあって、この如来の智慧の言葉《義言》はただ仏のみが悟ることだから、有情(凡夫)は《諸智土》を聞いて、如来会に説かれる教え、真如のことば(如実の言)を信ずべし」と記述されています。
ここに遍虚空の義言は「仏のみが悟る」とある部分をとらえて、「わたし達のような凡夫に仏の世界はわからない」としては間違います。
諸智土を聞いて、その言を聞信せよ。
という方便諸智土の意味をあらわす部分ですから、わからないのではなく、次の行にあるように「信慧多き時まさにいまし獲ん」とあるように、直接「遍虚空の義言はわからなくても」「諸智土を通して獲ることができる」とあるのです。
そしてこれを「信慧」としています。
次の行に「こういう妙法をすでに聴聞すれば諸仏も喜ぶ」と如来会の引用を結ばれていますから、親鸞は「一心→至心信楽→浄信→信慧」と「信に仏の智慧がそなわる」と定義づけているのです。
ですから【9】の「浄土論註」の引用で「如来のみ名を称し→光明智相の如く→名義の如く→如実修行相応」と論を進められて、「称名に光明智相がそなわり、如実修行と相応する」と明言されています。
続いて、この流れを「無碍光如来の名を称する」→仏の光明は智慧の相→光明十方に障礙なし→光明は十方衆生の無明を破る。
ゆえに無碍光如来の名号は「よく衆生の一切の無明を破り、一切の志願を満たす」のであると前提定義をしています。
この前提定義に基づいて、このようにならない人は、如実修行相応していないひとであるとされています。
そこで、如来は「真如から来生した《如実相(実相)》であること、この実相は物の為(衆生の為)の身であるとわかってない」と記述して、その理由を三不信にあらわします。
一つには「信心が淳くなく、信心があるような無いような状態だからである」といわれます。(ここで「淳」の文字の深い意味が出されていますので、味わってみてください。)
二つには「信心が一つに決定していないからである」といわれます。
三つには「信心が続かない(相続しない)からである」とされます。
そして、この三つを転がっている(三句展転する)から如実修行相応しないといっています。
これを、「信心淳からざる→決定なし→念相続しない→決定の信を得ない→心淳からざるべし」と論を通して、こうじゃないものを「如実修行相応」として「天親が《我一心》といった」のであると定義しています。
【10】には曇鸞の「讃阿弥陀仏偈」から、「阿弥陀仏の徳号を聞き、信心歓喜して聞くところを喜ばんこと、いまし一念におよぶまでせん。至心のひと回向したまへり。
《ここでいう「至心のひと」は如来の徳号(至心)を受け入れて(信心歓喜して)利他を行じているひと(聞くところを慶こぶ)》
生ぜんと願ずればみな往くことを得しむ。。。ゆえにわれ頂礼して往生を願ず」と引用しています。
この讃阿弥陀仏偈の引用が興味深いのは、これまでと違い、「讃阿弥陀仏偈」にいはく、と記述してからあえて、「曇鸞和尚の造なり」と記述されていることです。
これは、文類として「このようにある」ではなく「曇鸞和尚も言っている」という主語を曇鸞和尚に定義して、親鸞のいはく。。。
【9】の引用は、浄土論の解釈である論註によって「天親菩薩」のいう「無碍光如来のみ名を称する」から《三不信》を論じたのですが、なにも天親菩薩だけがいっているのではないのです。
これは、曇鸞和尚ご自身の見解も同じですから、念のために「曇鸞和尚独自の作」である「讃阿弥陀仏偈」を見てみましょう。
この通り、曇鸞和尚も「阿弥陀の徳号を聞く信心」が自利利他を行ずるかなめであるといっていますね!
ですから「信心」ということが、「すべての衆生が悟りを得るための重要なポイントだ」とわたし「親鸞」は定義するのです。といった論調です。
次からは善導によって論を展開しています。
2019/03/29[5−2]
信文類は、多くの「讃」のあと、「真如一実の信海なり。」と「真如」に落とし込まれます。
あくまでも「色も形もなく、言葉も絶えた」「真如」前提です。
そして、この往相回向の《大信》は、「念仏往生の願」から来るものだと、「法然」の《選択本願念仏集にある願名》をだし、あくまでも「念仏往生の願より出ているのである」と記述しています。
しかしここで「乃至十念」定義ではなく「至心信楽」定義にされていることがポイントです!
(真如前提だからといえます。)
その後の「往生」のところで「往相回向を案ずるに」と書き出されている「往相=往生」と、まずは第一段階を符合定義させています。
そして「この大願は。。」と進めつつ、そこで「選択本願と名づく」「本願三心の願と名づく」「至心信楽と名づく」という流れで、
願の内容を「至心信楽」の「信心」に細分化していきつつ、最初の「往相の回向を案ずるに。。」から進めて「往相と信心」を再結合させて「念仏往生の願は至心信楽の願だ」と第二段階の定義をします。
そしてこの第十八願を「往相信心の願」と名づけるべきであるとして、第十八願は「信心の願だ」と最終的な定義をしています。
この辺は「法然」のいう「念仏往生の願」では、第十八願を「乃至十念」で定義しなければいけなくなり、「信心の根拠」にならないからだといえます。
続いて、しかるに「常没の凡愚〜が無上妙果を得られないわけじゃない」のだけれど「ただ真実の信楽を獲るのが難しいだけなんです」といっています。
なぜ難しいかというと「如来の増上縁のチカラによるものだから、わかりにくいでしょう」といった「まぁ普通に世間の常識を生きていると信じがたいですよ」と先手を打つロジックになっています。
とはいえ「たまたまにしろ縁あって《浄信》を得ることができれば、心が転倒することもなく、虚偽に生きることもなくなるのです」といって、信心を得れば「浄(涅槃の徳)」になれることを明示しています。
そして事実も基づいて、「だから極重悪人が大慶喜心を得て、諸々の聖尊の重愛を獲るんです」と《九条兼実や弁円などで実証された事実》に基づいて「聖尊」という「わかる人はわかっている」から、「重愛を獲られる」と記述して、「浄信」の典拠に移られます。
典拠の重要な部分が当然といえば当然の第十八願です。
ですから【2】に「至心信楽の願」として、《信心》を論じる上で重要な「本願の三心」をあらわす願名をあげて、第十八願を丸々記述されます。
次の【3】には「如来会」をひかれますが、これも四十八願経ですから同じ内容になるところがポイントです。
行文類の143ページの【9】【10】の二十四願経を引用すると、「蜎飛蠕動」まで入ってくるほか、「聞名」がポイントになり、信心に関する文言がないために、信心を論じるのには不適切だからだと推察できます。
事実上「聞名は信心になる」のですが、「真実則」なのでここでは「方便則」を示しています。
そして【4】【5】に成就文を出されて、【4】でいえば「名号を聞く=信心歓喜=乃至一念=至心回向」と適切な文言が並び、「聞名=至心が回向されていること」という「信心の一念(信楽)は至心の回向による」としきりに「至心信楽」と言っている根拠を明確にするのです。
これが「如来会」の成就文も同じ構造になっています。
「聞名=一念=浄信=歓喜=所有の善根回向したまへる」
というロジックです。
ここで「如来会」では「浄信(法楽)」となっているのが、サンスクリット原典の「プラサーダ」に符合します。
如来の至心(真実心)が込められた信心なので「浄信」になるのですから「浄信」は「至心信楽」を包含した単語であり、ひとことで「至心信楽」をあらわすのです。
そして【6】において、「聞法不忘」「見敬得大慶」「即我善親友」になるから「発意せよ」と「聞く見る大慶、即我善親友」という結論を出して「信」を勧めています。
【7】においても、「この浄信に生きる人は大威徳の人で、たくさんある仏教の中から、よくこの浄土に生まれる世界に来たね」と「至心信楽」の「信心の人を讃じて」、信心の人になってくださいと「法楽」を得ることを勧めています。
【8】においては、「如来の功徳」「世尊の開示」「二乗を含めて他の及ばないところ」「諸有の有情、作仏する」「行は普賢を超える」「彼岸に登って一仏の功徳をひろめる【讃嘆】」「その時間はほぼ永遠である」と
今までの内容をまとめて讃じていますが、ここでポイントが出てきます。
☆☆☆
「この中間において身は滅度すとも」とありますが、ここにも往生は「現生」とする根拠があります。
「有情作仏」して「彼岸に登って一仏の功徳を敷演せん」「時、多劫の不思議を超えん」とある時点で、すでに往生しているからです。
そもそも「浄土教」においては「浄土往生」後の話を、親鸞さんは、「現生正定聚」に定義しなおしている以上「現生」の話としなければ、「中間に身は滅度するも」という文言が、
「往生即成仏」を説き、「現生正定聚」定義している以上は成り立たなくなります。 ☆☆☆
そして、「仏の勝慧はよく量ることなけん」という、《往生讃嘆》はすべて仏のすぐれた智慧によるからであるという「方便則」の理由を明記しています。
続いて、「信・聞によってもろもろの善親友の摂受を具足して」と「信と聞によって如来の願行が身につくこと」を述べて、聖尊の重愛を獲るのであるといっています。
そしてこのことは、「すべて如来の《勝智》が遍く虚空にあって、この如来の智慧の言葉《義言》はただ仏のみが悟ることだから、
【有情(凡夫)は《諸智土》を聞いて、如来会に説かれる教え、真如のことば(如実の言)を信ずべし】と記述されています。
ここに「遍虚空の義言」は「仏のみが悟る」とある部分をとらえて、「わたし達のような凡夫に仏の世界はわからない」としては間違います。
あくまでも「方便則」において。「以下の二種深信」につないでいくためです。
とにかく【諸智土を聞いて、その言を聞信せよ。】
という《方便諸智土の意味》をあらわす部分ですから、わからないのではなく、次の行にあるように「信慧多き時まさにいまし獲ん」とあるように、直接「遍虚空の義言はわからなくても」「諸智土を通して獲ることができる」ということです。
そしてこれを「信慧」としています。
次の行に「こういう妙法をすでに聴聞すれば諸仏も喜ぶ」と如来会の引用を結ばれていますから、親鸞は「一心→至心信楽→浄信→信慧」と「信に仏の智慧がそなわる」と定義づけているのです。
☆☆☆
ですから【9】の「浄土論註」の引用で「如来のみ名を称し→光明智相の如く→名義の如く→如実修行相応」と論を進められて、「称名に光明智相がそなわり、如実修行と相応する」と明言されています。
続いて、この流れを「無碍光如来の名を称する」→仏の光明は智慧の相→光明十方に障礙なし→光明は十方衆生の無明を破る。
ゆえに無碍光如来の名号は「よく衆生の一切の無明を破り、一切の志願を満たす」のであると前提定義をしています。
この前提定義に基づいて、このようにならない人は、如実修行相応していないひとであるとされています。
そこで、如来は「真如から来生した《如実相(実相)》であること、この実相は物の為(衆生の為)の身であるとわかってない」と記述して、その理由を三不信にあらわします。
☆☆☆《このように「無碍光如来の名を称する」こそが、「仏教と相応する真実則」と定義しています。
一つには「信心が淳くなく、信心があるような無いような状態だからである」といわれます。(ここで「淳」の文字の深い意味が出されていますので、味わってみてください。)
二つには「信心が一つに決定していないからである」といわれます。
三つには「信心が続かない(相続しない)からである」とされます。
そして、この三つを転がっている(三句展転する)から「如実修行相応しない」といっています。
これを、「信心淳からざる→決定なし→念相続しない→決定の信を得ない→心淳からざるべし」と論を通して、こうじゃないものを「如実修行相応」として「天親が《我一心》といった」のであると定義しています。
【10】には曇鸞の「讃阿弥陀仏偈」から、「阿弥陀仏の徳号を聞き、信心歓喜して聞くところを喜ばんこと、いまし一念におよぶまでせん。至心のひと回向したまへり。
《ここでいう「至心のひと」は如来の徳号(至心)を受け入れて(信心歓喜して)利他を行じているひと(聞くところを慶こぶ)》と、「方便則」の「至心」に起こる「利他行」を「明確」にして、「生ぜんと願ずればみな往くことを得しむ。。。ゆえにわれ頂礼して往生を願ず」と引用しています。
この讃阿弥陀仏偈の引用が興味深いのは、これまでと違い、「讃阿弥陀仏偈」にいはく、と記述してからあえて、「曇鸞和尚の造なり」と記述されていることです。
これは、文類として「このようにある」ではなく「曇鸞和尚も言っている」という主語を曇鸞和尚に定義しています。
☆☆☆
ここで「先の《無碍光如来》の真実則」が「方便則」に変化することを「明らかにして」います。
親鸞のいはく。。。
【9】の引用は、浄土論の解釈である論註によって「天親菩薩」のいう「無碍光如来のみ名を称する」から《三不信》を論じたのですが、なにも天親菩薩だけがいっているのではないのです。
これは、曇鸞和尚ご自身の見解も同じですから、「方便則」から「曇鸞和尚独自の作」である「讃阿弥陀仏偈」を見てみましょう。
この通り、曇鸞和尚も「阿弥陀の徳号を聞く信心」が「利他を行ずるかなめ」であるといっていますね!
ですから「信心」ということが、「すべての衆生が悟りを得るための重要なポイントだ」とわたし「親鸞」は定義するのです。
次からは善導によって論を展開しています。
2019/04/05[5−3]
216ページの【11】から、善導さんになりますけど、「曇鸞さん」の引用について。。
「曇鸞さん」を行文類では、「真実則」から「法蔵菩薩モデルコース」っていう観点から引用していました。
つまり「無碍光如来」を《讃嘆している諸仏の讃嘆》を《聞信して》わたしも諸仏のように《讃嘆を行じるものになる》ことが、「五念門」を行じる「行者」になる「法蔵菩薩とともに功徳荘厳を成就する行者になる」っていう「法蔵菩薩モデルコース」をあきらかにする「真実則」で引用されてきました。
しかし「信文類」では、「曇鸞さん」を「方便側面」から引用して、【10】で定義する《阿弥陀の徳号》を「聞きて信心歓喜」することが、《実のごとく》《名義と相応》するってことを論じるために、まず【9】に《光明智相の如く、名義の如く、実の如く》【称名】するために《重要なポイント》として、「三種の不相応」って書いて「三不信」を記述して、「信心の重要性」を書いてはります。
この「三不信」の文言については以前[3−1][3−2]に書いてるので、いまは文言の詳細は置いといて、
「まずは《不信》があれば《実のごとく修行できない》《名義と相応しない》ってこと」を明確にするために、曇鸞さんを引用しています。
「曇鸞さん」もいうてるように、「不信」状態では「ダメです」ねんって書いてはるんです。
そして【10】に「阿弥陀の徳号を聞いて、信心歓喜して。。。一念におよぶまでせん」
「至心のひと回向したまへり。。」て「信心が要りますねん」って信心の重要性に誘導しています。
ここで「論註」を引用して「一心」を「一念」に置き換えていることは「ポイント」です。
また、この文言に「唯除五逆、誹謗正法。。。」までに引用が及んでいるのは、これ以後「信文類」に記述される「結論までを簡潔に引用」しているからだと推察できます。
そしてここから【11】に「善導さん」を引用して、「信心」を《こと細かく》論じられるんです。
この【11】にまず「如意」ってありますけど、よく「如意棒」なんて「孫悟空」なんかでいわれるように、これは「思うままに」っていう意味で使われる言葉ですけど、ここでは「真如から来生」した「如来の意のまま」にと読む方が「深い意味」が理解できると思います。
つまり「如来」は意のままに、「衆生のこころや思いに応じて、弥陀がその意のまま」に「さとらせなきゃいけない衆生を観て、その衆生のところへ《一念》を《前後なく》《身心等しく》っていう状態で赴いて、さとりの利益を与えます。」って書いてます。
ここにある「一念を前後なく身心等しく」っていう文言は、このあとに進むに従って論じていく「阿弥陀が至心っていう《真実心》を衆生に《回向(振り向ける)》こと」と「それを《信の一念》」っていう「信楽(しんぎょう)」から「欲生」への意味を「暗示」しているように思えます。
少し具体的にいえば「如来の意」を「信の《一念》」で受け入れる「信楽」の一心は「時間軸の《前後》」にこだわる性質のものではなく、《身も心も等しく》阿弥陀の意に「無疑」になるっていう【50】や【60】の内容を「暗示」しています。
そして【12】からの部分を、この講義の[3−2]では、「さとりへの誘導対象を確認してる」って書きましたが、「阿弥陀如来乗託コース」っていう観点から読むと、この辺りから「ボチボチ」《二種深信がスタート》しているようで、「みんな《五濁、五苦、六道》に逼悩(ひつのう)してますやろ」って「逼悩」っていうのは「さしせまる、狭まる」ことですから、けっこう「追い詰められてますやろ」っていう感じで、「凡人(凡数)」であるあなたは「そういう状況でしょ!」って感じで、「人間の状態を認識させて」います。
この辺から、けっこう「危機感を自覚させる感じ」「無自覚な危機的状況を自覚させる感じ」で論が進んでいきます。
🔴ここからです❣️
2019/04/08[5−4]
「逼悩」っていう「さしせまる、狭まる」苦悩の中にいる「凡夫」は、この苦を受けないように[3−2]で書いたように、「必生彼国」って「浄土に生まれたらいいねん」から、「三心」のプロセスを経たら「浄土に生まれられて、「逼悩」から「解放されますよ」っていう内容になっています。
そこで「仏の真実心(至誠心)」について書いてて、「二つには(二者)深心」ってところから、218ページの後ろ4行目には「真の仏弟子」って書いてて、ここには「わたしたちも《仏の捨てたものを捨てて、仏が行じたものを行じて、仏が去らしめた処を去る》」っていう感じで「仏願に随順する」ことですよ❣️
そうやって「行を深信」すれば、間違うことはないです!って書いてます。
詳細は[3−2]に書いてるから省きますけど、この論の流れは、こういうことです。
特に、ここに「二種深信」について書かれてて、わたしが苦悩から離れるために「向かうべき状態」について書かれてます。
この「二種深信」に、「曠劫(むちゃくちゃ昔から)いまに至るまで、つねに没して、つねに流転してそこから出るも離れるもできないわたしだから」仏願に従えば、「間違いない」って書いてるんです。
この「話し」を聞くまでもなく「無常無我、空」に背いて生きてるんやから、苦しむってわかるなら、あえて「二種深信」は不要です❣️
そして、仏願に随順するってのは「一心に弥陀の名号を専念すること」って定義されますけど、
これが「号」っていう「果位」である以上、ここには「利他」ることが「内在」されてます。
だからこの辺に「十方諸仏が弥陀の名号を称念して、衆生を勧励(かんれい)して往生を得る」って「讃嘆」するんです。っていうように、「名号の称念」が「果位」として「利他」ることが書かれてるんです。
そして「三者回向発願心」に移って、「得生の想いをしなさい」って「浄土に生まれているっておもって生きたら、違う見解やなんかに迷わされなくなる、振り回されなくなる」ってことを明確にしてます。
だから「現生往生」が基本にならへんかったら「間違う」んです。
221ページ後ろ4行目からの問答は、
「この教えに疑問を呈して、そんなんで往生できるかいな!」「今までいっぱい罪を作ってきて、それが除かれてもいないのに、三悪道にしか行かへんって!」「そんだけ罪が深いのになんで《無漏無生》の状態(国)に入って、さとりを得るなんてありえへん」って思いますねん。
っていう、基本的な仏教の「同類因、等流果」で考えるべきなんちゃんますか?って問いが書いてあって、
回答には、「諸仏の教えも行も数限りなくあって、さとり「という認識」を得る機縁は「一つじゃないんです」たとえば「世俗の人が見てるものを信じるけど」それらはみんな「法の中」だから「待対の法」っていうて、「絶対的な観点じゃあなくて《相対的な不確定な見方》で千差万別」ですねん‼️
って「見てるものを誤認したり、それぞれの限定的な観点」だから「仏法不思議の力」が「種々にいろんな利益がある」ことが分からへんのんです。
だから「仏法は、それぞれの状態に従って、それぞれの状態に応じた《解脱智慧の門》がありますねん」だから「縁に随順して、行を起こして解脱を求めたらええんです」
「眼を過去に向けるんやなくて、過去が罪深いって思うんなら、なおさらさとりっていう前向いて《所愛(求めるところ)》は、「縁がある行」なんだから、「縁と願い(楽)」に随がって、「その行を行じたらええ」んです。
そして「行者」になって「学べば」「さわりない(無碍)」になるんです。
って書いてますけど、これが、「ただ念仏を称える」教えの構造にある「称える身になったら《学ぶものになる》」っていう「念仏のシステム」なんです。
って感じで、「罪深いこと」が「さとりへ向かう念仏行者になる方向づけになって、学ぶものになること」を「方便則」で語っています。
ここで「有名」な「二河白道」の譬えが記述されます。
これはあまりにも「知られています」し「完全方便則」の譬えなので、あえて「省きます」けど、「白道四、五寸」っていうのは、「衆生が《清浄願往生の心を生ませることに譬えられている》」とするなら、「貪欲、瞋恚」の「水と火」が「強い」ことをあらわしているっていうことですから、「清浄願往生の心が強くなる」と「四、五寸がじつはむちゃくちゃ広かった」ってわかります。
どれだけ「水(貪欲)」や「火(瞋恚)」が、白道に覆いかかってきても、白道を進んでいれば、「水も火にも落ちることがない」ってわかるからです❣️
白道を進み始めたら「不退転」だってわかるから、「水や火の河」も「白道」だったってわかるんです‼️
とにかく「僧侶や同行」という「行者」である以上、「真実則」の「法蔵菩薩モデル」で五念門を行じるにせよ、「方便則」の「白道コース(阿弥陀如来乗託)」で称念するにせよ、進むしかないのですから、「白道があるんです」っていう「法話」ではなく、「白道の上を進んでます」っていう「法話」でなければ「意味」がありません。
「戯論(お遊びの論を話している)」にしかならないんです。
結果227ページの真ん中らへんに「三心をすでにをなえたら、行が成る」「願行が成る」そして「浄土に生きる」っていう「ことわり」があるってわかって、なおかつ「どんなすぐれた行にも通じる」ってまとめてはります。
ここに「定善の内容をおさめている」(通摂)って書いてるのは、「返って《定善》の行以上の行である」っていうてはるようです。
続く【14】も、「このように一切往生の知識(往生してそこを生きている行者)」に「慚愧すべし」って書いてるのも「二種深信」を意味していて、「釈迦が善巧方便で私たちに無上の信心を起こさせる方法」として「説いたんです」って、「方便則」定義をしています。
2019/04/17[5−5]
227ページの【14】に「慚愧によって、。。。《種々の善巧方便》によって、我らが無上の信心を発起する」って書いてあって、【15】にも「慚愧」によって「深心」という「真実の信心」が得られる。
そして「善根薄少」で「火に覆われた家から出られない」まま流転していると知って、「名号を称する」ことで「往生」する。このことに「疑心」がないから「深心」って言います。
そしてこの「一心」を至せば「往生を得る」って、つまりは「二種深信」が「善巧方便」のポイントであるって書いてます。
【16】の往生要集の引用も「一心」をクスリにたとえています。
そして【17】において、これは見えない「摂取の光明」だけれど、それは「煩悩に眼がさえぎられているから」で、「大慈悲の光明は飽きることなく照らしています」って書いています。
この部分は、「あくまでも善巧方便」ですから、ここの論調は「論」というより、「情」に訴えかける「こういうことです!」といった、多少「強引な流れ」になっています。
【18】には、行文類、信文類で記述している「行信ともに」「阿弥陀如来の清浄願心」によって回向されたものであって「これが因になって往生する」のだから「ほかの因があるわけではない」んです。
って、「方便則」で「阿弥陀如来の」という「人格表現」されています。
本来ここは、「真実則」でいえば、「法蔵菩薩の清浄願心」となり、「その願心」をよりどころにして「五念門行」を行じることが、本来、天親さんがいっている「世尊我一心、帰命尽十方無碍光如来、願生安楽国」になります。
けれど、ここでは【19】の問答によって、天親さんの「一心」は、第十八願の「至心信楽欲生」の「三心」を「信楽」の「一心」(疑蓋無雑)に「圧縮して」表現されているのであり、けっきょく天親さんの「世尊我一心」は「信楽」のことです。っていう論調で、「真実則」と「方便則」を同じゴールに設定しています。
この【20】の部分は[3−6]に記述しましたから、ここでは「省きます」が、【21】の部分でも、「機(人間種)の愚かさ」を徹底して記述して、「如来が与えてくれた《真実心》」を利他の真実心として「疑蓋無雑」の(信楽)で受け入れることがポイントで、この「真実心」は「至徳の尊号」です。
って書いてはるんですが、[3−7]に書きましたが、「尊号」という「理屈抜きで尊い」と記述して、しかも「有為法」であるかのように「その体」と書かれているのは「方便則」だからと言えます。
とにかく信文類の「三心釈」といわれているこのあたりの部分は、「人間種は真実心がない」という「無常無我、空」を抽象概念がわからない人向けに「阿弥陀如来という善巧方便」を使って、「至心」または「至誠心」を受け入れることを強調しています。
これは、「結果」《二種深信》を論じていて、「方便則」からしか「さとりに向かえない人」に向けて「あえて」設定された論点であると言えます。
ここまでには、「人間種(機)の愚かさに対する真実心」について書かれていますが、【22】からは、「至心」がどういうものかということについて詳しく述べています。
ただしこのあたりは「善導によっていて」人格表現で阿弥陀如来を表しているので、「有為法表現」です。
ですから、【25】においては「釈尊と善導さん」というペアで、「真実心=至心」と定義しています。
しかし【26】には、「涅槃経」によって「最終的に仏性を真実」として、「真実則」定義されています。
そして【27】からは、「至心」を受け入れる「信楽のあり方」に論を進めて、詳説していかれます。
🔵いずれにせよ「信文類」は、「二種深信」前提で解説されていますので、全面的に「善巧方便」について書かれているということは、一貫しています。
|
教行証文類講義その4 |
234ページの【25】で「真実心」は「至心」であると定義されます。
そして【26】に「真実」とは何かを定義するために「涅槃経」を引用しています。
そこで「真実」を「実諦」という「無為法、無漏法身」のさとりの「法」に定義するために、
「実諦」について、「一道清浄」と略して「一道」が「清浄」であるという引用をしています。
ここの「二あることなし」という文言は、本来は「一如」を意味して、「一即一切」の意味も重ねつつ、「至心」という「イチ」であると読めます。
つまりこの辺りは「至心は真実心で実諦で一道清浄」であり「他にはない《二あることなし》」って読むのが普通でしょう。
このように表面的には「至心は実諦であり、これ一つである」と記述して、「至心」という「一道」しかないと論じているようですが、ここは「至心をさとりの無為法」に定義されているので、
「一道清浄、二あることなし」は「一道は一如で一即一切」であると読んでも問題はなく、かえってそう読む方が、つぎの「真実というはすなわちこれ如来なり」という変化に違和感がなく、
また、「如来は真実」「真実は虚空」「虚空(無為)は真実」「真実は仏性」「仏性は真実」という流れになる意味が読み込めます。
改めて、ここでこのような定義をしているのは、ここまでの「善巧方便」の根本が「無為法」であることを定義していると考えられます。
そして【27】で、「不簡内外明闇」の部分に、「如来は世間の無明の闇を明確にする《光明》しかも《智慧の光明》《智明》であり出世である」と引用して、「如来」という文言について、
「阿弥陀如来」という「方便人格」は「有為法」ではないことを「論が逸れないよう」に改めて定義しています。
ここまでに「如来」を「阿弥陀如来」に「方便定義してきた」ようであるけれど、この「如来」は、「真実無為法《出世間の法》」そのものの「光明」であると「改めて明確」にして、「至心」を「無為法」であると「仏教の原則」から外れないように論じています。
そもそも「さとりの法」を「善巧方便」であらわす中で「自性唯心」や「ファンタジー」「スピリチュアル」と「誤解」しないように、このように「論」が逸れないように配慮していることは、「信文類」を読む上で「重要な観点」です。
2019/04/25[5−7]
【28】からは、「信楽」について記述されます。
これは、第十八願の「至心信楽欲生」の三信の2番目について解説されています。
冒頭に「如来の満足大悲」という「大慈悲が満たされている」という「有為法表現(方便則)」をおき、その根拠として「円融無碍」という「華厳の法界縁起」をあらわしているような「真実則」表現を置いて、「真実の理法が、大慈悲に満たされている」という、「方便則の阿弥陀の教えには、真実則の智慧(無碍)が根底にある」ということを明確にされています。
そして、このように「真実が込められている善巧方便の大慈悲」が「信心海」であると明確化しています。
ここで、親鸞聖人は、このような「真実が込められている大慈悲」を「疑蓋間雑(ぎがいけんぞう)あることなし」という「疑いない状態で受け入れる」から「信楽」と名づく。
とありますが、これは、「円融無碍[の]」とある「の」を「満足大悲円融無碍」に「ついて」《信心海》になる。という意味で「の」が使われているであろうと推察します。
であるが故に、この「利他回向の至心」が「信楽の体」という定義が成立します。
ここでいう「体」というのは「本質」という意味で「理解していただけば良いと考察します。
そして続いて「しかるに無始よりこのかた」〜「一切群生海には至心も信楽もなく(真実の信楽なし)云々」とここでも「海」を使っていますが、「群生海」が「信心海」に転じることを包含しながら、
人間が迷いの中を転じてきていることを述べて、「人間の善行など」は、「真実の業(行ない)」とも言いがたく「虚仮雑毒の善」と定義して、このようないわゆる「自我行(自力)」では、真仏土と規定される「無量光明土」に至れないと確定定義しています。
ここにその理由として「如来が菩薩だった時には、三業の修行も、その他においても《一念も一刹那も》《疑蓋まじわることがなかった》からである」としています。
このように(阿弥陀)如来は「苦悩の衆生を救いたい一心で行をされた」ので、「如来自身が[疑蓋まじわる]ことがなかった」から、衆生が「大悲心」を受け入れることが「法蔵菩薩因位」に報われた「報土」の「正定の因」になると「方便則」のストーリーについて言及されています。
簡潔に言えば「如来は苦悩の衆生を救いたいという真実心で《悲憐》して「無碍広大」の「浄信」をもって、衆生の「所有海」に「振り向けてくださったのだ」ということから「利他真実の信心」と名づくとあります。
これは、私たち人間には「浄心(プラサーダ(澄浄))」の心はないから、この「信楽」によって「信心」を得て「浄信(浄の心)」になり、「利他真実の信心に生きるようになる」という、「方便則」のストリーに込められている意味は「このようなことである」と言っているのです。
2019/04/30[5−8]
ここまで【28】に、「信楽」の意味と、その効果を証明されてきました。
ここで「ここまでの内容が成就されている」ことを【29】から解釈されて行きます。
ここで「大経」の「本願成就文」を、「本願信心の願成就の文」と記述していることが、「あくまでも」第十八願は「乃至十念」ではなく「至心信楽の願」であるという位置付けを貫かれます。
とはいえ、「設我得仏〜不取正覚」という「このように十方衆生がならなければ、わたし(法蔵菩薩)はさとりを得ない」という願文と、それが「成就している」という「成就文」には矛盾があります。
事実「そのようになっていない十方衆生が存在する」からです。
それは「阿弥陀の教え」に出会っていない人も含まれるハズです。
「蜎飛蠕動の類」(昆虫)と「異訳」にある以上、「ひと限定」ともいえないからです。
この矛盾は「善巧方便則」で読む以上、論理上解決しません。
続きの【31】に至って「一切衆生悉有仏性」という「真実則」に基づいていることが「理解されなければ」、「法蔵菩薩」はいつまでも「正覚を取れない」のです。
ですから【29】と【30】において「方便則」では「信心」が「浄心」をもたらすことを前提として、「方便則」がじつは「真実則」によって成り立っていることが、続きの【31】で明確になります。
【31】で、その「真実則」の根拠を「涅槃経」において説明されます。
つまり、すべての「有」は「仏性」であることを「仏性は如来なり、仏性は大信心と名づく」と236ページの後ろ4行目に引用されていることが「重要」です。
☆☆☆【ポイント】
ここを「従来」のように、「如来が至心によって与えた《信心》が衆生の仏性になる」と解釈すると「仏教」ではなくなります。
ここは「如来によって、仏性を知った」衆生が「信楽」を「大信心」だと讃嘆している。
と読まなければ、「如来とわたし」という「外道(バラモン教など)の二極分化した《仏教ではない教え》」になってしまいます。☆☆☆
ここで、このような「真実則」の「讃嘆」が続き、【33】では、このことは「思議」によって「わかる」のではなく「阿弥陀ストーリー」を「聞くことでわかる」ということと「得道のひと」がいるということを「信じて」わかるということを「涅槃経」の引用の「結論」にしています。
このあと【34】の華厳経の引用も「同じような内容」ですが、特記すべきは239ページの後ろ3行目の「如来の家」が「五果門」に対象していて、この「信楽」を「善巧方便」と明確に定義していることです。
この「善巧方便」を行じるなら「信楽が浄心になって、増上の最勝心」を得て、常に《波羅蜜》といわれる「行」を修めて、「摩訶衍(まかえん)と称する《大乗の行》が身につく」と記述しています。
そして「このことで《無碍》を得る」という内容の記述が続き、【37】で論註によって、「信楽は、世尊がいう一心であり、《如実修行》と相応する」と「行文類」の内容に戻っています。
つまり、「行文類」で論じた「五念門、五果門」という「真実則」が「結果」、「信文類」でここまでに論じた「善巧方便」の「信楽」が「同じゴール」に至ることを「明確に」しているのです。
2019/05/17[5−9](補足135参照)
ここまでの「至心と信楽」の関係を、【38】の「如是」の解釈で、「至心」を「疑蓋無雑」で受け入れることが、「天親菩薩のいう我一心」と同じであること。そして「経典」が「如是」と始まるのがこれと同じであると解釈しています。
「如是」が「至心」を「受け入れた」状態である「信楽」つまりは「信」と同じで、「ブッダの説くところ」を「如是」つまり「この通り」または「如を是として」受け入れた状態と同じだから「信が能入」「信楽がスタート」だと解釈しているのです。
そして、このようになった「行者」は、「欲生」という心になることを【39】から解釈していきます。
親鸞の論の上では「行文類」で「南无」の二文字に「帰命、発願回向、即是其行」を定義しています。
これは「行文類」で論じている「南无」を「帰命」と言い換えて、「真実則」の「行者の心」を「克明」に明らかにしています。
つまり「行文類」では「願力を聞くから必ず往生を得る」という意味での「南无」は「帰命」なり云々という、「法蔵菩薩の菩薩道」を「設我得仏〜不取正覚」という「本願(四十八願)」に聞いて(帰命して)「往生の道をいま歩むこと」を論じています。しかしこれはあくまでも「五念門五果門」が前提になっている「真実則の論」です。
しかし「信文類」でここまでで論じている第十八願の「至心信楽」が、天親の「我一心」と同じであるという「論」は、この第十八願の「三心」は「方便則」であるけれど、結論は「真実則」の「一心」と同じになる。
と論じているのですから、「信楽」は「行文類」でいう「帰命」とも同じであると定義していると考えられます。
このように推論するなら、行文類の「発願回向」と「欲生」について、これらは同じであるということを、この部分は定義していると考えられます。
だからここに、「欲生」の体は「真実の信楽」(至心信楽)であると記述されています。
そしてその上で「欲生」は「至心信楽」から出てくる「発願回向心だ」といっているのです。
親鸞はこのように「行文類」の「真実則」に準じて、「信文類」は真実に基づく「方便則」であることを論じていると推論できます。
あとの記述は、煩悩の人間界(衆生、有情)には「真実心がない」から、「回向(ふり向ける)」を「首(しゅ)」にして、如来の大悲心から「最終的にさとりを目指そうとする欲生心」を生み出すような構造をもった「第十八願」の「三心」という「詳細に組み立てられたシステム」が作られているということを記述しています。
つまり、如来の「至心」を「疑蓋無雑」で受け入れる「信楽」(信心)がおこり、そこから自ずと「さとりへ向かおう」という「欲生心」が生まれてくる仕組み(システム)が、「真如」から「煩悩の人間界」にふり向けられている。
という内容になっています。
ただし、「信文類」でいう「至心」は、「善導」に依る「本願招喚の《勅命そのもの》」を強調していますから、「本願」そのものに《内在的に込められた》「法性(功徳荘厳)」のことではなく、「本願」から「阿弥陀如来が至心を与えるから受け取ってこちらに来なさい」と言っているという「二河白道」のストーリーに象徴される「人格の阿弥陀如来」が「喚んでいる」という設定になります。
ですから「信文類」にある「本願招喚の勅命」は、「行文類」に記述される「本願招喚の勅命」とは異なります。
(真宗について学習するときに、こういうポイントを「既成概念」で読むと結果「難しい」とか「仏教ではない」ことを学ぶ失に陥ってしまいます。)
「行文類」においては、「真如から如来している諸仏の讃嘆」を「本願に帰せよ」と聞くという意味で記述されており、「本願」が明確に「第十八願定義」ではなく「四十八願定義」になっていることが「重要」です。
「行文類」においては「阿弥陀如来も諸仏も衆生もすべて真如法性」前提になっていて、それを「人格化」しようとしてもできない「無碍光如来」を「体」としているというのが「根本的に重要な論点」です。
そもそも「天親のいう仏教」は、「倶舎、唯識」ですから「我空法有」前提なので、存在を「有為法と無為法」に分類して「さとりの法」は「無為法」ですから、「阿弥陀如来」を「有為法」という人格化することは原則「仏教と相応しない」ことになるため、親鸞はあえて「行の体」を「無為法定義の無碍光如来」にしていると考えるのが必然です。
ですから「教学」において、この辺があやふやになっているために「本願を四十八願」だと解釈する学派と「第十八願」だと定義する学派に分かれますが、「本願」は「行文類」においては「四十八願」であり、「信文類」においては「第十八願」であると読み込めば「親鸞の意図」つまり「念仏は仏教と相応する」という意味が明確になります。
「行文類」における「本願」という文言を「教行証文類」における「総序」から「南无」の解釈までの論の流れのなかで、「第十八願」に「確定定義」出来るような内容がないのです。
それ以上に「五念門五果門」の、特に「讃嘆門」を論じています。
そのうえ、親鸞は「行文類」において、「南无」と「阿弥陀仏」を、かなり後半に至るまで、「結合」させません。
185ページの【67】「選択集」に至るまで「確定的」に「南无阿弥陀仏」と六字に連結させていません。
ここまで「詳細に論じて」いる親鸞なら、「早々に南无阿弥陀仏」と記述しても良さそうですが、「南无」を解釈し、「阿弥陀仏」の四字は「万徳は四字にあらわれる」と繰り返すのみです。
186ページ【71】に「真宗の行信」という記述がありますが、ここまでで「信」について言えば「信力増上」の信というほどにしか論じていません。
また、たとえば、192ページの後ろ3行を読めば「菩薩、人、天」の諸行は「阿弥陀如来の本願力による」と記述して、それを「仏力」として、「四十八願はいたづらに設けている」わけではない。
という論の流れから見ても、この段階では「本願」は「四十八願」と解釈せざるを得ないのです。
そのうえ、「信文類」においても、【1】に「第十八願」を「この大願を選択本願」と記述し、改まって「選択本願」を「第十八願」と定義しているかのようです。
そして【2】には、「至心信楽の本願」と記述してあり「至心信楽の願」が「本願」であるというより、「四十八願」の中で「至心信楽の」「本願」と「四十八願」の中の「至心信楽」と呼ぶ「本願」と読めるような記述をしています。
けれど、この後から「徐々」に「第十八願」が「本願」であるという定義に移行していっており、「信文類」で改めて「本願」は「第十八願」であると定義しているかのようです。
そういった点を鑑みるに親鸞の論においては、さながら「南无阿弥陀仏」より、「帰命尽十方無碍光如来」を根底に重視して「無為法」扱いのまま論を進め、「信文類」に至って「有為法」にもなりうる「阿弥陀如来」という「善巧方便」の「方便則」を論じる論の流れになっています。
そして「方便則」の阿弥陀如来の救いの論拠が【40】【41】の「成就文」になっています。
「第十八願が成就」しているから「至心を信楽の一心で受け入れれば浄土に至る」のであるという理由づけです。
ここで「方便則」においては「無碍光如来が阿弥陀如来」として人格化しますが、このように「無為法を有為法化」することは「論理上」中観派の「空論(我空法空論)」であれば「問題はない」ことになります。
そこで必要な「倶舎、唯識と中観派」を折衷して「真実則と方便則」を「論理的に整理」しているのが「曇鸞」の「論註」になります。
しかし「この方便則の論」には「矛盾」があることは当然で、「設我得仏〜不取正覚」と四十八願にあるのに、「およそ現実的にさとりに向かってもいない、向かおうともしない衆生ばかりの人間界に《成就》」はあり得ません。
それである学派においては「すでに救われているのに気づいていない」という観念論を語ります。
西本願寺ではこの論法が多く語られています。
しかしこれは「戯論、空論」でしかなく、「現実的」ではありません。
また、「教行証文類」においては、縷々この講義で述べているように「真実則」と「方便則」の「二重構造」が同時に記述されていますから、この二方向のいずれを「行」とするかは、それぞれの「機(人間)」に委ねられることになるため、「どちら」が「対象者にとって現実的か」ということは一概に言えないのです。
そしてこのポイントが明確なのは、「行文類」には「第十七願成就の文」があり、「信文類」には「第十八願成就の文」があるということです。
もちろんこれは、行文類が十七願に依っていて、信文類が第十八願に依るから「当然」だとスルーしてしまいがちです。(これも学習における既成概念に陥る失です。)
しかしもし、この「浄土真実教行証文類」を「真実則」で読むなら「教行証」という「法蔵菩薩の菩薩道」を「設我得仏〜不取正覚」と歩むのであるから、「第十七願が成就」していて、諸仏「現実的には釈尊が説いたとされる大経」の「四十八願の法蔵菩薩道」を歩むことを「帰命尽十方無碍光如来定義」(天親定義)で明らかにしていると読めます。
そして「浄土真実教行証文類」を「方便則」で読むなら「教行信証」という「歩み」になるから「阿弥陀如来の至心を信楽の一心(信心)で受け入れて南无阿弥陀仏と乃至十念で往生する」と定義するためには、仏教的には「空論」で可能になるけれど、「経典の論拠」が必要になるから「第十八願の成就文」が「どうしても」必要になる。
といったことが背景にあることから「第十八願成就文」が「信文類」で強調されているということが明確です。
しかしこれは、「第十八願成就の文」としている部分の「至心回向」を本来の「(有情が)至心に回向して」と読んだら、主語が「有情」になるから、実は「成り立たない」のです。
だから親鸞は、あえて「(阿弥陀如来が)至心回向したまへり」という「如来」を主語にしたから、「成就文」として意味を持つというロジックを使っています。
【41】も同じように読み替えをしています。
親鸞は、このような読み替えを「随所に持ち込んで」念仏門を「仏教と相応する」と論じていますが、こういう「意図的な創作」は、「真実則」の「教行証」として読むケースにおいては「不要」であり、ナチュラルに読んでいけます。
「とにかく念仏したら阿弥陀如来のチカラで極楽に往生できます」という「現在の浄土宗」的な教えを「仏教と相応する」ように論じるためには「こういった創作」が必要になります。
とはいえ、このケースにおいても親鸞は「あくまでも現生往生」だと解釈しているとしなければ、「仏教と相応」しません。
このように書くと親鸞は「確信犯」というイメージになりますが、「念仏」を「インド仏教」(特に天親)と同じである前提で、あくまでも「善巧方便」という位置付けで論じる上では「天才的な読み替え」です。
そういう意味で「この論」の「タイトル」は「顕浄土真実教行証文類」なのです。
本来は「教行証」でいいということです。
ですから、「聖人一流の御勧化」は「信心」を「本(ほん)」とするのではなく、「真実の行」を「本とする」というべきです。
もちろん「方便則」でしか理解を得られない衆生には「信心をもって本とする」と言わなければ仕方がないのです。
そういう「時機」(時と人)を考慮すれば「蓮如」の時代は、それ(方便則)でよかったと言えます。
しかし、現代においては「その両者」が存在するために「布教者」はその「見極め」が必要になるようです。
ただ「両者」が存在する理由として、「布教者」が「方便則」しか語らないという現実があります。
「布教者」が徹底して「根本的な真実則」を踏まえて「方便則」で語るシーンがあるとすれば、
「布教現場」の様相はかなり変わるのではないかと推察します。
そして「本文」は、この前提で【42】にスッと移って「回向」へと「論点」を進めていっています。
2019/05/19[5−9の2](追記)
前回「南无」と「阿弥陀仏」を親鸞は「なかなか結合させない」という部分に関して、「行文類」146ページの【12】の「破闇満願」の部分に「南无阿弥陀仏」を「正念」と記述がある。
という「質問」がありました。
ここを「見落としていた」というわけではありません。
前回論じていたのは「確定的に結合した《南无阿弥陀仏》」が「第十八願成就(第十八願定義)」によって「機(人間)」が「往生」ないしは「成仏」の「増上縁または因」として論じられているかどうか、ということです。
「この【12】の部分」までは、必ずしも「南无阿弥陀仏」である必要はなく、また、人間サイドからすると「わが名を聞く」ということであり、ここにある「南无阿弥陀仏」の「しかれば、名を称するに」の主語(主体)が「諸仏サイド」にあると考えられるからです。
もし、親鸞が「この文言の主語」は「衆生サイド」です。といったとしても、「ここまでの論」を読む限り、「しかれば名を称するに、よく衆生の一切の無明を破し。。」という記述は、「諸仏の称名」を「聞いていれば」、「聞いている衆生の一切の無明が破されるのである」と「読み取れ」るのです。
このような「主語」が不明瞭な記述が多いのは、日本語の特色かもしれませんが、「論の流れ」から行けば、この時点の「南无阿弥陀仏」は「諸仏サイド」です。
こういうところを「既成概念」で読むと、「ここに南无阿弥陀仏が《破闇満願》の称名念仏って書いてあります」と簡単に流してしまうのです。
当初(2、行文類とした部分)の「この講義」において、「この南无阿弥陀仏」を「衆生サイドの称名」と書いていますが、「既成概念」があったころのことです。
この講義の、30/12/19[3−13]のあたりから「既成概念」が「問い」になってきています。
この日の「講義」には「なんでここでいきなり南无阿弥陀仏がポップアップしてるのか?」と書きました。
いずれにせよ、今までの「既成概念」を捨てて、素直に読むと、ここで「第十八願定義の南无阿弥陀仏」にはならないと読むべきであろうと「確定推論」できます。
とにかくこの部分は「我が名を聞く」ことが、どういう意味を持つのかということについて記述されているのです。
単純に「南无阿弥陀仏」という「ことばがあるかないか」ということではありません。
ただ、この部分の「読みにくさ」についてもうひとついえば、「しかれば」とあるけれど、この部分は次の【13】の前提として記述されているならば、
【14】の〈信力増上〉の部分で152ページの4行目「十方諸仏を念ずべし」から、同ページの後ろから行目の「問うていはく」の問答で、「つぶさに無量寿仏を説くべし」「この諸仏世尊〜阿弥陀仏の本願を憶念すること〜〈もし人われを念じ名を称しておのづから帰すれば。。」というところで、ようやく「人の称名」になります。
しかし、ここにおける「本願」も「確定第十八願」ではありません。
「十仏の名号」でもいいけれど、「阿弥陀仏」にするのは「本願」という「明確な願い」があって、「願と行が整う」という「菩薩の行」としてふさわしいことを暗示しています。
なぜそういえるかという部分が【17】に至って「菩薩はかくのごとく五門の行を修して。。」と146ページの「般舟三昧を父とし、無生法忍を母とする」続いて「この菩薩」と記述されているように、ここまででは、「菩薩の行」を確定するための「論述」だと考えられるからです。
そして「この菩薩」の「この」は「法蔵菩薩」と考えるのが妥当です。
そういう意味では、この辺りの「本願」は「四十八願」を意味していて、「五門の行」を論じて、156ページに至って「帰命尽十方無碍光如来」に「五念門」を定義して、157ページの「問答」において、本来は「無生」であるが、あえて「往生」とするという部分に「仮名の人」のなかにおいて「五念門を修せしむ」と記述されており、このポイントで「仏教と相応する」という定義をしています。
そして「行文類」ではこの後も「華厳経」などを「論拠」として、「阿弥陀仏」を念じることの背景にも「仏教の真実則」が背景にあることを論じて、169ページの最後に「真如の門に転入す」と記述しています。
ですから、170ページに「巧方便をもつて」と記述して、【34】に、「しかれば、南無の言は帰命なり。。」と記述されているように、「仏教の真実則」を背景にした「易行」が「阿弥陀仏」の四十八願を「広讃嘆(説く)」する「讃嘆門」を行じることである。
結果「四十八願と讃嘆門メインの五念門行」が真実則であるということになります。
ここでこれが「四十八願」である以上、「法蔵菩薩」とともに「設我得仏〜不取正覚」と「阿弥陀仏になる道」を歩むと言えるのです。
このように、「破闇満願」部分における「南无阿弥陀仏」が「衆生または人」の「行」ともいえず、「確定」第十八願定義ともいえません。
なお、ここで「信文類」の次(242ページ)に出てくる「回向を首とする」という部分や「往相還相」の部分が出てきますが、「行文類」におけるこの部分を「信文類」に出しているのは、「信文類」において「善巧方便(239ページ[巧方便])のストーリー」として出てくる「阿弥陀如来」の「至心信楽からの欲生」が「仏教と相応する論拠」をここまでで明確にしていると考えられます。
つまり、「行文類」のように「菩薩の行」として「四十八願」と「五念門」の「願と行」で「二回向」を《真実則》で「行じる」か。
「信文類」にある「第十八願」の「至心信楽」を「欲生」の道として《善巧方便則》に乗って「白道」を進むのか。
いずれにしろ「ゴールは同じ」という「この講義の論」は、どっちを進んでも「自我名字」を「無為法名字」の「無碍光如来を基底にした法蔵菩薩」に置き換える。
「至心を信楽」で受け入れて「自我名字」が「南无阿弥陀仏」に転じられる「無為法名字」を生きることになる。
という「自我名字の置き換えまたは転換」が「自覚の上で法蔵菩薩道」を歩むことによるのか、「無自覚」に「誘導される」のかという違いでしかないのです。
いずれも「仏の智慧による無我化(破我)」と「利他を行じる」という結論(成仏)へ向かうというあり方です。
しかし「阿弥陀如来」を「阿弥陀さまが、お浄土に生まれさせてくれて、永遠に楽園を生きられる。」
「阿弥陀さまのお浄土でまた会える」なんて語ってしまうと「自我のまま」「世俗の持ち越し」になるため「仏教」とはいえません。
ここが「重要な論点」です。
2019/05/21[5−10]
そもそも親鸞が「信文類」を書いたのは、信文類の「序」にあるように、「自性唯心に沈む」人が多かったということだと考えられます。
一般的には、「行文類」から「信を詳説」するためと言われていますが、そうではないと考える方が論が通ります。
「行文類」は「単独で完結」しています。
しかし、「阿弥陀如来」や「諸仏」だの「浄土」だのといっていれば、「阿弥陀如来が、来世で永遠の楽園に連れて行ってくれる」という「自性唯心」な人がいたのだと推察できます。
このように「浄土の真証」を理解できない人が当時もいたために、「真如」や「空」だのといったことについて理解できない人へ向けて「善巧方便」をさらに「方便化」して「理解を促す」ためには必要なポイントだったと考えることで、「行文類」との関係の中で筋が通ります。
そういう意味では「信文類」は、「善導」に依っていて、要所要所に「天親、曇鸞」を引用しています。
そして「善導」のなかでも「わかりやすい」《二河白道》が中心になっています。
そこで次の部分ですが、242ページの【42】に「浄土論(論註)」を引いています。
これは、「行文類」の159ページにも引用されている内容ですが、「回向」について「往相と還相」があると言っている部分です。
「回向」という文言は「仏教」では意外によく使われますが、意味について意外と一般的に知られていない文言です。
これは「回転趣向(えてんしゅこう)」といって、簡潔に言えば「方向転換して趣くところへ向かう」という意味です。
ここで親鸞は、「どのように回向されるのか」あるいは「なぜ回向されているか」という書き出しで、「一切苦悩の衆生を捨てない」「心にその願いを持って」「衆生に向けることを第一(首)にして」「大悲心を成就した」のだからと言った「阿弥陀如来の回向」に依って「欲生心」が起こることと、「回向されている内容」は「往相還相回向」であるということを明確にしています。
ここでは本来「証文類」に記述する「還相回向」までに及んで記述していますが、「行文類」においては「往相回向」で留めてあります。
これは、「教行証」の流れであるために「あえて留めてある」と言えます。
こういうところからも「信文類」は、信文類だけで「阿弥陀如来の方便ストーリー」が完結するように「別立て」で構成されているということが「明確」です。
次も同じように【43】の「浄入願心」というポイントは、「証文類」の「還相回向」の解釈部分に引用されている部分ですが、先にこの「信文類」に引用して、「ここまで記述してきた《因果》ともに阿弥陀如来の《清浄願心》によって成就されたのだから、清浄な因といえるので、他にはこのような清浄な因はあり得ない」と「知るべき」であると示しています。
これは、「自性唯心」の人などに対して、「人間が適当に《私の心の中に阿弥陀さまがいてくださります》といった性質のものではない」ということを、念押ししているかのような「簡潔な引用」です。
【44】に「還相回向」についてこれまた「簡潔に引用」しています。
ここでは「五果門」の第五「薗林遊戯地門」を引用して「応化身」を示されることを記述していますが、ここを【42】の還相についての説明であると読み込まないと「単純」に「阿弥陀如来が応化身を示す」と読んでしまいそうになります。「本願力の回向をもってのゆえに」の文言を「サラッと見逃す」と「阿弥陀如来の話」と読んでしまいます。
「信文類」において、親鸞は、ここまでの流れで、「阿弥陀如来の至心を信楽すると欲生心が起こるので、信楽の一心による乃至十念の往相回向によって浄土に往生し、還相回向によって利他教化する」という内容に「方便阿弥陀ストーリー」をまとめ上げて、「教行証」がわからない「自性唯心の者」に「信文類」だけで完結する内容に仕上げています。
そして【45】において、善導の引用から「かならず決定真実心という阿弥陀如来の《至心》のなかに回向された願いをもって《生まれることを得た》という想い(イメージ)をなせ!」として、「あらゆる異見、異学、別解、別行」に迷わされたり壊されないように、「決定して一心に正直に進んで他の人の意見を聞くな!」これは「進もうかどうしようか迷っていると道から落ちて往生という大きな利益を失うことになる」とかなり「強硬な姿勢」を示しています。
このことは「教行証」がわからない。「仏教がわからない者」をムリクリでも「阿弥陀ストーリー」でさとりに向かわせる意図が強いからだと言えます。
親鸞は、こう言った点で「わからない者はほっとけばいい」とはならない「大乗仏教」を「ホンモノの大乗仏教」として構築したと言えます。
ここで「落ちて往生という大きな利益を失う」ということを「譬喩」で説明するためにも、【46】において、「二河白道」の「白道の四、五寸」を歩むことは「大道を歩むこと」で「道」に定義し、その他の仏教を「路」に定義して、「小路」だと称しています。
しかも「二河」という「河」に対して、「大信心海」だから「壊れない金剛のようである」と「海」に定義し直しています。
【47】においては、「僧侶も一般の人も時の人々はみな」さとりに向かう心を起こしても、「なかなか生死を厭いがたく」と記述されていますが、この「生死を厭いがたい」について、なぜ「生は厭いがたい」ではないかという部分をサラッと見逃すと「この世は厭いがたい」と読んでしまいます。
ここで「生死は」になっているのは、「虚妄分別、生死分断」を意味していて、「けっきょく生きるだの死ぬだの、良いだの悪いだの、という《無明による分別》を意味していること」を見逃します。
人間が「菩提心(さとりに向かう心)」を起こしても、「ああだこうだ」と言ってばかりで「仏法を欣う」ことは難しい。
という意味であって、その上で「至心信楽」という「金剛の志をおこして」そういった「虚妄分別」を超えて断ち切って、「正しく、確かな」「至心」を受けて「信楽の一心(一念)」に相応すれば「結果」涅槃を得るのである」ということを示して、「人間的な迷いを信(金剛心)」で断ち切りなさい」と言っています。
ただし続く【48】においては【47】と同じように思えますが、ここでは「真の楽、法楽」について述べています。
「苦」の「娑婆(忍土→この世)」を厭い、「無為の楽」を求めることが「常楽」であるという、「真仏土文類」に記述される「涅槃の徳」のうち「常楽」について述べ、この状態になるためには、金剛心を得て、「慈尊」に従うことであると言っています。
そして、【49】において「金剛は無漏の体」だという引用をしているのは、「信文類」でここまで書いてきた「阿弥陀如来」「至心」という「人格的な内容」を「金剛」と定義して、それは、「無漏身」つまり「さとりの法」であるという定義づけを確定しています。
【50】においては、これまでの「重要ポイント」を「至心、信楽、欲生」という三心は「疑蓋無雑」という「疑いの蓋がない」ということで「同じ」「真実の一心」「金剛の真心」と定義して、これをさらに「真実の信心」と統合定義をし、ここには、必ず「名号」がそなわっていると記述しています。
ここで「名字は因位」、「名号は果位」という原則でいえば、この「真実の信心」には「利他行」としての「称名」がそなわっているという意味になります。
そしてここで「名号」を「単なる唱えごととしての称名」ではなく、天親が、まずもって「我一心」という「信心を基にして」「信心を前提」にしたように、「願力の信心」をそなえた「利他の称名(名号)」こそが、「如実修行」に「相応」している。と、「信心なき称名では無意味である」ということを述べいています。
これは、「化身土文類」の「第十九願、二十願」の称名について「仮の方便」として定義していく内容を記述しています。
そしてこの「信文類」に記述してきた「善巧方便」は「空性」「実相無相」であることを、【51】に記述して、「結果」仏教の本質にそむかないことを、いったんの結論にしています。
2019/05/22[5−11]
245ページの【51】がなぜ「善巧方便」の「実相無相」の記述になるかといえば、「およそ大信海を案ずれば」から「貴賎緇素を簡ばず、男女老少を問はず、。。。行にあらず善にあらず。。。尋常あらず臨終にあらず、多念にあらず、一念にあらず。。。如来誓願の薬はよく智愚の毒を滅する」といった表現は、「中観派の空」を背景にしていると考えられて、結果この部分は「実相無相である」という「中観、唯識論」を総合的にあらわしている、「信文類」の「リアリティ」を「論として」結論的に「仏教学」に落とし込んでいるからです‼️
つまり親鸞は「善巧方便であろうと、こういう論理を無視して記述を終わることはできなかった」その「論理的な性格」を表していると思わざるを得ません。
ここが「論」と決定的に言えるのは「内容」もそうですが「阿弥陀如来」と記述せず、「如来誓願」になっていることです。
草稿本で「釈迦」と書いた部分を消して「如来」と書き換えているような緻密な親鸞ですから、信文類で「阿弥陀如来」について多く記述しているのに、ここであえて「阿弥陀如来の誓願」としなかった理由があるはずです。
考えられることは、「真実則」の《論理》を「簡潔に記述することは外せなかった」のだと推察すべきでしょう。
そして【52】において、この教えは「迂回していくのではなく」まるで「バイパス」で横切るようなことで、「横(出)」は「自我の混じった念仏行」を「他力と勘違いしている《自力の菩提心》」であり、この願力回向の信楽(一心行)は「横(超)」の《願作仏心》の《大菩提心》であると記述しています。
ここで「自力」と「他力」の分類は「願い」が「自分に依るか、仏に依るか」という「仕分け」であると読み込めます。
それはこの部分に、いずれにせよ「入真を正要」として「真心を根本にする」という記述があり、「邪雑な心」これで救われたいという《我執》や《あれもこれも信じたり》というありかた」を「錯覚」だとして、さらに「疑いや情動」の心を持つことは「失(うしなう)」ことになると警告して、「教えを聞くことが前提になっていない邪心を離れよ」と念を押しています。
この部分の「疑情」について、一般的には「疑いの心」と読むことが多いようですが、親鸞は「疑いと情」に分類しているように読み込めます。
つまり親鸞の時代は「疑い」が《論理的な疑い》ではなく、浄土宗を本義にしている人からすれば「気に入らない」というような《情動的疑い》が多かったと考えられるからです。
また、たとえ「浄土宗」ではなくても、この時代の人の多くが「情動」によっていたからとも言えます。
つまり親鸞は「わたしは論によるのであり情によるのではない」というメッセージを、【51】などの各所で明確にしていることからも、このように考えられるのです。
ですから【53】においても「観経」を「王舎城の無量寿経」という記述の引用をして、「上品(ぼん)、中品、下品(ぼん)」という「人間資質(行)の違いにおいて」も、これらはみな「仏心によって作られた願い」に基づくもので、「衆生をさとらせたい」という「願作仏心の現れ」(仏心による願い)によるけれど、ここに「もし、かの国土の受楽が絶え間ないと聞いて、自分の楽のために生まれたいという者」は「往生しない」と「仏心によらない欲生心」を記述されているのも「我執による自力行」への「錯誤を警告」しているということは「確定的」に言えます。
だから続いて、「自分の楽を求めるのではなく、一切衆生について《抜苦与楽》しよう」という「無上菩提心」は「阿弥陀如来のように、己の功徳を一切衆生に与えて、ともに仏道に向かう」ということである。
と定義しています。
けっきょく「真実則」のように、「法蔵菩薩道を歩む」ということに「結論合致」するのです。
「どっちを選んでも《ゴールは同じ》」なのです❣️
とはいえ【54】で、「こういう生き方をする人は世間では難しい。しかし世の中を挙げて希(まれ)なこと」であるとして、
【55】で、しかしながら「どんな人も《決誓猛信》をとれば、どんな《死に様》をしようとも往生する」といい「なにに縛られようと世の中で下類と言われようがなんであろうが《成仏する法》である」と「強く表現」しています。
(具縛の凡愚について「自分の煩悩やあらゆる煩悩で作られた世界に縛られる」という意味で「なにに縛られても」と記述しました。)
さらに【56】に、このように「この《悪世》で普通に修行して成仏する」ことは「難しい」から「諸仏が讃嘆している意(こころ)」を「信受しなさい」(他利)あるいは「信受させなさい」(利他)とありますが、「行じて成仏する」ということについて「現生」だの「死後」だのということは記述されません。
(「せしめよ」のひとことが「他利と利他をあらわす」と読めます。)
それこそ「現生にあらず死後にあらず」ということが「真実則」ですが、「いま」から「欲生」「発願回向」するならリアルには「現生」に定義しなければ「物語り」で終わります。
このAが、「このように生きていてもなかなか事実として理解されない」ということが、「ここに記述されている通りだ」と実感します!
また「特にお西の教学で《決定要期》(けつじょうようご)、つまり、浄土に生まれる身になったことを喜び感謝する」なんていうことは、「確定的」に現代で「リアルにあり得」ません。
その上、ありがたそうに「なまんだーぶと大きな声で念仏しているひと」が「度衆生心」を行じているとも思えないし、かえって《一般の現代人》が「そのシーン」を見ると「奇異なひと」であるという「謗法になる」ことをわかっていないと「観じ」ます。
本堂や仏事で「決定要期を喜んでいる」と「装っている布教者」を見ていても「日常的現実的に喜んでいるとも思えません」そういうポイントで観ると「近年において」「度衆生心」をもった「念仏行者」を観たことがありません。
30年前には「そういうお同行」といえる人や「布教者」もいましたが、「ほぼ今では」「そのように見えている人も《自性唯心》なひと」しか居ないようです。
親鸞が言っている「真実則」(行文類)は「論として理解は得られる」けれど「資本主義社会」において、「一定水準の文化的生活を考えると難しい、自分のことで精一杯」と言われてしまうという意味です。
しかし、「教行証文類」の「真実則」を行じていると「他者のことを考えていくことが歓喜になります」から、「一歩を踏み出せば、自分のことで精一杯」にはなりません。
この辺を「こういった講義で《解学》ではなく《行学》していただきたい」のです。
だからさらに【57】には「この教えで成仏すること」は「難信」であることを親鸞は記述しています。
ここで、さらに《重要》な「悪人」が「超截して往生すること」について【55】の文言から「抜粋」して解釈しています。これは、「信文類の末」や「総序」に「阿闍世」が出てくる前提を記述しているといえるでしょう。
そして「こういうことが《難信》なのは、世間的には当然である」と解釈して、しかしこれが、「阿弥陀如来を真実明。。。不可思議光」と言う《理由なのです》と、論理的ではないけれど、「信」をもって「情動」に訴えかけて「論(システム)を伝える」という「信文類」特有の「誘導」をしています。
【59】で、「浄土の論」を教える者は多いけれど、「こういう要(かなめ)」を教えているものはない。
と記述していますが、「指ふる(おしえる)」という文字は「指し示す(化身土文類に出てくる月を指す指)」という意味で、「教える」の意味を「示唆する」の意味で定義しています。
その上で「このような教え」を得られないひとは、「疑い」と「愛(執着)」二つのこころが「邪魔をしているのだ」と自覚を促すように記述して、「弥陀の洪門はつねにおのづから摂持している」ということが「必然的な道理」であると「阿弥陀如来の無漏身と無漏心」を「自然の理」について合致させています。
この部分を根拠に「すでに浄土に生まれる身になったことを喜び感謝する」という「お西」でいう「弥陀の救い」というお話になっているのではありません。
ここは「決定要期」を意味しているわけではありません。
「浄土の教えのかなめ」について「指ふる」ものが少ないということについて記述しています。
その「かなめ」が、「弥陀の洪門は。。。」という「無漏身の人格化が、自然に摂持していること」です。
だから「この部分で《すでに救われていることを喜び称名する》とする解釈にはムリがあります。」
とにもかくにも信文類の「信」を「真実則」からいえば、
「無常無我、空」を「四十八《願》」から「仏の智慧として受け入れて」《教えを広めるという讃嘆》を「自我名字を無碍光如来に置き換える(破我)」という形式の《五念門の行》として行じれ」ば、「自ずと願行を伴って《摂理》に叶う」
という「論理」になりますが、これを「信文類」では「情的な表現」であらわしていると理解できます。
「無常無我、空、唯識、華厳、涅槃」などの「論理的なさとり」の部分を「阿弥陀如来の清浄願心」「阿弥陀如来の真実心」などの「無漏法身や報身」に「表現を変えている」のです。
こういった部分が重要な「真実則」と「完全善巧方便則」の仕分けになっています。
これは、「字も書けない読めない、抽象論がわからない」というひとが多い時代向けな内容であると言えます。
2019/05/24[5−12]
250ページの【60】は「信の一念」といわれるように、これまでに述べてきた「信楽」という心理状態になった「瞬時、刹那」を「一念」といい、この心理状態が開くときの「時剋の極促」を「顕わして」いると書かれています。
この「顕わす」という文字は「見えてくる」という意味でも使います。
また「促」は「せきたてる」という意味ですから、これを【61】などにあるように、「信心歓喜」「乃至一念」について、「早く信楽を開くように極限的に促す」という意味になります。
ここで「註釈版」の補註7を見ると「〜本願を聞いて疑いなく信受する信心が開け発った最初の時を信の一念というのである。」と記述してありますが、ここにはなぜ「顕」が使われているかという、親鸞の緻密さを「スルー」しています。
この点は重要で、このように「一念」というのは「信心が開け発った最初の時」と記述している以上、「最初」という「時」があるということになります。
ここでそれが「顕らか」になると「顕」を含めて解釈すると、「信心が開け発った最初の時が《顕らか》になる」という意味になります。
このように解釈すると「どう考えても《親鸞会》さん」のいう通り、「信心が起こった瞬間がわかる、覚知される」と解釈せざるを得ません。
しかし「従来のお西の解釈」では「信心開発の一念があるけれど、自覚はできない」と弁明して来ていますが、そうであるなら「この一文の持つ意味」が「抽象的な戯論」になってしまいます。
そしてまた、補註7にある「一多証文」の「一念といふは信心を得るときのきはまりをあらはすことばなり」という内容を「同じ意味」だと解釈するなら《親鸞会》さんの説をあながち否定できません。
しかし「第十八願成就文」が意味する「乃至一念して欲生する」という内容を「救急的に蓋を開けて欲生を促す極限(時剋の極促)」を「至心に回向したまへり」されていると理解すれば、「その名号を《聞きて》、信心歓喜する《疑いの蓋(ふた)が開く》ために《救急かつ極限的に促されている》こと」が、「信楽開発の時剋の極促」ということであり、その根拠が「至心に回向したまへり」であると解釈する方が、一貫した「流れ」として読み込めます。
繰り返しになるようですが、「名号を《聞く》プロセスの中で、至心という如来の真実心が、《急いで(時剋)》信楽《疑蓋無雑》の一心を得て《フタを開けよ》と、《極限的に促している》と《顕らか》になる」と読むと自然です。
「一多証文」の「一念といふは信心を得るときのきはまりをあらはすことばなり」の意味も、「一念というのは、信心を得よという《極限的な促し》に応じて信心を得ることをあらわすことばなり」と読み込めて、【61】や【62】の引用も「最初の一念」といった「時剋」を意味していないことが「明確」です。
結果この部分から親鸞が言いたいのは、「如来の《極限的な促し》を《聞いて蓋が開発(かいほつ)》する一念」ということであると「スムーズ」に理解できます。
そういう点で【63】の直前に「如来会」を「一行だけわざわざ」引いて「仏の聖徳の名を聞く」などと記述する理由が理解できます。
そしてこの「聞いて」「疑いの蓋が開く」ことで「広大で難思の慶心を彰わすなり」という「歓喜地」について記述されるのです。
「彰わす」は「表情になる」といった意味を持つ文字表現です。
「疑いの蓋が開発されると慶心という表情になる」という意味合いになりますから「歓喜せん」になるということです。
続いて【63】から「聞く」の意味をさらに詳しく記述されます。
2019/05/27[5ー13]
230ページの【63】の涅槃経の引用に、「聞不具足」について記述されています。
この内容は意外に、「善巧方便の阿弥陀ストーリー」を聞くなかで、「現実的に頻発している」ことが書かれています。
「善巧方便」を聞く上で聞き方をこのように「ミスる」ケースが多いように思います。
「聞不具足」という「聞いていても《真実が聞けていない》状態」を定義しています。
如来の教えについて「十二の内容(パターン)」があるけれど、それを「半分聞いて受け入れた」としても、「読誦」にすら値しない読み方で「正しく理解したつもりになって、他を悟らせるといい、教えを説く」ようなことは「聞不具足」になる。と書かれています。
この部分でいえば、「真宗の布教者」にも、このケースは多いのではないでしょうか?
日々「正信偈」を「意味不明」なまま読誦して、「歎異抄」や「和讃」などは読んで理解しているつもりだけど、「教行証文類」は読んでないというパターン。
「阿弥陀さまのおはたらきで、死んでもまた会える世界があるんです」「これを生死の解決と言います」なんて「およそ仏教とはいえないことを平気でありがたそうに語る」布教者。
(これでは「生死の解決」の意味が「死をごまかす」ことだと言っているようなもので、「虚妄分別(生死分断)」「無明の解決」という本来の仏教を錯誤させてしまいます。)
「お聴聞が重要です」といいながら「当の本人」はお聴聞をしていない。
「お聴聞をしている布教者」が「そもそもテキトーなお話しばかり」を聞いている。
また、一般的にいえば「般若心経」を読誦しているけど、「意味不明」な状態で、「読誦」していることで「利益(りやく)を得ていると錯覚」したまま「ご利益(ごりやく)」を語るひと。など、 このようなケースがほとんどではないでしょうか?
また「議論を吹っかけて、勝つため」に「聞く(学ぶ)」ひと。
「布教のお礼目的に聞く(学ぶ)」(利養)ひと。
「来世でいい種(人間や天人)という《有》つまり《我の存在》になるため」に聞くひと。
「持続読誦」という「このようなために読誦を続けているひと」は、すべて「聞不具足」であると定義されています。
現実的にこういう聞き方をしているケースは多いようです。
この点に関して、266ページの【113】にある「まことに知んぬ、悲しきかな愚禿鸞。。。」の部分に、「愛欲の広海に沈没し。。。名利の太山に迷惑して。。。」とある部分を、けっきょく「親鸞」も「聞不具足」と「同じであるといっている」という「大迷惑」なことを「堂々と語る布教者」がいることが、結果「テキトーでいい」という理解の推進力になっています。
この部分は「真の仏弟子」のあり方を論じているなかで、264ページの【103】にある「弥勒と同じ」「念仏の衆生は横超の金剛心をきわむる」から「臨終一念の夕べ」(死後ではなく自我滅の意味が進行形になっていて、この身が滅すれば大般涅槃をさとる)という部分を受けて、「喜、悟、信」の「三忍」を得た「韋堤」と同じであるように「弥勒菩薩と便同である」真の仏弟子は、「弥勒大士→等覚の金剛心→念仏衆生は横超金剛心→臨終一念の夕→大般涅槃を得る→便同→韋堤と同じ→往相回向の真心徹到」という流れにおいて、注意すべき「仮」と「偽(いつわり)」に陥らないように警告して、【113】に「仏の一道」だけが「清浄」であることを記述し、ここでまず、「わたし親鸞は《愛欲》《名利》に迷惑しています」と「慚愧の自我滅」を表現しているのです。
ここで親鸞は「韋堤と同じ」であると《表現して》、かつ、この後に続く引用の「阿闍世」の「慚愧自我滅」を論じる「前提表現」として記述していると「確定推察」できます。
この「韋堤と同じ」ということや「阿闍世」のようにという以上、このストーリーにおいて、この二人は「現生」ですから「わたしたち」も「現生定義」でなければ論が立ちません。
(ここでこの講義において「慚愧」を「自我滅」と付け足しているのは、仏教の根幹である「無我に至ること」と「慚愧が同じ」ということを明確にするためです。真実則について論じている部分では「破我される」と記述しています。)
この親鸞の文章のあとには、「救いようのない阿闍世がさとっていくプロセス」で「慚愧(ざんき)」が重要ポイントになっており、「慚愧はつまりは自我滅」であることが「仏教」の正しい真理性に相応することを論じ、このように「慚愧自我滅」するものが「真の仏弟子」であると論じているのです。
ここで、【63】の「聞不具足」に戻ると、「親鸞が名利のわたし」と言っている意味は、決して「聞不具足」でいいとか、「テキトーでいい」という《意味ではない》ことを明確に「布教に臨む」べきであるということを、確認すべきだと考察するからです。
以前「灘本先生」が「わたしは偉いひとと言われたいから勧学になったんですよ」と言ってから「講義をされた」ということについて、「まず自我滅(慚愧)から布教に入る」というすがたであると記述しましたが、
この「聞不具足」において、「真宗を完全マスター」しなければ「布教してはいけない」という意味ではなく、「わたしは愚者だという《自我滅》」前提で「布教」しなければ、「慚愧」にならず、
「マジ名利」になり、「嘘八百」な布教になるからです。
Aの友人の布教使に「わたしの布教はマジ名利です」って「マジメ」にいう方がいます。
このかたは、日常的に「こう表現する」ことで「自我滅」されているので、Aは友人ながら「リスペクト」しています。
そういう意味でも「布教 中神章生師」(「さん」でも同じ)なんて書かれると「違うねんけど」って思います。
だれが布教使や布教者でも「名前なんかどうでもいい」んです。
ですから「善巧方便則」でいえば、「聞く」は「一心専念」であると【64】に定義して、【65】に「なぜ仏願が生まれて、自我人が《至心信楽》で自我滅されて《欲生心を起こす》ようになるのか」ということを「聞く」のであるという内容に論を進めています。
2019/05/29[5−14]
前回までに、【60】で「信楽の一念」を「早く得てくださいと促され」て、【61】「第十八願成就の文」【62】「如来会」などにある「聞く」について、《善巧方便則》の「信文類」では「至心」から「信楽」の《一心》を得て「欲生」するというプロセスの中で、「名号を聞きて。。」や「名を聞きて。。」と記述されている部分について、【63】で「聞不具足」という「正しい聞き方」を定義して、【64】に「聞く」は「一心専念」(疑いの蓋を開く無疑の一心と広讃嘆の乃至十念)であると確認定義しています。
そして【65】に「なぜ仏願が生まれて、自我人が《至心信楽》で自我滅されて《欲生心を起こす》ようになるのか」ということを「聞く」のであるという、「聞き方から聞く内容」について論を進めています。
いわゆる「大経の第十八願成就の文」の解釈をして、「仏願の生起本末を聞きて疑心あることなし」これを「聞」という。
のであると記述して「信心」の解釈に移っていますが、「其名号」の解釈がありません。
これは、第十八願《成就の文》の「聞其名号、信心」までを第十八願文の「至心信楽欲生〜乃至十念」にまとめて、
「すなわち本願力回向の信心なり」と記述されているからだと推論できます。
「仏願の生起本末」というのが、「真実心のない人間に、真実心を《至心》に回向して《信楽の一心》で受け入れ《欲生心》を起こさせて、さとりへ向かい利他を行じる広讃嘆の《乃至十念》の者になる」
ということを意味しているとして、この部分を「聞く」について、《まとめて》「仏願の生起本末」にしていると言えます。
そしてそのポイントが「本願力回向の信心なり」ということだと、同じように《まとめて記述》されているのです。
ここでこのようなややこしげな「記述」は、「聞く」「仏願の生起本末」も「至心信楽欲生心〜乃至十念」であり、
「本願力回向の信心」も「至心信楽欲生心〜乃至十念」だと「主体も客体も同じ(能所不二)」であることを明確にしているのです。
このことは重要ポイントで、真実則の「法蔵菩薩の誓願」と「五念門行」を行じることと、結果「同じ」《破我自我滅》を「乃至一念」から「乃至十念」の「讃嘆」を定義する内容になっているのです。
つまり、「論理的」に真実則を「名字(主体)」を「無碍光如来」(完全無為法)に入れ換えることと、字も読めない抽象論もわからない人向けの「信文類」における「阿弥陀如来ストーリー」においても、「主体」を「阿弥陀如来(報身、無漏身)の至心」に「信楽」で入れ換えて「欲生心」で生きることが、「自我滅して無為法、無漏法を生きる」ということと同じ状態になることを論じているからです。
そして、「歓喜」は「身心の悦びをあらわす(形)」という「かおばせ(貌)」だと定義して、「乃至」は「多くても少なくても同じこと」だと記述して、「一念」について、「一心」は「如来から回向された一心」だから「ふたごころ(二心)がない」という意味もある、と「二心」という定義も加えています。
とはいえ「一念」を「一心」定義で、「清浄報土の真因」と確定して、この「金剛の真心を獲得(因位と果位)」したら、「横に五趣八難の道を超えて」。。。「かならず現生に十種の益を得」と「現生十益」に移っていきます。
2019/05/30[5−15]
さて、「現生十益」についてですが、「金剛の真心を獲得すれば、横に五趣八難の道を超え、かならず現生に十種の益を獲。なにものか十とする。一つには冥衆護持の益、二つには至徳具足の益、三つには転悪成善の益、四つには諸仏護念の益、五つには諸仏称讃の益、六つには心光常護の益、七つには心多歓喜の益、八つには知恩報徳の益、九つには常行大悲の益、十には正定聚に入る益なり。」
と記述されています。
これについて、ランダムに「十益」が記述されているのではないことは明白です。
ここで親鸞は、「現生に獲る十益」を挙げていますが、これは、この十益は、ここまでの「信心が真実」である「証明」ということなのでしょう。
ここで明確に証明されることは、「至心信楽」によって、「破我自我滅」が起こり「自我が阿弥陀如来に転じられ」「さとりに向かう《欲生心》」がすべて《現生》での「菩薩道」であるということであり、このことを「利益(りやく)」と定義していることです。
「現生定義」は、これまでの「菩提心の釈」やこの後の「真仏弟子の釈」でも明確です。
この講義を、「先入観なく」読まれていて「ファンタジー」や「死後のこと」を書いていると感じられる方は多分おられないでしょう。
「仏教」においては釈尊も親鸞も「現実真理真実論者」ですから「絵空事」を論じることは「戯論(戯れの論)」とされています。
ここで「現生」に行じるから「現生十益」なのです。「十益」の内容は次のように理解できます。
一つには「冥衆護持の益」これは、「まずは阿弥陀如来の教えに出会ったもの」は知らず知らずに諸々の衆生に導かれて「さとりへ向かうように護られる」こと。
(諸々の衆生「冥衆」を観音・勢至、普賢・文殊、弥勒等の諸大菩薩や、一切の善悪の鬼神に至るまですべてを冥衆とすると解説されているものもありますが、虫や鳥など一切衆生に定義する方が現実的です。)
二つには「至徳具足の益」これは、「至心回向には万徳があって功徳この上ない」からこの「至心回向」を「信楽の一心で受け入れた上で万徳がそなわる」こと。
三つには「転悪成善の益」これは、「至心信楽」したものは「破我自我滅されて、そのひとの人生が過去から未来に至るまで如来の至徳に転じられる」ことで、この講義であとに回している「総序」に出てくる「悪を転じて徳を成す正智」と同じです。
四つには「諸仏護念の益」これは、「諸仏讃嘆を縁にして至心信楽というわたしになり、乃至十念の讃嘆を行じるもの」になるのですから、「至心を回向されることによる益」といえ、「諸仏がさとりへの歩みを護る」ということで「阿弥陀経の別名が《一切諸仏所護念経》といわれている」のもこのことです。
現状さまざまなところで「護る」という文言が出てきますが、「護る」の定義は「さとりへの歩みを護る」という定義でしかありえません。
五つには「諸仏称讃の益」これは、「諸仏が阿弥陀如来を讃嘆しているように、わたしも称名讃嘆(広讃嘆が中心の「教えを説く語る」こと)するものになるということです。
六つには「心光常護の益」これは、「真実則」の「無碍光如来」を背景にしていますが、「常に阿弥陀如来の摂取の心光の中に護られる」ことで「護る」の定義は四と同じです。
(なお、この《心光》という表現は「正信偈以外では信文類にしかありません。つまり論理的《光明》を情的な《心光》と記述していると推察できます。)
七つには「心多歓喜の益」これは、「至心信楽欲生心」(第十八願文)から生まれる「信心歓喜」(第十八願成就の文)を意味しています。
八つには「知恩報徳の益」これは、「わたしをさとりに向かわせる如来や諸仏などが、何をわたしにくださっているのかという恩を知り」そのいただいた「恩(いただきもの)」が「如来の万徳」つまり「至心であると知って」それに「応じること」で、つまりは「仏道を歩む者になること」です。
九つには「常行大悲の益」これは、「仏道を歩む者」になれば「常に阿弥陀如来の広讃嘆」という「大慈悲を行じる」「利他を行じる者になる」ということを意味しています。
十には「正定聚に入る益」これは、「ここまでの九つがすべて《現生に往生した正定聚》の者」が得る「さとりへの不退転地」であると「十益をまとめて利益の結論」にしています。
このように、「現生十益」についても「ファンタジー」な内容ではなく「現実的」な内容であるといえます。
あくまでも、現生での「至心信楽欲生心」「乃至十念」を行じる者の「利益」です。
2019/06/03[5−16]
252ページの【66】に至って、「至心信楽」によって欲生心になり、それがなぜ「聞く」ということによって「正定聚の益」に至ることになるのかという《根拠》を、
【64】の引用に戻って解説しています。ここに、
「専念」→「一行」として、
「専心」→「一心」→「第十八願成就文の《一念》」→「専心」→「深心」
「深心」→「深信」→「決定心」→「無上上心」→「真心」→「相続心」→「淳心」→「憶念」→「真実の一心」→「大慶喜心」→「真実信心」→「金剛心」→「願作仏心」→「度衆生心」(衆生を摂取して安楽浄土に生ぜしむる心)→「大菩提心」→「大慈悲心」
というように「無色無形絶言」のさとりをあらわす「俗諦(言語表現)」を並べて、
「専念」の「一行」は「専心」によるという「引用」がもつ意味「内容」を《言い換え》というロジックによって定義しています。
定義の結果、この(これらの)心は、「無量光明慧」によって生じるといい。。
「無碍光(アミターバ)の《光明》」「阿弥陀如来(法蔵菩薩)」の「智慧」から生まれたと記述して、これが「至心信楽」の根拠であるという「暗示」をしています。
そして、そこから生まれる「利他の欲生心」について。。
「願海平等」に依ると解釈して、「発心等し」→「道等し」→「大慈悲心等し」と定義し、
「大慈悲」は「仏道の正因」であると「仏教と相応」すること、
そして【70】で記述する「如実修行相応」に定義していきます。
ここでこのことを【67】で、「欲生心」の者(かの安楽浄土に生まれんと願ずるもの)は、《無上菩提心を発する》と論を展開し、
【68】で「かなり端的」にここまでの「ストーリー」を「論」として、その「論拠」を記述しています。
内容は「是心作仏、是心是仏」について「火が木からでる」例えを用いて、「欲生心」というのは「仏が作った心」であると定義づけているように「思えます」が、ここは「論註」に依れば「観察門」を解釈している部分(七祖編83ページ)なので、「本来的には《観察》を論拠」にして、さらに「観察の根拠」を「法界無相」と定義して、「実相論」からそれは「無分別智」だと定義して、「正遍知」に定義していますから、「無量光明慧」(至心信楽から導き出される《欲生心》)というストーリーに依って「発心」する「心」というのは、「阿弥陀ストーリー」に依って「仏性」が「現われてくる」ことを「例え」で明らかにしているともいえます。
いずれにしろ【69】において「この至心信楽から出てきた《欲生心》」という構造について、「仏心はこれ以外にはない」という内容を記述して、【70】で、「一心」を「如実修行相応」(真実の仏教の修行と相応)であると記述して、「行」という「行為」の側面を「心」という「意業」に定義しているのは、つまりは「乃至十念」という「讃嘆行」が「如実修行相応」の「行」であると「論証」しているのです。
だからこの部分で「正教→正義→正行→正解→正業→正智」だと「分解定義」しています。
この点について【71】に「三心は一心である」と記述して、「引用文」の中で「答へをはんぬ」「知るべし」と結んでいます。
「知るべし」が「現生の十益」そして「正定聚の益」について、このように「仏性」乃至は「仏心はこれ以外にない」ということが根拠になっている「知るべし」という意味にも読み取れます。
いずれにしろ、究極は「無量光明慧」に依るからであると「知るべし」だといえます。
また、【72】で「止観の一にいはく。。。」という引用をし、ここまでの「阿弥陀ストーリー」から生まれる「一心の行」は、そもそも「真実則で《五念門》に定義される行」と同じように、「善巧方便則」で「信文類」に「論じてきた」「一心行」も、「仏教の修行の基本である《三昧》《正定》を《菩提心》とする」原則にかなった「道心」「菩提心」であるという「あくまでも釈尊の仏教」と同じであることを「解釈」していると「推定定義」できます。
2019/06/5[5−17]
【72】の摩訶止観の引用に「菩提(心)」は「道心」と定義された続きに、【73】に「横超断四流」で、この「道心」は、
煩悩の内容である、
- 欲暴流。欲界、五欲の境に執着して起る煩悩。
- 有暴流。色界・無色界における見惑と思惑。
- 見暴流。三界の見惑すなわち誤った見解。
- 無明暴流。四諦などに対する無智。
または、「生老病死」の四つを「一念須臾の間(一瞬にして)」「横に超え断ち切って」、
「無上正真道」を「超え証る」道心であることを明確にしています。
【78】にこの内容は詳説されています。
これはこの部分に「願成就一実円満の真教、真宗これなり」と記述しているように、この部分に「列挙」している人たちであっても「大願清浄の報土」には「品位階次」を問わないで、
「信の一念」にあるように、「さまざまな促しに応じて」「第十八願」を受け入れて「歩む菩薩道」の性格を「詳説」しています。
そこでこの願を【74】には「無上殊勝の願を超発する」と讃嘆し、【75】には、「名声聞十方」と示しています。
また、【76】では、「この願」は「悪趣(人、修羅、畜生、餓鬼、地獄)」を截り、このような悪趣が自然に閉じていき、極まりないさとりに昇っていくうえで「窮まり」がなく、「往き易い」のに「このように菩提心をもって菩薩道を歩むひとがなかなかいない」この道は「間違いなく自然が引いてくるさとりの法」であると記述しています。
【77】で、「大阿弥陀経」を引用して、【76】と同様な内容の典拠にしています。
この中で「阿弥陀仏国に往生すれば。。。」という記述がありますが、「この講義で一貫している」ように、「現生往生前提」で読めば、「空想ではない現実の問題」になります。
【76】の「往き易く、人なし」は、「現実的」に「これを歩むものは少なく」、往生は「死後の話」だのなんだのといっている「現実的状況を歎いている」と言えます。
倶舎などの「仏教の時間論」において、「死後だの今だの」という議論は「戯論(たわむれの論)」としか言えません。
「主な仏教の時間論」で言えば、「自己の意業を含めた行ないによる過去法」によって、「未来法」が《現在》(存在として現れる)する」のですから、「いま」と言った刹那に「過去法」になることで現れてくる「未来法」の中から、さとりの法である「択滅無為法」(ちゃくめつむいほう)を受け取って「無漏身」を得ていくプロセスに、「死後」という設定は、元来「仏教的ではなく」また「世俗の持ち越し」としか言えません。
ですからこの辺りの「論」も、全て「今(現在)」というより「現生」に「行じる菩薩道」であり、そこで得られる「自然の状況」であると考えるべきです。
「時間論」で言えば「刹那滅における現在」のことではなく、「刹那」に《生の一定期間を想定した》「現生」という意味で理解する方が適切と言えるでしょう。
ここで参考までに記述しますが、そもそも「仏願の生起本末を聞く」というのは、「日々《仏願とともに歩む》ことで」「択滅無為法」を「観察できるようになる」という重要ポイントがあるということです。
これは、《自然》に対して「屈服礼拝」し、「言説讃嘆」し、「さとりへの願いである四十八願を自己の願に置き換え作願」して「択滅無為法を観察」し、「さとりに向かうように回向された願を行じる回向発願」するというなかで、
「横超の願」は「人間に《択滅無為法》を示す願い」として重要なのです。
ですから【78】に、「六趣(六道)、四生」の因果が滅する。また、「頓(とん)」に「三有の生死を断絶する。。。」と「択滅無為法」を受け入れれば、「有為法の迷界」を脱出することができると記述されています。
2019/06/08[5−18]
255ページの【79】から、【78】の典拠を列記されます。
【82】の終わりには「すなはち形と名と頓(とん)に絶えぬるをや」と「存在を定義しない」《形》という「幻想」と「名」が絶える。(仏教において基本的に存在は「色」によって認識定義されます)
という記述もあり、わたしたちの「無明による虚妄」が即時に「虚妄だった」と智慧(無為法)により認識されるとあり、
【83】には、「無為の法楽を受く。乃至成仏までに生死を経ず」と「現生から成仏までの状態」を記述されています。
【84】に「真の仏弟子」について、「この《信行》によりてかならず大涅槃を超証するから真の仏弟子という」と記述されていて、《行信》の順ではなく、《信行》の順になっているのは、「方便則」の「信文類」だからだといえます。
つまり「真実則」でいえば、「諸仏」が「無碍光如来」を讃嘆する《行》を受け入れる「増上縁」としての「信力」から「衆生」の「讃嘆行(五念門)」へと移行するプロセスになります。
この時点において「《信》はプロセスであり、特別な重要ポイント」とはいえず、「行」こそが「重要ポイント」だと言えるからです。
【85】から典拠によって「真の仏弟子」のあり方を示唆しています。
【85】から【91】まで、それぞれのポイントを列記しておきます。
「光明を蒙ると身心柔軟(無我であるからどのようにも対応できる)にして、人天に超過せん」
「わが名字を聞きて。。無生法忍。。。深総持(智慧)を得る」
「身心安楽にして人天に超過せん」
「法を聞きて。。。わが善き親友なり」
「智慧あきらかに達し、功徳殊勝なる。。」
「広大勝解者」
「大威徳のひと、よく広大異門に生る」
「人中の分陀利華」
【92】から「道綽の安楽集」によって、「安楽集」の中に記述される「典拠」をさらに引用して、「諸部の大乗」を「更なる根拠」にしています。
「安楽集」中の「大集経」「涅槃経」「大智度論」「大経(下)」「大悲経」といった「経典」の引用をして、あらゆる「経典」に典拠があるといった記述をしています。
2019/06/09[5−19]
【93】の善導の引用は「疑い」について警告し、「いま」しか「専心に回向しなければ」チャンスはないことを述べて、このように「娑婆の本師」である「釈尊」の「勧め」を受け入れよ。。
という「現実的に真の仏弟子」になるためには「釈迦の教え」に依るという「現実論」を述べています。
【94】も「釈尊というさとりを得た人がいる時代」なんてなかなかないチャンスだから、「信受してその智慧」に依り「自信教人信」すべきことを述べています。
【95】は「十方如来(諸仏)も勧めている」ことを述べて、そこに「十地」の願行が「自然に彰われる」と記述されていて「初地」から「十地」という「等覚」までにも至る「願行が自然に表面化する」ことが記述されています。
【96】で、これらの根拠として「善巧方便則」で、「阿弥陀仏を専念する衆生《のみ》ありて」「かの仏心の光」が「つねにこの人を照らして摂護して捨てたまはず。。。」と記述されていますが、
ここで「専念する衆生のみ」と記述されている部分は「方便則」だからで、「阿弥陀の情動的ストーリー」によって「さとりに誘導するため」の記述で、「信文類」において想定される「行者」は、「真実則」がわからない前提であるから、このように「限定」記述されていると「確定推論」できます。
つまり「無碍光如来」の「真実則」「無為法」でいえば、「すべて仏性」ですから、「限定しなくても理解できるひと向け」なので、あえて「限定しなくても、道を逸れることがない」という前提です。
しかし「方便則」のひとは「道を逸れる可能性を含む」ので、このような「のみ」という「限定表現」を必要とするといえます。
そしてここで「現生護念増上縁」という記述があるのですが、「行文類」169ページには「摂生増上縁」が「証生増上縁」であるという「真実則」の論として「増上縁」が記述されていますが、ここでは「方便」の「増上縁」という位置付けになっています。
倶舎原則でいえば、「無為法」は「因にならない」ので、阿弥陀如来の法が「縁定義」されることは、「行文類」と変わりません。
ここで「ここまでの釈尊の存在」や「自信教人信」や「十方の如来の勧め」が「阿弥陀如来の心光」に依る「増上縁」であるという流れにおいて。。。
【97】で、その「光明」が「眼前する」「現ぜん」ということを「心歓喜得忍」と「踊躍に勝へん」と記述され、これが「韋堤希夫人の心に起こった」ことであるとして、「真の仏弟子」の事例として記述されています。
その上で【98】において「そこまでの教えの流れ」から「専念」「能念の人を指讃」「この人を分陀利の好華とする」「親友知識のごとくなる」「今生に命を捨てて諸仏の《家》に入ることを浄土とする」という「利益」を述べて、「五果門」の《宅門、屋門、薗林遊戯地門》に落とし込みされています。
また「今生に命を捨てて」が「現生において自我を捨てる」を意味していることは自明です。
【99】から「この真仏弟子は弥勒菩薩と同じ」であることを記述しています。
2019/06/11 [5−20]
【99】の引用は、「信文類」のここまでの内容をまとめていて、「往生を得て」「不退転に住す」と記述しています。
そして「不退転をサンスクリット語」では「阿惟越致(あゆいおっち)」というと定義し直して、「法華経」を典拠にして、「弥勒菩薩が得ている報地」であると記述し、「初地、不退転地」をいきなり「等覚」に持って行っています。
ここ【99】には「親鸞の大いなるロジックテクニック」があり、「阿惟越致」も「本来《初地不退転》」を意味しているにも関わらず、「梵語(サンスクリット語)」では、「法華経」の「弥勒の報地と同じ」を意味します。
と引用の中で「錯覚」を与えつつ、「阿惟越致が等覚位を意味する」と論じていますが、これは「完全方便則」における「言語定義のすり替え」によって「納得させる」手法です。
そもそもこれは親鸞オリジナルではなく、王日休というひとの「ロジック」です。
(参考)「王日休」の引用原文
我聞。無量壽經。衆生聞是佛名。信心歡喜。乃至一念。願生彼國。即得往生。住不退轉。
われ『無量寿経』を聞くに、〈衆生、この仏名を聞きて信心歓喜せんこと乃至一念せんもの、かの国に生ぜんと願ずれば、すなはち往生を得、不退転に住す〉と。
不退轉者。梵語謂之阿惟越致。法華經謂 彌勒菩薩所得報地也。
不退転は梵語にはこれを阿惟越致といふ。『法華経』にはいはく、〈弥勒菩薩の所得の報地なり〉と。
一念往生便同彌勒。
一念往生、便ち弥勒に同じ。
こういった手法(論法)は「かなり強引」ではありますが、「因に果が含まれる」「ましてや不退転だから」という「論理上」は「不自然」ではありません!
「治るクスリを飲んだのだから、飲んだ時点で治った」と言えるということです。
いずれにせよ、親鸞は「仏名を聞いて信心歓喜し、乃至一念せんもの《かの国に生ぜんと願ずればすなわち往生を得る》そして往生を得て不退転に住す」という文脈から、「生ぜんと願ずるなら」《即時》に「往生を得て不退転に住す」という、「願即往生」ですから、ここでも「現生往生」でなければ「不退転」は成立しません。
この文脈をさらに「不退転地」を「法華経」から「等覚の弥勒菩薩と同じ」という位置付けを定義しています。(初地という41位を51位と同じと論じているということです)
ただ、「すなわち」を「便ち」という記述で表記しているのは、「便宜上」という意味を内在していて、「初地不退転」は便宜上「等覚位の弥勒菩薩と同じ」という意味合いになっています。
そういう意味で【100】において「次いで」という「諸仏の次に」あるいは「弥勒菩薩のように次生に(成仏)」というポイントを明確にしています。
またここで「仏が弥勒菩薩に告げた、六十七億の不退の菩薩が往生したけれど、その菩薩は無数の《諸仏を供養》していて、次に弥勒がつづく」という引用で、「諸仏の供養」というポイントが示されています。
これは【101】も同じように、「仏が弥勒菩薩に告げた」として「無量億那由他百千の仏の所にして、もろもろの善根をうえて不退転を成した、だからかの国に生ずべきである」というように、ここでの「もろもろの善根」は「供養」を意味していると考えられますが、親鸞の教説でいうと「五念門」の「讃嘆門」と「五正行」の「讃嘆供養」は同じ定義なので、いずれも「供養」は「讃嘆」を意味していると考察できます。
しかし、【102】において、この「供養また、もろもろの善根」をもって「一切の衆生がさとりに至る」という教説は、「華厳や法華」以上の「不可思議功徳(阿弥陀如来の万徳)」がその根拠であり、その根拠から得る最高の「利」であるという意味を表現していると推察できます。
ですから【103】で親鸞は「格調高い情的な表現(方便則表現)」で、「弥勒は等覚を窮めたから《竜華三会の暁》に無上覚位を極める」(竜華三会は弥勒菩薩が五十六億七千万年後成道説法を意味しています)ということを、
「念仏衆生は横超の金剛心を窮めるから《現生自我滅》の臨終一念(信の一念)という《夕べ》に《大般涅槃を超証する》という利を得る」ということに対象させています。
ここで「便同」ということをあえて記述して、「便宜上」「弥勒菩薩と同じ」というということを明確にしています。
そして、「念仏衆生」について、「信の一念」という「金剛心」を獲る(獲は因位)ものを「真の仏弟子」についてあらわした「韋堤希」と等しく「さとりの三忍(喜、悟、信)」を獲得する」と記述しています。
ここで「さとりの三忍」を「等覚位では因位で《獲る》」「妙覚位では果位として《得る》」を含蓄させて「韋堤希」と等しく「獲得」するという表現をしています。
さらに、これは「往相回向の真実心」が「徹して衆生に信として到った」ということであるという「不可思議の本誓」によるということを【102】の「不可思議功徳の利」に合わせています。
結果ここにおいて「真の仏弟子」という位置付けには、「因位では韋堤希と等しく」「弥勒菩薩と同じ因中の果(等覚)」の利を「因果において獲得」することを明確にして、その根拠が「本誓の不可思議功徳」であると言っています。
なお、ここで「本誓」と記述されて、「本願」と記述されていないのは、「願は衆生にも適用される文言」または「誓」には「願という因が必ず果を引くという意味を持つ」からと推察できます。
2019/06/14[5−21]
信文類が単独で「方便則」として成り立つように構成されているのは、つぎの【104】から、「真、仮、偽」について記述されているところからもわかります。
【104】で、念仏者を讃じて、【105】で、中国のあらゆる賢人も最後には「浄土を願っている」という内容が記述されています。
ここでは、とにかくあらゆる賢人を記述して、「仏教がわかっている人」や「そうじゃない人」まで、ごちゃ混ぜなので、「浄土を来世」と願ったひともいるかもしれません。
おもしろいのは、「天台大師 智顗」が挙げられています。
この「智顗」は「摩訶止観」を書いていながら「行じてない」といわれる人ですが、世の中は、そういうことより「偉い人」定義(肩書き)ですから、こういう人が連ねていても、スゴイことになるのでしょう。
【106】は、「仮」の「善巧方便」ではなく「マジ方便」について「聖道のひと」や「定散のひと」は「浄土の方便」のなかのひとという定義です。
そして【106】から【109】までに、そういうひとは「この善巧方便則」以外の全ての仏教で、それらは「善巧方便則ではないマジ方便則」だから「無生の生」のさとり(真実証)に至るまでには時間がかかると記述しています。
【110】から【112】までは「偽」のニセモノについて、「邪道」と定義しています。
【113】に、親鸞は「自我滅」して、第十八願にある「唯除」がさとる「真実」を、「阿闍世」になぞらえて「慚愧」という「自我滅」について、「長い物語り」を引用して、「因縁話し」のような記述をしています。(あまり長いので、詳細は省きます)
しかしこれが、【121】で「唯除」の「抑止文(おくしもん)」の解釈であり、【122】で「謗法も闡提も」「回心(えしん)」すればみな往く」と記述して、【123】において「極悪の五逆」のものも「慚愧自我滅」して「回心という一心」で「さとりに至る」という「真実則」を「方便則ストーリー」で解釈しています。
これは「五念門」の「流れ」で「回向発願」するという「真実則」に符合することを、「真実則」がわからないひとへ向けて記述されていて、「言っていることは同じ」なのです。
ここまでで「信文類」は終わりますが、第十八願と成就文を「至心信楽」と「至心」を「疑蓋無雑の一心(信楽)」で「疑いの蓋」を開けて受け入れれば、自ずと「欲生心」が生まれて、「真の仏弟子」になり、「慚愧自我滅」するひとになって、「利他を行じるさとりに至る」という、「教行証」の流れを「善巧方便則ストーリー」で解釈して「自性唯心」のものを「さとりへの教え」に導いています。
ですから「信文類」は、「文字も読めない書けない」と言ったひと「論がわからないひと」へ向けた「教行証文類」の「方便則文類」といえます。
つぎに「化身土文類」に移ります。
|
教行証文類講義その5 |
374ページから「化身土文類」です。
「化身土」について「観経」と「阿弥陀経」の「意」だとしていますが、「化身土」を、タイトルでは「方便化身土」と記述しています。
つまりここで「論じ」られる内容は「善巧方便」ではない「マジ方便」ということを言っているのでしょう。
これを「仮」と定義して、「仏教以外」を「偽」としています。
とはいえ、《仮》という定義であっても、「真実則」からでている、または「真実への誘導」ならば、これも「真実の中身の一部」といえますから、「否定」ではありません。
しかし「意外にも」この「化身土文類」の《偽》の部分は「かなり長い引用」がされていて「明確な否定」をしていますから、よほど、「偽」について「仏教ではない」と明言したかったのだと推察できます。
【1】において、化身土は「無量寿仏観経」の「真身観」に説かれている仏身と「観経」に説かれている、「三昧(観想)」における「浄土」という定義をしています。
ここでなぜ「無量寿仏観経」という文言と「観経」という文言を並記しているのでしょう。
推察できるのは、「真身観」は「無量寿仏を三昧という行で観察する」「観経の第九観想」限定の《方便法身》であるというポイントを明確確定しており、「浄土」は「観経などにおける《あらゆる部分共通》」の浄土であり、「菩薩処胎経」などにある「懈慢界」という「観経を中心にした広い意味での浄土」という定義になるからだと考えられます。
ここで、浄土を単に「土は。。」という記述がされているのは、「器世間」という「場」をあらわしていて、「阿弥陀如来の浄土」に限定していないと考えられます。
また、ここでこの「化身土文類の仏も土も」ここまでと同じように「現生における《行》」とその《果》について「一貫して《現生定義》」で読まなければ、「あいまいな理解」におちいります。
そこでここをまとめると、「仮の仏と浄土」は「現生で真身を観想するための形」である《第九真身観》に説かれている「観想(瞑想)上での仏身」であり、その「果」は「懈慢界」になる。
「そしてまた《果》について」は「大無量寿経」に説かれる「疑城胎宮」になる。
という内容です。
この「真身」を「図形」であらわしたものが「私たちの本堂や仏壇」に安置されている「方便法身」だということになりますから、「仏像」を「真実と思っては間違い」ます。
ここで、「懈慢界」や「疑城胎宮」という《果》について、これらの文言の内容は「この時点」では定義されません。
この時点では、察するに「観想行」の仏をイメージしても「無色無形絶言」という「真実則」から論じたら、この観想は「不確定なイメージ」でしかなく「そのイメージが《行者に依存され》かつ《実在というイメージになる》」から、
「懈慢界」という「おこたりや慢心」という「果」になるということです。
まだこの時点では、よく言われる「自力念仏」に「行」を定義していません。
標挙には、「至心発願」「至心回向」という記述がありますが、内容は不確定です。
この段階でこの「因果」を推定する理由は「このように観想することは難しいから怠る」または「このような実体ではないものを観想したときに《慢心》が生まれる」ことが「《浄土教や観経の基本定義》である《仮の方便》がもたらす果」だからでしょう。
これを「念仏限定」するのは、この後にいたる流れの中で「定義」されます。
また、この「果」を言い換えて「疑城胎宮」というのは、この時点で文字から察するに「疑いによってお城にいる気持ちになる」つまり「慢心」という「自我におさまってしまう」けれど「じつはその行者は胎児が子宮にいるような《生まれる以前の状態》」と言えて「《証果》を得られない」という状態であると定義していると推察できます。
2019/06/28[6−2]
そもそも「化身土文類」は、「廃立」つまり「仕分け」(裁き)のような側面がありますが、それが、「排除ではないこと」を根本にしていることが重要ポイントです!
さとりに向かわせるために「あえて記述されている」と考えなければ、単純な「セクト」になってしまい「これ以外はダメ」という「選択肢」を与えて「選べ!」と強制しているように読むべきではないでしょう‼️
なぜ「それが《仮》であるか、《偽》であるか」を論じて、「仕分け」の論理を示している。
そう理解しなければ「返ってほかの宗派や信じていることを持っているひと」とケンカしなければならなくなります。
または、「これ以外の人は《地獄に行く》」という「自己満足」で終わります。
この「自己満、自己中」を「自我」として「廃すべし」という内容なのに、逆に「自己満、自己中」を「増上」してしまうことになります。
「お西のごく一派の論題」こそ正しく、あとの「世界中の思想」は捨てなければならない。
なんていう「カルト」になってしまいます。
そういう意味では、まったく「逆効果」になってはいけないので、あえてこの重要ポイントを書いて進めていきます。
ーーーーーーー
そこで375ページの【2】は、「汚れた時代に群れているもの」「よごれた悪を認識に含む(阿頼耶識に種子を含むもの)」は、九十五種類に分類される「外道(仏教以外)」を邪道として、「やめる」ないしは「受け入れないように」して、「仏教の中でも中途半端な教え」の「法門」に入っても仕方がない。
だから、「希(まれ)な真実」に入るべきである。
しかし世の中には「仮や虚偽」が多くはびこっている。
だから釈迦は「いろんな良いことや諸々の行をすれば浄土に生まれる」という「福徳蔵」(福や徳がしまわれている阿頼耶識)という「方便」で真実に誘導して、結果「阿弥陀如来の第十八願」によって、「諸有」(二十五有)の衆生海、深めれば「諸有(一切有)」の海に真実を与えられるといい、しかし、釈迦が「諸説を説くまでもなく《大悲の願》(悲願)」があって、第十九願の「修諸功徳の願」に、「臨終に現前する」「現前して導生」「来迎して引接」する願いがあります。
という論理で「第十九願」は、主に「観想」を説き、その他の「良い行い」を含む「願」であると定義して、これは「自己のイメージで、至心を作るように発願する願い」であると言っています。
【3】にこれは「大経」の「第十九願文」が根拠であると引用しています。
【4】は異訳で「悲華経」の「第十九願に該当する文言」を引用しています。
従来、これ(第十九願)を「単純に死ぬ時」に「来迎が来る」ことを説いているという解釈が一般的ですが、ここで親鸞はあくまでも「定散九品」という定義を【5】に記述していますから、「観想(三昧)」を基本にして、「さまざまな行」に広げているので、「現生に観想する行」という定義で読む必要があります。
そこでいう「臨終」は、「心の命の臨終」または「自我の終わり」を意味しているといえます。
そういう意味で【6】【7】には、「観想」を示すような引用がされています。
そしてこの【7】においては、冒頭の「懈慢界」「疑城胎宮」をポイントにあらわす内容になっています。
ポイント部分の「疑城」は、「まるで《自我がお城の主》」であるような、まったく「仏の文言を受け入れていない(屈服していない懈慢界のおごり)」ということをあらわしていて、「胎宮、胎生」は「母胎の子宮に着床」するほどの「生」ということで、「生まれ出ていない」と解釈すれば「あいまい理解」にはなりません。
どうも「真宗学」では、「浄土に生まれた」けれど「疑いの城に閉じこもっている」というような解釈で、生まれているのに「城に閉じこもる?」っていうことが、現代では「お城に(引き)こもれる方がラッキー」なんていうふうに理解されてしまいそうです。
このあたりは「観想」つまり「天親の唯識論」前提であると理解すれば、同じ「天親の倶舎論」からの論理であると言えるので、「倶舎論」の「十二縁起論」でいう「無明の着床」という部分と「胎生」は「一致」します。
「子どもが母胎の子宮にまでは着床したほどの状態の生」と理解すると容易にこの部分が理解出来ます!
いずれも「自我行(疑城)」ということと、「子宮の胎児という生果(無明の着床→胎宮)」で理解すれば、「諸行や観想」による「勘違い」が導く「果」は、浄土にまともに生まれられない「胎児」でしかなく、「無明の生になる」ことを言っていると解釈できます‼️
2019/06/30[6−3]
【8】の如来会の引用で、「疑い(疑悔)」によって「仏智を求め」て、自己の善根を積むことをしているものは500年は「宮殿」に住んでいるだろう、というような内容になっています。
「わたしは功徳を積んでいる」という「自己満」、いわば「おめでたい宮殿にいるようなもの」ということでしょう!
この辺の表現は、「観想的」ですが、「弥勒菩薩」に釈尊が「仏智を信じたものは」。。「浄土の蓮華に禅を組む」ように「化生」しているという記述に「?」となるかたもいるでしょう。
なにがというと、弥勒菩薩はこんなに釈尊のことばを聞いていて、なぜ「菩薩」のままなのか?
仏が滅した「五十六億7千万年後」に「成仏する」ことに、なんの意味があるのか?
「そもそもその頃には地球自体がないかもしれない」のに。。
さっさと「成仏して、還相回向したらいいじゃないか⁉️」って。。
これも「僧侶ではない方」からの指摘ですが。。
まぁ「地球が🌏あるかどうか」は置いといて。。
「あえてそういう選択肢がある」としかいえないけれど、「そういう選択肢がある」といえます。
あくまでも「修行中」であるという立ち位置で、如来のことばを素直に聞くというスタンスに「身を置く」という、「現生正定聚」である「真実則」で読めば、「弥勒菩薩」は「わたし」であるという立ち位置になります。
現生で「浄土に居ながらも還相回向の菩薩」のように「利他る」ことが、「弥勒菩薩もじつはすでに成仏を経て、還相回向の菩薩」という意味での「菩薩」であり、「利他」る衆生が居なくなると考えられる「五十六億7千万年後」までは「他利利他」に徹するという考え方もできます!
仏教は「無常無我」(三、四法印)の根本を間違えなければ、自由に解釈できます❣️
ただしこの「三、四法印」が抜け落ちたら、仏教ではなくなり、「世俗の持ち越し」になってしまいます‼️
いずれにしろ【9】【10】において、「とりあえず、小行の菩薩も少功徳を修習のものも、みんな往生する」「とにかくそういう人は多いであろうけど往生する」ってあるのは、「とりあえず生まれても《辺地》《宮胎》に堕ちます」という【11】の文言につながり「結果これらのひとは、辺地や宮胎にしか住めない」ということが、いいたいのでしょう。
これは、「現実的に、三、四法印」に背いていて、「すべて自我行」なので「破我」の「屈服礼拝」にすらならないから、「雑毒の善」というように「自我(毒)が混じっている」ということになるからです。
「わたしは良いことをしている」というひとほど「厄介なひと」はいないといえるかもしれません。
押し付けや押し売りのようになったり、それが「自己防衛」だとわからないままになります。
「毒」は「自然界」では「生命体の自己防衛」として存在しています。
「雑毒」というのは「自己防衛」。。つまり「自我防衛」だといえます。
そういうステージで、「往生してる」「往生できる」と思っていても、ほんの「辺境」でしかなく、「深い理解を得られず」「お城の殿さまのよう」に、自己満に堕ちる(はまり込む)という事実を言っています!
これを「観想」からいっても「自我の世界観から出られない」「自我の浅い次元から広げられない」ということを意味しているといえます!
仏智を信じて「往生」を得て「正定聚」に「住むもの」は「如来になれる」ということを「スゴイ」と「喜ぶより」以上に「他利利他の観察」に生きる重要性を「破我」「屈服礼拝」の中から得(獲)て、「讃嘆行」に生きるようになるということが、「利他のために現実を深く見る」「高いステージに自然に上がり、俯瞰できるようになる」という現実になることの方を「選択本願」する(本願を選択する)のです‼️
【12】に「仏智を疑って浄土に生まれて、これは辺境だ、教えが得られない」「まだ胎児のような状態だ」と思うなら、「疑いを捨てるべきである」という記述があるのは、「死んでから先では、判断できないこと」であり、ここまでが「いま」を論じていることが読み取れます。
【13】【14】はここまでのいったんの「結論」です!
2019/07/03[6−4]
381ページの【14】は、「念仏証拠文」などという、当時から「証拠」という文言に意味があったのか、わざわざこの文言を入れています。
まどろっこしいので、大雑把にいえば「自分がいかに《無能》か」ということをよく考えて、第十八願は、「特別の中の特別で、もうどういえばいいかわからないほどスペシャルな願い」だと書かれているから、「弥陀を称せよ(弥陀を称讃せよ)」とごり押し的な引用という感じがしますが、 ここにある「おのが能を思量せよ」が重要なポイントです。
「自我に振り回されていて、さとれるなんて思ってる」のですか‼️という、けっこうキツめな内容です。
この辺は「観想念仏」と「人間の能力を《定散の仕分け》《三福九品の仕分け》に定義することが目的だから、やたらと「観経」が出てきます。
そこで論としては「ここまで《真実則方便則》《一元と二元》のダブルスタンダードで教行証文類が記述されてきたのと同じように」。。
「観経」もダブルスタンダードであり、結果「真実則の一」という「論」を展開していきます。
それが【15】に「観経」の三心について、問答形式で説かれている「顕彰隠密(けんしょうおんみつ)」という内容です。
ここでもわかるように「化身土文類」の冒頭と同じように、真実則で「観経」を記述するときは「無量寿仏観経」という記述がされます。(どうやらこのことは「現代語訳」には反映されていません)
そして「方便則」の場合には「観経」や「観無量寿経」と記述されていて、ダブルスタンダードをキッチリ分けています。
そして、「信文類」に「至心は観経の至誠心」ってすでに「解釈している」ことを、改めて、「表面的には違って見えるけど、じつは同じなんです。」と親鸞は言いたいのですが、
とりあえずお決まりの
人間を仕分けて、「三福」について、「善導が」「第一の福を世俗善」という「世福」とし、「第二の福を戒善」という「戒福」とし、「第三の福を行善」という「行福」と「仕分け」ています。
ここでいう「世福」は「世俗の善根のことで、仏法にはまだ出会っていないけど、「孝養に努め仁・義・礼・智・信」という「儒教などで推奨している善根」の徳目(道徳)を行じることをいい、「戒福」は「戒に《人天、声聞、菩薩》の戒があって、戒の実践」を示しています。
「行福」は、「大乗の心をおこしたもほが、キッチリ修行して、人にも勧める」という利他を実践して、かつ「悪を捨てて心をそのまま維持すること」をいいます。
九品は、
「上品上生、上品中生、上品下生」は「大乗の善(行福)を修める凡夫凡人」
「中品上生、中品中生は、小乗の善(戒福)を修める凡夫凡人」で
「中品下生は(世俗の善根)を行なう凡夫凡人」
「下品上生、下品中生、下品下生は罪悪の凡夫凡人」という「能力仕分け」の目安です。
この文言の「二善」は「観想念仏の《定善》」と「日常的な心を意味する《散善》」で、「三福」は↑上に記述した「ステレオタイプ」の「能力分類」です。
とりあえず「こういう自我でなんとかしようなんていう人たち」は、そもそも「報土の真因じゃない」し「諸々(上中下三輩)」の人間も、「自利各別(それそれの思いで個人的な)三心だから」無我という定義に統一した「利他の一心」ではありません!
あくまでも「如来が仮の方便として」まずは「とりあえずなんでもいいから浄土を願(欣)わせる」真実とは「違う(異)」あくまでも《方便》で、「観経の《表向き》(顕)のスタンダード」ですという「論述」です。
そして「彰」っていうのは、「真実が隠れて彰されている」ということで、
「如来が弘く色んな者(機)を摂めとろう」という「利他に通じる《一心》を彰して」いるという「如来が《真実則の一心》に誘導しようとしている《如来からの至心信楽のこころ》」が、ここには「隠されている」んです。
というと、「ありがたい!」ってなりそうですが、ここで「自我」を喜ばせていると「我への欲」になりますから、「静かに《無我という生命状態》になっていける《真実道》なんだ」と読み込んでいきましょう。(欲について補足その5の151を見てください)
しかし、こういう「ダブルスタンダード」があるということを、親鸞は発見したということを俯瞰してみると、ほんとうに「ジーニアス(天才)」だという「超人的な論述」であるという感は否め。。とにかく「スゴイ」と思います。
2019/07/06[6−5]
【15】で「顕彰隠密」の「顕」について、「観経の三心と大経の三心」が同じか違うかということから、前回↓記述したように、「定善、散善と三福」のものは「各々が自己によって判別する《自利の行》だから《利他》がない」ので、「大経の三心と観経の三心」は「表向き《顕》を見ているだけなら違って見えます」と記述しています。
そして「彰」とは、「如来の弘願を彰して」「利他通入の一心をひろくグングンエネルギーを増していくように広められていく」と記述して、そのキッカケが、「提婆達多、阿闍世」の「悪逆」だったことを記述し、この出来事が「釈迦出世の本懐(素壊)」を彰す「事件」であると記述しています。
またさらにこの「事件」によって、「韋堤希が南无阿弥陀仏を選んだということ」により、釈迦が微笑むような「弥陀の大悲の本願がそこで開かれた」といういきさつを以って「隠密」と定義しています‼️
ここでいえるのは、この「事件の表向きの人間のありさま」の中に「真実がある」と釈迦は言いたいのであり、この事件そのものが「事実かどうか」でなはく「布教使が〇〇なことがありましてね〜」などという「因縁話しを創作する」のと同じようなことかも知れません。
涅槃経や観経など、けっこう「あちこちにこの話」は出てきますが、「事実というより、釈迦の持ちネタ」だったのかもしれません。。「なんていうと目くじら立てて怒る人もおられるでしょうが」ど真剣です‼️
これが事実なら「ミラクルなこと」になります。
観経は「一経二会」といって、「韋堤希」が牢獄から「助けて〜」って叫んだところに「釈迦が現れて」同時に二ヶ所で説かれたということや「阿闍世」の病魔が、この教えに出会って治ったなんていうことは、ほぼ「ミラクル(奇跡的)」なことであり、
よくいわれるこの「王舎城の悲劇」は、「比喩的に創作されたストーリー」でなければ、釈迦は「この事件の全体の問題を解決せずに、個人的な救いだけに関わっていた」という、「木を見て森を見ない」ということになるでしょう!
もとい、つづきに「教我観於清浄業処」と「主語は書かず」このように「わたしに清浄業処を見せてください」と請われている場面ですが、ここでの「清浄業処」は「本願(ここは四十八願)が成就した功徳荘厳」という「報土」を指していると記述しています。
そして、「観経」によく出てくる「教我思惟」(わたしに観察を教えてください)と「請い願う」という「方便説」と、
「教我正受」(わたしに正しく受け入れられる法をを教えてください)という「金剛の真心(つまりは信心)」という「真実説」が説かれていて、それは、「諦観彼国浄業成者」つまり「あきらかに彼の国を浄業によって成した者を諦観しなさい」と言って「阿弥陀如来」を指し示しています!
ここで382ページの4行目は「清浄業処」という「場所」を指していて、この部分は、「浄業成者」という「生命体」をあらわしています。
そしてそうなりたいのなら「本願成就」の「尽十方無碍光如来」を観知すべし。。
とありますが、これは「無為法の如来」を「本願という智慧を通して観察」しなさい。
という意味がここまでの内容から「推察」できます。
「光明」→「智慧」→「本願」の次第が、「本願」→「無碍光」→「阿弥陀如来の観察」という「方便則の次第」になっています。
つまり、ここでは、ほぼこの部分の主語が「韋堤希」ならば、「方便則から真実則」へ向けなければ「成仏不可能な機(人間)」には、通じないからだと思われます。
こういう部分を「教行証文類」全体の流れから読み込まなければ、「ここでなんで《無碍光如来》の立ち位置が逆転しているのか」ということがわからなくなり、「意味不明」に陥ります。
つまり「無色無形絶言」から「無碍光」という「光明」が「如来して」、それを「智慧」と定義して、「機根(真実則がわからない対象者)」のために、「方便則」の阿弥陀ストーリー(なかでも四十八願)によって「仏智を得る」という流れで進んできており、その流れで「信文類」では、ほぼ無碍光如来には言及せず「阿弥陀如来の完全方便則」で「さとりに至るシステム」になっているから「《無碍光如来》の出番がなかった」のに、いきなりここで、「阿弥陀如来(本願)と無碍光如来」の立ち位置を逆転させているのは、「観経の対象者」が、「真実則」が理解できないと思われる「韋堤希だったり阿闍世だから」と言えます。
しかしここであえて「尽十方無碍光如来」を「親鸞」が出してきているのは、「根本は《智慧》と言いたい」からなのでしょう!
「無色無形絶言」から「智慧の本願が出て」それを「無碍光如来」と「無為法の真実則定義」をして、「対象者」に応じて「智慧の本願」を「有為法と錯覚させる《阿弥陀如来》」の「善巧方便」として説いた。
という「教行証文類」の全体が「ダブルスタンダード」だからという理解です‼️
なお「真実則」の「四十八願」は、「法蔵菩薩(有為法)」の「五念門行」として「定義されて」います❣️
2019/07/08[6−6]
382ページのつづきに「広説衆譬」(広く諸々のたとえを説く)といって、「観想」の「十三の方法」を説いている「定善十三観」を示して、「汝はこれ凡夫、心も想いも羸劣(劣っている)だと知りなさい」というような「観経」の内容から、「汝」を「韋堤希ではなく、この化身土文類の読み手」に設定しています。
ここで、「悪人往生」の「機(人間)」と「読み手」に認知を促して、「諸仏如来には云々」と「観経」の「隠彰」は、結果「みんな下品下生である」と「顕わして」いると記述されています。
親鸞の緻密さは、ここで「彰」から「顕」に文字を変えて、「隠れていたものが現れてきたこと」を明確にしています。
こういったことは「註釈版」ではなく「漢文のまま」で読むとわかりやすいですが、「現代語訳」などにおいても「キッチリ漢字をわけてありますから」緻密な表現であり、親鸞の緻密さは「半端ない」ということが明確です!
このペースで書いていると、「化身土文類」は長いので、ポイントを拾い上げていきます。
383ページのはじめに「観想」を「方便」であると確定定義します。(善巧方便よりレベルの低い方便)
だから、【15】に終わりに「大経と観経の三心は同じ」と定義します。
ーー→なんだか最近、あくまでも「仏教以外」だから「お知らせ」(インフォメーション)に載せている、キリスト教と仏教の関係において、「仏教の真実則の観点」から見たら、キリスト教にも「顕彰隠密」で「論が立てられる」ということが、この化身土文類にかぶってきて。。
【重要】
《「化身土文類」は「排他論ではない」「摂取の論だ」という前提を間違えずに読めば。。》
ーーー
「中国に渡ってきたキリスト教」である「景教(けいきょう)」が、空海、最澄の時代から、高野山や比叡山(日本)にもあったということや、西本願寺に「景教のバイブル」があるということからしても、親鸞が「景教」を知っていながら「どこにも記述していない」とするなら。。
景教にも、「仏教から見たら顕彰隠密があると思えて仕方がない」という「アタマが先走」っていて、このことから、「化身土文類の《顕彰隠密》という観点は、あらゆるところにある」と思えるから、ニセモノ(偽)に居るものを、まずは「第十九願」の諸行まで「誘引して」、さらに「第二十願」の自力(自我)念仏に誘引して、結果「第十八願」の他力(無我)へと誘引するという「果遂」。。
【68】の「三願転入」の前提に論じられる「顕彰隠密という論点」は、「世界中に張り巡らせてある」といえるなぁって思いながらも、じゃあそれが「世界中のさまざまな価値観の中」で、「仏教」や「浄土真宗」という「文言である必要もない」という「深い意味」が理解されるだろうか?
「さとりという境界」では「《コトバ自体》が俗諦を誘引する方便」という「無色無形絶言」を伝えるため「俗世にあわせるために使用されている」だけなのだから、《文言が》「なに教」や「なに哲学」でも「なに科学」でもいいといえる。。
お西の稲城和上は「西洋哲学」を引用したりしていたけれど、「哲学は宗教に準ずる」という「位置付けか」ないしは「部分引用」だからか、誰もが認めていた。。否、「稲城(和上だから)」誰もが「なんの疑いもなく」受け入れていたのか。。
お東の「清沢満之」は「西洋哲学骸骨」という書も書いている。
そういう意味では、すべてに「顕彰隠密があり」いまや「キリスト教」にも見える。
けれど「このA」が言っていても、ほぼだれもが「なにいうてるんだ」っていう感じになるというか、「言うてる内容が意味不明」となるだろうなぁ。。
って思いつつ、人間の脳が導き出しているかに思える「創造」の世界というのは、「神であろうが、如来であろうが」《人間以上の何か》に寄っていて、結果同じなんだと「観察して」います。
そうすると大概の現代人は「宗旨が違っても、行き着くところは同じでしょう」って簡単に言うてくれるけれど、「そういう人は行き着くところの付近まで来てから言うてほしい」。。
「傍観者」には「絶対にわからない」‼️
さらにいえば「浄土真宗」にこだわっている方が「辺地懈慢界」にいて「疑城胎宮」だった気がして。。
「蒜山(ひるぜん)高原」で感じた「無条件な自然」の中で「どーでもいい感じになって」ひろーい世界に出られた「以後」この感覚のなかにいるから「すべてが顕彰隠密だ」という観察があり、「浄土真宗」という文言にこだわることが「疑城胎宮」なのだと思えて仕方がないのです。
そしてまた「このタイミング」での「高原と化身土文類」というシンクロ二シティが、ユングの「共時性」と言う感じもあり、まさに「言葉にできない絶言」の感覚です‼️
(もはや、「おまえの勝手」「自然界は厳しい側面がほとんど」だとかなんだとかいわれても、論を尽くせない状態です)
(また、「自然界」においても、日本はほぼ《山》と平地だから広いところにいて、「空が近い」「周りになにもない」という自然界は、「智願《海》」と同じなのかもしれないから、親鸞は「海」をよく使うのだろうか。。と思ってみたりします。)
だからといって「なんでもいい」と言うのではなく、あくまでも「教祖のような意図的な人物が、操作のために作った団体や」いわゆる「カルト」や「資本主義などのイデオロギー原則のもの」は、「ニセモノ定義」で「摂取すべき機(ひと)」だといえます。
多くの僧侶が、それを「嫌悪する態度を示しますが」嫌悪するのではなく、以下のような姿勢で、「受け皿」になるべきことを学ぶべきでしょう❣️
https://r.goope.jp/sainenji/info/2680906
「化身土文類」は「排除の論」ではない‼️
このことは「腹に据えなければ、正意はわからないことに陥ります」から、何度も記述しておきます!
ただ、どうしても「このことはこの本論に書いておかなければいけない気がして」いまここに書いて、今日はこのままで、キーボード(筆)をおきます❣️
2019/07/11[6−7]
【15】383ページに、「観門」は「方便の教え」と定義し、「三種心をおこすために説かれていて、便宜上、即往生と説かれてはいる」と記述して、文の流れから「このことは、三種の衆生が、当来に往生を得る」ことだから、さきに記述している「三輩」各々に「三種の三心がある」と抑えています。
この「三輩」は「定善(自力、自我諸行)、散善(自力、自我念仏)、本願(他力)」の三輩と「教学上」定義されますが、
これは、この講義の[6−4]に解説した「観経」の三輩と、「大経」の三輩(註釈版41ページ「大経下巻」始め)を合わせて、定義をしています。
「大経の三輩」↓
① 上輩→菩提心をおこして、無量寿仏を念じ、諸の功徳を行じる。
② 中輩→沙門となって、功徳を行じる心をおこして、ただ無量寿仏を念じて、善を修める。
③ 下輩→ただ菩提心をおこして、一心に無量寿仏を念じる。
こんな風な細かしい「仕分け」をしているのは、「顕彰隠密」を明確にするためですが、
この内容は「とにかく自力行は、所詮《自我行》でしかないけれど、ここから入らないと納得しない人が多い」から、
あえて「大経と観経」の「表向きは違うように見えても、じつは同じ結論に至る」ということなんだと明確にしています。
ここでは、このことが理解できればいいんです‼️(あえていい切ります。)
だから
【16】には、まず「釈迦」が「韋堤希」に請われて、浄土の教えを説くなかで「とりあえず浄土の教えの《要門》をひらいて、「安楽の能人(阿弥陀如来)」がそのなかでも、「特別な《弘願》を顕彰したのです」と記述しています。
これは、浄土の「要門」を「釈迦」が説き、そのなかでも「第十八願」は、「大経で《釈迦が弥陀三昧》」で説いた「弘願」であり、この「第十八願」の弘願が「観経の隠密」であると論じています。
(弥陀三昧は、教文類の「五徳瑞相」に従っています。)
このように「やや複雑な内容」ですが、「観経では《観仏三昧》や《念仏三昧》を説いているように見えるけれど」、「観経」でも「釈迦が弥陀と一体になって」「一心に回向発願(回願)して、浄土に往生する」ということが結論です。
【17】に、同一の内容を記述しています。
ここでも結論は、「観経」も「菩薩蔵」であり、「他力の《頓教》である」という結論を論じています。
ここで「菩薩」「蔵」が、「法蔵菩薩」を暗示していると読み取れます。
【18】からも「このこと」を詳細に論じていますが、「以上の内容」に「特別異論がなければ」ほぼ斜め読みでも問題はありません。(といい切らせていただきます!)
ーーーーー(以下参考)「大阿弥陀経の研究」佐々木大悟氏より
第十節では、「大経」(無量寿経)の異訳である『大阿弥陀経』の「付加の問題」を取り扱った。『大阿弥陀経』は、最古の訳であるため、さらにそこに古層・新層が分けられるのかという関心から、古米様々な付加の議論がなされてきた。
そのうち、「面白」や「義」・「礼」・「仁」、「自然虚無之身無極之体」の単語を基にする付加については先哲により指摘されている。
文章単位では、「帝王と乞人」の筒所・「三輩段の直後の二輩」・そして「三毒五悪段」についても、 異質性が指摘されており、 これら の付加には私も賛同する。
ただし、「観音・勢至に帰依する箇所」「阿闇世王太子授記の場面」については 従来にも付加の指摘があったが、 『大阿弥陀経』のもつ雑多性という特徴から、付加ではないと判断した。
ーーーーー(以上引用)
つまり「観経」は中国で作られたというのはほぼ定説になりつつあり、また、「大経」にも「古くから、中国で作られた部分が混ざっている」という指摘があるが、「三輩」についても「中国で付け加えられた可能性」は高いと言えるかもしれない。
2019/07/15[6−8]
【18】について、斜め読みでも結論が、【67】にありますからいいといえばいいのですが、あえて言えば【18】からは、「信文類」216ページ【13】の内容を、「自利真実」と「利他真実」の側面から論じ直しています。
これは、「教行証文類」が「教→行→証」の「五念門メイン」と「信文類」メインの「ダブルスタンダード」で論じてきて、「真仏土文類」で、「真仏土を光明と智慧」に定義して、「その両者に《化身土》を論じるため」に、再度「信文類」で引用した、「観経の三心と、大経の三心が同じである」というポイントについて、「無碍光如来と阿弥陀如来」以外の教えとの対比によって明確にするためだと思われます。
そうでなければ、この辺りは同じ内容の繰り返しを「対比の中で持ち出してきている」というまどろっこしい繰り返しにしか過ぎないことになります。
そこで【18】のポイントは、「如来」は「相手の資質を見て説く」ということです。
【20】に、「自利真実」「利他真実」と記述して、「自我行と他利利他行」の違いについて記述しています。
そして「利他真実」は、「讃嘆」であることを強調しています。
ここは善導の引用なので、「一心専念、弥陀名号」の文から、正行の「読誦、観察、礼拝、称名、讃嘆供養」を引用して、「一心」を基にした「正行」を行じることを「正定業」と定義しています。
ここでは、先に「深心→深信」によって「別解。。異学。。」によって「退失傾動(退いたり、動揺したり)しないよう」に警告して、「正行、正定業」を行じることを勧めており、この部分の終わりには「三つには回向発願心」「みな真実の深信の心のうちに回向して、かの国に生ぜんと願ず」という「五念門」に落とし込んでいます。
これは、善導もこの結論に落とし込んでいるので、「善導も曇鸞も」「浄土論」に抑えを置いていることがよくわかります。
【21、22、23】はここまでを、端的に「箇条書き」しています。
【24】では、「信文類」のように、ザクッと「三心」の解釈をして、「もし一心かけぬれば」の部分に「少」を持ってきて「少(か)けぬれば」と記述しているのは、「少しでも自我が混じっては、生を得ない」と「観経」の「隠密の意」を明確にしています。
ここにつづく「菩薩はすでに生死を勉れて(まぬがれて)。。。仏果を求む。。」という「自利」の中身に「すでに」「未来際を尽す、これ利他なり」という記述は重要で、「菩薩道には《仏果と利他の未来すべて》が含まれている」という内容になっているのです。
ここでも、この教えは「死後定義」ではなく「現生定義」であることが明確であり、また、「しかるに今の時の衆生。。。縁に随(したが)って。。。往生せんと願ぜん。かの国に到りをはりて。。。《自然任運》にして、自利利他具足せざることなし。。」という記述に、
《自然任運》とあるポイントを、お東の「清沢満之氏」は《任運に法爾に》と「絶対他力の大道」に書かれていますが、「利他真実の三心により回向発願すると、今この時に《未来際を尽くして》利他を行じるものに《自然任運》になる」ということが記述されています。
2019/07/17[6−9]
【25】に、「専(正行)を捨てて雑業を修行するひと」について、《本願と相応しない》から「雑縁乱動、云々」と記述があり、「どうでもいいような世俗にまどわされる」と言った意味内容を読み取れるような記述をしています。(本願と相応することが、仏教と相応することになります)
そしてこれらは、「慚愧懺悔」という《自我滅》を得ないことを指摘して、三品それぞれの「懺悔」を観想行から順々に記述して、「わたしは観想行も善根もマトモに及ばない」という「懺悔」があれば、「重障」が滅して、「真心徹到」することを記述して、「雑業に迷わされることなく、懺悔自我滅」へと導いています。
【26】には、このような雑行のものも、照摂されることを端的に明示しています。
【27】には、五濁の人間界における、如来は「その資質を見て教化すること」をあきらかにして、色々な行が説かれているけれど、【28】には、「その色々な行」は結果長〜い間、修行しなければならないから、「畢命(とどのつまり)」は「専念念仏」しなさいという論の流れになります‼️
【29】には、「定散」ともに回して。。とありますが、つまりは「回心すること」がポイントだという意味を記述しています。
【30】には、論註から、「有漏心」(煩悩)による「功徳に似通った相(ありよう)」は「虚偽顚倒」の「不実功徳」であると警告しています。
【31】は、末法の五濁の時代には、「浄土の教え」のみが「さとりに通入」すると記述して、「行」を絞って限定してきています❣️
つまり【29】で「顕彰隠密」の「オモテ」に見えている「定散」から「下品下生」の《称名への行の定義》への移行です。
【32】には、【28】にも記述したように、「長〜い間(一万劫)経っても満たされることがないような諸行をしているもの」は、「家に火がついていることに気づかないもの」のように「顚倒墜堕」します。
そしてそのような「諸行のもの」が獲る「果報」は、「偽」であると、「徹底して」「自我行に陥らない」ように警告をさらに深めています‼️
この【29】にもある「回心」は、親鸞の著述によく出てくる文言ですが、「信心の内容」は、事実上《自我中心》から《如来中心》の心に《方向を向き返す》という状態になり、これを「回心」(えしん)といいます。
現実的になにもしなくていい、「まるまる、いままでと同じ煩悩の凡夫のままでいい」ということにはなりません。
それでは「如来の教え」の存在意味がありません。
この「化身土文類」のなかにも、「韋堤希や阿闍世」のような「極端と思われるひと」が出てきますが、これを「わたしも同じ」だと読み込んで、「時代も人間も(時機)、みんな下品下生」だと読まなければ、「観経」の「三輩三福九品」の分類は、「カーストを説いているのか⁉️」という理解になります。
韋堤希が選んだ、「ただ《称名》ならできる」というのが「下品下生」ということではなく、それしかできないという「慚愧懺悔」がそこには付属します。
これは、事実上「自我滅(破我)」をあらわしていて、根本仏教の「無我」になるのです。
つまり、オモテ向きに説かれる「観経」は、「わたしは下品下生」であるという「認識」を促すだけのように読み込めて、かつ「そのような愚者」には「称名しかない」と説いているように見えます。
しかし「隠密の意」は、「みんな下品下生であると自己観察できるようになり、称名(ここでは五正行)しか方法がない」ということを「認識」する。
このように読まなければ、「三輩三福九品」の“カテゴライズ”に意味がない、ということを「化身土文類」では「隠密の意」だと論じているのです。
つまり、わたしやこの教えに会ったものは、「慚愧懺悔」して「方向転換の心理状態」になる。
これが《回心》です。
「三輩三福九品」を「カーストと勘違い」してはいけません‼️
「わたしって、下品下生なんだ。。」と思って見ても、「なんか蔑視されてる⁉️」という「差別感」が残ります。(特に現代では。。)
「わたしって下品下生だから、一心専念弥陀名号しかない、だからそうしよう‼️」というところまで行かなければ、この仕分けの「三輩、三福、九品」に意味がなくなります。
または、「三輩、三福、九品」に分類する「理由」がなくなる上、「顕彰隠密」だと解釈する意味もなくなります。
以上のようなプロセスで「行を称名メインの五正行」に定義して、「そこしかできないというより、そこがわたしのためのさとりへの道」であると進んでいくことが重要なので、「回向発願」に落としこんでいるのです。
2019/07/19[6−10]
【32】には、大経では「真実から方便の願」がおこされている。
といい、「観経」では、「顕彰隠密」というロジックで、「方便から真実」の教えが「顕彰されて」いる。
そして、「小本(小経→阿弥陀経)」には、ただ「真門」を開いて「方便の善」はない。と記述されています。
そして、「三経ともに、方便は善根を修することを説いていて、これを要と」しています。
ーーー
ここまでを解説すると、「観経」は「要門」といい、「多くの仏教の教えから《要》の行」「要とは肝要、門とは通入なり」ということを説いた。
「小経」は「真門」といい、「真実の《実り》がない《真》の行(称名)のみが説かれて」いる。
という意味で、「観経は要門、小経は真門」と定義されたといわれます。
そしてこれらの「方便」は、まずは「自己の善根」を修行することだと説いているけれど、まずは「自己の善根」に対峙して、わたしには「不可能」と知ることが、「カナメ」であるといっています。
ーーー(つづき)
そこで「方便の願」として「第十九願」を出して、「真と仮」を明確に仕分けます。
また、この願にある「行、信」をフォーカスされます。
とりあえず、この願を「臨終現前」の《願》として、《行》を「修諸功徳の善」とします。
そして、《信》を「至心、発願、欲生」として、「信楽を発願」に置き換えています。
つまりここまでは「浄土の教えに誘導する」方便を「要(カナメ)」として、まずは「発願に近づいた」という意味を表しています。
ここであえて「方便名」を使っているのは、「方便から真実への存在意味(顕彰隠密)を明確にすることが目的である」といえます。
意外に「この要門」を捨てものとして解釈されますが、これも「如来の摂取不捨」のうちで、「多くの内外道の中から、浄土の教えに誘導するフォーカシングだ」という側面から見れば、「かなり重要(カナメ)である」と言わざるを得ません。
「四十八願にムダはない」のです。
結果、多くの仏教の教えから「正行、助業、雑行」まで絞られた。(フォーカシングされた)
またそのうえに、この「正行、助業」から「専修と雑修」にさらに絞られたと記述しています。
そして、対象者(機)は、「定散」の者という観経に出てきている「機(対象者)」を記述して、それらにはそれらの「三心がある」として、この「三心」は、修行する人によって違うから、「自利各別」と定義しています。
ここでの「自利各別の行の結果」は、一つ目の「即往生」ではなくて、二つ目の「便宜上の往生」で、「胎生辺地」で「釈迦入滅時に釈迦を覆うように生えていた沙羅双樹の下の往生」と記述して、有為法ではない釈迦を理解せず、有為法の釈迦を求めるように「現生においての胎児のような生」という結果で終わると、「方便を明確に仕分けて」います。
「即往生」は「願に報われた《報土》に、自然に生まれ」るということで、「観経の隠彰」について明確にします。
「観経」も「即往生」であると記述して、これが「観経」にも説かれているというために、「金剛の真心を開いて、摂取不捨を顕わしている」と記述し、だから、「釈尊は、《至心信楽の願心》を宣説」して、「報土の真因は信楽による」と「大経」に説いていて。。。
結果的に「観経」にも「深心」と説かれていて、「小経」には「一心」と説かれているのです。
といい、「一心」も深い意味での「利他真実の心」のことです。
と、解釈しています。
ーーー(解説)
結局ここでは、「観経」も「小経」も「利他真実の心」であるといいたいのですが、めんどくさい言い回しになっていますから、端的に記述すると、「大経の信楽」は「観経の深心」で「小経の一心」のことで、「自利各別の心」ではなく、
「利他真実の心」です。
ということが、「顕彰隠密」で明確になった内容だといっています。
【34】からは、この結論に至る「教えや行のフォーカシング」のプロセスについて詳細に説明しています。
2019/07/25[6−11]
【34】においては、「仏教の八万四千」ある法門のすべてが、「(ブッダの)心によって勝行を説いたものだから、漸教も頓教も、対象者によって説かれているから、その縁(無為法は因にならない原則)によって解脱を得る」けど。。
わたしたちのように「常没の凡愚は、《定心》(瞑想)を行じるなんていうことを修する《息慮凝心》なんてできないし、「良きことを行じる《散心》である《廃悪修善》もなかなか難しい」んです。ってまずは記述しています。
ここで、「良いこと」ぐらいはできるでしょう。。という「感想」を持たれる方もおられるでしょう。
しかし「人間」が判断する良し悪しは、「何に基づいているか?」という課題があります。
「情報」なのか「感性」なのか。。「なんにせよ」自己の思いと勘違いして「生きている」のが人間です。
「あなたが仕事をしている」として「その仕事はほんとうに良きこと」なのでしょうか?
あるひと曰く「儲けるためには、どこかに《騙し》がなければ儲けることは不可能」といいます。
「要りもしないものをいる」と思わせる。
国家的に「表示をごまかした商品」を売る。(遺伝子組み換えでないと書いていて、ほんとうなのかだれも確認しないしできないなど)
「コツコツと売れないものを作っても売れない以上」家族に経済的苦悩を背負わせる。
「誰かが大学などの定数があるところに《合格》すれば誰かは落ちる」
「クルマに乗れば排気ガスを撒き散らす」などなど。。
大なり小なり迷惑をかけている「自己」が《善》を修するなんて、「意外にけっこう難しい」ことです。
さらに394ページにあるように、「立相住心」というような「阿弥陀如来のすがたを行として、観察する」なんていうことをしてみても、「千年かかっても、法眼は開けない」といわれているぐらいだから、「真如を法性として観察する」なんて「因位」においても獲られないからこそ、「わたしたちのような、末代濁世の凡愚が出てくることをわかっていて。。」って記述していて、とにかく「本願一乗海」に「行」をフォーカスしたということが記述されています。
ーーー(ただ)
この「行について」は、末代ではなく、「韋堤希」や「阿闍世」が基本になっている以上は、「釈迦の時代」がすでに「末代の濁世の凡愚」の時代で、そういうひとに向けた内容としなければ、前後のストーリーに「次元の変化」を与えてしまいます。
しかも「八万四千の法門」を貶めてしまいますし、「実際にできない」という確定は不可能です。
「ブッダが全知全能の神」でなければ、「確定」できません。
およそ、化身土文類は、「人間を深く見つめて」「自己の問題」として、「凡愚である」という「人間という存在の深い意味や事情」を読み込めないと、先に記述した、「とにかく良きことはできない」という単純な解釈では、じつは「本義」を理解したとはいいがたいのです。
仏教は「基本的に出世間の教え」なので、「人間の繊細な機微について」意外と触れていません。
たとえば「観経のストーリー」の元になる「阿闍世出生の問題」において、「占い師から、仙人が死ねば、その生まれ変わりとして、子どもを授かるといわれた王」が、仙人の死を待てなくて、仙人を「殺させた」という「ストーリーの流れ」で「授かった子どもである阿闍世」は「仙人の怨みをもって授かった」から「未生怨(アジャセ)」として生まれる」から、生まれると同時に殺したほうがいいなんていう状況から、大人になった阿闍世が、このことを「提婆達多から聞いて」阿闍世が「父を殺し、母を牢獄に入れた」なんていう話は。。。
あまりにも「単純すぎるストーリー」で、よくある「ワイドショー的」な内容で、この内容にある「ひとりひとりの深い事情や理由」を「報道しないプロパガンダ」のような話でしかない。といえます。
また、ここで「下品下生」のものに説かれた、「一心専念弥陀名号」が「八万四千の法門」の《最高の教え》なら「上品上生」だろうが、「定散のもの」であろうが、それが「八万四千の法門」の《最高の教え》なのだから、論理上「仏教に八万四千の法門」は《必要ない》ことになります。
また、ブッダの「隠密意」がそうならば、「隠密意」にしなくても、明確に「すべてのものは、一心専念弥陀名号」で悟れます。と記述すればいいのです。
そういうことからして、「化身土文類」も、「信文類」と同じ《方便則》が原則であると明確にしないと、「論が通りま」せん。
そういう意味では、この辺をこうやって「詳説する」必要はないといえるので、単純に。。
397ページの「冒頭」にまたがっている「大経」の三心と「観経」の三心は《同じ》という部分がわかればいいといえます。
2019/07/28[6−12]
【37】から、「阿弥陀経(小経)」について、「大経と観経」の三心と「小経」の一心が同じであることを論じます。
ここでポイントと思われるのは、「大経は《大本》」と記述されて、「阿弥陀経は《小本》」と記述されていることです。
「観経」は、雑多な行から「五正行」(称名)にファーカスするために、多くの方便があるためなのか、扱いが比較的「雑」のように思えます。
それも「師」である「法然や浄土宗」は、観経中心で「観経の下品下生」にこそ《南无阿弥陀仏》が出てくるにも関わらず、粗い扱いのように感じます。
これは、親鸞の扱いが「雑や粗い」のではなく、「観経自体」がほとんど「雑行、雑修、雑心」という内容になっていて、「顕彰隠密」で「ふるいにかけて」絞り込むまでの「論が複雑」だということが、理由のひとつだと推論します。
また、真宗学において、「大経」は「救いの法」、「観経」は「救いの目当て(機)」、「小経」は「諸仏の勧め」という位置付けをされますが、この三つの中で「無為法」の側にあるのは「大経と小経」だといえます。
そういう点でも「観経」の扱いが「有為法」つまり「世俗」の側で語られている以上「観本」とかけないということなのでしょう。
親鸞の論は「こういったどうでもよさそう」なところに、けっこうポイントがあります。
そもそも「小経」は、あえてここで「方便経」としなくとも、教行証文類を「真仏土文類」まで読んでいれば、「真実則」で読み込めます。
しかしあえて親鸞が、ここで「真実門」とせず「真門」として論じようとしているのは、この「小経」の根拠になる「第二十願」を「植諸徳本の願」と定義することに理由があるからです。
この「植諸徳本の願」は、第二十願の願意を解釈する中で、すでに浄土教に「過現門と現未門」という解釈があり、
過現門は、過去世の中で具えた徳本を現在世において回向すること。
現未門は、現在世で具えたものを未来世で回向して、それぞれが未来世で往生を得るという説。
「過現門とは過去世の中に衆の徳本を植え、現在世の中に至心に回向し、第三生の時まさに往生を得る。現未門とは現在世中に衆の徳本を植え、未来世の中に至心に回向して、第三生の時まさに往生を得る」といった説を受けているので、
ここでいう「至心回向」が「方便である」と述べているのです。
ここに親鸞が、「一つには善本、二つには徳本」と記述しているのは、読み手が「徳本」だけでは誤解を招くだろうとして、「徳本に善本」という「世俗のいいことをする」という内容が「功徳の本(徳本)」というなかに含まれることをあらわしたと考えられます。
またここ(真門)で「善」について言及する必要があるためと言えます。
これは「観経」からの流れとしては、「必要な文言」だといえます。
いずれにせよ、「浄土教」で、「徳本を植えて、至心に回向する」とある内容を、「小経の信」にもってきて、「至心、回向、欲生」という三心とし、「第二十願」の内容に定義したのだと推察します。
ですから、397ページの後ろから7行目に「観経に准知するに」という記述を「前提にして」、この経の「顕彰隠密」の義があると論を進めていきます。
顕義によれば、「経典に詳しいひとたち」が「一切諸行の少善を《あんまり意味がない》」と貶めて、この「善本徳本の真門」の一心を開示して勧め、「自利(自我)の一心」から「難思往生」を勧めるだろうけど、これは「あくまでも顕の意味である」と記述しています。
ここの「難思往生」は、第十八願に定義する「難思義往生」から、「義」という「道理をあらわす文字を抜き」自力「自利(自我)」の「行」であるという定義づけだといわれています。
そして「小経にある」「多善根、多功徳、多福徳因縁」を根拠にして勧めるだろうし、そのほかの「解釈」を根拠にするだろうけれど、これらはみな「顕義」であり「真門のなかの方便」であると論じています。
しかし「彰」の観点から読むと、「真実難信の法を彰す」と論を進めて、「隠密意」の内容を論じていきます。
2019/08/07[6−13]
【37】には、398ページから、小経の内容について記述されていますが、この辺は「日々の読誦」で馴染み深いところかと思います❣️
また、398ページには、「執持」や「一心」「無問自説経」「如是」などの解釈で、真実「隠彰」をあきらかにして、「三経」ともに、「金剛の真心」である「大信心」を「最も要」だとあらわしており、とはいえ、この大信心は「仏力より発起」しているから理解しにくくて「入りにくい」けれど、この「一心」を受け入れれれば、「楽邦」つまり「浄土」へは行(往)きやすいと記述しています。
(往生の文言は、真実則の「無生の生」が大前提です‼️)
そしてその根拠としてそれは「願力」によるからだと記述しています。
また、この「一心」が「三経ともに」すべて「同じである」ということであり、「三経一心の意味」であると結論づけています。
そしてここで、いったん結論づけた「小経」の方便について、【38】から記述を進めています。
こういうところが親鸞の独特な論理展開ですが、いったん「真実」に定義した「小経」を「方便の観点」から改めて記述を進めているのは、ここまでに「信心」の観点から「大経(第十八願)において連結する」ことを、いったんの結論としたものの、「行」の観点からの一致を論じるにあたって、この流れが自然なのだと思います。
しかしここで間違ってはいけないのは、「行と信が別物」と思ってしまうことです。
構造としては、ここまでに「三経の一心」が同じであると論じて、観経の行→大経の一心
小経の行→大経の一心
という「行」を「大経(第十八願)に帰結させること」を意図して、この論の流れがあると推察できます。
そこでここから「小経の名号の称念」に「助業」と「正業」が混じって「雑」になる「間雑」の心で「称名や憶念」することを「罪福を信じて」「本願力を間違って受け取り欲生する」こと、つまり「自力の専心」と名づけると論じています。
またこの嘉名は「善本」であり「徳本」であると記述していますが、それを「自力の専心」つまり「自我行」として行じることについて記述しているのです。
これは、「如来の嘉名」には「万善円備」しているということを思って、「自己の罪が消える」ということを「自我」として持ちながら「行」じることを意味しています。
これは、平易にいえば「損得勘定」から「念仏を行じること」を論じており、それでもそこは釈迦牟尼仏が「功徳の蔵」を説いて、とにかく「十方濁世」を勧化するためには重要なプロセスあるいはポイントであるとして、「名号には《功徳がある》から、とにかくあれこれ迷うことなく《称念》すれば良い」と勧めているということです。
またそもそも「阿弥陀如来」が「第二十願」で誓った「功徳の本」は、「わが名号を聞いて、念をわが国にかけて、もろもろの徳本を植えて、至心をもって回向して、わが国に生まれたいと思うなかで、自我滅に転じるるようにさせる」ということを「果たし遂げる」ということであり、最終的に「第十八願」の「純粋称念」へと「転じさせる願い」として「重要」なステージともいえる「名号を聞く」というところに「衆生を誘導する願い」を根元にしているから、釈迦牟尼仏が勧めているのである。とあきらかにしています。
ここで親鸞が、「名」について「嘉名」「徳号」などという文言で「名号」を表記している点は、その文脈において、そういった表現が適切であるとして記述されていると読むことも重要でしょう。
【38】において、「第十八願の称念」と「第二十願の称念」について、「果遂」という重要なポイントを「読み取ること」は逃してはならない内容であるといえます‼️
2019/08/17[6−14]
400ページの【39】から第二十願文を引用して、「念(読、ネン 意、おもい)を係け」て、「もろもろの徳の本(もと)」を植える、「心を至し回向して」「果遂せずは」というポイントについて、あげており、「特に、諸行から、まずは《念仏一行》へ誘導して、さらに真実のさとりに至らせる、つまり真実の願いを《果たし遂げる》ために重要な願い」という部分は重視されています。
また【40】では、「諸智において疑惑して信ぜず」「罪福を信じて」「善の本を修習」「その国」「かの宮殿に生ず」といった文言をポイントにして、「自力(自我)行念仏」について定義しています。
つまり「万徳そのものの名号」は、「如来(真如)そのもの」であり「自分からおもいをかける」というような「自我からはたらきかける性質」ものではなく、また「名号は自分から植えるような功徳の本ではない」ということ、そしてそこにつながるような「自分から至心を回向する」という必要もないことを【40】に関連付けています。
【40】における、「仏の智慧を疑い信ぜず」「罪を消す善の本」だと「自分から念仏すれば罪が消えることを期待して」「その国」という表現があらわすように、「かの国(彼土つまりさとりの国)」ではなく「そこにあるような俗世の延長のように《かの国》であるべき部分を《その国》という認識」で、「その国に生まれたいと願う」といった思いを持ちながら念仏を修めても、結果「宮殿」に象徴されるような「自我国」といってもいいような「果」にしか到れず、「さとりの浄土」「功徳荘厳」を現実に観察することはできないといっています。
(ここであえて「かの」と「その」の違いについて記述したのは、「かの」よりも「その」の方が距離が近い表現なので、ここであえて「その」と使われている文言を「経典に象徴的に記述されているその国」は「世俗の感覚で認識している世界観」であり、「本来経典の表現は、功徳荘厳をあらわしており、そこから導き出される《さとりの観察》という世俗を超えた認識についてかの国」と定義するからです。)
【41】では、「とはいえ」「善本がないひとは、そもそもこの経を聞くことさえない」のだから、この経を聞いているということは、「清浄に戒」を有ってきたから、「正法を聞くことができている」と諭しています。
【42】は、異訳の大経における同様の部分を引用して、「自力(自我行)念仏についてあやまりをあかして、
【43】(異訳の大経)lにおいては【41】と同じ内容の部分を引用して、その後半から「聞見したなら精進して求めよ」と引用し、
【44】で「観経」を引用して「無量寿仏の名を持て」と「徐々に真実の称名」に誘導しています。
【45】においては、「阿弥陀経」を引用して、阿弥陀経にも「少善根、福徳因縁ではかの国に生まれられない」から「阿弥陀仏を説くを聞いて名号を執持せよ」と「真実の称名」に誘導しています。
【46】から善導の引用で、「とにかく念仏すべき」ということを記述しています。
2019/09/01[6−15]
「化身土文類」を書き進める気にならない理由がわかった気がします。
昨日のお知らせに載せたように。。以下↓
ーーー
「方便と真実」について。。
キリストつまり神の愛を信じて「天国に行き永遠の楽園」で「永遠のいのち」を得る。
仏の大慈悲を信じて「極楽浄土に行き永遠のさとりの身」を得る。
同じような構造の中で「真宗は賜りたる信心」だから。。
イエイエ「キリスト教も神の愛が届いたところでの信心」だから。。
「仏には慣れるけど、神にはなれないでしょ!」
イエイエ「神が真理そのものだから、仏も神の内なんです!」
とかなんとか。。
いずれも「言葉にできないことをあえて言語化」している以上、いずれも方便のストーリーだから「張り合う必要はない」うえ、結果そのストーリーの中で。。
「神に任す」「仏に任す」という状態になるのだから、どっちも事実上「無我」を生きる《真実》《自然》に任すという状態になっているのに。。
いずれもが「方便言説」にとらわれると、また「自我」に戻ります。
問題は「真実真理」に生きているかどうかであり、どっちが正しいかではないのに、大概の場合「言説方便」に執着してしまう。。
結論が同じなら、プロセスはフィットしたものでいい❣️
そこが重要なんだから。。
ーーー(以上)
と考えると「教行証文類」には、「教行証」という「真実則ルート」と、「信文類」単独で成り立つ「方便則ルート」が走っていて、ダブルスタンダードで論じられている。
と考えていましたが、そこに「マジ方便」の「諸行と称名(第十九願)」「自我称名(第二十願)」があって、これらが「要門」「真門」として「大会衆」を集め、この三願を転じて第十八願に入るという「三願転入」や「果遂の誓い」という「尊い願い」の中で導かれているということと「現代の矛盾」をどう表現しようか、「自然のご縁が起こるだろう」とそのタイミングを待っていました。
しかしこの間、東京で文化人に「景教との関係」について講義をしたり、母の滅にあたって「キリスト教の牧師さんと話したり」ということがある中で、その関係性を否定できないと思うことが多くあって、「偽」とされる「外道」さえも「方便になり得る」と思ったことから、「結果どこの入り口から入っても、最後究極を会得しているひとは、同じ境界にいる」と実感したので、親鸞が「偽」としている「外教」でさえも、「方便」であり、その究極は同じ「無常無我、空」になっていると思っていたのです。
「偽」は捨てられる教えではなく、「偽」でさえも「摂取不捨のうち」と考えると、親鸞は「廃立」ではなく「摂取」ですべて書かれていて、そういう意味では「トリプルスタンダード」になっているのではないかということを発見して、その論をどう教行証文類から構築できるかと日々考えていたのです。
そして、このポイントについて「論がたった」ので、「明後日のオカンの本葬」が終わったら、論じてみたいと思っています❣️
2019/09/05[6−16]
まずは「顕彰隠密」から論じたいとおもいます。
なぜ「観経」と「阿弥陀経」に「顕義」と「隠密義」があるのか?
もしこの2つの経典に「密意」があるとしたら、なぜ「密教」のように、あらかじめ「秘密がある」と「経典」に表現されていないのか?このような疑問が出てきて当然でしょう。
しかしこの「密意」を発見したのが「親鸞」だけだとすると、この密意を知らないまま通り過ぎてきた人がほとんどであるということになり、この2つの経典の存在意味が「ミスリード」されてきたことになります。
親鸞は、この「顕彰隠密」において、今までのひとがミスリードしてきたということを言いたかったのでしょうか?
ここで親鸞はそのようなつもりで「顕彰隠密」を記述したのではなく、「隠密義」があると読めば、「救われるひとが増える(下品下生や五逆謗法まで)」ということを言っているように思います。
そこでページは飛びますが413ページの【68】にある「三願転入」という「第十九願から第二十願に進み、最終的に第十八願の真実に入る」という流れ、または如来の誘導と同じように。。
その後に「三時(正像末)」という時代背景から、「外教」について記述されているけれど。。
これらも同じであり、「三時」というそれぞれの時代背景から、いろいろな「外教」があったけれど、それら全てが「真実門に転入する」という、「如来の摂取不捨」は「外教に至るまで」すべての「教え」とされるものを、真実門に入れる「誘導する」ということを記述していると考えられます。
つまり「外教」も「化身、化土」だという「論」が「化身土文類」なのです。
これは、に書いた「入出二門」が持つ意味であり、いったん「真実の無碍光如来」の門に入ってから、「薗林遊戯地門」に出るという構造があらわす「深い意味」であるといえます。
じつは「顕彰隠密」も「三願転入」の論理も、結果「外教」までも真実門に誘導するために、親鸞が如来大悲を現実化するために発明したシステムであり「独自の論理」であるといえます。
この論理とシステムが「教行証文類であきらかにしている如来の慈悲が、真の意味で大悲である」ことを証明したのです。
その証明根拠が、468ページの【106】の(弁正論)あたりからの内容です。
【106】のラストは「老子の。。。法の真教に入流せよとなり」となっていて、【107】のラストは「いかんぞ捨てて弥陀を念ぜざらん」という「どうして弥陀を念じないのか」という問いかけになっており、【108】のラストは「外道に帰依せざるなり」というように、この後も「外教や外道に帰依しないように記述して」化身土文類の「マジラスト」の
【120】に「末代の道俗仰いで信敬すべきなり、知るべし」とあって、【121】に「もし菩薩が、いろんな行を修行しているものを見て、それらのものが善不善の心を起こすことがあっても、菩薩はみな《摂取》する」という結びになっています。
このように「教行証文類」の最終結論は「とにかく摂取」で結ばれている以上、この「化身土文類」はすべてを「三願転入」のように「真実門」に誘導する「法蔵菩薩」となった如来の大悲が「摂取」であることを「顕彰」しているのです。
成仏して如来になった「いのち」が「薗林遊戯地門」として「自在に還相回向」する「出門」するという意味は「これでなければならない」という「戒め」でも「これは外道だ」と裁判することでもないのです。
「広く深い次元に入って、そこからさまざまな次元に出て、自在に遊ぶように(遊煩悩林)真実に転入させる」というのが、「第十八願の真実」「無碍光如来」の真義であると「親鸞は廃立(はいりゅう)」ではなく「摂取の教説」を「化身土文類」で明確にしたのです。
この点をミスリードして「外道はダメ」といった姿勢ではなく、いろんなひとがいて、いろんな教えがあって、もしそこに「第十八願」と同じ真実があれば、「キリスト教」でも構わない。
究極「どうしてこの人は《お守り》を握りしめるのか」ということにも「意味があり」それさえも、そうだから「廃す」のではなく「なぜこのひとはこうなのだろうか」と問いつつも「摂取する」というのが【121】の菩薩の「摂取」なのでしょう。
そういう「如来の次元(目線)で現生を生きる」「往相還相因果同時」を生きることが、「あらゆるいのちのあり方」を認めることでもあり、すべてには「自然法爾」の理由がある、という広大にして無碍なる「無碍光如来(無量寿如来)の法」なのだということを、親鸞は教えているといえます。
2019/09/10[6–17]
化身土文類の内容にもどります。
【46】の善導さんの引用は「とにかくほかの行」より勝れている「念仏」を行じる方が良いと記述しています。
【47】において、善導さんが「華厳経の法界縁起」の「一即一切」の論によって、「念仏のイチ」は「諸仏が証った(さとった)」さとりそのものである「真如」からの勧めである。
ということを、「十方の諸仏ことごとく。。。みな同じく讃め(ほめ)、同じく勧め、同じく証したまふ」
の部分に「同じく証し」と記述していて、「さとり」を「行の結果として証明された状態」を意味する「証し」という「証文類」の「証」の文字が使われていることが、それをあきらかにしています。
これは、「念仏のイチ」に「一切仏のさとり」が含まれてることを意味する表現です。
そして、その理由を「真如と同体になる大悲」だから「念仏のイチが真如のさとりを証明する」ということを論じています。
ここに「一仏の所化は一切仏の所化。。」であるという記述は「華厳経の論」によると考えるのが的確でしょう。
続いて、「一切凡夫を勧めて、一日七日、一心に弥陀の名号を専念すれば。。云々」とありますが、「阿弥陀経」において、この辺で「混乱する」のは、「阿弥陀経」には、「極楽の荘厳」が説かれていていながら、124ページ(阿弥陀経)【5】には、「極楽国土」に生まれたものはみな「阿鞞跋致」(アビバッチ=不退転地)である。
と記述されて、さらに、「一生補処あり、その数はなはだ多し」とあって、これは、親鸞が「現生正定聚」で「現生」に定義した存在がいる。
ということになり、また更に「まさに発願してかの国に生ぜんと願うべし」という理由に、「このように発願すれば、諸上善人と《ともに一処に会する》からであり。。。もし善男子、善女人あって。。」という部分が、この「一日七日」につながっているので、よくお話に出てくる「倶会一処」は、「名号を執持して」という行を行じるものが「一会にて行じる」という、「五果門の大会衆門」をあらわしていると読むことで正確な読み方になります。
「浄土でまた会える」という「世俗の持ち越し」ではないのです。
もしこれが「死後に往生して会する」というのであれば、親鸞において、出会うのは「諸上善人」ではなく「諸仏諸菩薩」であるはずです。
つまりここで「親鸞」が言っているのは、「この自我名字のものが、自我名字を捨てて、発願すること」が、「現生にて《破我されてこの迷いの命が終わり即往生して》いま浄土において執持名号を行じる」と読むことで、「大会衆と出会う」「阿鞞跋致」「一生補処の身になる」という全てが一貫するのです。
ですから、「化身土文類」のこの部分の「一日七日、一心に弥陀の名号を専念すべし」が、現生定義で読めるのです。
この部分の終わりに「信を立つ」とある文言も「現生定義」で読むことができます。
そもそもの「阿弥陀経」のこの部分を「来世定義」するなら、「この部分のすべて」が「来世」のことになってしまいます。
このポイントは重要です。
浄土が「西方」なのは、「スペース(空間)」のことではなく、「次元をあらわしている」と論じる方が適切だと言えるでしょう。
当時は「東方」はオリエンタルな「俗世」をあらわして、「西方」は「出世のさとり」を意味していたという論文を読んだことがあります。
このことと「太陽が沈む、大自然でしか感じ得ないこと」が一体になって、「西方定義」があるとしたら、これは、もはや「スペース」ではなく「次元」を意味している、深くかつ高度な思考による世界観です。
そういう意味で、往生が現生か来世かという議論は「戯論」であり、人間が「高度で深い思考のさとりを観じる」には、「場」の問題ではなく、「次元」の問題が「場」のあり方や「観えかた」を変えるのである。
と「現実的に変化が起こること」を親鸞は論じているといえます。
事実、「如来を行じていく中で、いろんなことにおいて次元の変化が起こっている」ことを、日常の中で観じるようになります。
ここまでにいろいろ論じてきましたが、教行証文類の最もラストの一文は華厳経を引用して
「もし菩薩種々の行を修行するを見て~菩薩みな摂取せん」と
とあるところを見れば「化身土文類」においても、「真」のみならず「仮」も「偽」も「すべてを摂取する」と言う言葉で結ばれていることは重要なポイントではないかと思われます。
華厳経で「遊女」などを含めた53人の人に教えを乞うたことと同じスタンスなのではないかといえるのです。