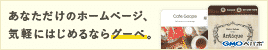正信偈‼️特定の方に向けて表に出せないことを書いています。ご了承ください。
とにかく、教行証文類のどこを読んでも、親鸞さんは南无阿弥陀仏が嫌だったとみえる!
たぶんにおいて、法然さんの念仏は「呪文」の要素が強くて、「唱える回数や唱え方」が問題になっていた。
しかも「念仏往生」なんて、中国のあまり知られていない「善導」という人の「観経疏」以外に、どこにも根拠がないのである。
そんないい加減なものを信じるということには、よほどの「賭け心」か「どうでもいい」という冷めた気持ちがあったはずである。
ならば、なぜ法然さんに付き従ったか。
簡単である「当時の親鸞さんを受け入れる度量のあった人が法然さんだった」ということである。
そこには教えもなにも、直接的には関係ない!
「ただ対、人対人」ということでしかない。
ーーー
つまり私を救ってくれた人が念仏を行じていたと言うに過ぎないであろう。
しかし現代とは違う当時において親鸞さんは、そこに身を寄せるしかなかったであろうし、その仲間たちと一緒に生きるしかなかったといえる。
ならば、法然さんの行じている念仏とそこにいる皆が行じている念仏を共に行じながら生活すると言う事は必然だったと言えるであろう
今のお寺社会でもそうであるように、自分が納得できなくても周りがそうである以上、そこに自分を合わせて生きていかなければならないと言う環境下にあった事は推測できる。
Mくんも、〇〇寺に助けられたというのか、奥さんや、まさきさんに助けられたというか、いずれにしても、その環境の中で自らを生かしていくと言うことを真剣に考えているからこそ、こういう学びをしているのじゃないかと思っています。
話を戻しますが、親鸞さんが、当時街中を流れていた「念仏と言う素晴らしい教えで救われることを説いている法然と言う方がいるらしい」と言う噂を聞いて法然さんのところに行ったとしても、伝記を読む限り法然さんから親鸞さんは教えを聞いて教えを解釈してもらって教えの中で救われたから法然さんのところに帰依をしたと言う風には読み取れないといえる。
それよりも、法然と言う人の人柄であったり、語られる教えの中身や具体的な南無阿弥陀仏と言う事以上にその語り口調であったり、その救いを解かれる風貌であったり、そういったところから、「この人は温かい人でありこの人は人を大事にする人格者である」と親鸞さんが思われたと言えるであろう。
簡単に言えば、教えが素晴らしいと思ったと言うよりも、この人は素晴らしい人だと思ったと言うことが事実ではなかろうかと思うのである。
そこから親鸞聖人が念仏の教えを理解しようと努力している姿が、他の弟子との問答であったり、他流の念仏との交流であったりと、
そういった中で、念仏を心から理解しようとしている節が見られるが、やはりそれはもはや、無碍光如来であって、阿弥陀仏ではないと言うところがこの時代に少しずつ見えてきている。
ーーー
話は戻すけれど、人は、一度ご縁を受けた人や仕事や思想や宗教などの人間関係を、そう簡単に捨てきれるものではない。
私でさえ、〇〇寺さんと特別な契約関係や濃い親戚関係と言うわけでもないけれど、この関係を簡単に捨てきれるものではないと言える。
古い時代であればこそ、コミュニティーや生きている世界が狭い以上、現代以上にその傾向は強いものがあったであろう。
だから、親鸞さんがその法然門下と言うコミュニティーの中で生きていくということが最も的確であると考えられたとしても不思議ではない。
しかし、法然門下の弟子たちもそうであったように、とにかくただ南無阿弥陀仏を唱えれば良いと言うことを智恵第一の法然聖人がおっしゃっているのだからそのようにすれば良いといった人々や、単純にそれだけの理由で南無阿弥陀仏が一切を救うと言うことを納得できないと言う人たちもいたと言う事は散見できる。
私は、親鸞さんはそのように単純に納得ができるような人ではなかったと、教行証文類を読めば読むほど、そのように思われるのである。
ーーー
そんな中、親鸞聖人は、浄土の教えの根幹を「浄土論と論註」(以下特別なことがない限りこれらを「浄土論」と記して同じものと扱います)に求めていったと考えられるのです。
それは、浄土論のみが、「浄土の教えは仏教と相応する(与仏教相応)」としきりに書かれていて、本来の仏教の原則である「無常、無我、空」と異なると思われるような浄土の教えが、仏教であると言う理由を論じているからだといえるでしょう。
しかし、師匠である法然聖人は、善導大師や観無量寿経を重視しておられ、また、それほど浄土論を重要視されていないと言うことがあり、親鸞さんは、納得いかない自分の気持ちと、それを整理してくれる浄土論と言う書物と、法然聖人の姿勢との間で悩まれたである事は想像に難くありません。
そして、そういった自らの気持ちの流れの中で、念仏を唱えると言うことよりも、その念仏の持っている悟りへの思想構造と難しい事のわからない人に向けた、「信心による」と言う教義を、教行証文類に確立されたと言えるでしょう。
ーーー
いずれにせよ、七高僧の教えの中で、浄土の教えが根本仏教である、この無常、無我、空の教えに相応していることを明確にしているのは浄土論しかいないと言えるのです。
そこで親鸞聖人は、自分に嘘をつくことができず、浄土論を根拠にして、浄土の教えを組み立てていったと考えることができます。
そこで、教行証文類では、行は「無碍光如来のをみ名を称する」と定義され、南無阿弥陀仏そのものでもなく、南無阿弥陀仏を称えることでもない。
つまりは、「無碍光如来の法を語っていく、説いていく(讃嘆する)こと」が、真実の行であると定義されたのです。
しかし、無碍光如来の法を語ることができない人は、法然さんのいうように、ただ「南無阿弥陀仏」を唱えつつ、慈悲深い人になれば、周囲の人が感化されるということになるというわけです。
しかし、どうでしょうか。
現代において、南無阿弥陀仏を唱えながら良い人格の人になっていったとしても、それが南無阿弥陀仏によるものであると思う人もおよそいないと考えられますし、現実問題、お聴聞をしてそのような人格に変化が起こると言う事は、まず考えられないのが現代であると思われます。
おおよそ、そういう人たちがいたのは、戦前までであろうかと思います。
そういう現実的な観点から言っても、南無阿弥陀仏を信心と言う観点から現代人が行じることさえ、大変に難しいことかと思われるのです。
とは言え、親鸞さんの気持ちの中には、根本仏教に相応している浄土論の教えと、「善導大師の文献」以外に「ほとんど根拠がない」法然聖人の念仏とのあいだで、悩みながらも、無碍光如来の真実とほぼ呪文でしかないような南無阿弥陀仏を折衷させて教行証文類を作られたと考えられます。
そして、その行文類の中においては、無碍光如来の教えを説かれ、それを真実とされ、終盤に至って南無阿弥陀仏の念仏を方便として説かれています。
つまり、これが行文類の結論なので、行文類から信文類へと移行する中で、正信偈には、その両方が織り込まれていると考えられ、それが故に理解や解釈が難しくなってしまうのです。
※無碍光如来を真実とされる理由‼️
まず、無量寿経や浄土論は、「法蔵菩薩のストーリー」を大事にされていて、そもそもこの法蔵菩薩のストーリーあるいは法蔵菩薩と言う人格こそ、我々が目指すべき人格であると言うことを明確に論じているのが浄土論であり、そもそも無量寿経なのです。
無量寿経においては、法蔵菩薩は私を含む全てが救われなければ、法蔵菩薩は仏になれないのです。
「設我得仏〜不取正覚」という大きなテーマがあるのですから!
親鸞聖人は、そこをうまく法然さんと折衷させるため、「本願成就文」と言う部分が無量寿経にあるとして、信心を得たものは、「本願成就の阿弥陀の力によって救われる」と信文類に記述されましたが、この部分は、もともと無量寿経においては「本願成就文」でも何でもなく「回向すること(私が本願に転じ変わること)」をもって大乗菩薩道を歩む身になると言っているに過ぎません。
このように、親鸞聖人は本来の原典を読み変えたり、意図的に変化させることによって法然聖人の教え(方便)とそもそもの真実の教えの両方を教行証文類に苦労をしながら書かれているように思われます。
こういった、前提があるので、正信偈をかんたんに理解する事は難しいのですが、どの部分が真実でどの部分が方便であるかと言うことを親鸞聖人が考えながら書かれたと言う前提を理解して、仕分けて読むと、それほど難しいものではありません。
それでは、次回から本文に入っていきたいと思います。
(わからない事は遠慮なくお問い合わせから聞いてくれたらいいです。)
ーーー
「帰命無量寿如来」「南無不可思議光」
これは南無阿弥陀仏が持つ2つの意味を分けられて、敬いの意味で「帰敬序」と言うふうに解釈されるのがお西における一般的で適当な解釈です。
もちろん「अमितायुस् Amitāyus」(アミターユス)と「अमिताभ、Amitābha」(アミターバ)と言う、無量寿と無量光と言う意味が南無阿弥陀仏には含まれていますが、単純にそれをここで2つに分けて、敬いを表したと言う程度のものではありません。
まず、もう一度、親鸞聖人と法然聖人の違いについて考えてみましょう。
法然聖人は、善導大師を大事にされ、観無量寿経を大事にされ、第18願の中で「乃至十念」に重きを置かれたと言う、親鸞聖人と大きな違いのあるポイントがまずあります。
親鸞聖人は、天親菩薩を大事にされ、仏説無量寿経を真実とし、第18願の中で「至心信楽欲生」に重きを置かれたと言う大きなズレがあるのです。
師匠と弟子で、根本的にこれほどのズレがあると言うことが大きなポイントになっているわけです。
だから、親鸞聖人は、仏説無量寿経を真実とされたのですが、それは、仏説無量寿経には、「阿弥陀仏」と言う文言は一言も出てこない、浄土三部経の唯一の経典であると言うことを意識されていたように考えられるのです。
そして、仏説無量寿経には、「無量寿仏」という表現でしか出てこないのです。
ここで考えられるのは、親鸞聖人が、阿弥陀仏を固有名詞ではなく、普通名詞として捉え、時空を超えてすべての命を無量寿仏と捉えたのではないかと言う事です。
そして、自分の命を含む、命の全てが、真如から現れた、本来的に悟りの性質を持った「如来である」と言いたかったのではないかと思えるのです。
無量寿経にとかれる、「無量寿仏」は時空を超えた全生命を表し、それらが全て真如であると言うことを親鸞聖人はまずおっしゃりたかったのではないでしょうか。
ですから、「無量寿如来」に「帰命」する。
という文章において、煩悩の私が、煩悩のない本来の悟りの命(仏性)である自分の命を含めて「如来である」と「帰命する」と言うふうにこの1句目は読むことができそうです。
ーーー
「南無不可思議光」
これも「アミターバ」という、阿弥陀仏の一側面ですが、なぜ「不可思議光」なのかというポイントが重要になります。
そもそも、「無量寿や無量光明土」ということが真宗の原点だということが、真仏土文類に詳しく書かれています。
もちろん浄土論も「光明」という側面から記述されているわけです。
249-6
等・不可思議光と号したてまつるなり」と。{以上}
【59】 『楽邦文類』の後序にいはく、「浄土を修するものつねに多けれども…
これは、「浄土の教えを聞いたり行じても、真意(光明)を知らぬまま終わる人が多い」ということです。
337-3
【1】 つつしんで真仏土を案ずれば、仏はすなはちこれ不可思議光如来な
り、土はまたこれ無量光明土なり。しかればすなはち、大悲の誓願に酬報するがゆへに…
とあって、この世の中全てが、「無量寿仏(ここでも阿弥陀仏を用いない)」の光明に照らされて、全てが「本来真如から生まれた存在」であると、智慧の教えが展開されていくんです。
まぁ、ここまで親鸞さんの念仏が「行と信」という以上に根本的に違うものであることを考えると、いまの西本願寺や空華学派が「夢物語を語っている」ことがよくわかるでしょう。
また、お坊さんなんかも「この意味不明な内容についていかなきゃいけない」という、Mくんのような人が多いのです。けれどたいがい、うやむやで終わっている僧侶住職が多いので、本物が広まっていかないんです。
しかし、根本を間違えなければ、とても仏教として筋の通った教えであることがわかります。
ーーー
ここで、「不可思議光仏」について少し触れますと、親鸞聖人は、
「愚禿鈔」にも、
539-2
「我」の言は、尽十方無礙光如来なり、不可思議光仏なり。「能」の言は、
不堪に対するなり、疑心の人なり。「護」の言は、阿弥陀仏果成の正意を顕す…
と書かれていて、不可思議光仏と「尽十方無碍光如来」を同じにされています。
この「尽十方無碍光如来」は「浄土論」に出てくる文言であって、ここからも「無量寿仏」を「尽十方無碍光如来」と解釈されていることがわかります。
こういうことから、普通名詞である無量寿仏(いのち)の真実は、無碍の光明(智慧を意味する)によって明らかにされると言うことを、正信偈の冒頭に明確にされていると言うことが理解できます。
この冒頭を、単純に、南無阿弥陀仏と言う言葉の持つ2つの側面を表して、帰敬序としていると言うような適当な解釈では、全てがわからなくなってしまうのです。
さて、ここから「法蔵菩薩因位時」と、仏説無量寿経の教えのポイントである法蔵菩薩のストーリーを明らかにされていきます。
ーーー
もう少し明らかにしたいことがあるので、ここでもう一度話を戻します。
まずは「帰命無量寿如来」において、帰命から始まっているのは、親鸞聖人がよりどころとされた浄土論の中に、作者の天親菩薩が「世尊我一心、帰命尽十方無碍光如来…」と書かれていて、南無阿弥陀仏の文言の使用をなるべく避けたい上に、浄土論に依っていることを明確にしたい親鸞聖人においては、南無無量寿如来とは書けなかったのではないかと推測できます。
そこで、「無量寿如来」と書かれて、仏説無量寿経の「無量寿(仏)」をあえて「無量寿(如来)」にされたのは、「真如(道理摂理の世界である真理)」からすべての生命が生まれていることについて、すべての生命を「如来だ」とここで定義していると言えるでしょう。
そして、「その理由や如来としての生命の真実を知るため」には、「智慧の光明」が必要であると言うことが、2句目に、先述した浄土論から、「不可思議光=尽十方無碍光如来」と読み解いていくことで明らかにされて行くのです。
※Mくんとよく言っている「キミはキミのままで…」と言うところに回答はおさまっていきますが、「あなたの命はあなたが果たすべきところに果たすべき能力や力を持って生まれている」と言えるのです。
あくまでも、人間を能力やその他のことで差別をしたり、貴賤を述べたりする事はあくまでもさとりから離れた思考や行いであると言うことが言えるのです。
こういったすべての命=無量寿仏と言う真実を、尽十方無碍光如来(不可思議光仏)という光明が明確にしていくのです。
ーーー
さて、ここから「法蔵菩薩因位時」と、仏説無量寿経の教えのポイントである法蔵菩薩のストーリーを明らかにされていきます。
これは、「生命の真実を光明で明らかにしていく」と言うことについて、具体的な例え話をもって我々に示すために法蔵菩薩のストーリーが仏説無量寿経に説かれていると言うことであるといえるでしょう!
ここで、なぜこの菩薩の名前が、「法蔵」であるかと言うところに目を向けてみる必要があるでしょう。
そもそもの浄土論を書かれた天親菩薩は、倶舎と唯識学の人なので、法蔵菩薩の法蔵は、「あらゆる法」を収めている阿頼耶識であるともいえます。
まぁ大体、倶舎だの唯識だのという難しいことは置いといて、とにかく天親さんの浄土論でいえば、「本来すべてが法(धर्म Dharma)そのもの」だという法の概念を説いているわけなので、「法(धर्म Dharma)」を「蔵する」という意味で「法蔵」とされたともいえるでしょう。
なので、法蔵菩薩の原語は、サンスクリット語でधर्माकर(dharmākara)=「法の入れ物である蔵」と書かれていると言えると思うのです。
一言で言えば、「すべての生命は、法蔵菩薩から生まれ出ている」と言うことが、ここに「法蔵菩薩因位時」からの正信偈の内容に示されているように思えて仕方がありません。
※ここまでをまとめると、「普通名詞である無量寿仏」が「尽十方無碍光如来(不可思議光)如来」の智慧によって、その生命の本質を明らかにされ、その具体的内容が仏説無量寿経の法蔵菩薩からのストーリーであるという流れになっているように思います。
ーーー
さて、ここで法蔵(菩薩)の願いと行について説かれていくのですが、願いは方向性、行は歩むことをいいます。むかしは「造作進趣」(ぞうさしんしゅ)なんていいました。
現代的には、私たちの進むベクトルのことであると言えるでしょう。
私たち人間は、ろくなことを願いません。
また、行ないについても、生活に追われたり、快楽に耽ったり、それこそこれもまたろくな行ないをせずに、日々を虚しく過ごしています。
そういう私たちに、願うべきは悟りであり、悟りに至るために名号を受け入れることを説かれています。
とは言え、その名号は「南无阿弥陀仏」に限定されたものでは無いのです。
どちらかと「帰命尽十方無碍光如来」を重視されています。
その理由として考えられるのは、
そもそも仏説無量寿経に「阿弥陀仏」という名号は出てこないこと、
無量寿経を解釈している浄土論に「帰命尽十方無碍光如来」と出てくるということ、
「尽十方無碍光如来」であれば、人格を持たないので、「偶像崇拝」にならない、
といったことが考えられます。
そして、帰命尽十方無碍光如来の名号によって願うところが悟りであり、悟りへの現実的行動が無碍光如来による智慧によって明らかにされていき、私たちが慈悲のものになることだといえるのです。
「観経」や「善導」の南无阿弥陀仏だと、韋堤希さんのように、自分が救われることが主眼になって、仏教本来の「利他」がわからなくなるともいえるでしょう。
ですから、正信偈の後半の「龍樹の教え」に「唯能常称如来号」とあり、その続きに「天親菩薩造論説」から「天親菩薩は浄土論に帰命無碍光如来」と記述されて、如来号を「帰命尽十方無碍光如来」とされているとも読み込めます!
ーーー
さて、この法蔵菩薩のストーリーは、
昔々あるところに1人の国王がおられ、大変に優秀な能力で、大変に豊かで恵まれた国を作っていたと言われるところから始まります。
この国王の国民は現代で言う経済的な貧困と言うのもなかったであろうと思われるほど、豊かな国であったと言われるほどだったのです。
しかし、それほど豊かな国であるのに、国民の表情はすぐれず、その国王自身も何かが違うと言うような思いに駆られ、ある日、城から出て街を散策しながら、どこに問題があるのだろうかと考えていました。
すると、光輝く表情をし、威風堂々とした、炎が燃えるが如くすばらしい行者と出会ったのです。
この行者は、世にありながら、自らを見失うことなく、堂々と在るという意味で「世自在王仏」と言われており、この王がこの世自在王仏に出会ったとき、まさにこの人こそ私の求める姿であると「讃仏偈」と言う偈文に讃嘆されています。
そして、この王は「どうぞ私を弟子にしてください」と自ら懇願されました。
そして、その決意は固いと言う事から、王の座を捨てて、出家して法蔵菩薩と名乗られたのです。
まず、世自在王仏は、あなたがなにを願い行じるかなどということは、「まず汝当に自ら知りなさい」と言われましたが、法蔵菩薩は「私にはそれほどの知恵も能力もありません」と答えられました。
そこで、法蔵菩薩は世自在王仏に、様々な仏の国々や人天を見せていただく中で、自らが本当に願い進む方向を見出していかれたのです。
つまりそこで見出していかれた、願いや行が、世自在王仏に言われた、まさに知るべき「自ら」だったのです。
決して、世自在王仏から「こうせよ」といわれたというようなものではなかったのです、
いわば、世自在王仏は、法蔵菩薩の心の中に自然として在る、願いと行を引き出したといえるでしょう。
この自らを知る中で、この上のない願いを立てられ、それがすべての生きとし生ける命を「摂め取る」という摂取不捨の願いだったのです。
ーーー
この「摂取不捨の願い」は、およそ多くの命の根源(無量寿仏)が願っているところであると考えられます。
しかし、具体的なことになれば、例えば「Mくん」の命そのものに、なんら企てや、自我や自己満足による計らいによらないところから「このように生きたい」と言う命のベクトルである本願(願い)が起こっているはずなのです。
そして、自分の事だけを考えたり、他人を蹴落としたりといったことを考えず、素直にその命の願いに従って進んできているのが、今の状態なのではないかと思うのです。
本来、社会福祉事業をするわけではなく、お寺の住職をするつもりで草津に来た、と言う流れであったとしても、そのお寺の住職になるに当たって社会福祉事業が不可欠な要因であるならば、「そこに純粋に身を投じていこう」とさまざまに悩みながらもやり通し続けていると言うことが、Mくんの命の願いのベクトルであると言えるでしょう。
それが、まさに「汝当に自ら知るべし」という世自在王仏からの問いかけに導かれた法蔵菩薩そのものであって、「お寺の住職をするために社会福祉事業も一生懸命にやっていると言う命のベクトル」これこそが、Mくん自身の命が、法蔵菩薩として「自らを知った」と言うことであると言えると思うのです。
人間の誰しもが、なぜ人間として誕生したのかと言うことすらわからないまま、ある日ある時、自らの意思さえもない状態で、命として誕生したと言う中で、自らの命の在り方を求めて彷徨っているのです。
Mくんという命が、なぜそこになぜそういう立場で、なぜそういう生き方をすべく命が選びをしてきたのかと言う意味において、Mくんは、生まれた時からMくんでしかなく、そのMくんが、自我にまみれたり、人を傷つけるようなことを画策するようなひとではなく、そういう計らいを超えて、与えられている社会福祉事業や住職と言う職務を果たすという命の置かれているところで、精一杯湧き上がる命のベクトルを生きているということ、それが「MくんはMくんのままで」と言うことだと思っています。
そういう点で、法蔵菩薩と世自在王仏との出会いとそのやりとりが、「私たちの命から湧き上がるベクトルを知るべきであること」を教えているのです。
ーーー
この教えに該当するのが「覩見諸仏浄土因〜超発希有大弘誓、五劫思惟之摂受」の部分です。
一切の命を「諸仏」として、そのひとりひとりの内面から見える「浄土」はどんな特徴があるのかといったことが、「国土人天之善悪」という文言でしょう。
ここで「諸仏浄土の因」という点について詳しく掘り下げておきます。
私たち「命」は、先に書いた自己の命のベクトルを求めつつ生きています。
これを「因位」の状態とするのは、「法蔵菩薩因位時」と同じです。
そして、わたしたちの命はやがて、好む好まないに関わらず、そのベクトルを生きていくことを受け入れていくのです。
このような状態が、たとえ「不平不満な状態」でも、それは仕方なくも受け入れざるを得ないのです。
みちこ常務が「ズッと問題や問題や」とあれこれ言っていながらも、その「命の場」を生きているのと同じです。
そして、その命から見えている世界観が「国土人天之善悪」ということになります。
同じことを見ていたり取り組んでいても、見え方や取り組み方が違うのは、それぞれの命の個性があるからで、これを、「人天之善悪」というふうに理解して行くのです。
常務は常務の個性で、それぞれの職員や人々の命の個性だと受け止めて、その良し悪しを検討して願いを建てていくなかで、法蔵菩薩の願いが「全生命の共通した願い」だと知るのです。
だから法蔵菩薩は「建立無上殊勝願」ということになるのです。
そして私たちも、自己の命の個性に、この法蔵菩薩の願いを生きていくことをプラスして生きるという法蔵菩薩道を歩むものになるのです。
ーーー
法蔵菩薩道っていうのは、つまりは「すべての命を摂取不捨していくこと」なので、いろいろな人や違いを超えて、理解しあったり受け入れあったりしながら、建設的に命を生かしあっていくと言うことになります。
そういう意味では、Mくんの社会福祉事業は、そういった側面を強く持っている事業であると言うこともできるでしょう。
その中で、このように仏道を求め、生活や仕事を仏道によって成り立たせていこうと言うモチベーションは、すべての命を互いに生かしあっていくことを学び、実践していくと言うことなので、非常に尊いと言うことができるでしょう。
そしてまた、仏教に会うもの、僧侶、門徒さんなどのあるべき姿だといえます。
しかし、阿弥陀如来は私たちは何もしなくても極楽浄土に救ってくれると言った意味不明かつ、意味のない教えを西本願寺の僧侶たちは説いているように思います。
ですから、西本願寺の僧侶たちから、社会を良くするように運動をする、運動まで行かなくても、そのような気持ちで人々に接すると言うことが起こってこないと言う事実を生み出しています。
しかし、法蔵菩薩は、自らの願いを全生命の願いに見出して、摂取不捨と言う願いを整え、それを無碍光如来などの名前として広まっていくことを願われ誓われたのです。
それが、「重誓名声聞十方」という部分に表されています。
次第は前後しますが、この名前によって広まっていくようにと言う願いを含め、法蔵菩薩の願いは全生命にとって深い意味を持つと言うことが、この前にある「五劫思惟之摂受」という部分です。
この願いが、五劫と言う長い間、思惟して出来上がったと言われるほど、全生命に共通した願いだと見出したと言うことの重要さと壮大さを表しておられるといえます。
このように、全生命の願いを「菩薩として生きていく」と言うことを、我々に勧めているのが、この無量寿経の教えであると言えるのです。
ーーー
さて「重誓名声聞十方」までは、以上のように、あらゆる命の根本的な願いを明確にし、それを法蔵菩薩道として我々が歩むと言うことを説かれています。
次からは、「普放無量無辺光」(あまねく無量無辺に光明を放って)と、12の種類の名前を挙げて、この「あらゆる命の根本的願い」と「法蔵菩薩道を歩むため」に、12の角度から光明の意味を表して、様々な智慧の光が私たちに注いでいると言うことを讃嘆しています。
この12の光明の名前は、仏説無量寿経に出てくるものです。
そして、この12の名前の一つ一つの意味については、言葉の通りの内容ですから、今ここで一つ一つを説明することは省かせていただきます。
ここで、「超日月光照塵刹」「一切群生蒙光照」と12の光明について結ばれていますが、太陽や月の光を超えた光で塵のようで刹那な存在である私たちを照らすとあり、一切の群れて生きるもの、つまりは、周りに振り回されて、群れなければ生きられないような愚かな生き方をしている私たちの全てが、この光明に照らされていると結ばれています。
私たちは、すべての命の願いと言う意味での自らを知ることと、それぞれの命の個性から生まれているそれぞれの命のベクトルを素直に生きると言う事は、世自在王仏に法蔵菩薩が自らを知らされたことと同じなのですが、自らを知ることなく、周囲に振り回されながら人の顔色を伺いつつ、不平不満の中につかりながら生きると言う事は、周囲の人々と気持ちを1つにしていると言うように錯覚して見えますが、全く異なるものなのです。
こういう有り様を群れるといいます。
しかし、仏道の「サンガ(和合)」は、群れると言うこととは全く意味が違うのです。
すべての命の願いと、自らの命の個性とを踏まえた上で、周囲の命の願いと、周囲の人々の個性を尊重し、わかりあうと言う努力の上に成り立っていく協調した生き方が、本願に生きると言うことであり、法蔵菩薩道を生きると言う事なのです。
ーーー
さて、このように生きていくと言う事は、その行為が課題となっていくわけで、その行為を業(ごう)といいます。
この次に、「本願名号正定業」とあって、「本願の名号」これは無量寿経の四十八願によるので、「阿弥陀仏」ではないといえるでしょう。
何度も書きますが、無量寿経には阿弥陀仏の文言は出てこないのです。
本願の名号が、無量寿経を解釈した浄土論による、尽十方無碍光如来であり、命の真実を見せる智慧の光明によって、我々が「日々の行いをする事(業)」が正しく悟りに定まった法蔵菩薩道という歩みであると示されているのです。
私たちは、仏教の教え等の智慧を学ばなければ、いつまでも日々の生活が、六道そのものを歩んでいるだけで、六道から脱出することができないと言うことなのです。
つまりは、迷い、苦しみ、不安、恐れなどの心理状態をどうすることもできないまま、愚かな行動をしてしまったりするのです。
そこに、第十八願にある「至心(智慧によって知らされる真実心)」を、「信楽(疑いなく受け入れる)」ことによって、悟りの世界へと法蔵菩薩道を歩む日々を過ごすことになるのです。
ですからこの部分を「至心信楽願為因」と示しされているのです。
私たち仏教徒は、日々の生活に於いて「これで良いのだろうか」と言うような、教えに問うということが習慣付けられていないように思います。
しかし、このように、無碍光如来の智慧の光明に照らされつつ、日々自らの有り様を省みて、この本願に基づいた行為(業)をしているかと言うことを検討するような生活がクセ付けられることが大切なことであると思うのです。
ーーー
さてこのように、命の本願を生きるようになると、それは「覚りと等しい=等覚」といってもいいし、そして行き着くところは「大涅槃」という「無上の悟り=煩悩滅して自己という命が全生命の根源にあたる真如へと帰していき完全な利他をするもの」となるので、「成等覚証大涅槃」と記述されて、「法蔵菩薩道を生きるもの」の現在と、その道の結果を明らかにされています。
そしてこの流れ(因果)は、第十一願の「必至滅度の願」が成就しているからですと、根拠を示されています。
ーーー
このように、仏説無量寿経には、私たちの命が「何を願い、どうなっていくのが命のベクトルを生かすこと」になるのかということを明確にされていることを、ここまでに明らかにされています。
そして、「如来所以興出世、唯説弥陀本願海」と如来が世に現れたのは「弥陀如来の海のように広くて深い本願」を解くためであると記述されていますが、この部分の「如来所以~」の「如来」の部分が、草稿では「釈迦所以~」となっているのです。
ここから読み込めるのは、そもそも親鸞さんは「釈迦の説くところは~」と書いては見たものの、釈迦も「無量寿仏(全生命)」の一人であり、「生命は真如からうまれている」ので、「真如から世に現れ来た命が言いたい(説きたい)こと」は、「無量寿(弥陀)の根本的な願い」であると記述されているのでしょう。
そして釈迦は「いのちが如来であること」を明確にするために、世の中に現れた「出世本懐」がこのことであることを併せて表現されているとも読み込めるのです。
釈迦も「全生命」と同じであり、人間なのですからこの部分は、「釈迦に代表された人間である」といえるのです。
また、ここに「弥陀」と記述されていますが、これは七文字の偈文にするための表現だと理解しています。
なぜなら、「弥陀」という表現は、サンスクリット語では「有量」となってしまうということを、親鸞さんがしらなかったとは思えないからなのです。
サンスクリット語では、「阿」が否定語としてついていてこそ「無量=有量の否定」になり、この「阿」を記述しないのは、単に省略であり、大切なはずの「阿弥陀」を軽めの扱いをしているといえるのです。
私の師である灘本和上は、「阿弥陀を弥陀とかくのは本来ではないことを知っている親鸞さんが、あえて弥陀と記述しているのは、やはり阿弥陀仏という文言をなるべく避けているからじゃないか」と教えてくださいました。
私たち全生命は「無量寿如来」なのです。
ーーー
そういうわけで、如来として現れた全生命は、このような「本願」をもって生きているのだから、「五濁悪時群生海、応信如来如実言」とあって、全生命の本願の海は、ここで違うのだから、「群生=群れて生きる」という「海」に沈んでしまったら、「五つの汚れ(五濁)と悪い時代」の影響を受けるであろうことを注意警告して、「自らの命の願い」である「如来(真如から来た命)が願うところの本願(如実の言)を信じるように生きる」という菩薩道を教えられています。
実はこの部分は一般的には、
釈迦如来が’世に現れた理由は(出世本懐)、阿弥陀如来の本願を説くためだったのです。
だから、五濁の群生を離れて、この釈迦の真実の言葉を信じるべきです。
という風に解釈されますが、これでは、ファンタジーの領域をでることもなく、現実性もないただの「お話」といったことになってしまいます。
仏教本来の教えとしてこの部分を読んでいけば、「あなたの命の純粋な願いを生きよ!」という読み方になるのです。
ーーー
続いて「能発一念喜愛心、不断煩悩得涅槃」と記述されています。
これは、これの前の部分の、「真如から出てきた命=如来の真実の言葉を信じ応じることが大切」(自己の命から自然と湧き上がる思いを、じつは自己の中で言葉にしているのだから、それを信じて応じて生きていくのです)というふうに書かれている内容を受けているのです。
つまりは、「無私(自我の計らいのない自己)」から生まれ出た願いの一つ一つの一念」を喜愛して、これは煩悩だろうかどうだろうかということにとらわれず、まっすぐに進んでいけば「煩悩なんかどっかヘ行ってしまって」涅槃という「滅度」(炎が消える如くに静かに滅する)にいたるのです。
ーーー
そして、次の「凡聖逆謗斉回入、如衆水入海一味」ですが、
これは、自分自身や他者から「凡人、聖者、五逆(五つの大罪)、法を謗る」といった類の者であると、言われようがどうであろうが、そういう人たちみんなが、「命の真実」を知って、「計らい、邪念、思い込みなど」を捨てて、心を命の願いに忠実に従うように「回心(えしん)」するなら、みんながひとしく同じ海の水のように一つになれることを、「命は真如から来た」だから「一如」なんだという論を背景に示されているのです。
ここに「衆水海に入りて一味がごとし」とあるのは、多くの山々からいろんな水が海に入ってきても、結果どの水も海の味の一味になるという譬えであり、ただこのことは、回心しなければわからないことなので、あえて「回入」とあるのです。
つまり、この教えは、何もしなくても、私たちが命の真実を知らなくても構わない、というような教えではないことを、明確化されています。
回心は、文字のように、心の方向転換といえばわかりやすいのではないでしょうか。
私たちは、教えから自分や他者の命の願いを知って、その方向へ歩みを進めるものになる。
という大転換を遂げるのです
ーーー
次に「摂取心光常照護」とあります。
これは、すべての命の願いこそがその命の本願であり、出世本懐であるということを智慧の光明によって知らされることが「摂取」であり、この願いの心を照らす光明なので、「心光」というのです。
この私の命が存在する理由である「本願」を常に照らし、思い起こさせて、この命の進む道を守っている光明なので、「常照護」とあるんです。
そして、だからこの光明を「無碍光如来」というのです。
「阿弥陀仏」という文言ではそういう点を定義できないのです。
そういう点で、私たちは自分の命が。どういう理由で生まれたのかということが明確になっていくのです。
ですから、已に能く(よく)無明の闇を破ってくれると言うふうに書かれています。
そして、これが無明を破ってくれるといえども「雖」という風に、そうではあるけれどという表現から、
私の貪欲、愛欲、瞋恚、憎しみといったこれら(之)の煩悩の雲や霧が常に、この命の真実を信じていく、最高(天)の気持ちを覆(くつがえ)そうとします。
と、現実問題を問題提起して、
けれど、譬え(たとえ)霧や雲が日光を覆っていても、雲や霧の下は明るくて闇がないことと同じである。
と書かれていて、常にこういう気持ちを維持することは難しいという事実を明確にされていきます。
そこで注意すべきは「覆」という文字が、命の真実を「覆そう」としても、という読み方をしたうえで、日光を「覆う」という読み方をさせている点です。
一般的には、どちらも「覆う」と読んで、前者も「真実の信心の天を覆う」と読みますが、そういう読み方をすると、非現実的な実感さえできない「おとぎ話」になってしまいます。
一気に次元が下がってしまいます。
私たちは「自分の気持ち」を維持できない迷いにはまることがあります。
けれど、常にこの教えに立ち返れば、また真実の気持ちになっていけるのです。
ーーー
さて、ここに「獲信見敬大慶喜」と書いてあって、「獲」はものごとを得るにあたって、スタ=とラインに立ったっていうときに使われる文字なので、「自分の命の存在理由が見えてきたとき」つまり「私の命は○○のためにあるんだ!」って「信じられる」ようになったとき、現実の尊さを「見て敬い」、大きな喜び(大慶喜)を獲ることができる、っていうことが記述されています。
ここでちょっと解説すると、「獲」は因位、「得」は果位、だと親鸞さんは定義してるのです。
そういう意味で、「獲信」をスタートラインというふうに書いてみました。
だから「得度」っていうのは、本来は「渡ることを得る」という意味で「果位」になるので、「得度」という位置づけにはかなりの重みがあるのです。
さてそして、続いて「即横超截五悪趣」と書かれていますように、自分の命の存在理由がわかって位置づけやすべきことがわかると、「給料が安い」とか「人間関係がつらい」といった「むさぼり、愚痴」といったことがなくなっていきます。
このことを「すなわち横に地獄(苦)、餓鬼(むさぼり)、畜生(愚痴)、修羅(怒り)、人(虚妄分別)という五悪趣を断ち切る」と書かれているのです。
ちなみに「人」っていうのは、「正しい智慧がない分別をするもの」と倶舎論で定義されています。
つまり、何が正しいとか悪いとか、だれがどういう人だとか、人間は、自分の知識と経験そしてDNA由来の知恵で分別しているけれど、それはみな「愚痴やむさぼりなど」に基づいていて、虚妄でしかないということなのです。
そういう意味でも、ここに「自分の命の意味や理由など」がわかってくるにつれて、自然と冷静かつ他者の命の在り方が見えてくるっていうことです。
平たくいえば、他者の「適材適所」も見えてくるというようなことです。
ーーー
続いて「一切善悪凡夫人、聞信如来弘誓願、仏言広大勝者、是人名分陀利華」とあります。
ここで「一切」について特記すべきことは、皆さん「一切」を「すべて」という意味で理解しいるようですが、これは間違いで、倶舎論に「一切」は「自分が認識している内容のすべて」をあらわしていて、私たち人間は、全部が見えるとかわかるということはないんです。
あくまでも自分の認識の範囲内を生きているにすぎません。
だから「一切」は「一切れ(ひときれ)」なのです。
私たちが認識する「ひと切れの善悪凡夫の者」でも、「命の根源から出てくる誓願をまるで自分の心の奥底から聞こえてくる声を聞くようにして、そうそうこれだ!」と聞いて信じることが、「聞信如来弘誓願」ということであり、そういう人は「計らいや計略」などをせず、「純白の心で生きる」ので、「分陀利華(白蓮華)」のようだといわれるのです。
人間は、自分の命の真の願いを生きることをせず、世間や誰かに認められたいなどといった五悪趣の思いに振り回されて、結果、くすんだようにしか生きていないということを教えています。
ーーー
さてここで、少しめんどくさい文言が出てきます。
「弥陀仏本願念仏、邪見驕慢悪衆生、信楽受持甚以難、難中之難無過斯」
という部分ですが、これをそのまま読むと、「阿弥陀仏の本願にある念仏は、間違った見解を持つ人や、驕り高ぶった人には信じて保つということは難しく、難しい中にもこの上なく難しい」と読んでしまいます。
しかしこれでは、またおとぎ話になってしないます。
ここは「弥陀仏=本願念仏」だと読むのです。「弥陀仏の本願念仏」ではありません。
これは、私たちの命の本願を生きることが、「如来=仏」を念じる(思い起こすこと)つまり「念仏」であり、
無量の命とそのいのちの存在理由が、「弥陀仏」という三文字に含まれているのです。
つまり「無量の命の本願を無碍光如来(不可思議光仏)=弥陀仏(真如=自然)が思い起こさ(念)せてくれて、命の本願(仏)を繰り返し繰り返し、その本願の道を「歩むことができる」のであり、フェイクを真実だと思ったり、間違った見解に固執したり、あえて邪見や企て(計らい)をする人や驕り高ぶっている人には、この「命の本願」を信じることが難しすぎてできない。そういう人にとって「自らの命の本願」を知ることは難しい中にもさらに難しいことなんだ、
と書かれていると読むのです。
ーーー
さて、以上までが「無量寿経」の内容をもとに解釈された部分で、ここからは、七高僧がなにを説いたかという内容になります。
「印度西天之論家、中夏日域之高僧、顕大聖興世正意、明如来本誓応機」
と書かれているのが、インドや西域(チベットらへん)の論者、つまり龍樹さんと天親菩薩さんのことをいいます。
中夏は中華とは実は意味や時代は全く違うのですが、現在の中国で、曇鸞さん、道綽さん、善導さんのことです。
日域は、日本ですがここに日域と、この時代に書かれているのはちょっと興味深いですが、この時代には、日本という国名はなかったと思いますから、日と域が合わさっているのには、日本の成り立ちの上での意味をもっているのかもしれませんが、それは、日本の歴史に興味ある人に任せておきましょう。
日域は、源信さんと源空さん(法然さん)ということになります。
ここでは、これらの高僧が、「大聖(釈迦)が世に出た正しい理由(意)を顕わして、如来(全生命の命の本願とその通りに生きるという誓い)を明かすことが、人々(機)に相応しい」と説かれています。
ーーー
つづいて「釈迦如来楞伽山、為衆告命南天竺、龍樹大士出於世、悉能摧破有無見」と書かれています。
インドの「龍樹」という僧は、中観派、いわゆる「空」を説く派の祖なのですが、この僧について「釈迦如来があるとき楞伽山で、命の底から湧き上がるように、みんな(衆)の為に告げ(告命)られました」という「告命」という表現がされていますから、親鸞さんは「龍樹」という僧の出番が待ち遠しいほどのひとだったのだろうといった気持ちを感じるのです。
そこには、南インド(南天竺)に龍樹という人が現れて(出於世)、悉く「有るとか無いとかいうものの見方」を破られた(摧破)。
と、中観派の「空の思想」が重要であるということを記述されているんです。
「空(くう)」というのは、すべての存在や物事、出来事は、「何らかの条件の集合体」なので、それらは「実体のない幻」のようなものだから、執着するべきではない。
という教えです。
近年の量子物理学でいえば、すべては物質の最小単位である「量子」の集合体だから「実体はない」といっているのですが、そういう意味で言えば、この「中観派」は、科学的といえるでしょう。
しかし、ただそれだけでは存在のありかたを論じているだけで、私の命すらが、「量子のエネルギー」による動きに過ぎないといった「無機質な存在」という風になってしまいかねません。
龍樹さんは、そういうことがいいたかったのではないと、親鸞さんは思っておられて、あえてここで「有無の見解を破った」と記述されたと思うのです。
では、それはどういう意味を示しているのでしょう。
それは、ひとえになにかにつけて「こだわるな!」ということを言われているのではないかと思うのです。
私たちの命が苦しいのは、「自分の気持ちや情報」といった見解に「とらわれて」、じつは気づかないうちに自己の命を拘束してしまっているからなのだ、ということです。
親鸞さんは、その拘束からの解放が「不可思議の光明」(智慧)によって行われてくるんだということをここで明確にされているのです。
〈オマケ〉
そこに私たちの命の存在理由を「キリスト」は教えていると言えるのかもしれません…(こういうことを異端と決めつける「こだわり」もいかがなものかと思うのです。)
ーーー
このような「中観派の教え」を、龍樹さんは説いたのですが、これを親鸞さんは「龍樹さんが大乗無上の法を宣く説いて、命の歓喜地を証明して、これが安楽に生まれる、または、安楽を生きる道であると教えられました」と続いて示されました。(宣説大乗無上法、証歓喜地生安楽)
そして、あえて自分の命の本願を無視して、何だか知らないけれど「修行だと言って、行を行ったり、難しいことがありがたいかのように行にこだわって、自分の命の本願以外に悟りがあるように思って頑張ってる人がいるけれど、そういう人は難行を行じてるんです」と、難行が「陸路を延々と歩いて進むような苦しい生き方だよ」と教えてくださっています。(顕示難行陸路苦)
それよりも、「自分の命の本願に目覚めて、それを受け入れて生きる(信楽)こそが、水道を船で楽しく進むような易行ですよ」と教えられたと記述されています。(信楽易行水道楽)
ーーー
そこでこの龍樹さんの説かれた内容を「憶念弥陀仏本願、自然即時入必定、唯能常称如来号、応報大悲弘誓恩」
という風に、「無量の命の本願を心に念じられるようになると、自然にそのまま必ず智慧の完全な禅定にはいることができるのです。」と書かれています。
ここで「即時」とありますが、これは時系列の流れの中でいえば、憶念しているなかでの「ある定点」を意味し、
かつ、「時空を超越」している命の本源という観点からいえば、「憶念の生き方(生活)をスタートさせたとき」といえるでしょう。
そして、ただよく常に如来号(如来の号ではなく、如来号つまり命の叫び)を称えていることが、「真如から来たあらゆる命(如来)の様々な誓いや願い」の恩(賜りもの)に「報いることつまりは応じること(報は応じるという意味を持つ文字)」になって、本願に目覚めさせてもらったという「大悲」を生きることになる、とまとめられています。
☆こちらをご参考に👇
https://namas45.com/info/4617785
この内容が「自然」ということにつながりますが、私たち「命」は、「自然」に依っているので、自然=真如に逆らうことはできません。
そこで、「自然に必ず禅定(正しい智慧=悟り)に入る」という文章は、「自然に従えば、必ず命のベクトルに乗ることができる」というふうに読むことができるでしょう‼️
日々「なんとなく起こっていることこそ、自然の流れだと思えるようになる」ことでしょう。
ーーー
さてここから、天親菩薩についての記述です、
親鸞さんは、天親菩薩と天親菩薩の論の注釈を書いた曇鸞さんを等価にみていると思われるのです。
なので、天親さんだけ「菩薩」という尊称が付き、天親菩薩という表現が2度出てくるのです。
こういうところで天親菩薩を重視しているというポイントを含めてみていきたいと思います。
「天親菩薩造論説、帰命無碍光如来、依修多羅顕真実、光闡横超大誓願」
天親菩薩は、「浄土論」を造って「帰命尽十方無碍光如来」という「名号」を「修多羅」つまりこの上のない「経典」によって、これを「真実」だと顕らかにされたんです。
そもそもこの「浄土論」は、「無量寿経」によって、おとぎ話のような「浄土を説く教え」も「仏教と相応する(仏教なんだ)」ということを明らかにされているんです。
天親菩薩さんは「倶舎論」や「唯識論」という、仏教の難解な理論を構築されているのです。
この浄土論で、唯識学の観点から、「認識によって、生きる次元が変わる」ということを明確にされたんです。
そこから、正信偈冒頭に重誓偈から引用した「名声聞十方」の「名声」を「名号」とイコールと解釈して、この名号は「帰命尽十方無碍光如来」であるということを、ここまでに縷々書いたように、親鸞さんはさりげなく主張しているように読めるのです。
しかしそれは事実、「浄土論」で天親菩薩が明確にしているからです。
この「無碍光如来」こそが「智慧である光明」であり、この光明に帰依してこそ「修多羅(経典の中でもサンスクリット原典のあるもの)」によって、「無量寿と表現される全生命の真実が顕らかになる」んです。
そして、「横に飛び超えるようにして、いのちの大誓願が光闡(広く明確になって広まっていく)されていく」ということについての「エビデンス(証明)」を論拠と典拠において明確にされたんです。
ーーー
そして、「広由本眼力回向、為度群生彰一心、帰入功徳大宝海、必獲入大会衆数」とあります。
ここで、「回向」という単語について言及すると、これは、「方向を転換する」という意味と、「転換して進む」という動詞を含みます。
ですから、ここは「本来の命の本願の力(エネルギー)への転換」とよみ、トータルで「広く本願のエネルギーへの転換をすることによって」「群がっている衆生たちの為にもこの命の本願の一心を彰かにすること」で、「ともどもに功徳の大いなる宝の海に至り入る(帰入)」ようになり、「必ず、五果門の大会衆門のメンバーになる」ということになるんです。
つまり周囲が「おめだはおめだのまま、ぐずろくはぐずろくのまま」で輝けるひとたちの集まりになるということなんです。
ーーー
ここで、「得至蓮華蔵世界、即証真如法性身、遊煩悩林現神通、入生死薗示応化」と、五果門の究極である「薗林遊戯地門」つまり「還相回向」について書かれているんです。
まず、「得至蓮華蔵世界」の「蓮華蔵世界」は、「華厳経」に説かれている、人間世界を「命の本願」という眼で見れば、どの命も蓮華のように、根っこでは無限につながりあって、それぞれが輝いている、っていうことをいうんです。
ただ、それらの命がその本願に気づいていないから、凡人の目で見るとくすんでいるように見えるだけなんだってことです。
しかし、すべての命は「じつは本願によって生きている」っていうことに気づいていないけど、そこに気づくことができたら、「即時にすべてが真如法性の身だ」って見えてくるようになるよっていうことを記述して、そういう見方ができるようになると、「イヤイヤ生きてるようなひとも、くすんでいるように見える人も」じつはそのままで生きている意味や理由があって、みんないろんな事情や背景をもっていて、私にはひとりひとりのそういった「事情や背景」はわからないけれど、それぞれが「存在の意味や理由」を生きているんだなって、いのちの輝きを見ることができるようになるってことです。
そして、煩悩の林に遊んで、神通力を表すようにして、「生死、病気健康、金持ち貧乏」などといった、たんなる状態の違いに「快不快」「幸不幸」をあてはめて、「虚妄分別」で悩んでいるひとたちに、応化身をあらわして命の本願に気づかせてあげることができるって書いてるんです。
つまり、「自分の境遇は恵まれていない」とか「わたしの人生は不幸だ」といった思いで生きてる人たちに、「○○さんのされている○○は素晴らしいですね」といったり、「○○さんならできますよ」といったような言葉を自然にかけていたり、Мくんが私にしてくれているような応援をしたりというようなことが、自然にできるようになっているってことなんです。
「利他を行う」なんてきれいごとや気張る必要もない。
自分の命の本願に気づいた人は、他の人の命の本願に触れるようなかかわりを自然にやっているものなんです。
ここで「自分はできてるだろうか」なんて思う必要も意識する必要もないんです。
まぁそういうことから、ここの文面を読むと、
これは、仏道を「家」に例えて、仏道に入るっていうのは「如来の家」に入るようなもので、そこに、何があるのかを観察して、その家のなかを見た後は、庭に出て遊ぶような感じで「まだ本願に気づいていない人」を教化するっていうことなんです。
これは、天親菩薩が「浄土論」で論じている内容ですが、ここでポイントだと思われるのは、天親さんが、「五念門と五果門」に浄土の教えをまとめていて、それを「入門と出門」に配当してて、この五果門の第五門、つまり「ラストが出門」になっていて、「家を出て教化する」という意味は、「宗派」とか「セクト」をでるってことを明言してるってことです。
だから、浄土真宗じゃなきゃダメだ、なんてことをいうことをいうような道理はない、ってことになります。
そして、こういう利他を「還相回向」だから「死んでからの話だ」という人が、本流のほとんどでしょうが、賢くない人のいうことは放っておきましょう。
とにかく、教行証文類の還相回向は、往相回向と因果同時なんです。
ってことで、この教えに入ったら、だんだんと庭に出て自然といろんな言葉がけや、いろんな仕方で他人の命の本願を生かしている人になっているってこと、とくに、この教えから「広い世界に出て」教化するってことが、ここのいけてる部分です。
ーーー
ここからは曇鸞さんになります。
「本師曇鸞梁天子、常向鸞処菩薩礼、三蔵流支授浄教、焚焼仙経帰楽邦」
ってはじまりますが、なんとここで「曇鸞さん」も「菩薩」に定義してはるんです。
本師、まぁこれはニュアンスでわかるでしょう。の「曇鸞」さんを「梁の天子」がいつも曇鸞さんの方を向いて「菩薩様といって礼拝していた」っていうんです。
これは、中国の「梁の王」が、曇鸞さんを「菩薩」って定義してる。っていうことがかかれているんです。
これはびっくり、曇鸞さんも菩薩なんです。つまり、天親さんとおなじだとここで定義してはります。
しかも「天子」といった「権力」を嫌っている親鸞さんがあえて「梁という国の王が…」って書いてるなんて、
ありえないような書き方をしてはりますが、それほど曇鸞さんの「’浄土論註」を重要視してはるということなんです。
また、曇鸞さんの逸話として「菩提流支三蔵」というひとから「浄土の教え」を授かって、それまで熱心に修行していた「道教(仙人になる教え)」を捨てて、「楽邦」に帰依しはりました。
ってあるんですが、ここで授かった「浄教」はなんだったのかっていうことについて、「観経」だというひとが多いのですが、私は「浄土論」ではないかと思うのです。
なにせ、親鸞さんは、天親菩薩と曇鸞さんを菩薩としておられる以上、「浄土論」でなければ意味がないのです。
ただ、ここに「帰楽邦」つまり「楽国(極楽と思われる)」に帰依されたというのを、「仙人になろ教えは、不老不死を求めるものだけど、現実性は乏しいと感じていた曇鸞が、浄土の教えに出会って、本当に永遠の命を得る教えだと感動して、浄土の教えに帰依して、仙人になる教えを説く仙経を焼いて、浄土の教えに帰依した」という読み方をすると、観経に出会ったという説もさもありなんといえます。
けど、それだと「曇鸞さん」の「浄土論註」の内容とはずれてしまいます。
なぜなら、「浄土論も論註も」、永遠の命を生きるといったファンタジックなストーリーの仏教的本質を明かしているからです。
つまり、「全生命は真如から生まれていて、すべてが一如の本願を生きていることを明らかにしている」からです。
けれど、ここで親鸞さんが「帰極楽」でも「帰浄土」でもなく「帰楽邦」と書いていることが異例な文言なんです。
「楽邦」という文字を使われたのは、「真の楽の邦(くに)」は、人間が人間として把握して、期待するような極楽ではなく、「悟りという邦(くに)」であるということだといいたかったのではないかと思うのです。
いずれにしても、この部分は「曇鸞さんを菩薩とし」「親鸞さんが嫌っていた権力者(天子)」をもちだし、あえて、曇鸞さんの逸話である「仙人になる教えを焼き捨てて」といった情動的な記述になっているといった変則的な内容になっています。
これは、親鸞さんが、曇鸞さんを相当大切にしていたということではないかと思うんです。
ーーー
さぁここで「天親菩薩論註解、報土因果顕誓願、往還回向由他力、正定之因唯信心」ってあって、曇鸞さんが天親菩薩さんの浄土論を注釈されたことが記述されます。
浄土真宗では、当たり前のように「往相回向」と「還相回向」という二種の回向がありまして、云々…
と当たり前のようにいわれて、阿弥陀さんのお名号のお喚び声を素直に頂く『御信心』を’いただくと、お名号のひとり働きで、わたしがお浄土へ生まれさせていただくことができるのです。そしてこれを往相回向といいます。また、浄土へ生まれた私が、現世のひとを救うためにこの世に帰ってきて救う身になることを還相回向といいます。
わたしたちが、このようにお浄土に救われ、お浄土から救う身になって帰ってくるという往相回向も還相回向もすべてお名号のひとり働き、つまりは他力によって行われるのです。
そこにわたしがすべきことはなにもありません。
なんて言うことを平気で語ってうそぶいている坊主こそマジおかしいんですが、こういう解釈を本流がいまだやっていて、もはや、「量子コンピューター」の時代に、こんなことを本気で信じる人を生むというのは、カルト化するということでしかありえません。
ちょっと取り上げ見ると、真宗学なんて、「喚ぶと呼ぶ」のどっちが正しいかなんて言う議論をやるほど、どうでもいいことをとても重要なことのように議論する学問です。
この「呼ぶと喚ぶ」の議論は、私たちが中仏に行ってた時代に論じられて、二河白道から「喚ぶ」が正しいってなったほど、歴史的に真宗学はテキトーなことばかり論じている学問なんです。
真宗全書という40数巻ある本や真宗叢書といった、各学派の江戸時代あたりからの講義録などが載っている本を買って読んでみても、まぁ緻密な講義といえば、そう感じるのでしょうが、肝心なことがずっとおざなりにされて、どうでもいいことを緻密に論じているようなものが多いものです。
たとえば、簡単なところから言えば、「信心をいただかなかったひとやそもそも幼くして死んだ子どもは往生しないのか」といった問題に、いまだ何ら明確な論はありません。
こういうことは、現実問題として「お子さんをなくされた方」にはおおきなテーマだといえますが、それすらも「阿弥陀様におまかせしましょう。」とごまかすのです。
とにかくいまバカな学問をどうこういうのもあほらしいので、先に進みます。
ここで、「報土」っていうのは、「私の命の願いに報われて現れる次元の場」をいいます。
つまり、「自己の命の願いを知ったものは、世の中が違って見えてくる」んです。
それを「報土」といい、その報土に生きるようになった因果はすべて、「命の誓願にある」ということなんです。
それを顕らかにされたとうことです。
ここでちょっと難しげなことを書くと、天親菩薩は唯識学の人でもあったのです。
つまり私たちが見ている世界は、私たちの認識が生み出しているという論ですから、私たちの命の願いが明確になるか、そうではないかによって、認識が変わるのですから、見える世界も変わってくるんです。
なにもせず、「阿弥陀さんにまかせていても」なんの認識も変わりません。
それよりも、昔ならいざ知らず、量子コンピューターの時代に「浄土に往生してまた帰ってくるんだ」なんてことをむりに思い込まそうとすることの方が、異常な認識といわざるを得ません。
ここで、往相回向という悟り(命の願い)に方向転換して進むことも、「苦しみ悩んでいる人などに、そのひとの命の願いを見出してもらうように働きかけること」つまりは利他をする還相回向も同じベクトルの中で行われることで、「利己的自我」による力では行えるものではなく、なぜかしら「命の本願に目覚めるとそうなっている」という「自然=他力」のなかで起こってくることなんです。
「利己的自我」によって生きていると浮かんでこないような心境が湧き出てきたり、なぜか自然にそういう風になっていたりするものなのです。
もともと「他力」は、サンスクリット語で、「パラタントラ」といい、これは「縁起」という意味なんです。
そういう観点から言っても、私という命は縁起によって生まれ、私という命は「利己的自我」に迷っているときは五悪趣をさまよっていますが、「命の本願」に目覚めたとき、「すべてが縁起(他力)だった」と気づくことができるんです。
そこで「我執」といったとらわれになんの意味もないどころか、どんどん悪趣にはまっていくんだということを知って、「縁起利他力」のベクトルが、純粋にすべてのいのちの本願にあることをしるんです。
なので、みんなに「我執を超えた、純粋な自己から湧き出てくる願いを知っていきましょう」というスタンスの声掛けや働きかけができるようになって、ほんとうのいのちの輪(サンガ)が生まれるんです。
「他力」を「浄土に生まれるための力」に限定しているのが本流ですが、その限定がおとぎ話を正当化させてしまっているんです。
「他力」は「縁起力」ですから、「すべての動きはみな他力」なのです。
「自分が思って行うこと」も、縁起によらないものはなにもありませんから、それすらも他力なんです。
さて、本流が大きく浄土の教えを狭小にしている理由はこういうところにあるのですが、ほとんどの真宗僧侶や布教使は意味不明、本流のいうことを鵜呑み、口移しでいっているだけなので、ほとんど取り合うだけ時間の無駄です。
なので、つぎにすすみますが、次には、私たちが進むべきベクトルが、いのちの願いによって定まって、正にその願いに進む因は、ただ「その本願を自己の願いだと受け入れる信心にある」ということが書かれています。
ここで、その本願を自己の願いだと「受け入れる」という部分は、純粋な命の願いである「至心」を「疑いの蓋を外して受け入れる信楽」というところで定義されます。(信文類)
そして、「その至心なる本願を自己が受け入れたときに往相還相の欲生心がうまれてくる」のです。
つまり、「信心」というのは、自己の純粋な願いに自信があるとかないとか言ってないで、突き進め!
ということなのです。
また、小難しいいいかたをすれば、天親菩薩の浄土論の注釈においても記述されているように、「私の認識がおしえによって変わり、命の本願に生きることが利他のエネルギーを生む」んです。
もちろんこんな表現ではないですが、唯識論でいう、蔵識(阿頼耶識)つまり情報を入れる認識があって、そこに情報である「種子(しゅうじ)」が入ることによって、生きる次元、見える世界観が変わるということなんです。
つまり、わたしの蔵(阿頼耶識)の蓋を開けて、私の命の本願を情報(種子)として入れることを「信心」というわけです。
ーーー
そして「惑染凡夫信心発、証知生死即涅槃、必至無量光明土、諸有衆生皆普化」
とあるように、「迷いや惑いを生きている凡夫」が、命の本願に目覚めて、それを阿頼耶識という入れ物(蔵識)にいれること(信心)で、生きる次元や見えてくる世界が変わって「法蔵菩薩道」をいきるものになるんです。
ここは「浄土論註」からの解釈なので、「唯識論」の阿頼耶識ということをきょうちょうしておきますが、冒頭にも「法蔵菩薩」は阿頼耶識を意味するとも考えられると書いたように、「浄土論註」っていうのは、そういう論理的ポイントをもって浄土教は仏教なんだ!といっているんです。
さて、こういう迷いの凡夫が命の本願を生きると「生死は即涅槃だ」と生きていく中で「証明されて知ることができる」というんです。
そもそお「涅槃(ニルバーナ)」というのは、「勢いよく燃える炎がしずかに滅していく」といった意味を持つのですが、みずからの命の本願を知ってそこに生きる人は「勢いよく燃える炎のように生きて、しずかに滅していく(入滅)」ということを「証知する」ということなんです。
このように命の本願を知って生きるものは、「必ず無量光明土にそのまま至る」から、生きる次元や見える物事が変わってくるので、「諸有衆生(有るという存在にとらわれる衆生)を皆、教化することができるということに自然となるんです。
究極「浄土論註」でいう「帰命尽十方無碍光如来」の名号になるんです。
〈オマケ〉
「名号」という言葉が浄土教では重視されますが、そもそも「名前」というものは「その命の主体になる」という性質のものだと、インドヨーロッパでは理解されているんです。
インドヨーロッパでは、親が子どもに名前を付けるときには、どういう人になってほしいかという思いでつけられるんです。
こういったことは日本でも同じだと思いますが、最近ではキラキラネームとか意味不明な名前も多く、そういう意味合いでつけられていないと思われる名前も多いものです。
ですから、「帰命尽十方無碍光如来」という名号を受け入れたときに、命の本願にめざめて、「無碍光」という「無量光明の世界(土)」をいきるということがいえるんです。
ーーー
さて、このへんからつまらんくなるかもです。
「道綽決聖道難証、唯明浄土可通入、万善自力貶勤修、円満徳号勧専称」
じつは、浄土三部経の中の「観無量寿経」だけが、中国で作られたお経だとほぼ確定されています。
そこで、だれが「観無量寿経」を作ったかということについては、いまだ回答はありません。
しかし、普通に考察すれば、生涯で200回とも400回ともいわれるほど「観無量寿経」を講義したなんて言う話がある道綽さん。
そして、道綽さんのお寺は、もともと曇鸞さんがいて、そこに曇鸞さんの碑文があり、その碑文をみて、道綽さんは感動して住まいするようになった「玄中寺」というお寺なんです。
その玄中寺の近くに、ちょうど道綽さんの時代(609年~645年あたり)に、中国にキリスト教のネストリウス派(景教といわれる)の大秦寺(後の称号)があったことは、意外と専門家にはしられているけど、あまりだれもいいません。
「なにをいわないのか?」っていうのは、「観無量寿経は、中国に来たキリスト教の影響を受けた道綽さんが創作した」っていうことです。
まず、曇鸞さんが「浄土論註」を書いているけれど、その碑文に何が書かれていたか?は不明であり、道綽さんがそこで「浄土教」を知ったとしても、「無量寿経や阿弥陀経、涅槃経などの複数の経典や「浄土論註」なんかの論述書から学んだ未完成な浄土教」だったとえいるのではないかと思われるのです。
そこで、「イエスキリストのみ名」によって、天国に行くといった構造が浄土教に非常に酷似してるので、なので、観無量寿経って、その両方の要素がはいっているんです。
「韋提希」さんにお釈迦さんが様々な「観想」を説きますが。ここは、「浄土論註」にある観察つまり「唯識論」で、結果「下品下生」の人は「南無阿弥陀仏のみ名によって極楽浄土にいく」という最後はキリスト教になっていると充分に考えられるわけです。
そしてこの道綽さんに直接師事したのが、善導さんですが、641年に師事したということからして、善導さんが「観無量寿経」を完成させて、その解説書として、観経四帖䟽までもお創りになったといえるでしょう。
そして、法然さんが、この善導さんの観経四帖䟽が比叡山にあって、そのなかの「散善義」の「一心に弥陀の名号を専念して云々」という文言から「ただ念仏したら、極楽浄土にいける」っていう教えに出会って、「浄土宗」をひらいたわけです。
法然さんは、情的な人だったと思われるので「徳が高い智慧のある人」っていわれていましたが、それは、いいひとっていわれるひとだから、情的な多数派が言うことで、「論理的な」親鸞のような人は、比叡山や当時の仏教界では少数派だったのでしょう。
とにかく親鸞さんがあったかいひとだったと思われるような記述はほとんどありません。
それ以上に、法然さんの教えを理解するために、結局、曇鸞さんの「浄土論註」にもどっているんです。
そこには、仏教としての論があり、あくまでも親鸞さんにとって「極楽」は「浄土」でなければいけない、つまりさとりの楽でなければ意味がない、といった「正論派」だったんです。
なので、教行証文類は、論述の書なので、そういう観点からよまなければ、理解不能になるんです。
いまの僧侶たちのように…
そこで、戻りますが、法然さんがよりどころにした「善導さんと道綽さん」ですから、どうしても外すわけには行けませんし、讃嘆しないわけにもいかないので、「道綽さんは、自我力(自我による修行)を聖道の教えと表現して、聖道の行では、「難証」つまり「悟るのは難しい」と書かれて、「ただ浄土の教えなら通りぬけて入ることができる」と「五果門」について記述されているんです。
そして、よろずの自己満足の善行を行う自我力の修行を貶めて、「円満なる徳号(名号と書かれていないことが南無阿弥陀仏に限定していないことを表現していると思われる、)を専称したらいいと、道綽さんは勧めておられます。
っていう、なんだか、このあたりからあんまり積極的な内容に思えない雰囲気を感じさせています。
「他人事のような…」「仏教用語が減っていて…」「論理的展開が激減する…」そんなイメージです。
〈五念門と五果門の復習〉
https://namas45.com/info/4636130
ーーー
「三不三信誨慇懃、像末法滅同悲引、一生造悪値弘誓、至安養界証妙果」
この三信っていうのは、「淳心、一心、相続心」のことをいいます。
これは、「浄土論註」にある以下の部分からの引用にあるんです。
以下、ウィキアークっていうホムペからの引用です。
とりあえず流し見てください。
- しかるに名を称し憶念すれども、無明なほありて所願を満てざるものあり。なんとなれば、如実に修行せず、名義と相応せざるによるがゆゑなり。いかんが如実に修行せず、名義と相応せざるとなすとならば、いはく、如来はこれ実相身なり、これ為物身なりと知らざればなり。
- また三種の不相応あり。一には信心淳からず、存ずるがごとく亡ずるがごときゆゑなり。二には信心一ならず、決定なきがゆゑなり。三には信心相続せず、余念間つるがゆゑなり。この三句展転してあひ成ず。信心淳からざるをもつてのゆゑに決定なし。決定なきがゆゑに念相続せず。また念相続せざるがゆゑに決定の信を得ず。決定の信を得ざるがゆゑに心淳からざるべし。これと相違せるを「如実に修行し相応す」と名づく。このゆゑに論主(天親)、「我一心」と建言す。 (論註 P.103)
と二不知・三不信をしめしている。この三不信を『安楽集』では、三信と示している。
- また三種の不相応あり。 一には信心淳からず、存ぜるがごとく亡ぜるがごとくなるがゆゑなり。 二には信心一ならず、いはく、決定なきがゆゑなり。 三には信心相続せず、いはく、余念間つるがゆゑなり。 たがひにあひ収摂す。
- もしよく相続すればすなはちこれ一心なり。 ただよく一心なれば、すなはちこれ淳心なり。 この三心を具してもし生ぜずといはば、この処あることなからん。 (安楽集 P.232)
「正信念仏偈」では、この三不信を三信と示された道綽禅師の釈意を、
- 三不三信誨慇懃 像末法滅同悲引
- 三不三信の誨(おしえ)、慇懃にして、像末法滅同じく悲引す。
- 一生造悪値弘誓 至安養界証妙果
- 一生悪を造れども、弘誓に値ひぬれば、安養界に至りて妙果を証せしむといへり。(行巻 P.206)
と、道綽禅師の釈功とされている。
以上が引用だけれど、こういう空虚な解釈は、私の教行証文類講義にはきっちりと解釈しているけれど、そういう解釈は、実際現実的な意味をなさないって思うので、ここに書いていることをいままでのように記述します。
つまりわたしたちが、私の命の願いを「淳く信じて、その願いを一筋に、それこそが私の命の生きる理由だと継続して思いながら生きていくことができる」ことを三信といい、これと真逆な状態を三不信というわけです。
道綽さんは、浄土論註の内容を借りて、三信三不信をねんごろに示されているって書いてはります。
これが、「教えと行」が残る「像法の時代」も、「教え」しか残らない「末法の時代」も、同じく慈悲をもって悟りの道へ引き寄せる精神的ありかただといっているわけです。
この際「末法思想」はどうでもいいです。いつの世もたいがい「世も末だ」っていうんだから。
鎌倉時代でも「世も末だ」って言ってるわけです(笑)
なので、一生涯悪を造っていると思うようなひとも、この命の弘誓に値うことで、安養に至って、すぐれた結果を得ることができるって書いておられます。
〈オマケ〉
ここに実相身、為物身ってあって、ウィキアークでは、以下のように書いています。
とりあえずまた流し見てください。
ー
じっそうしん 実相身 いもつしん 為物身
真如実相にかなった自利円満の仏身。これに対して、衆生(物)のために利益をほどこす利他円満の仏身を為物身という。曇鸞は、この実相身・為物身によって阿弥陀仏の性格を明らかにしている。それは阿弥陀仏の仏身の全体を指して実相身とし、同時にまた為物身とするもので、阿弥陀仏の正覚は単に仏みずからのためのものではなく、衆生救済のために成就されたものであることを示している。→不如実修行、七祖-補註1。(浄土真宗辞典)
ー
さぁこの説明を読んでわかる人は、どれだけいるでしょう。
もはや数学以上に理解不能です。
実相身っていうのんは、私の命がなんか知らんけど生まれてきた根源のことで、為物身っていうのんはその私の命は自我のためにあるんやなくて、世の命の願いを互いに生かし合うためにある(物の為にある身)っていうことです。
こういう簡単なことを、あんな理解不能な書き方しかできひんのんは、わかってへんから頭ん中でこねくり回して文章を書くからなんです。
たとえば「自分の気持ちに整理がついてない状態でラブレターや謝罪文(あくまでも極例)なんかを書いたら何を言いたいか意味不明になる」ようなもんです。
ーーー
「善導独明仏正意、矜哀定散与逆悪、光明名号顕因縁、開入本願大智海」
さて、音読では音が上がる場所に参りました。
なぜ音をあげるのか?ということについて、いろいろと調べた経験がありますが、
たまたまこの部分で「本堂に暴漢が来た為に大きな声になった」とか「ある歴代の門主が音程を取るのが下手で、たまたまそうなった」とか「善導さんが重要人物だから」とか、いろいろありますが、最後のものは無いと思います。
とはいえ、日本の念仏一筋(専修念仏)は、この人の本を法然さんが読んだことから始まっていますから、最後のものでありなのかもしれませんが、それほど特別視するようなお人ではないと思うのです。
ここで親鸞さんは「善導さん独りが仏の正意を明らかにした」ってありますが、これがその通りならば、他の祖師はどうなるんでしょうか?
これは、法然さんが善導さんの観経疏から念仏の教えを開いた、ということに気をつかっているように思います。
そして、観経から「観想行をしようとする人(定善)や良い行ないを積んで悟ろうとする人(散善)」たちと、また反対に「五逆の悪を行ったものたち」のことを、それでは悟れないよと「矜哀(あわれん)」で、光明と名号の因縁を顕らかにされたっていうのです。
そこで、開入本願大智海ってありますが、これらを統合すると、私たちが命の本願に目覚めることは、帰命尽十方無碍光如来の光明と、その光明(帰命尽十方無碍光如来)を受け入れる「光明の名によって」という因縁を顕らかにされたっていうことです。
古来から、インドヨーロッパでは、「名による」という表現や意味は、「その名に統治される」という意味ですから、「尽十方無碍光如来」の名前を受け入れたら、その名前に象徴されるものごとに統治されることになるんです。
つまり、私たちが「帰命尽十方無碍光如来」と受け入れて、智慧の光明によって、私たちの命の本願が見えてくるようになって、「本願の大智海」に入るってことなんです。
ただ、ここは善導さんなので、名号は「南无阿弥陀仏」なのでしょう。
しかし南无阿弥陀仏は、光明と寿命を内在しているんですから、それで「命と智慧が一括り」になります。
ーーー
そして「行者正受金剛心、慶喜一念相応後、与韋提等獲三忍、即証法性之常楽」と書いてあるように、命の本願を生きる行者は、まさしくそれこそが自己の命の道だと明確になるので、ダイヤモンドのような金剛心を受けるんです。
そこには、慶喜心があってその慶喜心の一念と相応したのちに、韋提希のように三法忍という悟りに等しい心を獲るんです。
そしてそこには、「法性」つまり命の根源を認識した法性の常楽があるんです。
ここには、こういった内容が書かれていますが、あえて「三法忍」ってなんなのか、なんてどうでもいいことです。
ただ、善導さんの書物にそう書いてあるから、そう書かれているという程度で理解したらいいと思います。
ーーー
なんだかさらっと善導さんが終わったあとは、日本の「源信さん」に移っていきます。
「源信広開一代教」って、源信さんが、お釈迦さん一代の教えを広く開いたって書いてあります。
源信さんは善導さんと直接も間接も関係はありません。
そこで源信さんが書かれた「往生要集」って、意外と語られることが少ない書物で、語られるとしても「地獄の様相」などの六道を描写したような部分が多いものです。
そういう観点で往生要集を見ると、情動的な物語を書いた書のように思われますが、
じつは、往生要集全体を見ると、根本的には釈迦の教えから、「浄土論註」を根底にして論じられている論書だとわかります。
このことは、師匠の武田宏道先生の「往生要集講讃」(永田文昌堂)を読むとよくわかります。
源信さんは、釈迦の根本の教えから浄土論、ここも特に「五念門五果門」までを引用して、かなりな現代的な学問のような人間の人体の解剖だの宇宙の分析だのという理論をもって、仏教を確かに広く開かれています。
一度読んでみたらいいと思います。マジ…
《特に》
ここであえて書いておきますが、源信とあんまり関係ない内容なんですが、
わたしたちは、周囲の環境やいろんな情報に振り回されて「自分を見失う」んです。
いつまで、日本はマスクをしているんでしょう。また、コロナで戒厳令のようになるということらしいですが、
それは、世界の政治改革の中であえてされることなんですが、そういうことで、またワクチンだとかなんだとか騒ぐように持っていく悪魔のようなひとたちがいるわけです。
そして、ワクチンをわれ先にとムキになる人や、ワクチン打って「副反応がどうのこうの」というひとたちもでてくるわけです。
みんな智慧を持とうとせず、世間の情報だけで動こうとして、我を失ってしまうんです。
お金のためになんでもするようなひとも、資本主義という悪魔のシステムに踊り、民主主義という一見大衆を大事にしているようなイデオロギーが実は、賢くない多数派の意見によって、社会がどんどん劣悪になっていくという、これも悪魔のシステムなのです。
日本人が宗教を失って、こういった愚の世界を生きていることが、なげかわしくてしかたありません。
しかしこれを、「命の本願を知る教えによって’」誘惑に惑わされない、どこにいけば、どうすればいいのかということが智慧としてわかるようになるわけです。
つまり、この動きの中で「得をしているのはだれか?」そしてその人たちは「本願を生きているか?」といったことを見ればいいんです。
「得をしている人がいる」「けれど、そのひとたちの目が死んでいる」「ならば、誰かバックで動かしているものがいるだろう」「ならば、この情報は信用しない方がいい」といった具合です。
「ウラで動かしているものがどういうものか」を知る必要はありません。
情報に踊るか踊らないか、つまり本願を生きる自己の在り方が振り回されないように判断ができればいいのです。
(2022年7月7日現在)
ーーー
次には「偏に安養に帰依すべきことを一切に勧める」ってあって、「安養」っていう表現で、本願に生きることが、心身を自他ともに養っていく道であることを表現されています¥。
そして「専ら子の本願に生きるか、そういう決定心がなくて迷いながら生きるかという違いは、本願に報われた世界を見て生きていけるけれども、迷っていたら化土という〈化けた世界〉を見ていくことになるよ」と、報土と化土を分けて論じられています。(弁立)
って本願に生きるっことで見える世界が明確に変わっていくことを述べられています。
わたしたちは、自分の生きている世界をほかの人と同じように見ていると錯覚をしているんです。
じつは、科学的に言っても、眼球の網膜に移った映像を脳が処理して判断をしているわけですが、認知症になれば脳の視覚野が、きちんと働かなくなりますし、普通の人でも視覚野の判断は「脳の中の言語が定義します」から、たとえば「一人で部屋にいる」という状態を、「淋しい」という言語で定義するか、「静寂」という言葉で定義するかで全く異なった世界になるわけです。
また、脳はトランスに入ると、いわゆる催眠状態になり、暗示によって示されることを見てしまいます。
ですから、自己の本願を明確に生きていないと、人の言葉や情報で化けものをみてしまうのです。
「お金に目がくらむ」なんて的確にその辺を表現しています。
世の中の化け物の中で生きないようにするためにこそ、迷うことなく自己の命の本願に進んでいくのです。
☆今の私の本願は「クリスチャンとして生きる」ってことです。(笑)
ーーー
「極重悪人唯称仏」って、ここで「唯信心か唯称仏か」という疑問が少しわきませんか?
私はそう思ったんです。
親鸞さんにおいては「唱える」は、ただ口に出してとなえること。
「称える」は、自我の私が、自己の本願を受け入れた信心から出てくる「はかり(証明=証し)」としての「となえる」ですから、「極重悪人」にも、自らの本願があるはずで、「悪を犯すにしても、理由や背景があって、その理由や背景のなかで、自己の本願を見失っていくのでしょう。
さきにも書きましたが、、私たちは「自分を見失う」ということが、普通にあって、なんらかの情報や世間に乗っかっていくことで、知らず知らず自分を見失って「悪」(五悪趣)に走ることはあるものです。
なので、ここでは、自己の本願を見失って生きている人たちをも含めて「可能性を内在した悪人」とされているのかもしれません。
そういう点では、極重悪人もその理由や背景が自ら見えてきて「まるで真逆のような自らの仏心に目覚めて、本願を見出していく中で、称仏」ということが起こるのでしょう。
なので、このあとに「我も亦、彼の摂取の中にあった(在)」と知って、「煩悩(悪に走らす理由や背景)に眼がさえぎられて見えないようだけど、命の本願に目覚めさせようとする〈大慈悲〉は、倦(あきる)ことなく常に我を照らしているんです」って書かれているのでしょう。
つまりは「智慧の光明、無碍光如来」を意味しているんです。
ーーー
そしていよいよ、親鸞さんの「本師」である「法然聖人源空」の部分です。
「本師である源空さんは、仏教を明らかにしました」ふむふむ‼️
「善悪の凡夫人を憐れんで、真宗の教えとさとりの証明を、当時の認識でも極東の片境とされていた日本に起こしたんです」ってありますが、これは正確には「浄土教を興した」のであって、「真宗」じゃあないはずです。
当時、中国で景教は「真宗」と呼ばれたいたと景教の碑文にありますが、親鸞さんは、それを言いたかったのかも知れません。
そして、法然さんの「選択本願」は、第十八願に限定されるので、この第十八願の「乃至十念」を弘く悪世に広めたってことで、「この生死の家に帰ってこないように(還来生死輪転の家)」決まって疑いの情を止めていれば、「速時に寂静無為の楽(法楽)」にはいれるんだけど、これは信心をもってなることで、ただ唱えればいいってもんじゃあないんですよ!
っていうてはるんですが、
この意味不明な浄土教の真髄を、親鸞さんは今までに説かれて、その教えが法然さんに至って、こういった「とにかく唱えろ」的な教えになっているようだけど、信心がポイントだということから、ここまでの「命の本願」に生きる。
ということをサゼスションしていると思われます!
ーーー
さて、こうやって「無量寿経、浄土論」などから、七高僧などの教えによって、端っこのない(無辺)ほどの極濁悪を救う(拯済)ために説かれているこの教えを、
道俗(僧侶も一般人も)共に時の衆生たちは、心を同じくして、唯、この高僧の教えを信じてください。
このように、正信偈はおわるわけですが、あくまでも、方便法身のおとぎ話のような阿弥陀如来の教え、
として全体を読み込むこともできるのでしょうが、それでは納得できない私たちは、教えの根幹に流れている真実を読み込んでいく必要があるのです。
そういう意味で、今回は本質から正信偈を解きほぐしてみました。