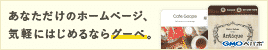第四十願まで。。全生命、四十八の願い‼️
अमितायुस् Amitāyusという「無量寿仏」の教えには、全生命の願いを48願にまとめいています。
異訳の無量寿経では、24願になっていて、教行証文類にも引用されて、シンプルですがここでは48で書いていきます。
本文は、それぞれ聖典とかで確認してください。
まずこの四十八願は、「設我得仏〜不取正覚」に括られていることを徹底しましょう。
親鸞さんが、信文類に無量寿経の下巻から「本願成就文」という定義を作ったので、ややこしくなっています。
つまり、設我得仏〜不取正覚ってあるのに、完成してますっていうことになってしまっているからです。
そして、道綽さんあたりから「浄土三部経」として、観経を当て込んで阿弥陀経とも繋いでいるので、そもそもの「法蔵菩薩」が三部経上「不在」になってしまったんです。
あくまでも「無量寿経」を単独で理解する必要があるでしょう。
親鸞さんは、正信偈にあるように、キッチリ法蔵菩薩を重要視しているんですが、
とはいえ、信文類で、これが出来ちゃいましたって「第十八願成就文」だと、あの「諸有衆生、聞我名号、信心歓喜、乃至一念〜」の文言を定義しちゃったので、「設我得仏〜不取正覚」が重要な意味を持たなくなってしまったんです。
この「諸有衆生〜」に「本願成就文」だという定義はあくまでも親鸞さん独自のものです。
この四十八願を、大経で無量寿(命)の願いという場合、その願いの成就を満たす必要性が、この「設我得仏〜不取正覚」なのですから、これを基本に理解することが重要です。
つまり願いの成就は行者にあるんです。
親鸞さんの教行証文類ではそうなっていますが、「信文類」だけが成就しちゃってますになっているのは、難しいことがわからない人へ向けての「方便則」が信文類だからなのです。
しかし、真実を論じている、教行証の各文類においては、行者によるという内容になっています。
そしてさらに考えるべきは、本来「無量寿経」は、三部経ではなく、それ自体で完結しているという基本です。
こういった前提から読んでいきます。
それでは本文を見ていきます。
第一願では、「本来的に地獄や餓鬼や畜生を願う生命はない」ということです。
どの命が「最初っから苦を求めて生まれる」のでしょう。
全てのいのちは、こうなりたくないのになってしまっているから、お互いの命がそうならない世界を求めて願いましょうっていう意味で、第一願がスタートするんです。
ーーー
さてここで、「国土」っていうことについて考えてみると、「無辺の国土」に「国」という枠組みが必要なのでしょうか?
じつは他でも書きましたが、私たちが見ている世界は「無辺」の中の一部でしかありません。
そういう意味で「我が国土」というのは「私が認識しうる国土」ということであり、その国土にはさまざまな人や命があるわけです。
しかし、そのさまざまな命が同じ次元を生きているとは言えません。
つまりは、「地獄や餓鬼や畜生を生きている」ということが言えるのです。
ですから、私が生きる世界を共有する命でさえ、もちもと「地獄や餓鬼や畜生を生きたい」と思って生まれてはいないのですから、私たちが法蔵菩薩道の中で、悟りへという観点、「命の本願」を互いに見出していくような生き方をすることが重要だということが、「国土」ということだと言えるでしょう。
第ニ願でも、国中の人や天人が、寿命尽きた時に、「あの人は結局、地獄や餓鬼や畜生道にいくような生き方をしたねぇ」なんて思うことがないように生きる場(国土)を共有している人たちには、仏道というか「命の本願を輝かせてあげられる働きかけ」を怠らないようにしましょう。
というふうに読んでいきましょう。
第三願にあるように、国中の人天が「命の本願を生きれば、金色に輝く」ことを言っています。
どんな命でも、尊ばれその願いいるていると、輝いて見えるものです。
「青色青光、黄色黄光…」と光ることができるのは、本願を生きているからです。
そうでなければ「何色もすべてくすんで」しまうでしょう。
第四願では、形や色が違っていても、好むとか醜いということを思いも考えもしないようにすることで、輝くことができるといっているのです。
第五願では、「宿命」という現代でいうDNAにあるものを認識(さとる)して、少なくとも「百千億那由多の諸劫の事」ってあるのは、中国翻訳のめんどくさい大袈裟なところで、「自分の命の本願とその本願に流れている長い歴史の可能性と限界を知るっていうこと」になるでしょう。
ーーー
第六願にも、「百千億那由多」とでてきますが、とにかくそれほど多いということと、多いけれど限界があるということを、無量に近いけれど数字を出すことで限界もあることを現実化しているといえるでしょう。
ここからは「天眼」第七願には「天耳」とでてきますが、仏教では「見ることと聞くことを同次元」で解釈します。
ここに「観音」を当てはめればよくわかるでしょう。
第六願で見たことを第七願で聞くとともに「受持する」ってあるように、私たちのいのちの願いと苦悩を聞いて見て「受け入れる」ことで、互いの命が呼応しあうといえるでしょう。
そしてそれらがいずれも「諸仏の国と説くところ」という風に、すべてのいのちを諸仏として、どんな状態が言えたとしても諸仏の国土のあり様であり、どんな叫びも教えであると受け止めていくんです。
いろいろな命の状態を見ても「我関せず」だったり、「聞いてもよそ事」だったりという姿勢で生きていると、いのちが呼応しあうことはないでしょう。
たがいに「我れ」という自覚を持つ命をもって生まれている不思議さの中で、「我れと我れ」が呼応しあうという「感応道交」しあうことにこそ、「我れが自我ではなく、自己として独立しうる」のです。
このへんの話は「抽象的」ですが、ことばを超えた境界を言説にする限界から読み取っていくものであろうと思われます。
こういう境界にいたればわかるという性質のものです。
なので、こういう文章が響かない人には響きませんが、おおくの人にはこの部分だけのお話では響かないでしょうし、ほとんどの「精神世界」についてなにも考えていない人には永遠に響かないでしょう。
なので、とにかく物質優先社会をそのまま経済のみでただ漫然と生きているということは、いかに一つの命としてもったいないことかということがわかるでしょう。
しかし、第六、第七願による、俯瞰して見る(天眼)、かすかな声も聞き洩らさない(天耳)によって知りえた命の叫びを受け止めて、百千億那由多とかかれている限界点もあるなかで、それらに呼応していけるかということが説かれているのでしょう。
ーーー
第八願には、「他心を見る智を得る」ということが書かれています。
実際問題、「他心を知るとか見るとかいうこと」は難しいものです。
たぶんこう思っているだろうと思ってもそうじゃなかったり、理解不能な言動があったりおよそ自分には理解できないことのほうがおおいものです。
そこでここに「智」とかかれています。
これは「智慧ということ」になるのでしょう。
では智慧というのはどういう形式のものかを考えてみますと、まず「知るということ」から始まります。
そして、そこに「興味を持つ」ということが必要になります。
興味が出てきたら、知るためには調べるということになります。
ここで、「他心」ということになると「聞く」ということになるわけです。
「どう思っているの?」「どう感じでいるの?」といったことを聞かなきゃわかりません。
そして、こういった姿勢で人とかかわっているとだんだんと「聞かなくてもわかる」という状態になります。
とはいえ第八願において、「聞かなくてもわかる」レベルを要求しているのではなく、いろんな命に「興味をもって聞いていきましょう」ということだといえると思うのです。
そのことによって、「下百千億那由他の諸仏国中の衆生の心念を」というふうになっていくんです。
ここに諸仏国中の衆生とあるように、諸仏と国中の衆生は同格で記述されているところはポイとになります。
いずれにせよ、より多くの命に興味を持ち、その命が何を考えて、何を苦しんでいるか」といったことに興味を持ち知っていくことが、法蔵菩薩(全生命)の願いだということです。
ーーー
第九願には「神足」をもって、一念の間に下百千億那由他を飛び越えて救いに行くという意味のことがかかれています。
これは、問題ありの観経に、韋提希さんが牢獄の中から「お釈迦さん助けて!」って叫んだら、霊鷲山で説法してたお釈迦さんが一瞬で目の前に現れて、南無阿弥陀仏の教えを説いたっていう部分に当てはまりますが、これは、この第九願から作られたんじゃないかって思えるほどです。
まぁそれはともかく、私たちでも若いころには、彼女に会うためならたとえどんなところでも素っ飛んで行ったっていうようなことを思い出すと、そういう純粋さっていうのんを私たちは、大人になるにしたがって失っていっているように思います。
とにかく行かなきゃいけないといって、唯一直線に突っ走るという純粋さこそが、命の本願なんだと思うのです。
いま、ちょっと忙しいからとか、また落ち着いたらなんていうのは、自分勝手なのか人生に疲れているのかのどちらかではないかといえそうです。
第十願ですが、「想念を起こして、身を貪計する」とありますが、私たちが「本願の命を生きるときは、想念による貪計」ではないんです。
あるがまま、自分の魂に嘘はつかない、自分を守ることよりも大事なことはたくさんある。
というように、想念によってむさぼりの思いから自分の身を計略的に扱って、自分の命をも自分が持て余していくようなことはない。
ということが、書かれています。
ここにある「想念を起こす」ということが、「不自然な自我執」を生むということを明確にされています。
人間はあれこれ考えて動くのではなく、命の本願のベクトルに素直に動く、魂に嘘をつかずにまっすぐに進むことがもっともよいということなんです。
ーーー
さて、第十一願です。
というのは、宗学をやってる方はご存知のように、四十八願から親鸞さんが「真実五願」(11、12、13、17、18願)の一つ目に入るからです。
私は、親鸞さんのこの「真実五願」という読み方を尊重すべきかどうかなやむんです。
「無量寿経」という経典からすると、この願いに「真実も方便もない」すべてが真実でなきゃあおかしいことになります。
かといって、経典の中に「真実と真実へ誘導する部分」があってもおかしくはないわけですが、厳密にいうとそういういわば方便も真実ですし、裏を返せば、こういう言説は「色もない形もない真理を知らせるためのことば」である以上、伝達には限界があります。
だからこそ、親鸞などのスゴイひとがその辺を明確にして教えてくれているのかもしれません。
が、結局その「解釈」が各学派といった「解釈を生んでいって」どこまでも言説は定義できない状況になってしまうんです。
そういう意味では、まずは原典である無量寿経の全体を真実の言説化と読み込んで、その中から理解不能であったり、現代人に意味不明な部分を親鸞さんなどに聞き返すという読み方の方が、正確な読み方になるのではないかと思っています。
そういうことから、特にここを「真実五願のひとつ」とあえて読まずに進めていってみようと思うんです。
ーーー
この第十願に書かれている、「想念を起こす」ということが、「不自然な自我執」を生み、その命の在り方が迷いや苦悩に生きるということをのりこえて、「自我執ではなく、命の願いを素直に生きれば、それが、まさしく悟りに向かっている定聚ということであって、ついにはそのいのちがラストシーンを迎えるころには、滅度というさとりにいたるんです。
このラストシーンがいつなのかということは、人ごとに違うのですが、自覚できる状態になるんです。
つまりこの第十一願は、命の願いをありのままに生きることが、悟りへの道であり、究極の自己さえ滅する「滅度に至る」ことを自覚できるということが願われているようです、
そして、その命の願いを教えてくれるのが、「智慧の光明」なのですから、第十二願に、あらゆる命の本願を見せる光明が「諸仏の国を見せる」って書かれていて、いままでの「国中」から他の諸仏の国という対象者が変わっています。
つまり、第十一願までは自己が自己の命の願いに目覚めて生きるようになるという第十一願に自己の問題がおさまって、この第十二願では、他者の命の本願も光明によって見えるようになるということが明確にされているんです。
さらに、第十三願は、すべての命は寿命に限定がないということを願っています。
これは、すべての命は本来、命に寿命はないからこそ、第十一願で滅度という「自己さえも滅する」という、真如法性への回帰によって永遠性を持つという本質を説かれているんです。
私たちすべての命は根源的に「一」であるけれど、現象的に「多」という姿をみせていますが、その「多」=「一切」は根源的には「一」であることを、華厳経がとくに教えていて、この無量寿経は、華厳経よりのちに成立していて、華厳経の影響を強く受けているのです。
そういう点で’この第十三願のように、すべての命には寿命に限りはないと、根源的な命の在り方を願いとしているんです。
ーーー
第十四願で、国中の人天が、十二、十三を経て、国中の声聞に代わっていますが、この辺はこのあとも「人天」にもどったちしますから、大きな意味はないと受け止めればいいでしょう。
なんせ、ここでいいたいことは、仏教で命の在り方を「十界」として説かれる場合がありますが、これは、「地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天、声聞、縁覚、菩薩、仏」という十になります。
このなかの「声聞」は声を聞く、つまり釈迦などの教えを直接聞いて悟りへ至る命のことです。
そして、縁覚というのは「十二縁起」などの縁起説を「自ら悟っていく」命のことで、必ずしも師匠を持たないので「独覚」と呼ばれれうこともあります。
そこでこの縁覚よりも下に位置する「声聞」のものが、下三千大千世界の声聞と縁覚が百千劫という時間において、どれだけ存在するかを計算して知ることができる。
とあります。
この第十四願は正直意味不明です。
声聞のものが、声聞や縁覚のものの数を知ることに何の意味があるのか?
命の本願について、教えてもらわなければいけない(師匠の声を聴くことを求めるもの)が、どれだけいるかを把握して、そういう人たちとともに聞かせていただこうという姿勢を持つためなんていうことなのでしょうか?
いろんな開設を見ても釈然としない部分です。
こういうところこそ翻訳のサンスクリット原本を見てみたい部分です。
第十五願は、「寿命はほぼ無量であるけれど、本願の長い短いは自在である」と書かれています。
これは、この無量の寿命を本願によって生きていると、いずれかのときには、そこ本願は本願という以上に自然に身についているために、どこからどこまでが本願による生き様であるかという境目がなくなっていくんです
つまりそこで、「なんだか本願に生きていた時期は短いなぁと感じたり、すっと本願にいていると思う人などがいる」ということです。
つまり、この命の本願の人生に入ると、すべてが自然に進んでいくので、どこからどこまでが本願であるといったせんびきはなくなるんです。
常に「自然法爾に本願を生きていける」ようになるのです。
第十六願において、「不善の名」とありますが、仏教や当時からの世界的宗教において、名前というのはその命のすべ得てのありようを示すので、「不善の名」はあってはならないといえるでしょう。
地獄や餓鬼や畜生という以外にも、多くの不善の名はありまあすから、’そういった名前を聞いた」ならば、認められないということになるのです
これは。世界人類が忘れかかっている、世界的にも「イエスキリストのみ名において」というように、「無碍光如来のみ名において」という以上は、不善の名はあってはならないのです。
さて、つづいて、真実五願の第十七願に入っていきます。
ーーー
第十七願ですが、これが結構な問題を引き起こしてきました、
漢文のままだと「咨嗟称我名」となっている部分を、「咨嗟称」「我名」なのか、「咨嗟」「称我名」なのかといったことなんです。
どっちでもいいって思いますが、前者だと「我名を咨嗟(讃嘆する)」となるので、「名号が単独で存在して、名号自体が行として救ってくれるっていう読み方」になるんです。
後者だと「称我名」して「咨嗟する」という「称名」によって救われるってなるんです。
けど。これって、別に親鸞さんがこんなことを論じたんじゃなくて、お西の空華という学派の学者が前者の言い分で、「名号が人間と関係なく単独で存在してひとり働きするから、人間の自力は関係ないんです。
って主張しているだけで、どうでもいいばかな話なんですが、「浄土往生にのみ他力をつかう」空華からすると、称えるかどうかという人間の状態が往生に関係するとはいえないってことがいいたいから、こんなどうでもいいようなことを論じています。
なので、「名号がひとり働きするから、疑いなくその名号を受け入れる一念のところに往生が決まる」って言いたいんですが、そうすると「信の一念がないひとは往生できないんですか?」という問いにいまだ回答はできていないのです。
そもそも念仏なんか知らんかった人や子供で南無阿弥陀仏の何たるかも知らないまま死んだ人はどうなるのかという、「小児往生問題」いわれますが、結果「阿弥陀様に任せておけばいずれかはなんとかしてくださる」といったテキトーな説明で終わっています。
そもそも、本来の無量寿経としてこの第十七願は、そんなことをいいたいわけじゃあないようです。
この第十七願は、十方世界の無量の諸仏がことごとく、無量寿仏(無碍光如来)を讃嘆しているということを言っているだけなんです。
つまり、私が認識しているいないにかかわらず、あらゆる世界の無量の命が、本願に生きることを喜んでいるってことです
生命は本来自己の本願を生きるために「無我の我」としてうまれてきたんです。
もし生命の本質が「完全無我」ならば、そもそも「我」という存在である必要はないし、「無我でなければならない」のなら死んでしまえばいいことです。
なぜ、私という命が「わたし」という認識をもって生まれているのか、また、いのちにはなぜこれほどの多様性があるのかという意味からすると、いのちは自然にその命を願いによって成長させる(次元を上げる)ために、それぞれのありかたで生まれているのでしょう。
そういう意味で、あらゆる命の在り方を「十方世界の無量の諸仏」といわれているといえるでしょう。
「あらゆる世界のあらゆる命がそれぞれの願いを持っていて、それを無量寿仏に集約して讃嘆されるようになる」という願いが第十七願だといえます。
これを全体的に表現するなら、「全生命が本願によって生きることを、全生命が歓喜して、各々の命を讃嘆している」というふうにいえる願いだと思うんです。
そこで、このことをうけて第十八願に入ります!
ーーー
第十八願は、この四十八願中の本願ともいわれていますが、なんで四十八のなかの第十八番目というあいまいな部分に本願があるかという問いがあったりします。
そういう意味で、本願はあくまでも四十八願全体であるという見解もありますが、私はこっちをとっています。
そういう意味で第十八願は第十八願としますが、たしかに本願といえなくもないといいたくなるポイントもあるんです。
「設我得仏、十方衆生、至心信楽、欲生我国 乃至十念 若不生者 不取正覚 唯除五逆 誹謗正法」
というのが全文ですが、まず「十方衆生」という部分は、親鸞さんも教行証文類にしつこく引用されている異訳の大経である「平等覚経」などに「蜎飛蠕動(ケンピネンドウ)に至るまで」と訳されていて、ここには「小さな昆虫のような虫」もはいるんです。
つまりここに、人間以外の虫に至るまでも「至心」という真実心の中でまっすぐに生きて、互いのいのちが至心に基づいてまっすぐに生きていることを受け入れあい「信楽」、すべての命がそのように受け入れあっていく浄土という命の本質へ至るようにと「欲生」という、これら三心でいきていけるようになることをまずは願っています。
そして、そこで命の本願を思って、「南無量寿仏」「帰命尽十方無碍光如来」と称えるのは、そういう気持ちで生きている証しであるということなんです。(この時点でこれを南無阿弥陀仏には定義できないんです。)
なので「乃至」というたとえば十念でもして、もし命の本源的世界に生きることがなければ悟りを開かないとあるわけです。
こういうことから、第十七願を受けて、全生命の本願を虫に至るまでも受け入れあって生きるという「生命の大讃嘆」を願っているのが、第十八願なんです!
そして「唯除五逆」は、「父、母を殺す、僧侶を殺す、仏身を傷つける、和合を乱す」の五つの悪ですが、これにしても、「誹謗正法」と教えを謗るということにしても、そういう状態のひとが、いのちの本願を生きているとも、互いの本願を認め合うとも思えませんから、除かれてしまうのは必然です。
言い換えると除かれるというよりも、自分から背いているということです。
なので、親鸞さんも大経の下巻にも「回心すれば本願を生きるものになる」と言われています。
至極もっともな話です。
従来からこの「除く」については、空論が多くありますが、単純に自分から本願に乗っていないというだけのことです。
ーーー
ここで、「欲生我国」について、これは、「我が国に生まれんと欲う」とよむことが多いようですが、「我が国に生まれんと欲す」と読めば、「自己が本当に自己の命の本願通りの状態が実現することを欲する」と読めるようです。
なにかと、「往生」といった言葉によって、どこか違うところに行って生まれるという風にとらえられがちですが、あくあでも「往復(往還)」の「往」なんです。
つまり、病院に行って治って帰ってくるといったようなもので、あくまでも「帰ってくるここ」がポイントなんです。
そういう意味で、場所の移動ではなく「次元の移動」と考えていただくとよいと思います。
医者に行くかどうかよりも、治っているかどうかという次元の問題です。
肉体はここにいても、精神は命の本源を見ていくことによって、あらゆるいのちの本願を見聞きして、それらが相互に成り立つ状態を目指して生きるということを「往相還相」をいきるというのでしょう。
現代において「時間はない」という物理学の論があります。
時間はなくて、「エントロピー(カオス状態)が増大していく」というなかにいるために時間があると錯覚しているというものですが、わたしは、この論によって、たしかに「時間」で動いているのではなく「混沌としたエネルギー状態が増大しながら動いている」ということを感じるようになりました。
この混沌として増大するエネルギー状態を「命の本願」という荘厳「構図」におさめていくことができるように生きていくことが「往相還相」を生きるということかもしれません。
そこで第十九願と二十願になるわけですが、これらも「我が国に生まれんと欲す」という文言に収まっていくないようですから、まずは「往生」をどう理解するかという観点からの説明をしました。
ーーー
そこで第十九願です。
これは、親鸞さんにおいては、「念仏一行ではなく、諸行を修行して往生しようとする」という点で、方便とされています。
しかしここには「十方の衆生が菩提心を起こして」ってまずかかれています。「十方衆生」つまり「蜎飛蠕動」にいたるまでの命の本願は「菩提心」つあり「すべての命の本願が互いに成り立つ状態をめざそうとしている」というすばらしいことが願われています。
そのうえで、もろもろの功徳を修して至心(まごころをもって)発願して、命の本源の世界に至ろうと欲するという願いになっていて、どんな命でもその命が寿命を終えるときに大衆と囲んでその人の前に現れるんだと願われているわけです。
いわゆる「来迎」ということですが、そういういのちのまえに現れるという解釈がされますが、ここを読む限りにおいて、大衆とともにみんなで囲うとあるだけですから、来迎が願われていて、即得往生ではないといって方便扱いするのはどうかと思います。
ましてやここには、仏教において重要な「菩提心」ということが書かれています。
この第十九願も、親鸞さんの解釈を置いといて、「仏説無量寿経」として読めば、いわゆる悟りを求める心である菩提心を起こして、命の本源に至りたいという願いによって、功徳を積んで「まごころから発願して」いるいのちについて書かれているので、このように願う命を「単に方便にのっかっている命」でこのあと二十願に転じて、最終的に第十八願に来るというプロセスのイチステージという論はいかがなものかと思うのです。
ただ、親鸞さんの場合には「華厳経の一即一切行」という思想があるので、第十八願の自己の本願に目覚めてそれに向かって進むという中にすべてが含まっているという論拠があるから、この辺を遠回りの方便と考えたのでしょう。
しかし、この第十九願の中にある、純粋な菩提心という願いのもとで功徳を積もうとか、「まごころで発願する」といったいのちのありかたもすばらしいものといわざるを得ません。
〈オマケ〉
とにかく、日本の浄土教は、浄土三部経をひとまとめで初めて完結するという学問の姿勢がありますが、これは、間違いといわざるを得ないでしょう。
そもそもこの三部経は、別々で発生しており、観無量寿経は中国撰述(道綽創作説)であるわけですし、浄土論はあくまでも「無量寿経優婆提舎願生偈(むりょうじゅきょううばだいしゃがんしょうげ)」といい、あくまでも「大経」について論じて解説しているのです。
そういう意味で、今回は大経は大経単独での理解をしていっているんです。
ーーー
そこで第二十願になります。
ここも、「十方衆生我が名号を聞いて」ってありますが、ここで十方衆生の後に「十方衆生(が)」といった風に入れなかったのには意味があります。
この我が国の「我」の主語は、あくまでも「各衆生そのもの」だと解釈する方が妥当だいえるからです、
だいたい大経において「名号」が何を指しているのかということが「無量寿仏」つまり「あらゆる命」というしかないんです。
ですから、赤ちゃんが誕生して「我れここにあり」と叫ぶように「我々の命はわが命ここにあり」と叫んでいるんです。
釈尊の「唯我独尊」のようでもあります。
私たちはその自らの命の叫びを自ら聞いて、念(おも)いを我が国にかけて、もろもろの「功徳の本(もと)」を植えるようにして生きることで、至心に心を純粋な命の根源に向けて純粋な命の根源を生きようと欲していくならば、必ず果たし遂げられて、その命は報われていくだろうという内容だと読み込んでいけます。
そうなるとひとやあらゆる命もその相を変化させます。
いわゆる「人相」といった点について、第二十一願には、そういう命の根源という次元を生きるものの「人相」が、三十二大人相という功徳の人相にかわっていくと書かれているのです。
ーーー
つづいて第二十二願ですが、この願は親鸞さんにおいて、「還相回向」をていぎした願になっていますが、じつは、教行証文類の証文類の還相回向部分では、この願文で還相回向を語るには無理があるため、まず、「浄土論の文」をさきにだして、そちらから定義されています。
ここには、論註の五果門の第五門の薗林遊戯地門をまず出されてから、この願文をだされています。
それは、この第二十二願だけでは、還相回向を定義できないからです。
さて、この二十二願がどうして「還相回向なのか」ということですが、文中の「その本願の自在の所化、衆生のための故に、弘誓の鎧を被て~諸仏の国に遊んで、菩薩の行を修し~恒沙無量の衆生を開化して~常倫を超出し~普賢の徳を修習せん」という部分をつないでいくと、
「それぞれが命の本願によって、衆生のために自在に自らの命の弘誓の鎧に守られながら、いろいろな命の世界(諸仏の国)に遊ぶがごとくに菩薩の行を行って教化して、恒沙無量の衆生のいのちの願いを開化して、常識にとらわれずに、普賢菩薩の徳を修めることができるんです」っていうことになります。
これが、浄土論の五果門の薗林遊戯地門に符合するんです。
ただこの二十二願の前半に「他方仏土の諸菩薩衆が、わが国に来て一生補処に至らん」ってあるんです。
つまり、いろんな命が「法蔵菩薩の世界に来て、その命の本願に目覚めて、不退転に至る(一生補処)」ということが、まず前提になっているんです。
なので、この「法蔵菩薩道」を歩んで「自己の命の本願に気づいたもの」の在り方として説かれています。
とはいえ、ここで「わが国に来て」って書いているから「死んでから浄土に行って、そのうえで帰ってくるってことです。」というようなあほな解釈がまかり通っているので、還相回向は死んでからの話っていうひとが西本願寺には多いんです。
この願いは、死後であるとかないとかではなく、あなたが自らの命の本願に目覚めて、教化をしようと思っていれば、遊ぶように教化をやっているよ!
っていうように読むほうが、的確だといえるんです。
ーーー
〈オマケ〉
ここで、鎌倉時代の親鸞さんの少し後に「一遍さん」という念仏行者がいたことに触れときます。
年代は1239年~1289年なので、前半期が親鸞さんの後半期にかぶってはいます。
この人は「時宗」の開祖になっていますが、これは、観経疏(善導)の「道俗時衆等、各発無上心~」の「時衆」が、江戸時代以後に「時宗」に替えられたものであるといいます。
つまり、もともと「宗派名」ではなく、「時の衆生などとともに念仏する」という意味だということです。
また、日常が「臨終時」だと思って念仏するという意味をも含むといいます。
これらは「往生礼讃」にもありますから、お西の僧侶は親しんでいる文言です。
そして、一遍さんも華厳経の影響が強く「念仏の一行にすべての行がおさまっている」と説きます。
そしてその念仏以外に一切必要なものはないとして、「あらゆるものを捨ててこそ得る」として、自分が書いた書物も焼き払ったといいます。
そして、念仏は「修行」ではなく、「遊行」(ゆぎょう)だといっています。
このへんが、この第二十二願の「諸仏の国に遊んで~」というところからもきていて、親鸞さんにつうじる部分です。
しかし、一遍さんは、親鸞さんではなく、浄土宗西山派で学ばれています。
これは、一遍さんのお父さんが浄土宗西山派の開祖証空という人に師事をしていたからだといわれています。
西山派は開祖の証空という人が「学問に優れていた」といわれています。
(いまの西山はどうかわかりません)
ですから、浄土論なんかも、かなり論じられ教えられていたようですから、「浄土論」に「薗林遊戯地門」が定義されているのですから、文句なしに「遊行」(ゆぎょう)なんです。
これは、「遊ぶように教化が楽しくてどんどん積極的に自由自在に教化する」といった意味なんです。
あらゆる命がその本願に生きるようになっていき、互いにその命の光を輝かせながら生きることほど楽しいことはありません。
しかし、本願寺派は、とにかく「薗林遊戯地門」は死んでからという理解をしたがるので、遊行ともいいません。
また、「今が臨終」という解釈よりも「もういつどうなっても浄土に生まれる身だから念仏を行じる」という感覚もありません。
阿弥陀様と(ご先祖である)還相回向の菩薩様が勝手になんとかしてくれちゃってるのでとにかく「おおきに、おおきに」と感謝してればいいねん。
という解釈なんです。
ここで概して「ご先祖や亡くなった方」が還相回向されると言うことをよく言いますが、これはこれで仏教ではありません。
教えもなにも知らずとも、寺なんか不要だ!と生前に主張していようとも、謗法していようとも、どんな人でも還相回向の菩薩様になってしまう(笑)
また、往生して「成仏」すると言いながら「菩薩」になると言ってる…
もう矛盾だらけで意味不明な葬式したい坊主の集まりになってしまっています。
この原因のひとつとして、蓮如さんが「もう平生に浄土往生の業(すべき行い)は終わってるので、いつ死んでも浄土にいける」っていう「平生業成(へいぜいごうじょう)」を説いているので、そうなっても仕方がないんですが、これは「蓮如由来」であることを明確にしておく必要があります。
しかし「なにもしなくて良い」とはいっていません。
蓮如さんは、とにかく「信心を取れ」ということに集約されています。
しかし、お西のいまの布教って、結果「何もしなくていい教」最終的には「教えを知らなくてもなんとかしてもらえちゃうでしょう教」になっています。
修行も遊行もなく、「そのまんまでいい行」を生きていればいいってことを説いて回っているんです。
そりゃ、あほらしくて話になりません。
なので、「お話の意味が分かりません」っていっても。「わからないのがいいんです」という意味不明なことを平気でおっしゃるんです。
→[命の存在について]https://namas45.com/info/4703652
ーーー
第二十三願に移ります。
ここで諸仏を供養する神力が、命の本源である「仏力」によって行われえることを書かれていますが、それが、「一食の間」に「無数無量那由他の諸仏の国に至る」って、おもしろい表現だと思いませんか。
けれど、このような表現をおもしろいって言っている私なんかは、「食」の貴重さを忘れているんです。
「一食」のなかにある命を生かす功徳を「一食」から感じ取っていくことが、あらゆる命の根源を大切にすることであるということでしょう。
命の根源を大切にすることが、あらゆる命を供養することにもつながっていくわけです。
そういう点でこの「一食の間」というのを、それほどの短い時間でという理解をしてしまうとここに内在されている大きな意味を見落としていくことになるでしょう。
そして、第二十四願には、さまざまな命(諸仏)の前にありて「功徳の本」を現らかにして、それらのいのちが欲求する供養の具(もの)を意のままにそろえることができるっていうことが書かれています。
なんだかこれだと煩悩の欲望を満たすように思ってしまう人もいるかもしれませんが、いのちは欲求によって成り立っていて、仏陀はその欲求までも否定しているのではありません。
それどころか、純粋な命の根源をいきる命への供養は、自然に整えられるといわざるを得ません。
最澄さんが、「道心のあるところに衣食あり」と書かれていますが、これは全く不思議にそのように思うのです。
私は、お金もちでも、僧侶以外にとくにこれという仕事を持っているわけでもありませんが、М君がそうであるように、この道を生きているこのいのちを支えようとしてくれる命があるんです。
この命が「中神章生」という俗名を生きつつも、「法を生きる」つまりは「中神章生」の命の本願をいきることによって、自ずと整うものが最低限度であってもそろうのです。
そろえてあげよう。供養してあげよう。というМくんのように、あらゆる命が動き出していくのでしょう。
そして、この中神章生も同じように供養すべきところに、その命(ひとなど)が私にもとめるところの欲求を満たすことができるのです。
資源がなければ道を生きられないのではなく、道を生きるところに資源が必要なだけ集まってくるのでしょう。
「掃くほどに風がもちける落ち葉かな」って良寛さんだったかなぁ…
そういうものなのです。
ーーー
第二十五願ですが、国中の菩薩が一切智を述べ伝えるといった意味です。
しかしこれが、そう簡単ではないのは、「一切智はすべてを知ることができない」という前提があることです。
くりかえしますが、「一切は一切れ」でしかなく、「自己が認識しうるもののすべて」であって、認識できない物事は認識できないのです。
仏陀つまり悟ったものは「無学」といって「学ぶ物事がなくなった状態」にあるひとをいいますが、そういうことは、どんなすぐれた人であっても無理なのです。
だから、仏教で「智慧」というのは、「一切の認識できない物事にもつうじる法則」を認知できるかどうかということなんです。
それが、「無常、無我、空、唯識」といった智慧になるわけですが、この根本仏教の基本的智慧から「華厳経の一即一切」という智慧に至って、「命の本願が一切から一として生まれてくる」という智慧が、「無量寿経の命の本願」ということなんです。
そういうことですから、みなさんが、自分の命の本願に嘘をつかないで、世間だの常識だのといったところでつぶされてしまうことがないように、一人一人が自分のいのちの本願を見極められるように延べ伝えていくことが、ここに書かれている一切智慧ということになるのです。
そして、その命の本願に生きるようになる。
すくなくとも自分の深い願いに嘘をついたり、世間や常識といわれるような物事に振り回されずに生きられるようになると、「金剛那羅延身」を得ると書かれているのが、〈第二十六願〉です。
肝心なことには、迎合や振り回されず、自己の本願を見失わずに生きていく身になるということなんです。
ーーー
第二十七願には、命の根源に素直に生きているものには、一切の万物が「厳かに浄らかに、光麗しく、形や色もそれぞれが独特で、窮微(極めて微細に至るまで)極めて「妙(すぐれている)」に見えるうえ、それについて、「量ること」がないっていうほど、こだわりや自己都合であらゆる物事を見ることはないっていうことが記述されています。
そして「天眼」うぃ得て、「名前と数を弁えることがあってはいけない」ということが「どんな命でも全て」という意味を内在しているようです。
これらは第三願〜第九願に記述されている内容をまとめているともいえますが、
ここまでで、〈国中の人天〉と〈国中の菩薩〉という表現が頻出していますが、これは「法蔵菩薩道」を歩む命と、そうではない命を区別していると思われます。
そこでこの第二十七願に「人天」とありますが、法蔵菩薩道を歩んでいないものにもそんなふうに見えるようになるのか?
という問いが出てきます。
結果これは、宇宙を見ている主体である「私」の見方が変わるからそうなるということであり、互いにそういうふうに見えているという願いの関係で関わるのと、「菩薩道を生きている自己だけがそう見える」というスタンスで関わるのでは、現実が大きく変わってくるんです。
また、私は各「願」に記述されている。
という書き方をしていますが、これは、各「願」にそう願われています。
というふうに書くと、願う主体が別にあるように無意識な認識が起こるという懸念の元、
願うのはあくまでも「この私の命と一切の命」ですから、ひとごとのような書き方をしないという配慮からです。
ーーー
第二十八願に移ります。
この願いはまたおもしろくって、「国中の菩薩」(乃至)「少功徳のもの」っていう配慮がされてるんです。
その「少功徳のもの」でも、道を歩むものだから、「道場」っていう表現が使われていて、その道場の「樹」が四百万里っていう、無茶苦茶高い樹で、無量の光と色(色はそれぞれの個を意味している)で照らすから「知見することができる」っていう意味の願いになっています。
これは、私やMくんが、たとえどんだけ少功徳でも、この法蔵菩薩道を歩むことで、そういう知見を得ることができるってことです。
なので、この人間界っていう道場で「菩薩道」を歩むことが、知見を得る道だって記述されているんです。
そして、この菩薩道を歩むものは、「経法を受読して諷誦持説するから、弁才智慧を得る」っていうふうに、経法を「説くことや伝えること、理解することができる智慧を持つ」っていうことが記述されています。
私たちは、日常的に「道を歩む」と決めたら、そういう本をとにかく身の回りに置いたり(積読)、そういう場所(お寺など)に行ったり、こういう文章を読んだり、日常会話で話題にするといったことで、「習うより慣れろ」で、「馴染むこと」ができるんです。
本があれば積んで置いても「ふとあるページだけでも読む」といったことが起こって来ます。
こういう文章でも、何回も読んでみたりします。
そういった「馴染むこと」こそが重要です。
馴染めば「自分の身になるので、弁説もできるようになるし、さらに深く理解や掘り下げることができるようになるんです。
だから〈第三十願〉に「智慧弁才」が限量できないほど深まっていくということを記述されているのでしょう。
学ぶというより馴染むことで、日常になりますから、果てしなく深まっていくんです。
ちょっとここで勘違いをして欲しくないのは、日常会話なんかで「仏教の話」をすることもそうですが、
実際に「仏道を歩むことで見えてきたこと」なんかで会話にするんです。
「最近〇〇さんを見てると、〇〇な点ですごく学ばせてもらってるねん」といった具合です。
馴染む中で学んだこと、深まってることを話していくんです。
これが「弁才」ってことなんですから…
ーーー
第三十一願に移ります。
ここには。「国土清浄」「十方諸仏世界を見る」「明鏡止水」といったことが書かれています。
ここで、この3つのポイントに通じるのは、「一切の人や場所」が、悟りの心境を表す「明鏡止水」のように、清らかな鏡に例えられています。
もともと仏教の禅宗などにおいて、悟りは「大円鏡智」っていわれます。
きれいで曇りがない「鏡」がすべてをありのままに映すように、悟りの心には、すべてがありのままの命の輝きを映されるっていうことなんです。
なので、命の本願を生きていると、あらゆる命と場所が清らかに見えるようになるという内容がここに記述されています。
第三十二願は’、長いですけど、第三十一願を具体的に言ってるということですから、そういう風な見え方なんだなぁと思えばいいんですけど、具体的ではあるけれど「非現実的」で、現代の日本人の感覚からどういう風に観察していけばいいかっていう、補助的な内容だと思えばいいと思います。
仏教、特に浄土教は、こういう非現実的な比喩が多いので、意味不明になっていきます。
また、浄土論では、こういう内容を「瞑想」によってみえるようにする。
という「唯識的な観点」から「観察門」という解釈がされるので、これも「難解」になっているんです。
しかし、浄土論で言わんとするところは、「無碍光如来」という智慧光が仏の智慧をもたらすのだから、「帰命尽十方無碍光如来」と「讃嘆(弁説)」していくことが凡夫が法蔵菩薩道を生きてさとりに入る道であるということに集約されるんです。
だから親鸞さんは、「行は無碍光如来のみ名を称する」と明確にされているんです。
そしてこの「無碍光如来に触れたもの」が「柔軟な心を持つ」といったことが、次の第三十三願に記述されていくんです。
ーーー
上記のように、第三十三願は、上記のように「そもそも命が光明をはなっていることを見せ、そのことを明らかにする智慧の光明」を蒙って触れると、「柔軟な身心」をもてるようになるっていうことが記述されています。
私たちは普段「ある思考やある場所」などの定点にこだわってしまいがちです。
というか、かなりこだわってるとおもうけれど、こうやっていろんな命の願いを見聞きすると、いろんな学びがあり、その学びが身につくことで、だんだんと「柔軟な人」になっていけるんですが、おおくの人間は自分の殻に閉じこもってしまうので柔軟になれず、押しつけがましくなったり、うまくコミュニケーションが取れなかったり、なんなら喧嘩別れしてしまったりするものです。
私は、カウンセリングをして人の悩みを聞くことが多いんですけど、外見やそのひとの言葉からは普通にはわからない背景を抱えている人って、結構多いです。
なぜこのひとはこうなんだろうと相手を見たり、相手の行動をよく知っている周辺の人から聞くことでは想像もつかないような背景を抱えている人って、たぶん全生命がそうなんじゃないかっていうぐらい、たくさんいます。
なんで「この命はこうなんだろう」という背景をしったり、学ぶことで、いろんな見方ができるようになるんです。
《つまりこの人やこの命が「とある状態にある理由」をより多くの可能性をもって考えられるようになる》のです。
こういう私になることで「柔軟になっていける」ってことなんです。
ーーー
第三十四願のポイントとして、「わが名字を聞きて」ってありますが、無量寿経における名字は「法蔵菩薩」であり、「無量寿仏」ということになり、ほかの名字は考えられません。
特に「設我得仏~不取正覚」の誓いがありますから、この法蔵菩薩の名前を聞いて「さとりの功徳である〈無生法忍→生まれるとか死ぬというとらわれを離れる〉」また「深い総持(忘れることがない)」をえることができるって書いています。
これも、利他を行じる中で、大切なこととして記述されていますが、あまり深く考えなくてもいい部分かと思います。
さて、この次の第三十五願は、「女人が法蔵菩薩の名前を聞いて、「喜んで受け入れ、菩提心を発して、女身であることを嫌い、その人が、命が終わって、「女像」となることはないっていう意味のことが記述されてるのですが、これは、「男尊女卑」の考え方に由来するというよりも、昔は事実女性は大変でした。
なにがって、まずは「毎月の生理」なんか大変だったので、日本なんかでは「生理中の女性は小屋に閉じ込めれれたりといったこともあった」と聞きます。
もちろん「妊娠出産」なんかもたいへんですし、女性であることの「身体的側面」について記述されているので、「女身、女像」という翻訳がされているのでしょう。
ーーー
なんか書く気がしない‼️
書いていて、真宗の仏教がこのように理解されてればいいけれど、じつは「合言葉付き」で私が書いている内容は、ほぼお西では理解されていない。
もともとお東の教学であったけれど、「お東」でももはや理解している人は少ないだろう。
また、こういう風に生きてきたつもりだけど、「セクト」に阻まれて、「異端者」だの、僧侶としてこう言った話をしてもほとんど理解されないし、実行されないから、無意味に思えてくる。
こうやって「Mくん」に向けて書いていて、Mくんは頑張っているけれど、それはMくんが私をよく知っているからであり、だからMくんから、「自分に向けて書いて欲しい」ってことで書いてるけど、「他の人からも合言葉を知りたい」って言われたりするけど、「アンタさんマジで学びたいなら、実行してや‼️」って思うけど、なんかそういう人って少ないんですよ‼️
知識として知りたい人っていう「カルチャーイメージ」なので…
だから、Mくんに直接話せばいいかって思うし、けどMくんが残るようにとプリントアウトしてるようなんで、書かなきゃいけんねって今、また思い始めました。
また、ボチボチ書き始めますね。
ーーー
第三十六願になると、「十方無量不可思議の諸仏世界の諸菩薩衆(ここが三十七願では諸天人民ってなる)が、「わが名字を聞いて」っていうのは、「命」そのものの名つまりは、命の根源から出たわが命の名を聞いて、やがてその名字の「寿(時間的な意味での寿)」が終わってのちも「命の根源である《命根》はありつづける」ので、見た目や姿の命が終わったように見えていても、命根が清らかな行を続けていくんです。
ってことがかいてあるんです。
この「命根」ということは、倶舎論に明確記されている「命の根源」です。
つまり「清らかな命の根源の永遠性をあらわしている」ようです。
なので、いちおう「いのち(寿)がある間」を「諸菩薩衆」(現に行じているもの)にしてあるのだと考えられます。
ですからつぎの〈第三十七願〉には「諸天人民」になっていて、その諸天人民が、「五体投地」などの「礼拝」について記述されています。
「礼拝」は、仏教では「屈服定義」ですから、「自我我執」を滅する意味を持っているんです。
そういう意味で、十方無量不可思議のとにかくあっちこっちのいのちは、その名字に屈服礼拝して、菩薩の行を行じるのですから、この者たちも第三十六願の「諸菩薩衆と同じだ」といいたいんだと思われますす。
まぁこの辺はどうでもいいように思いますが、こんな感じでくどいのが大乗仏教にありがちなパターンなんです。
なので、学ぶ方はめんどくさいかんじになるんです。
よほど、初期仏教や倶舎論なんかの方がスッキリあっさりしています。お釈迦さんって意外にドライですし…
さて、つぎの〈第三十八願〉になると、「国中の人天の衣服」について書かれています。
衣服は自由に得られるし、裁縫をしたり、色を染めたり、洗濯したりしなくていい、って書かれています。
これは、釈尊の「糞掃衣」から出ているので、「糞を掃除するほどのボロぎれ」ですから、そのままが書かれています。
私たちは、アダムとイブも「葉っぱを付けた」ように、一般的には全くの素っ裸で過ごすということはありません。
かといって「ぜいたく品」に流れることがないように、裁縫がいらない、色を染めない、洗濯もしない、といった記述になっているのでしょう。
ーーー
つづいて、〈第三十九願〉になります。
ここに、本願に生きる法蔵菩薩道の行者は、「煩悩が[漏れ出る]凡人とは違って」『悟りの快楽』を得る。
って結構な誤解を招きそうな内容が記述されています。
ここで「快楽」は「けらく」と読みますが、日本仏教によくあるように、読み方を変えることで、一般的な意味ではないことを表していますから、ここの快楽は一般でいう快楽とは全く違っているんです。
ここでの快楽は、「命の願いを素直に生きるところに生まれる歓喜のこと」をいいます。
自らの命がなぜあるかという意味において、あなたも私もそれぞれの存在理由があるんです。
そして、世間や常識にとらわれて、命の願いを封じ込めるのではなく、願いの通りに生きているときには、喜びは付属するものです。
なので、「自己満足や自己完結」「他者との比較」などにおいて得ているような「罪悪感バリバリ」の喜びではないんです。
この自然な快楽を得られていることが、「本願に生きている証し」でもあるといえるでしょう。
そして、第四十願です。
ここで、ここまでの願いから、自己の意思にしたがって(随意)いろんな命の願いを見ることや聞くことができる。ということや「宝樹」の中で皆ことごとく、光明に照らして見る(照見)ことが、まるで鏡に映して見ているように鮮明である。といったことが記述されています。
ここに「宝樹」ってあるのは、釈迦が「菩提樹」の元で悟りを開いたことに由来していて、明鏡止水といわれる悟りを表す表現が使われています。
私たちの命が、互いに「その命がある理由」を問うことができるようになれば、その状態はより、真の極楽浄土になっていくということなのです。