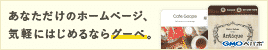教行証文類(全)前半正信偈まで。
このたびご依頼を受けて「教行証文類講義」を書いていくようにいたします。
今後はこの部分をメインに?書き進めて参ります。
テキストとしては、西本願寺の本願寺出版社から出ている
【浄土真宗聖典(註釈版)】を使います。
(カバーがグリーンのものもあります)
『注意』七祖編ではありません。
amazonでも買えます。
註釈版(写真左)を見ながら読んでください。
また、
【現代語訳】(写真右)を並行して、用いることにします。
【現代語訳】を使う場合は、その旨を表記します。
基本的に【註釈版】を用います。
更新日を同じようにつけます。
《補足項目》は《補足のタブ》をご覧ください!
よろしくお願いいたします🤲
とりあえず、「かなめの部分」をお話しして参ります。
ーーーーーーーーー(以下講義)⏬
◯教行証文類講義▶️(スタート)
1、教文類
とりあえず総序は置いておきます。
まずは「教文類」からはじめます。
冒頭【1】に【往相と還相(おうそう、げんそう)】の回向(えこう)がある。
と書いておられます。
これは「いく、かえる」「相」は”すがた”を表わします。
どこへいくのか。
浄土といえば、そのままですね。
もう一歩踏みこみましょう。
いのちが「さとり」へ向かうという「方向」が定まり、
その方向と「誘導するムーブメント(力)」があるという点を【回向】という言葉で定義されています。
わたしをさとりに向かわせる「方向」と「力」といいたいのですが、
力というより「はたらき(用)」という方がフィットしますが、
現代の方に馴染まないかと「ムーブメント」と解説しました。
そして往相還相は、異時か同時かという議論がありますが、
これは時間論とも関係があって煩雑になりますが、ザクッと「同時」と結論のみ申し上げておきます。
「一つには二つには」とあるので、時間軸は異時とする方がわかりよいのですが、
教行証文類を読み進めると「同時」とわかります。
【2】に真実の教えは「大無量寿経」と定義されますが、これは実は大きなポイントです。
なぜなら、法然上人は「観経」とされているのを覆すからです。
ここで阿弥陀の「誓い」と「法蔵を開く」と「選んで功徳の宝」を施するとあって、
《さとりの法蔵》を「道教」「真実の利」のことと定義されます。
そして「如来の本願を説く」を経の宗致として「仏の名号を経の体とする」といういったんの結論を書かれています。
なお、このようにわたしが「カギカッコで」抜き出した言葉には理由がありますので、ポイントだとご理解ください。
つまり、わたしが歩む「道=教え」は「誓いと法蔵」であり、それが「選ばれた功徳の宝」であり、「真実の利」だと明言されています。
この論を逆転させると「真実の利」は「功徳の宝」それは「法蔵」となります。
この場合の「誓い」は「設我得仏〜不取正覚」の部分を指し、「法蔵」は脚注には”法門の蔵”とありますが、それこそが法蔵菩薩であって、この道を進むことが「功徳の宝」ということをあらわします。
ここで「法蔵」をなぜ「法蔵菩薩」と読むのか?
これは論理の基本ですが、「ほかの表現も可能なのに”あえて用いる”表現」には理由があるということです。
これは「演繹推論学」の基本です。
また「大経の法蔵菩薩」が大経自体を通じて「法門を開く」とも読めますが、
いずれも「法蔵菩薩」に定義されます。
そしてその「功徳の宝」は、大経に表わされている「如来の本願」であり、その集約が「名号」だと書かれています。
これを「宗と体」に定義されるのです。
ここまでをまとめますと、
「わたしたちにとっての真実の利」は
「法蔵菩薩の誓いを生きること」で、
「その根拠は本願であり、このさとりへの道を名号(必ずしも六字のみではない)に集約してある。」
と読んでいきます。
つづいて、どうしてこの《大経》を、釈尊の一番説きたかった教え《出世の大事》とするのかという理由を書き進めて行かれます。
【3】に「大無量寿経」をあげて【今日世尊云々】と、いわゆる《五徳瑞相》について」記述されます。
この「瑞相」という言葉は、「天から与えられる《めでたいしるし》」という意味があります。
この中の「光顔巍々」という「讃仏偈」にもある表現ですが、「鏡の浄き影、表裏に暢るがごとし」という「ガラスが透き通ったような”透明感”」というポイントが「仏教全般にわたりさとりをあらわす【大円鏡智】をあらわしている」ようです。
そして「光」。
また136ページの5行目に「今日釈尊が如来の徳を行じたまえり。」とあって、
「去、来、現」という”仏教の時間論”の順に流れが表されている点、しかしそれが
「過、未、現」ではなく、「去る、来る、現れる」という表現にされているのは「如去、如来、現在する如来」をあらわしています。
ですから、ここで「いまの仏も諸仏を念じる」という表現に続きます。
これはつまり、今から説く教説は「如去、如来、現在する如来」すべてと通じ合って説かれる「教説」であると明言されて、時空を包み込んだ「all」な教えであることを「出世本懐」と定義されます。
また136ページの7行目の「威神の光」などのように「光顔巍々」と同じく、「光」があらゆるポイントで記述されることを「真仏土文類」で、「智慧」を意味していることが明確になります。
そして、そもそも弟子の「阿難」が「五徳瑞相に言及したこと」が「諸天に教えられたのか、自分の慧見なのか」と釈尊に問われて「自らの所見です」とこたえたことに、
釈尊が「問えるところははなはだ快し、深き智慧云々」「衆生を愍念せんとして云々」と「智慧と慈悲によって釈尊を含めた全ての如来が世に出興した理由」は「恵に真実の利をもって拯う」ためだと、「だれかの意見ではなく、自らの「智慧」ということが重要であると”サジェッション”されています。
ここで重要なのは、【すべての】如来出世の理由は「智慧と慈悲」によって衆生を「真実の利(さとり)」へ拯うためであると定義されています。
続いて、「このようなことは無量億劫に値ひがたい」ことであって、「多くの諸天人民を開化」することであると、これこそ大乗の極みという”意味づけ”を表現されます。
そして【3】結びに「如来の正覚は智量りがたく「慧見無礙」であり「遏絶(さえぎる)」ものはないと断言されます。
このように大経は、【時空を包み込んだ如来すべての出世本懐】であることを「明確化」されています。
137ページの【4】から。。
そもそも「大経」はサンスクリット語から中国語に翻訳されたものが”5種類”残っています。
これを、以後《異訳本》といいます。
ここからはこの異訳本についての説明です。
まず【無量寿如来会】が出てきます。
内容的にはほぼ同じなのですが、
【4】の4行目に「微妙の弁才を観察して。。」とあって、次の行に、
「大悲に安住して」とあり、7行目には「有情」を「利楽」せんがため。。。
ここにまず「観察」とあり、「大悲に安住して群生を。。」とあります。
いくら釈尊の弟子であるとは言え「観察」と言うことが、仏道において重要ポイントであることが示されています。
またこれは大経にも「群萌」とあるように、ここには「群青」と言う言葉が使われていますが、
さとりに至らない迷界のものは群れて生きることで、安住を感じようとする。
誤った安楽を求めていることをこの言葉は示しているように思います。
また、掬いの対象を「有情」とされています。
この言葉は「心のあるもの」を強く意味することばで、衆生以上に限定的な表現になっています。
これは衆生と言う対象をさらに絞った内容になっていると考えられます。
そういう点で「人間」を強く意識した内容であると考えられます。
このように群生している人間に「利楽(本当の安楽安住)」を与えるために、「如来に如是の義を問いたてまつれり」と示されて結ばれます。
ここでも「如来」とだけ記述されています。
またこの5行目にも、「なんぢ一切如来、応、正等覚」とあり、「阿弥陀や釈迦」と言う文言は一切出てきません。
【5】の異訳本「平等覚経」
この内容も「優曇樹」の話など、「大経にも霊瑞華」「如来会にも優曇華」などにたとえられる表現がさらに強調されます。
興味深いのは、4行目に「いまわれ仏になりて天下に出でたり」の文言は、「われ」が誰をさすのか。
もしこれが釈尊なら「仏になりて天下にでる」という文言は、釈尊は本来仏の「如来」であると言うことになります。
また138ページの1行目の「仏返にありて仏に侍へたてまつるなり。」
と、最後の「よく聴き、あきらかに聴け」は、まるで私たちに言われているかのようです。
教文類の最後の引文【6】は、今まで明らかにしてきたこと「五徳瑞相について」まとめられています。
この引文の重要ポイントは、【6】の7行目に「仏性不空」とこれら一切の根拠を「仏性」と「仏性は真の常住である」という「仏教としての根拠」を示され明確にされている点です。
【7】の御自釈においても、如来興世の正説。。。とあって、
じつは「教文類は、釈尊の出世本懐と言う以上に、すべての如来の本懐と言うことが明らかにされている」とわかります。
そして、この「大無量寿経」の教えが「一乗究竟の極説」(これ一つがすべてをさとらせる極みの教えである)などと結論づけられます。
https://r.goope.jp/sainenji/free/hodoku
の3と重要をご覧ください。⬇️
2、行文類⬇️
つづいて、行文類に入ります。
140ページに標挙(ひょうこ)として、
諸仏称名の願と第十七願が挙げられます。
いわば、この「諸仏称名」が結論でもあります。
そしてその下に、「浄土真実の行」と「選択本願の行」とあって、
脚注がありますが、この脚注はいったんおいといてください。
ここでは「浄土真実の行は諸仏称名」そしてそれが
私の称名になるという意味での「選択本願の行」と理解してください。
141ページの【1】の御自釈に「往相の回向に「大行と大信」がある」と記述されますが、
これは、「行と信」の両方について「行文類」にあかすという意味です。
そして、「大行は無礙光如来の名を称する」ことであると定義されます。
ここで学派によってこれは、諸仏や私に称名させている「名号」であると
定義する学派もありますが、そもそもここまでの段階で「南无阿弥陀仏」や
「阿弥陀如来」という文言すら出ていません。
また「大経」にすら「名号」は南无阿弥陀仏であるという定義はないのですから、
ここでこの行を「法体名号の南无阿弥陀仏のことである」とするのには無理があります。
ここは素直に「大経」にもあり、あとで出てくる「浄土論」に基づく、
讃嘆名の「無礙光如来の名を称する」と定義すべきでしょう。
そして、この行には色々な功徳があって、即時に功徳が円満すると述べられますが、
その功徳の根本は「真如一実の功徳宝海」であると記述されている、このポイントが
「法性を根拠とする」という意味をあらわしている重要な部分です。
(ここも脚注はおいといてください)
法性が根拠であるから「ゆえに大行と名づく」といえるのです。
つづいて、大経の第十七願をさまざまな名称で「名づく」とされますが、
「諸仏咨嗟の願」までは、「諸仏による讃嘆」であり、いきなり「往相回向の願」
とあって、「選択称名の願」とある点が大きなターニングポイントです。
つまり、諸仏の称名が”私の称名讃嘆”になって、”私の往相”になるというように、
《称名の意味づけ》が変化転換しているからです。
【2】からは、諸仏の称名や讃嘆の引文により、諸仏の称名行が私の称名讃嘆の行に
転換して、私が真如に至るまでの法の流れを解明されていきます。
【補足5】をご参照ください。
2、行文類
行文類の前段の引文を「ザクッと」いえば、
まず【2】から【8】までは
《諸仏の讃嘆》
【9】から【11】までは異訳の二十四願経によって
《諸仏讃嘆を聞いた衆生の讃嘆》を明かすという流れになっています。
なお、【10】には、この法を聞いて「信慧」あって聞見して精進し、この法を聞いて忘れず、見て敬い得て大いに喜べばこの者は「わが良き親厚(親友)」である。
と示されていて、「聞見」するものは、信慧に触れ、法蔵菩薩の親友だと記述されています。
そしてこのように「法に生きる」ようになれば「私と法蔵菩薩または如来(法性を根源にした存在全て)」が、真如の智慧によって平等であることがわかる」と明らかにされているといえます。
このことは、「仏説無量寿経(下)」47ページの後ろから3行目にも「善親友」と記述されています。
次に【2】以降のポイントを解説していきます。
【2】ここは「無量寿経」の第十七願文です。
「ことごとく咨嗟して。。」は如来の法を「教え伝えること」(広讃嘆とします)。
「わが名を称せずば。。。」は「称名すること」(略讃嘆とします)。
【3】は、この時点において「主語は真如からの如来」または「無礙光如来」の「名声が十方を超えて聞こえないところはない」とされます。
そしてその「名声」が「宝蔵を開き、その功徳を施す」と記述されて、
「つねに大衆のなかにして、説法獅子吼せん」とあるように、
名声が「三宝の功徳を私たちにあたえるように、獅子が吼えるほどの説法」をしていると、広讃嘆の内容が、「仏法の功徳である」と詳説されます。
【4】以降は、その名声が「諸仏の讃嘆」というかたちで伝わっていくことをあきらかにされます。
名声伝播の具体的なパターンを記述しています。
【6】のなかで「名を聞きて往生せんと欲へば」と「ことごとくかの国に到りて」と「不退転に致る」の「因果が同時」であることを明らかにされます。
【7】に、「如来に対して弘誓を発せり」と記述されています。
これは、「法蔵菩薩の誓い」は如来すべてに対するもので、「無上菩提の因を証す」とあります。
ここに、(証は験)と書かれているのは、「因が実際にあらわれたことを《験》という」という意味です。
つまり法蔵菩薩の弘誓は、すべての如来に対して「菩提の因としてあらわれたものであると証明している」ということです。
ここで、私たちも「法蔵菩薩の弘誓を生きることが菩提の因」になるという読み方が適切であると思われます。
また、ここに《菩提》について明言されているのは、華厳の明恵が法然に向けた「浄土教には菩提心がない」という非難への回答であるとも思えます。
142ページの【7】の後半も重要ポイントですが、「脚注」を参照ください。
このあと【9】に「蜎飛蠕動の類(ケンピネンドウのたぐい)」と昆虫に至るまで「我が名字を聞きて」とあります。
実際問題、昆虫までも「名字を聞きて」ということが成り立つのでしょうか。
じつは「大経」の29ページに「法蔵菩薩は十劫の昔に成仏した」という内容の記述があります。
この記述と「設我得仏。。。不取正覚」の誓いに矛盾があると思えるのですが、大経で言いたかったことは、
「あらゆるものが成仏しないのであれば、わたしは成仏しない」とありながら、十劫の昔に成仏したとあるという表現は、「本来すべてが真如であり、じつはすべてがさとりであるという」ことを表現していると読めます。
つまり、「本来すべて法性の存在であるとみているという」仏の智見をわたしたちが知ることになるのです。
このあと【11】までは同様の記述です。
このあと【12】に御自釈において、称名は無明を破るとあって、じつは「衆生の志願であるさとりへの無明を破るものである。」とあります。
衆生の志願は「成仏である」と衆生の”無自覚”な志願を定義されるのです。
そしてその方法について、称名を正業とされ、それは念仏であり、念仏は「南无阿弥陀仏」であると、ここではじめて、称名は「南无阿弥陀仏」と称えることであると定義されます。
あくまでも「称名」です。
続いて146ページの【13】において、この念仏を「般舟三昧」と「父親」(智慧)にたとえて、「大悲」を母親にたとえて、「ここをもろもろの如来が生まれる源泉」とされます。
つまりはこの十住毘婆沙論の引文で、世間道から出世間道に入り、「初地の歓喜地にに入ること」について「なぜ初地がなぜ歓喜地なのか」という問答があり、147ページの最後から6行目の「諸仏如来の種を増長する」というポイントを明確にされます。
ここからしばらく「歓喜地」の説明をされていかれます。
さて、この次に重要なポイントが出てきます。
151ページの【14】から、「信力増上」とあって「菩薩が初地に入ることで、もろもろの功徳を味はひを得るから「信力転増する」とあり、「信について」話が展開されていくのです。
ーーー以上30/10/29つづきは 2–2 ⬆️
30/10/30[2–2]
151ページ【14】の「信力増上」のところに、
「聞見するところがありて、かならず受けて疑いなければ増上と名づく。」
とあります。
この「増上」は、仏教の基礎的な因果論の原則によれば、「縁」ですから、ここでいう「無疑の増上」は、「縁信心」になります。
その後の問答は重要度の高いものだと判断できるのですが、
「答へていわく〜」
151ページの真ん中辺りに「菩薩が初地に入ると、もろもろの功徳の味わいを得るから《信力転増す》」とあります。
この時点で「因信心」に転じるのです。
これは「菩薩が初地にはいれば」という前提ですから、これ以前に説明されている、
諸仏の讃嘆を受けた衆生が「たどる信心のプロセスと状態」を明らかにしています。
それが「信力によって諸仏の功徳無量深妙」を信受して、「深く大悲を行じる」と、《仏の智慧から慈悲へ》のプロセスと状態という定義がされます。
教行証文類全体も同じ構造です。
【15】に「菩薩の道」の難易について、「水道の乗船」にたとえられて、「信方便の易行」と「縁信心は方便」であって、「因信心」になり「阿惟越致(不退転)」にいたることを明確定義しています。
ここで、信方便の縁信心から「因信心」に至ることで、「初地、不退転」に住するとプロセスを明確にされています。
阿弥陀仏を意味する「無量明」は「照らすところに辺際がなく」名号を聞くものは不退転(初地)を得る。
と記述されて、問答に入ります。
これは、
「なぜ聞名して、《執持して心におけば》不退転を得るのか?」
ここに《心におく》と記述されていることも重要です。
「阿弥陀如来は外に仰ぐものではなく、信によってわたしに内在する”法”」を意味するからです。
そして、
「ほかの仏や菩薩の名ではどうなのか?」
とあって、
答えとして、
「すべての仏菩薩も《阿弥陀仏の本願を憶念》していて、必定に至る」と答えられています。
つまり、不退転に至る根拠を「本願」に定義されるのです。
実際この答えは、答えになってはいません。
「経典」に根拠を求めても「論拠」にはなりません。
しかしこのあたりから、「阿弥陀の経典に内在する、さとりへのシステム」のストーリーに内容が移行していくので、「論拠」より「典拠」が重要になるのです。
そのシステムが、153ページの中ほどに、「心に阿弥陀を念じれば。。」とあり、最後から5行目に「信心清浄なるもの。。」は「仏を見て、その功徳を嘆じる」とあって、「われいま帰命礼したてまつる。。」とあるなかにも内在します。
それは、この「帰命礼」ということは「自我の放棄(五体投地)」が基本ですから、事実上この時点で「わたしの我が破我され」ただ「無量の徳を称讃するもの」になると「アミダシステム」による「破我の構造」が明確にされているからです。
30/10/31[2–3]
154ページ【16】から、「浄土論」「論註」に入ります。
親鸞はこの2つを「典拠」以上の「根拠」にされています。
まず「修多羅真実功徳相によりて〜仏教と相応せり」と書かれていて「浄土の教えが根本仏教に相応している」と記述されています。
これは、浄土の教えの本質が、ファンタジーではなく仏教の本質的な教えと同じであることを述べられていると考えられます。
【17】では《五念五果門》によって、自利利他が完全に成就することを述べられています。
そしてこれによって、阿耨多羅三藐三菩提という完全なさとりを得られると言う結論を述べられています。
【18】に論註を引いて、【15】に引用されている「十住毘婆沙論」の内容をそのまま記述されます。
その中155ページの4行目に「信仏の因縁」という記述がありますが、これも「信心の縁因」をあらわされているとみてよいでしょう。
155ページの中ほどに、「無量寿経優婆提舎」(浄土論)について、この浄土論は「上衍極致。。。」と無量寿経を説き明かした最高の論述であると定義されます。
そして、「十住毘婆沙論」の「易行」によって得られる「浄土往生」「大乗正定」をより具体的に記述されます。
つまり、具体的には釈迦仏が王舎城などにおいて「安楽浄土の無量寿仏の荘厳功徳」を説かれた無量寿経が龍樹菩薩のいう「易行」であると定義されるのです。
重要なのは、ここで「無量寿仏」は如来の「別号」であると定義して、「名号を経の体とする」とあることです。
「仏」は「如来」の別号。
「無量寿仏」は「無碍光如来」の別号だといっていて、曇鸞は「無量寿仏」の名号は「無碍光如来」であると定義します。
ただし、親鸞は146ページの【12】に称名を「南无阿弥陀仏」だと、転がして定義しています。
しかし、あくまでも「称名」であり、「名号が南无阿弥陀仏」という定義ではないのですが。。
そういう点で、親鸞は「曇鸞」に根拠を求めて、善導の「念仏」つまりは尊敬してやまない「法然」につながるように論じているという感は否めません。
しかしこれが、教文類の親鸞の記述の根拠であるといってよいでしょう。(135ページの【2】)
名号は「帰命尽十方無碍光如来」であり「南无阿弥陀仏」である。
もちろんサンスクリット原典上、どちらでも同じなのですが。。
結果、逆転して「南无阿弥陀仏」は「帰命尽十方無碍光如来」であるといい、
「光明」というポイントで、親鸞は抑えています。
このことは「真仏土文類」で明確になります。
だから、この”帰命尽十方無碍光如来”という抑えの流れで、天親菩薩が無量寿経の「教を服膺(服用と同じ意味合い)」して「無量寿経」にそえて「願生偈(浄土論)」を作ったのだといういきさつを註釈されています。
155ページ【19】のはじめに、「仏願は軽んずるものではなく、神力によるものである」という内容を記述されているのは、仏願の重要性を強調しています。
つまり、仏願は重要で要(かなめ)だから天親菩薩は《我一心》と”納得して”受け入れられたと記述されて、「浄土論」が「世尊我一心」と始まる理由を説明されています。
ここで曇鸞は「無量寿経優婆提舎願生偈」(浄土論)という浄土論の名称が、「無量寿経」とある。
しかし如来の名号は「世尊我一心帰命尽十方無碍光如来願生安楽国」と書き出されている「浄土論」の「無碍光如来」であると置き換えて、
改めて名号の定義をされています。
そしてこの前提を元にして、「五念門」の解釈に入って行かれるのです。(156ページ)
30/11/02[2–4]
156ページから。
「五念門」というのは、浄土論にある、「礼拝、讃嘆、作願、観察、回向発願」のことで、これらに対象する「果」を「五果門」といい「近門、大会衆門、宅門、屋門、薗林遊戯地門」をいいます。
これらを法蔵菩薩を含めた「菩薩の行」として、「浄土論註」によって説明記述されます。
156ページからこの「五念門」を詳しく説明されます。
まず、
「無碍光如来を念じて安楽に生ぜんと願ず」と
ここでの名号は「帰命尽十方無碍光如来」であり、
「帰命」は礼拝門で「尽十方無碍光如来」は讃嘆門と定義されます。
ここから「礼拝」について説明されます。
156ページの9行目に、一般的に「礼拝」といっても「恭敬」もあって、必ずしも「帰命」ではない。
しかしここの礼拝は「帰命」であるといわれます。
ここに「彼此あひ成ず」とあるように、仏とわたしがひとつになることであると帰命礼は「五体投地」のように、自らを放棄して投げ出すことであると、礼拝は「無我」と同じであると記述されます。
そして、「尽十方無碍光如来」を浄土論の偈文の後の論説(長行じょうごう)から、「讃嘆門」だと定義して、まず「称名」について(詳説)される中で、(称の字は《軽重を知る》《秤と同じ》として、「唱」との違いを明確にされています。)
ですから真宗の《しょうみょう》は[称名]と書くのです。
157ページに「光明智相」のごとく、かの「名義」のごとく、「実」のごとく、修行し相応せんと欲うがゆえに、
とあり、ここにある「名義」を「南无阿弥陀仏のいわれ」と解説されることも多いのです。
しかし、教行証文類において、この段階では、名号は「帰命尽十方無碍光如来」ですので、光明智相、名義、実を通して讃嘆門と定義されるのは、「大経の十二光」なかでも「無碍光」であるとするのが適切です。
ですから3行目に「尽十方無碍光如来」とのたまへり。
と記述され、「如来の光明智相の如く」讃嘆する。
と定義されます。
この「光明智相」こそ、さとりの智慧を光明で表されている【重要】な文言です。
そして「願生安楽国」を「作願門」として、天親菩薩の「帰命」の意であると抑えられていることも【重要】です。
「願生」が「如来の願を受けてわたしの願」となる意が内在されるからです。
【この次に重要な問答があります】
《親鸞が「浄土教は仏教であるという論拠」を記述されているからです》
157ページの中ほどに「問うていわく」とあり、仏教経典のさまざまなところに「衆生畢竟無生にして虚空のごとし」という、根本仏教も中観派も、その他すべて仏教は「無我、空、真如無分別」を説いているのに、「生まれるという表現はおかしいのではないか」という問いがあります。
この答えとして、「衆生畢竟無生にして虚空のごとし」と説かれているのに、「2通りある」として、
1つ目に「凡夫が、衆生(存在)を実存と思うように、凡夫が生死があると錯覚している観点からの《生まれる》ということである、しかしこれは亀に藻がついているのを亀毛といっているような、「所有なけん」つまり「あるはずのない間違った見方」であるといわれています。
ですから、このような見方は「亀毛のようであり、虚空のようなもの」であると定義され、ここでいう「願生」の「往生」は、「凡夫のいう《生まれる》」ではないと明言されます。
2つ目には、「諸法」は「因縁生」であるから、生まれるとか生まれないということではなく、「不生」であって、「あらゆることは無いというのは、虚空と同じである」と記述されます。
だから、天親菩薩の「願生」は、「因縁生」の意味でいわれていて、仮に「生まれる」と名づけているのであり、一つ目の凡夫がいう「生まれる」とは違うと明確にされています。
そしてつぎの問答で、「じゃあなぜ往生というのか」と問いを立てられます。
答えとして、
実存しない「仮の名で存在としている《仮名人》」であるわれわれが五念門を修行すると、
修行する前念と後念で変化するので、
煩悩界を生きていた「仮名人」が
浄土を生きる「仮名人」になった
という因果において一つ(同じ)であるというポイントを明確にするため「往生」という文言を使っているのであり、「行」が一つの流れで相続されることを明確にするためであると明言されます。
(ポイント)
この部分の原典(158ページの2行から3行目)に、「前念と後念と因となる」とありますが、脚注にもあるように、本来なら「前念は後念のために因となる」と読むべきなのになぜ、「前後ともに因」にされているのか。
ここに縁信心が、因信心になって「因果同時である」ということをあらわしてあると推論できます。
つまり、【親鸞の読み方は、往生は現世とか来世というものではない】という、重要ポイントがあるのです。
このような、親鸞の独特な読み方に内在される【重要ポイント】を「無視して」さらっと流しては重要な内容が抜けて「ありきたりな浄土教」になってしまいます。
30/11/03[2–5]
《浄土教が仏教である根拠》
158ページの6行目に、第一行の三念門を釈しおわったと区切られて、次の文言に入られます。
ここに「我依修多羅、。。。」と浄土論の偈文「世尊我一心、帰命尽十方無碍光如来、願生安楽国」について根拠を述べられます。
この根拠を「修多羅」によると記述されます。
これは「経典をよりどころ」にするということですが、
仏教の教えは「経典」などを「十二部経」といわれる分類に仕分けていますが、
その最も重要な「修多羅」によるとしています。
しかも、その修多羅のなかでも「四阿含」という、いわゆる「小乗の経典」やその他の『経、律、論の三蔵』までも差し置いて、「三蔵(経、律、論)」に該当しない「大乗の経典」であるというところまで絞っています。
その理由が、このあとの《真実功徳相》の記述になります。
158ページの終わりあたりから、この説明になります。
まず「功徳に2種類ある」という論調で、何度も出てくる「《凡夫》と《さとり》の2種について」功徳を解説しています。
凡夫の功徳は「顚倒(転倒)し、虚偽(うそいつわり)」であるから「不実功徳」である。
そして、菩薩の功徳は、「智慧清浄の業より。。仏事を荘厳す」として
「法性によりて清浄の相に入れり」とあり、
これがなぜ「顚倒(転倒)せずに虚偽(うそいつわりでもない」のかというポイントを
「二諦」によって、究極の結果として衆生を「浄」にいれるからであると解明しています。
ここの「二諦」については「法性(真諦)と言説(俗諦)」という前提で、
脚注のように「浄土の荘厳」というイメージは、衆生のイメージにあわせて「真如に導く方便」として「さとりの智慧を内在させて荘厳されたもの」だから、衆生が真如法性の真諦を体得するための《適切な言説によるイメージ》であるから、つまりは俗諦(方便)である
と、わかりやすく【浄土教が仏教である理由】を定義されています。
これは、「唯識派」の天親菩薩が、中観はもちろんのこと、さらに認識論から浄土を論じていることが明確になっているポイントでもあります。
現実の中で、浄土の荘厳を経典にあるように認識できるようになるための行が「五念門行」であるということです。
これが「唯識論」による【観察門】であるといっているのです。
これを石泉学系では「現実の中に浄土が現映する」などと表現されて、現生と死後を分断しない「一如」に相応した「仏教としての浄土教」を解明しています。
このように、159ページの中ほどに至って、なぜ「浄土教」が「仏教」と相応するかという課題を解析して、解明されている重要な部分です。
《十二部経》
https://r.goope.jp/sainenji/free/hodoku
30/11/04[2–6]
159ページの中ごろに至って五念門中の四門まで解説されました。
そして、「いかんが回向する」から第五回向門の解釈です。
ここに「苦悩の衆生を捨てず〜回向を首として大悲心を成就することを得たまへるがゆえ」
と記述されたうえで、わたしたち衆生に「大悲心をもって与えるのは往相還相の回向」であるという大悲の内容を「さとりへのベクトル」であると定義しています。
そのうえでなおかつ、「作願して《ともに》阿弥陀如来の安楽浄土に往生せしめたまへるなり」と、《ともに》さとりに向かう[往生]という方向へ進むという状態が「回向(発願)」であると明確にされています。
ここでよく使われる「回向を首としたまひて、大悲心をば成就せり」という和讃の定義が、法蔵菩薩とともに「さとりに向かう」ということであると定義されていることを見逃してはいけません。
30/11/05[2–7]
150ページの【20】からは道綽の安楽集の引用ですが、これはここまでの論拠のうえから、ほぼ「念仏を勧める」譬え話ですので、さらっと飛ばします。
ここでいう「念仏三昧」は「五念門、五果門」の集約とみてよいでしょう。
わたしはあくまでもこの時点での念仏三昧は「帰命尽十方無碍光如来」と見ますが、
「南无阿弥陀仏」が一般的でしょう。
そもそもここの安楽集の出だしが、「観仏三昧経」の引用ですから、
そういう点では「南无阿弥陀仏」の方が適しているのでしょうが、
演繹的推論では、ここも「帰命尽十方無碍光如来」で抑える方がスムーズですし、
いきなり「阿弥陀仏」にチェンジする必要もありません。
いずれにせよ、この引用で注目すべきポイントは【21】に現在の障を除いて〜念仏三昧を行ずれば、「現在、過去、未来の一切諸障を問ふことなくみなのぞくなり」の部分にも、仏教の時間論にまつわる記述があることです。
つまり、「現在の障(煩悩など)がさとりへと転じると、過去法も未来法も変化する」という内容です。
これを具体的にいえば、「現在の現実を念仏三昧によって観察」していると今までと「現実の解釈定義」が変わります。
わたしたちは、念仏三昧を生きるまでは、「むさぼり、怒り、愚痴」などの煩悩によって現実をみて、俗にどっぷり浸かっています。
すると、いろいろな物事が「障りや苦」だと思ってしまいます。
しかし、そんなわたしが「念仏三昧に生きる」と同じ現実が「浄土に見えてくる」のです。
もっと具体的に言えば「色々な出来事から自分の煩悩の愚かさを知らされて、そういう現実がさとりへの糧だ」と思えるようになるわけです。
そして「悔いていた過去やこれから訪れる未来の出来事も同じようにさとりへの糧だ」と思えるようになるので、「現在、過去、未来の一切の諸障が除かれる」という状態になるという念仏三昧による具体的な状態を明らかに表現しています。
【22】には「たとひ大千世界に〜。」など、よく使われる文言が出ています。
【23】には「無量寿仏国往き易くとり易いのに、外道に迷ってつかえてしまう」と外道に迷うことへの警告をされています。
次に、善導の引用に移ります。
30/11/06[2–8]
163ページの【24】から善導の引文になります。
あらためて記述するまでもなく、この善導は、法然が絶対的に支持した高僧です。
親鸞はこの善導の解釈について、ここまでに論理的根拠を構築してきたのです。
教行証文類の引文の並びが、「経、論、釈」の順番になっていると言うのは、「重要度順」というだけではなく、「根拠の順番」という意味ももっているからであるといえます。
事実「経典」の内容を、インド仏教哲学では「論理化」されているため、「龍樹、天親」によって経典のなかにある「さとりへのシステム」が明確になります。
そして、中国において「そのシステム」が民衆化したので、より「方便」が【単純化】します。
そのため、民衆化した「システム」の論拠(論)と根拠(経典)を前提として論を進めるためには、「経、論、釈」の順番が適しているといえます。
こういった前提で、ここから引用される「法然が絶対化」した善導の内容を理解していきます。
まず、この【24】からは、それまで五念門に定義していた三昧を「称名」の《一行》に絞っていくなかで、まず《一行三昧》というポイントを引用されます。
これについては、脚注を参照してください。
つまり、真如のすべてが「称名」に内在するという論理です。
これは、真言の「三密」に大日如来(宇宙のすべて)がおさまるという論理によっていると推論できます。
しかし、真言の「すべてがおさまる」というのは、ある種「神秘」です。
親鸞は、中国仏教あたりからこういった前提が説かれている「神秘の中身を分析」して、「すべてがおさまる」という《意味》を神秘ではなく、現実的な論に展開しています。
つまり、「おさまる」といわれる「行」を行じるプロセスを生きるうちに、結局のところ《その中身》を《自然と学んでいくことになって、さとりに向かうというシステム》に構築して、現実的で具体的な《方法》へと発展させています。
道元の「只管打坐」も「禅」はさとりへの《方法》ではなく、そのままが「仏作仏行」という《目的》つまり「着地点(結果)」であるというのも、
日蓮の「一念三千」という「唱題」にすべてがおさまるという論も、同じ根源であると推論できます。
法華経のすべてがその「題名」におさまっていて、「唱題」の一行でそのままが成仏状態であるという行を行じながら、実際には「法華経の中身」を学習していくようになって、さとりに至るという、【一行が学習のキッカケを作って、中身を知る】という構造は同じなのです。
もちろん時代は親鸞の方が先ですから、日蓮がこの構造をパクったといえなくもありませんが、いずれにしろ、平安仏教からこの基本構造が《中国仏教から日本仏教》に取り入れられているのです。
ですから、親鸞は信文類に「仏願の生起本末を聞いて疑いがなくなる」ことが重要とされています。
つまり、単なる「称名」の一行といいつつ、「称名しながら学ぶ」という構造であることを《仏願を学習して仏願に生きる》ことと構造化されて、そこに「誘導」していくのです。
こういう構造やシステムを、ここでは「称名の一行三昧」とされています。
そこで、164ページの問答に「観」から「称」への展開の理由を記述しています。
これは単純に「その方が衆生にとって簡単だから」という説明です。
同ページの中ほどの問答に「一仏を称せしむるに、なんがゆえぞ境現することすなわち多き」という問いに「境現」とあるように、称名の一行に「観察」が起こってくるという記述はポイントになっています。
答えに、そもそも諸仏はさまざまな様相を呈していて「形二の別はない」と「邪正まじる」「一多雑現」することを案じることは無意味であり、案ずることなく「西方へ向く」ことを「観経」を根拠に説明しています。
また続きの問答に「いろいろな仏があるのに、なぜ西方なのか」という問いに対して、
あえてその答えを解析して記述しなおせば、「阿弥陀仏(弥陀世尊)には、明確な願行があって、その願行を学習することでさとりに向かうからである。」ということになります。
この部分には「光明名号摂化十方」や「上尽十形、下至十声一声」「十即十生、百即百生」など、よく聞く文言が含められています。
とにかく、「諸仏」といってみても、衆生がさとりに至るための「ストーリー」が明確ではなく、さとりに向かうシステムがないからです。
その一点で「阿弥陀仏は願行」というストーリーがあり、「称名の一行」で自然とそのシステムを学び、そのシステムに乗って「さとりに向かう」ことが具体的に可能になるからです。
そういう点で、【25】の前に「仏語に随順するがゆえなり」と結ばれています。
30/11/07[2–9]
165ページの【25】から【27】は、「礼讚」を引いて、
とにかく阿弥陀仏の称名を勧めている内容です。
おおよそみなさんも馴染みのある部分でしょうから、特別な解説も必要ないでしょう。
【28】の問答ですが、ここに「八十億劫の生死の重罪を助滅する」という記述は、[2–7]に書いたことです。
またこの問答に「護念」とある「護」というのは「さとりへの歩みを護る」と定義しなければ、「今日も一日、阿弥陀さんや諸仏に守ってもらって、無事に過ごせました。」というありがちな受け取りをされて、まったくさとりとは異なる方向に進むあり方に向かうことになります。
また「阿弥陀経」の「命終らんとする時」という部分は、「破我」を意味する方便表現であると理解できます。
それは、そのあとの文言に「この人終らん時」と「この人」という、いわゆる「自我」について「終わる」とあります。
また、「心顚倒せず〜往生することを得ん」という状態は、「正定聚不退転地」です。
親鸞はこの「不退転地」のポイントを「現当一如(生死一如)」の仏教の原則を分割方便化して、あえて「現生」(因信心の時点)というポイントにおいて「一如」であると定義していると推論しなければ、「ここまでの論」が一貫性を失います。
ですから168ページのはじめに《あえて》「発願」を含めて引用し、それを「諸仏が護る」という「阿弥陀経」を長々と引いています。
そして同ページの終わりから5行目に「増上の誓願を憑むべき」だと「増上縁」として「縁信心から因信心」へ進むように「諸仏の励まし(諸仏称名)」の意義を記述されます。
【29】にも「増上縁」を明確にしています。
【30】は善導が「単純方便」の一行で「往生を得る」と記述している根拠を《善導の六字釈》をそのまま載せることで明確にします。
【31】に「増上縁」によって「往生できる」と《摂取》を説明しています。
増上縁という表現は意外に「真宗」では使いませんが、実は重要な「縁」であって、行文類には頻発します。
この「増上縁」は、《「無為法」は因にはならないという仏教の原則を前提として》無碍光如来という無為法が、方便として「阿弥陀仏」という《名字》という増上縁の「法」であることを明確にします。
そしてここでは、この《名字》が「往生を得しむ」法である《摂取の証明》を[縁信心]の時点で記述して、「摂取」に乗るように「名字の有意義」について説明しています。
これは、まず「お見合い」の例でいえば「この人はいい人だよ」「だから是非一緒になってください」といわれている状況です。
【32】に「善悪の凡夫、回心し〜証生増上縁なり」と「回心して因」に至れば往生を得しめんと欲す」と、
名字の方便が「回心」によって「縁」から「因」になれば、さとりへの道が確定することを「証明」しています。
そのことを【33】に、「業因」を滅するために「弥陀の号」が「業因」にとってかわって、「因」になって「真如の門に入る」と結論づけされています。
お見合いの例でいう「一緒に生きると決めて結婚する」ということです。
【34】から親鸞の六字釈(二字釈)になります。
実はよく読めば、ここには「南无」の解釈のみで、「阿弥陀仏」の解釈がありません。
南无に「帰命、発願回向、即是其行」のすべてを包摂しています。
そして「阿弥陀仏」については、180ページの【50】の「弥陀経義」の最後に「万徳すべて四字に彰る」とあって、その後の引文に「万徳」について記述されます。
また180ページの【53】最後から3行目に「すなわち無生を得んと欲はば、まさにこの法等を学すべし」とさらっと記述されていますが、
このあたりの引文は、念仏三昧が「さとり」の「空性」を得るものとして、空性を「万徳」として表現されています。
【60】に「諸仏はみな徳を名に施す。。。」などと「名字に万徳がある」などと規定しているように、「功徳」があることが延々と述べられています。
いずれにせよ、この時点で親鸞の六字釈は、ここまで論じて来た、無量寿経から浄土論、論註による、
《真如が無碍光とあらわれ、諸仏称名となり、わたしが諸仏同様に五念門(讃嘆門)を行じることで破我されるという論》
が、善導の「念仏一行」に《単純方便》化して帰結されている流れをいったん「総括」して論じられています。
そういう意味で「親鸞の六字釈(二字釈)」においては、
わたしの《無明》を破る方法は「南无」であると言っていて、あとの四字については言及されません。
繰り返しになるようですが、「阿弥陀仏」という「四字」を「万徳」であると記述されているのは、
《諸仏や現象のすべての根源である真如の言語化》として「阿弥陀仏」という名字に《万徳があらわれる》と「阿弥陀仏は法性である」という意味を包含されていると読み取れます。
(補足17、18をご参照ください。)
このような論の流れで親鸞は、
「南无」で「無碍光」を受け入れ(帰命)、人生の方向転換をし(回向発願)、法蔵菩薩の五念門を(行)じることが、《称名行》という因になることを、ここで定義されています。
ですから、「報土の真因決定する時剋の極促を明らかにする」と《真如の方便化を受け入れて、行じる[発願]の時点でさとりが決定する》
という展開になっていると読んでいくと、《行文類のいったんの総括》として、論理展開がスムーズに理解できます。
30/11/09[2–10](なぜかフォントが変わってます)
親鸞の六字釈でいったん《総括》されて【35】から、あらためて「さとりから一行方便化の流れは中国仏教でも同じ流れ」だと明確にされます。
【35】の引用に「如来、教を設けたまふに、広略、根に随ふ。つひに実相に帰せしめんとなり。真の無生を得んものには、たれかよくこれを与へんや。」と、
真如(さとり)から「教」が広略としてあらわされていることを明確にした引用をされて、
「阿弥陀法王」171ページ〈文を離れて解脱を求めんや〉「それ大いなるかな、至の理の真法、一如にして物を化し、人を利する」と続き、「九品に敷いてもって人を収むること、それ仏の名号なりと」という引用が全体をあらわしています。
その後の172ページあたりから、《とにかく》西方、弥陀の弘誓、を勧める引用です。
173ページの最後の行は「有名」な文言です。
176ページの【41】は、「このように簡単にさとりに至る方法があるのに耳を傾けない人が多い」と逆方向から「これを読むあなたは耳を傾けているかたですよね!」と勧める表現です。
ですから、このあとの引用は「本当に大丈夫だから」といわんばかりの内容です。
と、きりがないのでまとめておきます。
もし、不明な点があれば、ご質問ください!
だいたい今まで論じてきた前提で、みなさんがご自身で読んでいただいてもわかると思います。
そして、185ページの【67】から、ほぼ《行》の結論として、「法然」の「選択本願念仏集」を引用されます。
そして、186ページの【69】に、この選択本願念仏集に「南无阿弥陀仏」の《助業》があるけれど、〈混乱〉させないために、「これらを自我の往生のために回向する「行」だと勘違いしないように、「不回向の行」と定義しています。
仏教の本源から見れば、「無生の生」と同じように、「回向も不回向」もない、「ただ念仏成仏」のみであるとも読めます。
親鸞が「浄土論註」を重視しているというポイントを強調するのは、いったんここで「行」について、「南无阿弥陀仏」に落とし込んでいるにも関わらず、【70】に「しつこいようですが、論註にも「同一念仏」とあります」という雰囲気で《論註》をわざわざ引用しています。
そして【71】から御自釈にこれまでの引用を「解説」されます。
特記すべきは、「お説教」ぽい観点では、「群生」という《ムレ》から「正定聚」という《なかま》に表現が代わっていくことの味わいと、
かなめは、「龍樹」「曇鸞」の引用を解説の根源と位置づけていることです。
また【72】に、光明名号を「縁」(増上縁)に定義し、信心を「因」に定義されていることです。
この信心を「業識」と表現しているのは、188ページの脚注もありますが、そもそも倶舎論や部派による解釈、そして「原始仏典(阿含部)」によれば、十二縁起を輪廻になぞらえて、次のように解釈しています。
無明 は、根本煩悩のことで、人間が過去の世界で起こした一切の煩悩のことであり、
行は、人間が過去の世界で起こした煩悩の為に様々な業をつくってきた身心のことと解釈され、
《識》は、これら過去世の煩悩と業によって、この世の母親の胎内で生を受ける最初の心という、
《生命の最初の一念(認識主体)》を意味しています。
親鸞は、この十二縁起の解釈になぞらえて「信心」が「業識」になって、「内因」になると言われています。
これは、[2–8]に書いたように、光明名号を縁にしてあくまでも「その内容(真如法性)」を《学習》する「信心」が〈まるで母体に着床する《受精卵》〉のようなものであるという意味です。
ですから、《念仏は外に礼拝していればいい》という性質のものではなく、「法」がわたしに《内在》しなければ「因」にならないのです。
つまりは「縁信心」のままでは無意味なのです。
「受けとってわたしの主体に名字が入れ替わる(穢土の仮名人から浄土の仮名人へ)」という「因信心」に至らなければ、「往生も成仏も」ありえません。
そして【73】に「行の一念と信の一念」に解釈を進めていきます。
30/11/10[2–11]
187ページ【73】に、《行の一念、信の一念》と御自釈されて、
行の一念について、「称える数は問題ではない」と定義され、その《典拠》を【74】に「乃至」とあるポイント、【75】【76】に「下至」とあるポイントを出されます。
【76】には「深心」「信知」を含めて、「行を信」で受け取る「疑心あることなし」という「一念」にまで展開しています。
【77】の御自釈には、この行信の一念をあわせて「専心」「専念」という文言に込めて、「一念」を「ふたごころのない」「二心、二行なき」念仏の一行。
これを=南无阿弥陀仏と定義します。
【78】にこのことの《論拠》を「光明が無明を破り」《すみやかに》「無量光明土」に至って涅槃があきらかにあらわれ(証)、第22願の「普賢の徳にしたがう」と、「証文類」「真仏土文類」の結論を「短い文章」にさらっと記述されます。
本講義2にも書きましたが「証は験」という意味を内在させた「さとりが証明として現れた」ということを意味する文言ですから《あらわれる》と読み込みます。
一貫して論じられている「称名が学習を生み、俗にまみれていた時と《現実への解釈》がかわり、さとり(浄土)が「現映」する」という意味をもつことばが「証(さとり)」です。
【79】に、一念多念ということは特別問題にならないことを「業道成弁」という文言を中心に前後をもって説明されて、
【80】【81】にそれは、他力だから「如来の本願力」だからと論をたてます。
これは、ここまでに「真如法性」を真実として、「自力」を「自我(我執)」に定義した上で、
「念仏一行」によって生まれてくる「願行の学習が《真如の学習》になる」というプロセスが、
「自我」を破る「破我」になるという《念仏一行の構造》をひとことにされています。
そしてこの部分の「他力」はサンスクリット原語のパラタントラ(縁起)に定義されていると推論できます。
縁起はひるがえって「無我」「真如法性」になるからです。
当時親鸞がサンスクリット原語を知っていたかどうかに関わらず、
それこそが「仏教の本義」ですから当然といえば当然です。
ですから「如来《真諦》の本願力《俗諦》」というようことばを、《真諦》と《俗諦(言説)》の明示と読むと論が通ります。
この「本願力」もパワーではなく《ムーブメント》です。
如来がわたしに願行を通して「仏智の学習」にさしむける「ことばのチカラ」です。
ここで「みなさん右を向いて見てください」というと、
《見てしまう》でしょう。
もちろんこれを読んでて見る方は少ないかも知れませんけれど。。
そういうことばのチカラが「本願力」です。
戻って、親鸞はまたまた「五念門の第五門」から「五果門」について解釈されて、《自利利他》円満の「入出二門」を明らかにして、完全なるさとりへの阿耨多羅三藐三菩提へ至る典拠をあきらかにされていきます。
30/11/13[2–12]
190ページの【82】にまたまた「浄土論を論註」から引用して、
ここで、《本願力》が方便としてどのような結果をもたらすのかということを定義されます。
内容は、「本願力」という方便によって、《【83】の3行目》に
「たとへば、〜本願力より起るをもってなり。〜阿修羅の〜音曲自然なるがごとし。」と、
第五果門の解釈を根拠に「本願力」の定義がされています。
この定義は、「本願力」は「わたしを仏智で動かし、世の中がそのように見える(観察門の)ように動かすムーブメントになる」ことを記述しています。
これは「浄土が現映する状態を生かすという方便の構造」です。
このようにわたしを誘導する「ベクトルとムーブメントを与えるシステム」であるということです。
わたしにさとりへの「方向と動きが起こり、実際に移動していく」という現実論です。
そして、〈菩薩は四種の門に入りて〜191ページ3行目〉に至って、念入りに《本願力のストーリーを生きる》[入門]は五念門の礼拝などからであり、《如来に等しい身として改めて世俗にデビューする「出門」》を第五果門の「薗林遊戯地門」に定義しています。
そのうえで、191ページの4行目から、この状態が単なるストーリーではなく「速攻に無上のさとりに至る」《智慧》であると記述しています。
この部分の最後には、この〈道〉は〈無碍〉で「生死すなわちこれ涅槃なりと知る」と《一如》を前提として、現実にわたしが「世俗に振り回されない」無碍のありかたを《入不二》の法門といまわたしが歩む「行者」としての状態を説明されています。
このあと問答を記述して、諸仏諸菩薩が説かれる中、なぜ阿弥陀如来がその状態を作るのかという現実的な論理構造を明確にしています。
ここには、阿弥陀如来の「仏力」を「増上縁」にして、「四十八願が無意味」に説かれているわけではないこと。
それが無意味ではない証明として、ポイントになる三願をあげると記述して、
第十八願によって「輪廻を勉る(まのがれる)」と一つの証明をだし、
(これが「勉」の文字であることにも理由がありそうです)
第十一願によって、「正定聚」という「不退転に住み」、進んでいく結論として、
「滅度」に至ると証明し、
第22願によって、「常倫を超えた生きかたになり、菩薩の行が現前して、普賢菩薩の徳を学んでいく」という三つ目の証明をします。
この証明による生きかたは、常倫を超える「つまり常識を超えた状態」であることが、194ページにわたって念を押されているように、「世間の常識以上の生きかたになる」といわれています。
ですから、「今日聞いたからすぐ実行できる」という性質のものでもないために、行文類に「縁信心」が記述されているのです。
ビジネスでも「一万時間の法則」という分析があり、「ノウハウがあっても、その人が一万時間以上経験していないことはできない」というものです。
(1日8時間仕事したとして3年5カ月です)
今日まで事務職だった人に「明日から営業をしろ」といっても難しいということです。
そういう点で、「聴聞」も一万時間以上継続しないと、体得できないともいえます。
だから蓮如のいうように「ザルを水につけている状態で、仏教に慣れること」を増やし、
「わかろうとわかるまいと聖典をめくる」「お勤めをする」「本を読む」など、《できること》を、増やせば、1万時間は縮んで行きます!
とにかく、真宗の教えもそれだけ浸らないと難しく、「感謝しましょう」などというありきたりな「世俗の理想」をいっているのではないのです。
後のはなしになりますが、親鸞において《「報謝」は法に応じることと、慚愧すること(二種深信)》であり、「感謝」という性質の内容ではありません。
戻りますが、194ページの五行目からの「自力」についてのポイントは「人、三塗を畏れる」という自我が前提での行。
「他力」については「虚空に乗じる」という「無我」を前提に「わたしが」変換される「行」が結論とされているポイントは重要です。
そして、この他力に《乗る》因信心を生きることを重要な生きかただと述べて、
「局分」という[限られた世界観で計らうこと]をしてはいけないと規定します。
【83】に「この現実の中で、惑を破って真実が証明されて」いけば
「自ずと自力(自我)から他力(無我)への転換が起こる」といわていて
、
「彼此という分断は方便である」と明確に念押しして、「自心を悟らす」というシステムであることを明確にして、《行の定義》を締めくくられます。
ここにあえて「悟」という仏教全般に通じる「文字」で
「悟る」と記述されていることには、意味があると推察する方がいいと思われます。
親鸞がこの文字を使うのは比較的「珍しい」のです。
この意味は結果《仏教全般に通じるさとり》であると理解していくと論が通り、落ち着きます。
30/11/14[2–13]
195ページ【84】には「一乗海」という論です。
親鸞の時代には、「末法時代」であるということがテーマになった時代です。
つまり、さとりに至るために「ふさわしいシステム」を限定することです。
ですから、行文類には、「浄土論」から「如実修行相応」の論も展開されてきました。
(158ページ)
これが現代にあてはまるかどうかは置いとくとします。
[☆]
現代を「五濁」が進んでいるという向きもありますが、逆に《情報と知的教育の水準が上がっている》ともいえますし、ユニバーサルに「仏教以外に科学やほかの宗教や哲学で悟る人」がいてもおかしくありません。
実はこれがこの後の【88】に出てくる内容と符合します。
この点で、必ずしも「念仏」である必要があるのか?
という議論もあります。
じつはこの「限定と思われる一乗」が「限定しない一乗」であると論じられています。
とりあえず、本論に戻ります。
[☆]
戻って、《一乗=大乗=仏乗=阿耨多羅三藐三菩提=涅槃界=究竟法身》と称名念仏の行があらわす法身が究極の法身であり、ほかの法身や如来ではないことを定義します。
そして、この《一乗究竟》の法身は無辺で不断(無量寿)であると《時空を超えていること》を強調しています。
とにかく二乗も三乗もなく、ほかの仏道は結局この【誓願一仏乗】へ導くものであって、この誓願の中に「究極のさとり」へのシステムがあることを限定定義します。
ここまでの論であきらかになったように、諸仏諸菩薩があっても《さとりへの誓願と五念門行》というふうに「願行」が明確なシステムは他にないのも事実でしょう。
親鸞は、阿弥陀如来のストーリーこそ、諸仏などにはない「重要なさとりへのシステム」であると明確に論証したのです。
【85】の涅槃経によって、「実諦は一道清浄で二つとない」と、この阿弥陀如来のストーリーが「スピリチュアルな魔説」ではないことをあきらかにしたと推論できます。
この涅槃経に説かれる《清浄》については「真仏土文類」に改めて論じられます。
【86】で仏道を歩む菩薩が、結局この阿弥陀如来の教えを信じ順うのは「仏、菩薩、衆生」のすべてをさとらす法がこの一道だと了知するからであると、
大乗の対象を《すべてのいのち》に定義して、菩薩道の究極であることを明確にします。
【87】では、対象を《善男子》にランクを下げて、「方便」の《荘厳畢竟》について《一切衆生》ことごとく一乗あり。
と方便と対象を定義して、一乗の対象をさらに広く明確にします。
【88】では、さらにランクを下げて、《一切衆生》に絞って「声聞、縁覚、菩薩」の三乗と一乗について、仏教の「空性論」から、
「一ではあるが非一であり、非一は非非一であり、不確定であって、無数の法を包摂しているから、《一切衆生がさとる乗りもの》である」とややこしげな論を展開します。
もともと「中観」の空性論は、
「空は、非空であり、非非空である」といった、「空は空ではないから空であるが、空ではないと定義しては空にならないから非空でもない」というように、限りなく「無常無我」を論じているので、若干めんどくさいのです。
現代の「不確定性原理」に置き換えると理解しやすくなります。
とにかくここで「涅槃経」に展開される「空論」を根拠に、あらゆる法がこの「一乗究竟」そのものの《本質》であるといっています。
この「不確定な確定」という法の本質は、《すべてこの一乗》が証明している「さとり」であると[☆]の部分に解説した内容と符合すると想定できる内容を論じています。
それは、たとえば「心理学」で悟ったとしても、その「心理学」すら「法」であるということです。
この辺も重要なポイントで、「じつは念仏は、念仏に限定されない限定である」と「すべてを包摂」しています。
このことは次の【89】の「華厳経」によって明確になります。
華厳の「法界縁起説」は、「一即多、多即一」の「事事無碍法界」「重々無尽」を説くものですが、これは「すべてが一におさまり、一はすべてに展開する」という理論です。
現実的にいえば、「すべての現象は一部分の集合であって、一部分はすべてに影響する」という事実をあきらかにしている論です。
単純な事例ですが、一見(いっけん)するとつながりがないように思える「ブラジル」の人がいるから「コーヒーが飲める」ということであり、「あなたがしたこと」が見えてはいなくても、じつは全世界になんらかの影響を与えているという事実です。
このことを華厳経の「法界縁起説」では「事事無碍法界」といいます。
ここではこの華厳経を根拠にして、
「文殊菩薩」という「智慧をあらわす菩薩」を引用し、「一法なり」としつつ「無碍人」と華厳経でいう「無碍」の解釈で「事事無碍法界」であると論じています。
この華厳経の「無碍」が「無碍光如来」と符合することになるという「すべてが無碍光如来」の「智慧法」であるという推論も充分可能です。
異訳の大経に「蜎飛蠕動(ケンピネンドウ)=(虫)」も成仏するという意図が記述されていたり、唯信抄文意に「草木国土ことごとく成仏す」と記述されている「真如縁起説」の発展型が「法界縁起説」です。
またこのことは、「真仏土文類」に「光明」が「智慧」の展開と論じられるところからも定義できます。
そしてこれは、そもそもなぜあえてこの段階で「華厳経」を引用する必要性があるのかというポイントでもあります。
このことを親鸞が、「法界縁起説」の《一多包摂》に如来の根源を見ているからだと推論できます。
とはいえこの重要ポイントをさらっと流しているのは、「称名念仏」の一乗におさえるのが、そもそもの目的であるはずであるところに「なんでもあり」ということは明言しにくいからでしょう。
もちろんここでいう「なんでもあり」というのは、「すべてが真諦の法性つまりは真如法性から如来した無碍光如来、阿弥陀如来である」という理解を前提としています。
虫も草木国土も”心理学などのすべて”が法性であるから「無碍光如来」だといっているのです。
このことは、華厳経を知っているひとが読めば、明確なポイントです。
この辺にも、「法然と真実の間」で揺らぎつつ論じている「ホンネ」が見え隠れします。
とはいえ、”心理学など”でさとるより、「無碍光如来、阿弥陀如来」のシステムでさとるほうが、合理的であるという結論の【一乗】です。
このように、親鸞には華厳経の影響をじつは強く受けていると思える部分が各所にあります。
後の正信偈などに出てくる「蓮華蔵世界」もそうであると推論できます。
30/11/15[2–14]
197ページの【91】は、「一乗海」の《海》に込めた内容を説明しています。
「凡聖所修の〜川水を転じ」と凡夫が悟ろう、救われようとして自力を行じることを川にたとえています。
また「逆謗〜無明の海水を転じて」と煩悩にまみれた凡夫を「荒れ狂う海」にたとえていると考えられます。
しかしその荒れ狂う海も、「本願大悲智慧〜大宝海水となる」と《本願大悲智慧》に出会って、同じものが、転換して「万徳大宝海水」になることを譬えています。
雑行をやがて流れ着く「川」にたとえ、煩悩をさとりと同じ海にたとえていることは、比喩として論理にかなっている「たくみな譬喩」であるといえます。
親鸞が海に喩えることが多いのは、流罪の時に、海路で越後についたといわれて、その実体験のインパクトが強かったためによるともいわれています。
しかしそうであったにせよ、「海」を通して、深さや広さ、荒波、穏やかな海など、多くの状態をあらわすのには、適していることはまちがいありません、
また、仏教で「真如縁起」をあらわす喩えとして、「海と風」がよくつかわれます。
真如が海そのもので、「風」という「縁」によっておこる「波」が、個体や現象である。
という譬喩による説明です。
親鸞は、実体験と仏教でよく使われている喩えを用いたと考えられます。
この次に、「煩悩の氷が解けて功徳の水となる」とある部分は「個体として固まっている状態(自我)が、本願万徳によって水(無我一如真如)となる」というのも、真如の”波と水”の喩えに似ています。
つまりは、同じものが《固く個体という状態から水という状態に変化する》という喩えを使って、さとりに至るプロセスを明らかにしています。
【92】に、如来の智慧を海とあらわして、「深広にして涯底なし」と深く広いことをあらわしています。
【93】は浄土論註により「荘厳不虚作住持功徳成就」と《方便の荘厳は、無意味な方便ではなく、功徳を成就して「功徳の大宝海」としての意味があると記述されて、
「不虚作住持功徳」を《阿弥陀如来の本願力》《法蔵菩薩の四十八願》について、「力願あいかなってたがわない」と浄土論の「不虚作住持功徳」という文言をもって、
本願力は無意味ではなく「功徳によって成就されたものであると「典拠」によって、方便の功徳を説明しています。
つまり、本願力は「わたしの人生の意味を、《煩悩の凡夫》から《さとりへの万徳を生きる行者》に変える」功徳を持つことが実証できるという意味です。
【94】は、「海」には「死骸」が残らないという喩えで、「清浄智海生」と「浄らかな智慧の海に生きる」ということを喩えであらわして、「かの天、人〜傾動すべからざるなり」と、《揺るぎない》ことをあきらかにします。
あえて「生きる」とここで解説したのは、「かの天、人」が主語になっているからです。
いまだ天または人などが「揺るぎない」ということは、「天、人がそうなっていく」という現在進行形であると考えられるからです。
【95】から善導によって「一乗海」の解説から、本願力が「頓教」であるということをあきらかにします。
30/11/16[2–15]
198ページの【96】【97】は、仏教でいわれる「頓教と漸教」について、「速攻さとれるか、ゆっくりとさとるか」という教えの違いについて、
法蔵菩薩の願行は、「頓教」の《速攻さとれる》教えであることを記述されます。
そして【98】は「教」について、【99】は「機」について、対比されます。
【98】の「念仏諸善比校対論」はひとつひとつに意味がありますが、ここでは、結論にのみ触れます。
199ページの後ろから5行目に「本願一乗海を案ずるに〜極速無碍絶対不二の教なり。」とある部分の「極速無碍絶対不二」は、
「極速無碍で絶対不二の教」という読み方と「極速に無碍絶対不二を得る教」、
つまり「速攻に事事無碍法界を得る教え」という二通りの読み方ができます。
また「絶対不二の教」が、「他にはない教え」を意味すると同時に「絶対不二を説く教」であるとも読めるのです。
これらを推察すると、「極速と無碍」を結合させると、「無碍」が修飾語になり、これまで論じてきた意味内容を失います。
ですから、「極速に無碍絶対不二を得る教」と読む方が、これまでの論の流れからはスムーズで意味を失うことのない読み方です。
また、「絶対不二の教」についても同じで、「絶対不二」は法界をあらわす文言ですから、「絶対不二を説く教」と読む方が、「法の意味」を失うことのない読み方です。
このことは【89】に「本願一乗海」を、華厳経の「無碍人」と定義された後ですから、そういう意味を込めているといえるからです。
【99】に「機」について、とありますが、そもそもなぜ「人間を機というのか」というポイントで、「しくみがあるから」という理解が適切です。
つまり、現代でいえば「なんらかの情報を入力すれば、動くコンピュータのようなしくみがある」、だから「仏の智慧」が入力されるか「世俗の情報」が入力されるかによって、違う答えをはじき出すしくみをもつ「機械」のようなものであるという理解が適切です。
ここではこの「機」についても「対論」して、「金剛の信心」を「絶対不二の機」と定義されています。
ここで、主語が「わたしが絶対不二の機」ではなく、「信心が」という主語になっていることが重要な意味を持ちます。
「信心」は「業識」として、わたしに内在した「真如一如」ですから、主語が「不二」を生きる主体であると定義しているのです。
【100】はこれまでをトータルして、「一切往生人等にまうさく」という前提で「弘誓一乗海」を讃嘆しています。
このなかの、200ページの5行目に「妙蓮華のごとし」と法華経を意識している部分、201ページの2行目に「磁石」が出てくる部分は興味深い内容です。
そして、「一乗海」を「方便蔵を開顕せしむ」と結ばれて、「本願力」の方便を「真如法性」による「方便の蔵」であるとあきらかにしています。
この部分を、脚注には《その前にある》「福智蔵」と結合させて、「十九、二十願」を「方便蔵」と解説していますが、これは《論の流れ》として不自然であり、
201ページ全体の流れから、「すべての方便を蔵した法」を冒頭の「一切往生人等」に開き顕されると読む方が全体の流れが一貫します。
そして、【101】から、「仏恩の深遠なるを《信知》して」正信偈を作るとまとめられます。
30/11/19[2–16]
今日友人の勧めで《あるセミナー》に参加しました。
ほぼ昭和の新宗教の現代型ですが、
内容は、「天親の唯識」を現代的にアレンジしたものでした。
このセミナーの「指導者」は、「今このセミナーは全国会場に同時に流されていて、
全国で1万人の皆さまがお聞きになっています」と言ったのですが、
これが事実なら、「8,000万円」です。
わたしの行っていた会場が、大会場2000人収容で、満席以上で大会場から小会場(生中継映像エリア)まで聴衆がいました。
これが、ひとり8,000円の参加費でしたから、
1万人なら8,000万円です。
あながちウソではないのでしょう。
(わたしの参加費は友人が出してくれたので、わたしは払っていません)
そしてこの2000人〜1万人規模のセミナーが”月一”で行われていて、
かつ中小企業の社長などが、個別に毎月「顧問料名目」で「数百万円」のお礼を”喜んで”している
という事実もあるようなので、スゴイ収入です。
その団体に所属することで売り上げが上がっているということでもなく、
「単に内容がすばらしい」「超人的な能力者が育っている」ということで、喜んで支払っているようです。
失礼ながら、たいした内容ではありません。
超人的な能力も、トリックや演出とコールドリーディングの手法です。
(https://ja.m.wikipedia.org/wiki/コールド・リーディング)
これが、大阪でいえば、”ビッグサイト級”のセミナーですが、
運営しているメンバーは、信者さんの「ボランティア」ですし、
セミナーにかかる「会場費などの経費」の多くは”参加費用以外”に、
信者さんの寄付によるものだと聞きました。
コストは、ほぼ限りなくゼロです。
実際「ビッグサイト」でもされているようです。
まぁ経営的なことは置いといて、
セミナー後にわたしは「これは仏教の唯識ですね」と友人にいったところ、
「そうなんだけれど、それを具体的現実的に実践できる方法が、現代の仏教にないでしょう」
と友人はいいました。
《ないわけじゃない》のですが、真宗でも、親鸞が行文類に書いたことを、
間違って読んでいれば、現実的に「実現」しませんから、
《ない》のと同じです。
そういう点で「友人の指摘」は適切です。
実際は、《真宗の教え》は、天親の「唯識の要素」が、構造的に入っていますから、
同じなのです。
そのセミナーより正確です。
しかし、「法話」になると《おはなし》の表現が
「ファンタジックな世間知らずなお坊さんの説教」
としか言えないようなものだから、
あるのに「方法論がない」
と言われてしまうのです。
親鸞は、「行文類」に具体的に「方法論」を明かしてきたのです。
ただ、202ページの【101】のような「真実の行信と方便の行信がある〜」といった
鎌倉時代の表現を、現代に置き換えなければ、現代人には訴えません。
この202ページあたりは、あえて解釈の必要はないでしょうから、
《この講義流》に、この辺を現代的表現に直してみます。
ーー(以下)
わたしたちは《最高の人生を作る》ために、「諸仏が勧めているアミダシステム」を生きることが最前です。
☆この《最高の人生を作る》というのが、そのセミナーのテーマでしたから、
あえてこの表現にします。
あなたをはじめ、すべての存在には、その存在が存在する《なんらかの理由》があるのだから、
それを見つけると「あなたの周囲の混沌(カオス)」が幸せの「糧(カオス)」になります。
(この辺りの論の流れや表現の「混沌(カオス)」なども、そのセミナーの表現をあえて使います)
そのような、存在を含めた不変の混沌としたエネルギーには「存在する意味」があり、ものすごいエネルギー量ですから、混沌のなかに「それらの存在の理由」を見いだすことで、そのエネルギーすべてが「あなたの味方」だという事実が見えてきます。
ユングという精神心理学者がいう”コンステレーション”です。
「無数の存在が示す意味」ということをあらわしている用語です。
この《コンステレーション》という用語は、もともと「星座」ということで、無数の星をつなげて”スコーピオン(さそり座)”と意味づけるのと同じように、
「現実に存在するものごと(点)を(線)でつないで、状況に対して意味づけをしたり、意味づけを変えること」です。
そのように”世の中が見えるようになれば”「不要な存在はない」とわかります。
これは「俗世間の意味ではなく、さとりに向かって不要な存在はない」というポイントが、「新宗教の意味づけ」と大きく違う【重要ポイント】です。
これが、「報仏報土」という方便で教えられている「仏智」です。
この「仏智」を、《法蔵菩薩》の「願い(四十八願)と行(五念門行)」のストーリーを通して受け取るというシステムです。
「大経」が教えているこのストーリーとシステムが「わたし」は《縁起他力》(パラタントラ)の一部であることを教え、わたしを【空・無我】のさとりに誘導しています。
結果、このシステムを通して「わたしの存在意味が、わたしを超えて利他の和合を作ること」だと明確になります。
そしてさらに「真如法性の全体」が「わたし」に包摂されているということに気づけるのです。
これがすなわち「破我から無我へ」「無我から一如へ」というベクトルです。
そして「他力の正意」と書かれている《さとり》です。
これを「宗致」とも記述されています。
現実的な行としては、《真宗の称名念仏(五念門)》です。
これこそが、「わたしが浄土に向かうようになる具体的方法」です。
浄土というのは、「浄穢すべてが浄」だと展開する意味づけです。
すべてが「さとりへの等価である」という【真実】です。
繰り返しますが、この点が「新宗教」と大きく違う【価値】であり《意味づけ》です。
このように、このことは「わたしに浄土を現実化させる or わたしに浄土がみえてくる道を生かすムーブメントである《難思義往生》だ」といっています。
これは、人間の知恵では見えない「難しいけれど、確実にそうなれる道」ということです。
これを「誓願不可思議一実真如海」といっていて、
「人間には考えもつかない、多を包摂する、唯一にして《一即多》の方法」だと、親鸞はいっています。
そして、ここでも、改めて「論註」を引用して、
「恩を知りて、徳を報じる」
「理よろしくまず啓すべし」などと書かれていて、
「所願軽からず、〜神力を乞加する、このゆえに仰いで告ぐ」などと
記述されていますが、
これは、「アミダシステムの理法がすばらしいシステムだ」と讃嘆することが
【讃嘆行】として重要なポイントだということを教えています。
このように、誓願を生きること、
そしてこの誓願を「仰ぐ」という《讃嘆をしている時点》で、
わたしが《破我されるプロセス》のなかにいることをあらわしています。
また、この状態で「今まで見えなかった《混沌》がもつ《さとり》への意味」
が見えてきます。
つまり「観察門」が現実のなかに起こってくるのです。
アミダシステムに入ると《自然に》このような【如来の世界観】で
生きるようになれます。
このように真宗は、《誓願を生きる》という具体な方法です。
そして現実にさとりを「観る」ことができるようになるしくみです。
実際に、このように「人生の混沌の意味」が
「さとりに至る人生を作るためのものだった」とわかって、
”最高の人生が生きられる方法”なのに、
このすばらしい生き方を《しない》人が多いから、
けっきょく具体的方法として「この道を生きたから現実が変わって、人生が素晴らしくなった」
と「言えない」人が多いために、「現実的な方法論がない」といわれてしまうのです。
そして、ここから「正信偈」に入ります。
ーー(現代的表現以上)
親鸞は、
このように「具体的、現実的」方法を述べているのに、
実際に 「行じない人が多い」うえ、
「真宗には《行》はない」と言ってみたり、
「他力だから”このまま”でいい」といったりしてしまうことが、
ビジネス風にいえば「顧客を逃してしまい」
かえって「昭和から最近の新宗教を活性化させているなぁ」と思います。
友人に付き合って、セミナーに行くという「ご縁がたまたま」あって、
真宗はその良さを「部分的にうまく《パクられて》終わっているなぁ」と思いながら聞いていました。
結果「昭和の新宗教のセミナーに行く」という現実が、こういったことを教えてくれたのです。
「行文類」はこのように[さとりへの具体的方法]を、現実に即して論じています。
混沌(カオス)への意味づけ以上の「無上のさとり」に誘導される《具体的方法論》を論じているのです。
30/11/21[2–17]
202ページの最後に「正信念仏偈」をつくる前提に、
「大聖の真言に帰し」とあります。
これは、総序に「摂取不捨の真言」ともありますが、
脚注には「真実の教え」とだけ書かれています。
もし、「真実の教え」を意味するならば、ほかの言い方は
いくらでもあります。
「如実言」でも「実言」でもなんでもいいのに、
あえて誤解を招きそうな「真言」と書かれているのか、
推定する学習思考が重要です。
この時代に「真言」はメジャーなことばですが、
「密教」を意味します。
大日如来と結合する三密の重要な要素である「真言」ということばを
そのまま「無碍光如来との連結」という意味をもたせて、
「名字」は「無碍光如来」との《結合要因》として重要であることを
言っていると推定できます。
つまり「大聖の教えに帰する」と読むのではなく、
「大聖の説く《真言》に帰する」と読むと論理が
スムーズなロジックになります。
もうひとつ言えるのは、「真如の言説」という真諦と俗諦とも読めます。
いずれでも「真言」という言い方で論じている内容結果は同じです。
また「深遠なる」のことば通り「深い内容」にもなるので、論として一貫します。
そういう意味では、「大祖の解釈に閲して」の「大祖」を、
脚注に記述されている《曇鸞の論註》説をとり、
「仏恩の〜信知して。。。」とよむと、
ほぼ「浄土論と言いつつ曇鸞の論註によって」あきらかにしてきた「行」である
「無碍光如来のみ名を称する」の意味をひらく
(大祖の解釈を閲覧する)ことになります。
つまり「普通名詞」または「わたしの名という固有名詞」の名字(名)が、
「大聖の真言に帰し。。。」と「真言に帰す」ことで、
「南无阿弥陀仏」という《固有名詞かつさとりへの動詞》になるわけです。
まとめると、
《真言》に帰する【礼拝門】は、法蔵菩薩の願行に
「わたし」を投じ(五体投地と同じように如来に託す)ることで、
《無碍光の功徳・智慧》がことばとしてあらわれた「法蔵菩薩のストーリー」を聞き、
「わたし」が、自然に《法蔵菩薩の「願行の意味」を学習する》ことになって、
「称名讃嘆」しているプロセスのなかで、わたしの名が「南无阿弥陀仏」に変換していく
【讃嘆門】の《称名行》を生きるるものになるということです。
それは具体的には《法蔵菩薩の四十八願をわたしの願い》として生きる【作願門】の身になるということです。
そしてそのプロセスによって「わたし」が「破我」されていき【観察門】が
誘発されて、浄土が現映していくという《万徳》とされる「仏智」に生きるという、
「いのちのベクトル」が方向転換【回向発願】するのです。
このように、「仏恩を信知して」つまり「如来を受け入れて」
“方向転換したいのち”になったと、
親鸞は実体験とその論のプロセスを、
この「行文類」にあきらかにしたのです。
ですからここに十二部経のうちの「偈」を作って、「無碍光如来」という
「法界縁起を明かす真理の光明」によって導き出された「阿弥陀仏の万徳」に
「南无(帰命、発願回向、即是其行)」して、
「南无阿弥陀仏」の真言によって「真如と一体化」するプロセスを
「正信念仏」を《如来からの縁信心と因信心による念仏》だとあきらかにした「偈」という
スタイルで改めて「讃嘆」する。
という意味に読み込めます。
これはあくまでも行文類が「論註を中心」にして論じられているという
かなりな【重要ポイント】を外しては読み込めない内容です。
このように、膨大な論のようでありながら、内容は一貫しているのです。
30/11/22[2–18]
203ページの【102】に《正信念仏偈》という十二部経
(仏教教説の十二形態)の「偈(ガーター)」という形式で
【讃嘆門】の《願行功徳=法性》を正信した念仏について
あきらかにした偈を記述されます。
これは「行文類」と「信文類」の間にありますが、
行から信へのプロセスというよりも、《行信を結合》している内容だと言えます。
さて、冒頭の「帰命無量寿如来、南无不可思議光」について、
一般的には「帰敬序」と定義されますが、単純に「南无阿弥陀仏」のもつ
「寿命と光明」を分解して、「帰敬」をあらわすだけの内容であると
”流して”しまっては、重要な意味を見逃します。
ここは【礼拝門】【讃嘆門】と定義できます。
ここには次に続く、法蔵菩薩のストーリーの【根拠】が明確にされています。
「無量寿如来」は大経にあらわされる法蔵菩薩の結論ですが、
法蔵菩薩を真如からの垂迹とするなら、
「法蔵菩薩の根拠」を真如から来生した《言語上(俗諦)の存在》という
【念仏の教えすべての根拠】を無量寿如来とあらわして、
「帰命」するといわれているということが「重要ポイント」です。
ここを指して、わたしが「無量寿」いわゆる「永遠の命をいただく」と解釈してはいけません。
あくまでも「わたしがわたしで無くなる」ことが、仏教の「さとり」ですから、俗世間の価値観で読んでは間違うのです。
あくまでも「大経」の無量寿如来であって、「さとりそのもの」です。
そして、この無量寿如来が「光明」として現れるのですから、
「帰命尽十方無碍光如来」と同じ意味で、
「南无不可思議光」と出されています。
これは、
「帰命無碍光如来」「南無無量寿如来」でも良さそうですが、
「無量寿如来」は「大経」の本源ですから、これを先に出して、
浄土論の「無碍光」を「不可思議光」として、後の十二光に配慮したとも
推察できます。
《本源から光明が出て、法蔵菩薩の教えに具体化する》
という流れに読み込めます。
つまりこの二句は、《法蔵菩薩の言説の【根拠】をあらわす》と同時に、帰敬を表されています。
しかし、文類聚鈔の念仏正信偈の冒頭は、「帰命も南無も」ありません。
この点で、帰敬よりも、論の流れに意味があるといえます。
「法蔵菩薩因位時」からは、「大経」の法蔵菩薩のストーリーがまとめられています。
ここに、《願行》が整うことを明確にされます。
ここで【作願門】が定義できます。
ただここで「建立無上殊勝願〜大弘誓」と《誓願》は整うのですが、
《行》がどこで定義されるのかということが不明瞭です。
このことは「大経」15ページによれば、
「五劫を具足し〜清浄の行を摂取す」とあるので
「五劫思惟之摂受」の部分が、15ページの2行目の内容をあらわしていて、
この「五劫思惟。。。」が《願行具足》をまとめた部分だといえます。
しかし、「願」は、四十八願という詳細なものが記述されているのに、
「行」は《清浄の行》とあるだけです。
ですから、行文類に論じたように、この「行」を【五念門行】と
「浄土論」は定義したのです。
そして、「重誓名声聞十方」に至って、
「名字と声が十方に聞こえることを重ねて誓っている」
という部分の解釈もポイントです。
「名声」を即「名号」と解釈すると「南无阿弥陀仏」の喚び声という
早計な解釈になります。
この「名声聞十方」は《名字と諸仏称名の声を十方衆生が聞く》と解釈すると、
行文類と符合して、諸仏称名を聞く(信心)となります。
「聞えんと」を「聞こえるように」と読んでも、「聞こえる」と断定しても
文脈としては問題ありません。
ただ、この時点では《名》を南无阿弥陀仏に定義できません。
それは、この部分が「大経」によっている以上、「大経」には
「南无阿弥陀仏」という文言は出てこないからです。
とにかく「我が名字」という「不確定な名」です。
あえて「大経」のうえで確定するなら、「法蔵菩薩か無量寿仏」です。
いずれにせよ、ここで「不確定な名字」をこのあとの「普放無量無辺光」
から十二の讃嘆名であらわされる「光明」に定義されます。
これも【讃嘆門】と定義してもいいでしょう。
行文類では、仏の名字を確定していないのですから、
讃嘆名すべてが「名字、名号」であり、讃嘆名です。
名号については、155ページの論註の引用【18】の終わりに、
教文類にも記述した、「仏の名号をもって経の体とす」とありますが、
論註のうえで名号は、次のように書かれています。
[論註(卷下)自体を〈書き下しで〉みて見ます]
彼の名義の如く、 実の如く、 修行し相応せんと欲うとは、 かの無礙光如来の名号は、 よく衆生のすべての無明を破って、 よく衆生のすべての願いを満たしてくださるのである。
ところが口に名号を称え、 心に念じながら、 無明がなおあって、 その願いの満たされないものがあるのはどういうわけかといえば、 それは無礙光のいわれにかなうように修行せず、 名号のいわれに相応しないからである。
どういうのが無礙光のいわれにかなうように修行せず、 名号のいわれに相応しないのであろうか。
それは、 如来が「実相(じっそう)」「真如(しんにょ)」をさとられた自利成就の仏であると共に、 そのままが、 われらを救いたもう利他成就の仏であることを知らないのである。
―――以上「論註」
とあるように、「無碍光如来の名号は」とあって、この「の」を無碍光如来という如来の名号が別にあって「その名号は」と読めなくもないのですが、大経と浄土論の時点では「南无阿弥陀仏」という文言自体がなかったのです。
ですから、この時点ではあくまでも「無碍光」の
讃嘆名に帰結定義されます。
そもそも、南无阿弥陀仏と出てくる「観経」について、
中国撰述説があるように、「サンスクリット原典」がなく、
「異訳本」もないので、天親は「観経」自体を知らなかった
可能性があるのです。
曇鸞は知っていて、論註にも引用があります。
とはいえ、念仏の根拠を「真如、法性、空性」という仏教の根源からの方便である
と解釈して、
さとりへの構造をもったシステムであると【証明】する上で、
もっとも欠かせないのが「論註」ですから、名号の定義が難しいのです。
しかし、146ページ【12】の御自釈に、
「名を称するに〜念仏はすなわちこれ南无阿弥陀仏なり」とありますが、
なぜか、名号は「南无阿弥陀仏」なり。
と教行証文類で明確に定義されないのです。
称えられている名が「南无阿弥陀仏」です。
という表現ですから、ここで名号を「南无阿弥陀仏」に定義している
といってもいいように思えます。
しかし、明確に定義しない。
つまりそれは「大経の無量寿仏」の名号は「複数ある」からだといわざるを得ません。
これは、「浄土論註」には、無碍光とあり、
そもそも「大経」には「無量寿如来(仏)」とあったりするので
確定できないということだといえるでしょう。
ですから「称名」をあえて「念仏」という文言に置き換えて
「南无阿弥陀仏」に定義するという、
ややこしい論を展開する必要があったのでしょう。
そしてまた、この次に「本願名号正定業」「至心信楽願為因」
とある部分に《本願名号》とありますが、本願に名号はありません。
では、この本願名号をどこで抑えるかと推察すると、
「至心信楽」の《至心》を名号と定義するほかないのですが、
ここにも親鸞の主張したいポイントと法然のズレがあります。
これは、「正定業」と186ページの4行目5行目にも記述されていますが、
ここでは、185ページの【67】から、南无阿弥陀仏は念仏であると定義し、
念仏は正定業であると定義し、それをまた称名に定義して、
これは「仏の本願による」と法然が定義している内容を典拠にしています。
ここでズレがあるというのは、法然は本願の「乃至十念」で
定義しているのですから「本願名号正定業、念仏往生願為因」
とすれば一致するのです。
事実、親鸞は信文類の冒頭に「念仏往生の願より出でたり」と記述しており、
「選択本願と名づく」とも記述しているのですから、
「選択本願願為因」でもいいわけです。
しかし親鸞は、「至心信楽の願」という願名をここに出しているのは、
「無碍光」や「阿弥陀如来」の功徳、つまりは「真如法性」を名号に定義して、
それを「至心」に定義されるので、《正定業・本願名号》を
「乃至十念」に定義されないと推論できます。
30/11/22[2–19]
203ページの「成等覚証大涅槃」「必至滅度願成就」は、
「至心信楽願を因と為す」による第十八願の因による果を
「等覚を成り大涅槃を証することは」という
第十一願の「必至滅度の願成就なり」だとしています。
☆よく、四十八願の順番について、なぜ「大事な本願が18番目という中途半端な
順番にあるのか、なぜ因になる願が十八番目で果になる願が十一番目に戻るのか」
といったことを尋ねられますが、
それこそ四十八願をひとつひとつ読んで「願の流れ」をみればわかるのですが、
真宗では「11、12、13、17、18」と「19、20、22」を取り出して
語られることがほとんどなので、全体の流れがわからないのです。
今はそこを記述すると膨大になるので、
四十八願について「順番の意味や内容」について、以下を参照してください。
http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/四十八願
さて、四十八願の第十一願には
「国中人天、定聚に住し、必ず滅度に至らずは、正覚を取らじ。」
とあります。
これを脚注から[補注2]1556ページを見ると「滅度」を
「煩悩の滅した無為涅槃界」と記述され、
「臨終一念の夕べ」を引用して
「現生のいのちが終わると(死後)大般涅槃を超証す」
と記述されています。
ここに真宗学上の矛盾があるのです。
そもそも第十一願の文言では「国中人天」が
「定聚に住し、滅度に至る」とあるものを、
教行証文類では「定聚」を「因信心」の時点に規定していますから、
すでにここで「国中人天」でなければ、第十一願を崩すことになります。
ひとつには「国中に《人天》」が存在しますが、この《人天》は、
仏の変化身ではなく「普通の人天」でなければ、
「定聚に住し、滅度に至る」の文言が意味を持ちません。
そして、【重要】なポイントは、
「臨終一念の夕べ」に「一念」とあるのを「信の一念」とし、
「俗世間のいのちが終わる《臨終》」と定義しなければ、
「経文そのものを崩すことになり」それこそ、
親鸞は「そんな無茶なことをしたのか」ということになります。
ですから、「臨終一念は信の一念」の時点と定義して、
「夕べ」という意味は「正定聚から滅度に至るプロセス」
つまり「滅度へのウパーヤ(近づく)プロセス」と定義し、
「滅度」は、
「煩悩が滅すること=最終的にわたしが消滅すること」
つまり「真如無為に合一すること」と理解すると問題はないのです。
この「最終的にわたしが消滅する」と記述したのは「死」を意味しません。
生死に関わらず、「わたしの名字が完全に入れ替わること」であり、
親鸞のように「正定聚の初地が、南无阿弥陀仏が信心の業識として、
親鸞に着床し《等覚》に至って、
わずかに残っている《わたし》が消滅しかかっている状況」で、
ほぼ「滅度ギリギリ」という状態といえるでしょう。
ここで「夕べ」という「徐々に夜になる」という喩えのように、
デジタルではなくアナログ的《フェードアウト》だといえます。
ですから、「信文類264ページ【103】」の「夕べ」の前に、
「竜華三会の《暁》」と記述されていて、「弥勒菩薩と同じであり、
「等覚の夕べから暁に至れば無上覚位を極むべし」とあって、
弥勒菩薩が死んだ時に涅槃に至るのではなく、
弥勒菩薩と同じ等覚から、プロセスを進んで、弥勒菩薩より速く、
《暁》に至るという論であると解釈する方が、
仏教の根本原則に背かないのです。
つまり、「さとり、真如、空」は「俗世間の根底」にあります。
それは、「俗と悟」は《同時に存在する》ということです。
「さとり」は、時間軸にあるのではなく、
空間と存在の解釈(多次元時空)にあるのです。
問題は、《同時に存在する》どちらを見るのか
【観察】するかということですから、
「非僧非俗」の《非俗》の部分です。
結果、往生すら「無生の生」ですから、
同時に存在する《非俗》を見ながら生きると決めた
「信の一念」に「わたしが終わりゆく夕べを生きる正定聚」になり、
死後で有る無しに関わらず、現生にさとりを【観察】しながら
徐々に涅槃に至るという論になります。
戻って、「等覚になる」は「正定聚になる」という意味で、
「本願名号が正定聚へ至る業」でそれは「至心」という
《真実心(真如に導く如来の教え)》、
具体的には「法蔵菩薩の教え(中心は四十八願)」を
疑いなく受け入れる「信楽」によって決定するので、
「等覚の身になって(正定聚)」を生きる「念仏行者になる」ことで、
「涅槃が証明される」を「滅度に至る」ということだと
明確にされています。
ここで【回向発願門】が定義できます。
そういう点で「この根拠」を「第十一願」に定義しても
「ムチャでもなく、問題なく、かえって方便言説のなかに真如をみること」
になるのです。
30/11/26[2–20]
「如来、世に興出したまふ〜如来如実の言を信ずべし」
の部分は、「釈尊」をはじめとしてすべての如来が世に出た理由は、
ただ弥陀の本願海を説くためであると、諸仏出世本懐を明らかにします。
興味深いのは「ここで《群生海》」とある部分で、ちょくちょくありますが、迷いの衆生を群生といい「ムレ」と表されていることです。
仏法に生きる人たちは「ムレ」るのではなく、「和合」するのです。
いわゆる「ムレ」ている人たちは、それぞれの「能力を活かす」のではなく、失敗についても「かばい合う」ものです。
そして、そこには「ボス」のような人がいて、そういう人に「気を使いながら」その「ムレ」から落ちることに気を使うものです。
とはいえ、その「ムレ」に意味があるかというと、なんの「意味もない」というのがほとんどです。
誰がボスでもなく、互いに持てる能力を活かし会えて、トラブルにも適切な処理ができる関係を「和合」といい、仏教のめざす人間関係です。
親鸞は「正定聚という《なかま》」という観点を重視しているように思えます。
いずれにせよ、これが、三宝の「南无帰依僧(サンガ)」です。
さて、ここに「五濁悪時」とありますが、
阿弥陀経などでご存知のように「劫濁、見濁、煩悩濁、衆生濁、命濁」という「五濁」。
この文言の解釈はいろいろありますが、
http://labo.wikidharma.org/index.php/%E4%BA%94%E6%BF%81
http://www.higashihonganji.or.jp/sermon/shoshinge/shoshinge18.html
を参考にしてください。
ただ、この五濁悪時ですが、見えにくいところに、五濁や悪時の姿があるにせよ、けっこう時代の良し悪しからすれば、「民主化」「教育」という面では、そんなにめちゃくちゃ悪い時代とも思えません。
とにかく、いつの時代も良し悪しはあって、意外と現代もさまざまな課題はあるけれど、「さらし首」にされるような時代でもなく、法治国家という名の人治国家ではありますが、基本は法治国家ですし、「民主化されて言論の自由もある」時代ですから、ネットもいい方向で使えれば、このように簡単に情報共有できますし、必ずしも「五濁」が進んだ時代とも言いにくいとは思うのです。
そういう意味で、五濁は進むかどうか以上に、「ある」ことが問題です。
悪時であることは常なのでしょう。
どの時代にも、それぞれの時代の問題があるのです。
つぎに特記すべきは「不断煩悩得涅槃」でしょう。
親鸞は、和讃のあとに「獲は因位」「得は果位」としていますが、この教行証文類の時点でどうだったかは不明としても、
「煩悩不断の状態で涅槃を得る」という意味であると理解できます。
これは、仏教一般で「煩悩即菩提」などといわれるように、
煩悩も仏智でみればさとりの《タネ》になる。
という意味をあらわしているようです。
そもそも「如来」という言説による存在は、煩悩をもった私がいるからで、私がいなければ、如来も必要ないのです。
如来の教え、法蔵菩薩の願行によって、私がさとりに向かい、そのために「如来が煩悩の解釈を変えてくれる」のです。
「むさぼり、怒り、愚痴に生きる私」が、
《いずれも自分のいのちの防衛のための心の動きだった》
とおしえられるのです。
だから、こんな「防衛の仕方はかえってていい結果をもたらさない」と知って、そもそも「わたし」を守ろうとせず、
「無常の中で、摂理に従って生きる方が得策である」
と「無我、空性、真如」に生きるように方向づけられるネタになるのです。
このように、煩悩を「断つこと」を考えずとも、「涅槃に至れる」ことを教えてくださるのが、阿弥陀如来を受け入れる「一念喜愛心」にこういう実益を得られるといういことです。
だから「凡人も聖人も逆謗斉しく方向転換して、阿弥陀の海に入れば同じさとりの味になる」ということです。
30/11/27[2–21]
「摂取心光常照護〜即横超截五悪趣」
これは「摂取の心光」または「摂取心の光」と読むと、
微妙に違って、「心光」というと光明に「意思がある」ようになり、
「摂取心の光」と読むと「摂取心から出た光明」となりますが、
これを書いた親鸞は、「摂取の心光」と読ませています。
これは、光明に「智慧と慈悲の意思がある」ということだと推察します。
いずれにせよ、私をさとりに向かわす光明は、
「常にさとりへの道を外れないように護り」
私の”無明“の闇を破っていて、
もしたとえば「貪愛瞋憎の〈煩悩〉の雲や霧が」覆ったとしても
「阿弥陀の智慧に生きているものの上には、
真実信心の「無碍光・智慧光の天」がすでに「覆っている」から
問題にならないということを譬えています。
たとえば日光が雲や霧に覆われても、雲や霧の下は明るくて
闇がないようなものであるということです。
だから信を獲て、見て(観察)敬い(礼拝)大きに慶喜すれば、
すなわち横に五悪趣を超截すると、
大経の文言によって、
五念門行の内容をこめて、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人
の五悪趣を截ち切るといっています。
ここで五悪趣が出されますが、そもそも五悪趣の根源は
「人」の「思慮分別」にあります。
これは倶舎論頌にある解釈で、「人」の定義を
「思慮分別するを人とす」とされていますが、
人はたいがいの場合、思慮分別の末、
「いかり、愚かな思い、むさぼり、自分の思いに拘束される」
という「修羅、畜生、餓鬼、地獄」をさまよいます。
これが「趣く(趣)」ということです。
つまり、人の「虚妄分別」が自分を苦しめるのです。
自分で自分の首を絞めるということです。
そしてそもそも、この《分別の基準》が「無明」によるから、
この無明を破る「無碍智慧光」が「摂取心光」なのです。
私たちは、この光明に「護られる」のですが、
これも「さとりから退転しない」という「護り」です。
心光とされる「無碍智慧光」に照らされて、「無明の闇が破られて」
《虚妄分別》から逃れ、「真実の智慧」である《法蔵菩薩の願行》に
生きればこそ、五悪趣を截つことができるという《具体論》です。
ですから一般的に「善人と言われようと悪人と言われようと」
この「虚妄分別」は同じですから、「一切善悪の凡夫人」とくくり、
この凡夫人が「如来の弘誓願を聞いて受け入れる《信》ならば、
「仏」はこのひとを「広大勝解者(すぐれてよく理解したもの)」と称えられて、
「分陀利華(白蓮華のようだ)」と名づけられます。
と虚妄分別を離れて「無碍智慧光」に帰するようにいわれているのでしょう。
とはいえ、このような「虚妄分別」を、
人はなかなか「虚妄」だと認めないので、
弥陀仏の本願念仏を「間違って解釈」したり、
「難しい」とひとごとのようにかわし、
「おごり」によって「必要ない」と認識します。
こういういわば「悪衆生」、
さらにいうなら「愚衆生」、
「せっかく、広大な世界に解き放たれる
無碍智慧光があるのに、狭い自分の牢獄に
自ら繋がれる愚かなもの」
は「信楽(疑いなく受け入れる)」を
得ることは難しく、
この上なく「難しい」ことでもあるというのです。
とにかくこのように「”残念な人”が多いものです」といった雰囲気で、
親鸞はなかば「嘆かれて」います。
さて、ここまではおよそ「大経」によって解釈されてきました。
続きは「七高僧」による「解釈」を記述されます。
30/11/28[2―22]
「印度西天の論家(龍樹、天親)、中夏(曇鸞、道綽、善導)
日域(源信、源空)の高僧」
これらの高僧は、「大聖(世尊)が世に現れた正しい意図をあらわして、
如来の本誓が機に応じていることを明きらかにされました。」といった、
大経をもとに、七高僧それぞれに「無量寿如来の教え」が
「私たち凡夫にふさわしいこと」をあきらかにされたといっています。
そこでまずは、「龍樹菩薩」です。
本文のポイントを記述していきます。
「悉能摧破有無見」
これは、龍樹の中観を表しているとみてよいでしょう。
つまり「空」です。
一切はあるのでもないのでもない「因縁生」であるということです。
「有見、無見を破る」といいますが、
これは、「有る」という側面に執着していても、
「無常と縁起による存在」という事実からすれば「無である」といえます。
単純に「念珠」も《珠とヒモ》によって結合しているから「念珠」ですが、
ヒモが切れれば《珠とヒモ》でしかありません。
さらにこれを分解していけば、《原子》でしかないのです。
しかし《原子》が「有る」のかと言うと《観測者》がいなければ「無い」といえます。
存在というのは、このように「不確定」なものでしか無いのです。
「無い」といってみても、「因縁」がそろえば「有る」
という状態は現実化しますが、
これも《刹那》に変化していますから、同じ状態のものがある
と言うこともあり得ません。
こういった、「有無の見」を破った。
というのが、中観の「空論」であり、龍樹が祖とされている学派です。
これは、「曇鸞」も「論註」の各所に用いている論で、
「往生」に関する「無生の生」もこの内容をもとにしています。
ですから、死後に「お浄土」があり、死後に「往生」する
という教義は《仏教では無い》という以前に、
龍樹自体が「破った見方」なのです。
行文類に論じらてきたように、
あくまでも現生に「私と名づけられている存在は《仮名》でしか無い」のですから、
「私の名字を変換して、現生で《浄土の仮名人》となって
《無碍光如来や南无阿弥陀仏》と称名しつつ、
《自分の名前を入れ替えていくプロセス》の中で、
「現生に浄土(さとり)を【観察】して生きること」が、
「仏教と相応した浄土教の歩み」なのです。
根本仏教の「無常、無我」を生きる方便ということなのです。
通常「真宗学」では、
龍樹は「易行」をあきらかにしたといわれますが、
「信楽易行水道楽」というところから言われています。
しかし、行文類からの論理でいえば、
それ以上に「有無の見を破る」というポイントの方が
重要であるといえます。
その点で、「常に称名する」を「憶念弥陀仏本願」と言い換えても、
同じ内容であり
《法蔵菩薩の願行(弥陀仏本願)を生きるということがより具体的》
に表されています。
本願を憶念しながら生きることが【作願】になるからです。
ですから「自然即時入必定」になり、
「唯能常称如来号」【讃嘆】になるのです。
そして、天親菩薩ですが、
行文類のポイントとして「帰命無碍光如来」「依修多羅顕真実」
「横超大誓願」と重要な部分をあげ、
「本願力回向によって一心をあらわす」という
【回向発願】から
「一心という信心」への意味に「五念門」を
《行から信》へと論を進めています。
そして、無碍光如来の「功徳大宝海」に「入れば」、
五果門の《大会衆門》に入るといわれます。
ここで五果門に入るのは《無碍光如来に帰入した》
【讃嘆門】の時と《因果同時》となります。
「獲」を因位としても、(和讃の終わりの文による)
因果が因に包摂されなければ「必獲」とは言えません。
この点で【重要なこと】は、
そもそも時間論について、「大経」は
「過去、未来、現在」の《法性生起の次第》ですから、
凡夫の時間論ではありません。
そして、この「時間論」は天親が書いた「倶舎論」
にも解釈されています。
天親は、「倶舎論」を書き、やがて《唯識派》を大成したのですから、
天親については、「認識論」で解釈する必要がありますが、
曇鸞が「浄土論註」で「中観、唯識」に基づいて解釈し、
また、「大乗諸経」によっても解釈をしているので、
より深く「大乗仏教としての浄土論」という位置付けで解明できるため、
親鸞は、「浄土論註を浄土論」として取り扱っていると推論できます。
行文類で「浄土論=論註」になっているのは明確な事実です。
ですから、入の第三門【作願門】は「蓮華蔵世界」に入る
とされている、この「蓮華蔵世界」について、
親鸞は、196ページの【89】の「無碍人」を「華厳経」の
「法界縁起」で解釈していて、これが「無碍光」
を暗示していると推察できるのです。
いずれにせよ、親鸞は「浄土教」について、
「仏教と相応する」ということを、
「浄土論、論註」によって明確にしています。
ですから、「蓮華蔵世界に至る」と[器世間]について明らかにし、
「真如法性の身を証す」などと[有情世間]について明らかにして、
大乗仏教の根拠を、天親菩薩によって明確にしているのです。
30/11/29[2–23]
書き落としましたが、「天親菩薩」について、
真宗学では「一心」を明らかにしたとされます。
さて、
「遊煩悩林現神通、入生死園示応化」
これが、五果門の【薗林遊戯地門】をあらわしており、
還相回向をあらわす典拠になる部分です。
このあと「本師曇鸞〜帰楽邦」までは、
曇鸞のすごさを修飾した部分です。
このなかに、「仙経を焼き捨てて楽邦に帰す」とありますが、
これを「この世で不老不死を願っても無理だから、
お浄土に行けば永遠のいのちを得られるから極楽を願った」
というふうに理解しては、ファンタジーになります。
仙人になって、不老不死になろうとしていたけれど、
いのちの本来のあり方に目覚めて、
仙人になろうとしていたことが「アホらしくなって」
「浄土論」の真実と方便(利他の方法)に「帰依した」ということです。
そもそも補注42にも書きましたが、「七地沈空の難」にあるように、
「空」という概念は、当時でも知識層にはわかる概念でした。
ですから、曇鸞も親鸞もダイレクトに「真如・空」という
抽象概念を論理で理解できる人だったと思うのです。
しかし、その《真如》といった真理の概念や論理というような
「むずかしいことはわからない人」とでも、
これを共有し、和合しあえる「利他の法」がある、
ということが「浄土教であるポイント」だったのでしょう。
ですからこの法であれば「七地沈空」はないのです。
「天親菩薩論註解、報土因果顕誓願、
往還回向由他力、正定之因唯信心」
ここに、方便のすべてがおさまっています。
曇鸞は、天親菩薩の浄土論を註釈して、
無碍光如来という方便の中のさらなる方便を
あきらかにしました。
それが、「法蔵菩薩のストーリー」によって
《さとり》を学ぶという方便です。
その内容は、「法蔵菩薩の誓願と荘厳功徳を聞くことで、
自然にさとりを学習する」というシステムです。
このことを「報土の因果をあきらかにして、往相回向、
還相回向ともに他力である」と、
親鸞はいっています。
このことは、この「浄土というさとりへの道」を
歩もうと方向転換した信心の人は、
人生そのものが
さとりに定まった《正定不退転》の「因」に決定して、
この人生が自然と「往相と還相の他力のなかに生きるようになる」
と誘導していくという「浄土の教えの方便のシステム」を
解釈されたという内容です。
つまり、「浄土往生」と「プライベートな生活(俗世)」を
分けて、「往生が他力」というのではなく、
この教えに生きるようになれば、
「すべてが往生の道であって、
人生まるまる他力(縁起)だったと知る」
ということです。
真宗学では、「曇鸞」は、この部分にある「他力」を明らかにしたとされます。
そして、「惑染凡夫信心発〜諸有衆生皆普化」は、
もともとさとり《真如》そのものであった、
私たちのいのちが
「惑」に染まって、
「惑染凡夫」になったのですが、
その私が「信心をおこす」ことで、
「生死即涅槃」と生死を分断して「虚妄分別」に
迷っていたと証明されることを知り、
必ずのちに《真仏土文類》で定義される
「無量光明土」に至る。
と、「仏の智慧の状態」に至って、
諸々の衆生を「すべて教化するもの」になる。
と浄土論の真実と方便をあきらかにしたのが「曇鸞」です。
ある学派では、人間は「無仏性」であり、
名号が時空遍満して「信の一念」に、
私の仏性になってくださる。
という解釈をしますが、
「真如法性」からいえば、「無仏性」はあり得ません。
とにかく、親鸞はこの「浄土論と論註」を重視されたので、
天(親)と曇(鸞)から「親鸞」と
名乗ったと考えられます。
つぎに、
「道綽決聖道難証〜至安養界証妙果」
は道綽の部分です。
道綽は曇鸞と同じ「玄中寺」に住した僧侶ですが、
「涅槃経と観経」特に観経に強く影響を受けて、
「安楽集」を書き、
次の「善導」に観経を教えたひとです。
そもそも「観経」は中国撰述説の強い、
いわゆる《偽経》といわれています。
http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/観無量寿経
https://kotobank.jp/word/観無量寿経-49688
「親鸞」はそれを知ったか知らなかったかは不明ですが、
なぜか法然とは違って「大経」を真実経典として、
《阿闍世問題》以外に、
論として、
「観経を重視されている様子がない」のです。
http://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/無量寿経
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/無量寿経
たしかに、観経は《明確な方便経》で、
《韋提希と阿闍世》のストーリーが中心になっており、
仏教と言える部分は、瞑想以外になく、
仏教で肝心な法印とされる「無常、無我、寂静」
に触れる部分が重要視されず、
結果「瞑想(三昧)」で実現不可能な「観想」とされています。
だからなのでしょうか、
「浄土論」の「仏教と相応する」という部分が、
教行証文類では強調されて、
「浄土教は間違いなく仏教です」
といっています。
とにかく
この観経のストーリーは「涅槃経」から続く内容だと
言われていますので、
そもそも「涅槃経」学者だった
「道綽」の創作ともいわれます。
しかし、観経は曇鸞の論註にも引用がありますから、
これは時代的に合わないのです。
といっていても「うがつ学者」は、
道綽が論註に「書き足した」という人もいるようですが、
原典の文字の分析などのなかった時代、
時代考証のできない時代の学者のいうこと
ですし、なにが「ホント」なのかはよくわかりません。
このことには諸説ありますが、
曇鸞以前の中国の誰かが「創作」したのでしょう。
ただ言えることは、
そもそも法然が「道綽、善導」の「観経」を
よりどころにしていて、ここを外す訳にはいかないのですが、
「観経」はまるまる「方便経」ですので、
「方便の阿弥陀仏」を受け入れる「信心」については、《詳細》です。
裏を返せば、もしこれが「道綽」の創作だとすると
「道綽」は「信心推し」ですから、「信行両座」という、
ほぼ「覚如」創作の「御伝鈔」の中で、
法然が「信の座」についたということは、
これが覚如の創作としても、
法然さん的には「正解」なのかもしれません。
とにかく「道綽」は、観経をよりどころにして、
「聖道門と浄土門」を明確に分類して
「三信三不信」を明確にしたということがポイントです。
ですから真宗学では「道綽」は、「聖道門、浄土門」を明確にしたとされます。
30/11/30[2–24]
「善導独明仏正意〜即証法性之常楽」
これは、「善導」の部分です。
「善導ただ一人仏の正意をあらわす」
と記述してあると、七高僧でも、「微妙に」ほかの高僧よりすぐれている。
お勤めでも「節がかわるし」なんて単純発想をしてはいけません。
お勤めのことはおいといて、
善導がその時代にあって、中国に浄土教を広め、
かつそれが、
「明確に多くを救う(さとらせる)方便だということを明らかにした」という、
「どんなものでもさとりへ至る方便」をあきらかにした。
ということです。
この時代の僧侶も「ほとんどが学者・修行者」で、「仏教を大衆化」したのが、善導だったからです。
当時の中国で「中観だの唯識だの華厳だの法華だの涅槃経だの」と《八宗》を中心に学んでいた僧侶からすれば、
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/八宗
「西方極楽世界」など、
なにをファンタジックなことをいってるんだ。
と中傷されてもあたりまえなのですが、
そんななかで「大衆仏教」として、
「阿弥陀仏と極楽浄土」の教えを、方便と知りつつ説いたのですから、この点で「善導独明」となるわけです。
そして、「観経」にあるように、三昧ができるという
「定善」のひとも、良いことができるという「散善」のひとも、
むちゃくちゃ悪い「逆悪」のひとも、
上から下まで「あわれみたまいて」、阿弥陀仏の光明と名号が因縁となって成仏する教えであることを明らかにしたのです。
そして大衆仏教として、「本願の智慧の海」を開いて、
多くの人を導き入れ、念仏行者を育成されました。
そこでこれらの行者は「観経」にある「教我思惟、教我正受」の文言の通り、「正受」して「金剛心を得た」のです。
そしてこのように、「正受」して、慶喜一念して
「阿弥陀仏と相応したひと」は、「韋提希さん」と同じようにさとりを表す「三忍(喜、悟、信)」を獲たといえるのです。
http://labo.wikidharma.org/index.php/三忍
そして、即「法性の常楽」を証明できたということを説明しています。
教行証文類では、
善導の「観経四帖疏」などから信心について、多く引用されています。
真宗学では「古今楷定」といって、阿弥陀仏の教えを改めて意義のあるものとした。
と言われています。
つぎの、源信から「日本」になります。
「源信広開一代教〜大悲無倦常照我」とあります。
そもそも源信は「日本に念仏を広める基礎を作ったと言いますが、
地獄極楽を対象させて、絵図をもって、「地獄は怖いぞ」という
布教の仕方で、
また「この世は穢土」だから、「浄土を欣求すべき」という
布教の仕方をしました。
方便もすぎるぐらいの方便で、「動物を畜生」と定義した布教をしました。
現代は「動物愛護やペットは家族」という人も増えて、そもそも人間の方がひどいという観点が増えたのですから、畜生は「愚痴(愚かさ)」に定義する方がよいと思われます。
「人間に生まれて良かった」という「人間自己満」の時代ではありません。
「人間に生まれたからこそ、煩悩に向き合って《煩悩即菩提》というさとりへの功徳を生きることが重要であると考える時代でしょう。」
ジェンダーの問題から「変成男子」を用いなくなったようなことです。
また、「畜生」本来の「畜されて生きる」人間のあり方も問われるべきでしょう。
お東の暁烏先生は、この観点から講義をされています。
ーーー(畜生)
https://true-buddhism.com/teachings/chikusho/
(このページは親鸞会のページだと思われますが、この部分は内容的にわかりやすいので使います)
(どうぞ怒らないで、かえって方法論の学習と、知らない方への啓蒙のためにご覧くださいませ❣️)
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/畜生
(これは情報量が少ないですね!)
http://www.wikidharma.org/index.php/ちくしょう
(ウィキダルマ、これも同じでしょう)
ーーー
そして、念仏に徹するなら「報土」にいけて、あれやこれやの行を
やっていると「化土」という「真の浄土にいけないぞ」と
受け取り方をまちがうと、さも脅かしているような「アメとムチの布教法」に思えます。
そしてどんな極悪人もただ念仏を唱えればいい。
そういうものを阿弥陀さんが哀れんでくださっているのだからという教えが意外とわかりやすいと評判になったのです。
そして、「そんなことをいわれてもわからない」
というひとは
「煩悩に眼がさえぎられて、見えないだけで、阿弥陀仏の大悲はあきらめることなく、常に私たちを照らしています。」と、
結果的に「大悲心を説かれた」のです。
真宗学では、源信は「報化二土」を明らかにしたとされます。
さて、
いよいよ親鸞の先生である「法然(源空)」です。
「本師源空明仏教〜必以信心為能入」
特にこの部分について多くを語る必要はないでしょう。
「この日本という片州の《悪世》に選択本願をひろめ」
「決以疑情為所止」や「必以信心為能入」というように、
この悪世の日本では「信心を以って本願に入らないと、また生死輪転の家にかえってしまうよ」と
源空の教えを「信心推し」で勧めています。
ここで「家」と「楽(みやこ)」と対象されているのは、「みやこ」は本来「宮拠」で、天皇のいるところを意味しています。
そういう意味で「みやこ」と読ませているなら、「阿弥陀法王」のいるところ、ということでしょうか。
また生死輪転の「家」に「還来」というのは、「かえってくる」ということですから、「元に戻りますよ」ということでしょう。
しかし、そんな訳の分からない「みやこ」よりも「家」の方がいいという現代人は多いでしょう。
結果「苦しみをくりかえすよ」という表現の方が、現代人には訴えやすいとは思います。
まぁこれが、現代人にファンタジックに聞こえなければ、「みやこ」の方が都会らしくていいというかも知れませんね。
また、ここで「生死輪転の家」は浄土論の「宅門、屋門」に対象しているようにも感じるのですが。
ここはあくまでもかなりな「私見」です。
☆「帰る」と「還る」について。
「帰る」は「本来そうあるべきところに到り着く」という「とつぐ」という意味があります。
「還る」は「元いたところに戻る」という意味です。
このことは、仏教においては、キチンと使い分けることが必要です。
このように、源空については、「念仏であるけれど信心がポイントである」ことを重ねていっています。
真宗学では「源空」は「選択本願」を明らかにしたとされます。
正信偈、最後の「弘経大士〜唯可信斯高僧説」
も有名ですから、多くを語ることはないと思います。
ただこの中に「道俗時衆共同心」とあって、「皆が同じ心で和合しましょう」と、勧められていることは重要だと思います。
なお、親鸞は教行証文類を自分の体験を含めて、方便念仏が実際に効果があるという、実証前提の論として展開されていることを
忘れてはなりません。
☆中国で「摩訶止観」を書いた、天台大師智顗は、これを書いたものの「実行しなかった」といわれています。
親鸞は実行実践の上で論じられていることが重要なのです。
ですから読んでいるわたし達も「実践」がなければ意味がありません。
つぎにいよいよ「信文類」に入ります。