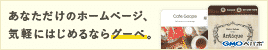私の知人の言葉に「論理を知らないで哲学をやろうとするのは、フランス語を知らないでフランス文学をやろうとするようなものだ」というのがある。これは名言ではないかと私は思う。フランス語を知っているということが、第一義的には、フランス語が使えるということであって、フランス語についての理論的知識をもっていることではないように、哲学をするために必要なことは、まずは、論理が使えるということであって、論理学の知識をもっているということではない。
ところで、私の知人にこう口走らせるきっかけを作ったのは、哲学系のある学会での発表を連続して聞いたことだったと覚えている。この学会は、論理学の専門家も所属する学会で、そこで発表するひとの多くは、それなりに、何らかの議論で、ある主張を支持したり批判したりしようとしていると見受けられる。そうした場所で、こうした言葉が引き出されたということは、皮肉なことである。しかし、他の学会でも、同様の感想を抱くしかないような発表はあるし、そもそもフランス文学がフランス語で書かれていることを知らないといったたぐいのものさえ、ないわけではない。というのは、「論理」と言っても、ひとは必ずしも論理のことを意味しているとは限らないと思い知らされるような場面に出会うこともあるからである。しかし、論理学という学問が存在することは、各人が「論理」で、好き勝手なことを意味してよいわけではないことを教えるはずである。
論理と無縁の哲学といったものがありうるような錯覚は、哲学についての誤解と、論理についての誤解の両方から来るのだろう。哲学は、世界や人生についての広い展望を与えることを目指すというのは、たしかに正しい。しかし、そうした展望は、それを理解する努力を惜しまなければだれにとっても理解可能であり、疑義を出したり、批判したりできる議論に基づいているのでなくては、哲学とはみなされない。哲学のなかには、ひとに大きな感銘を与えたり、視界が一挙に開けるような感覚を味わわせてくれるような言葉もあるかもしれない。そのような言葉の価値を否定する必要はない。ただ、哲学の観点からは、どのような議論が、あるいは、どのような思考の筋道が、そうした言葉を支えているかということを無視することはできない。
他方で、論理を使うというのは、何も特別なことではない。日常の場面でも、理由が問題になるときには決まって論理がはたらいていると考えてよい。何かが、別の何かが正しいとするための本当に良い理由になっているかを考えるとき、ひとは論理を使っている。たとえば、自分の家に帰ってきて、こどもの靴が玄関にあるのを見た私が「靴があるから、出かけていない」と言ったのに、妻が「サンダルで出かけたのかもしれないから、そうとも限らない」と言うとき、立派に論理がはたらいている。私の言ったことの背後には、「出かけるならば、靴を履いて行くだろうし、靴を履いて行くならば、靴は玄関に残らないだろう」という推論と、「だから、靴が玄関にないならば、出かけたのだろう」というもうひとつの推論がある。それに対して、「出かけるときに靴を履くとは限らない、サンダルを履いて行くこともある」と言う妻は、私の推論に対してその反例を出していると言ってよい。
こうした日常の推論を理解することは、むずかしいことではない。しかし、哲学では、一般的な仕方で物事を考えるから、話がいきおい抽象的になりがちである。したがって、そこでは、何が何の理由として挙げられているのかが、すぐにわからなかったり、反例となるような具体的な事例を考え出すことに困難を感じることもあるかもしれない。こうしたとき、推論の正しいパターンというものを知っているならば、それにあてはめてみるということは役に立つし、また、ある結論を出すためにどんな前提を置き、そこからどのように進むべきかについての知識があれば、それも大きな助けになる。先にも言ったように、重要なのは、論理が使えることであって、論理学の知識をもっていることではない。それにもかかわらず、哲学において、論理学の知識が、不可欠ではないにしても、大きな助けになるのは、こうした事情による。
現在の哲学については、論理学の知識が必要となる、さらにもうひとつの理由がある。議論における明晰さの基準を与えるのは、論理学である。よって、論理学の発展に伴って、明晰さの基準も変化してきた。19世紀の終わりにおける論理学上の大きな変革の結果成立した現代の論理学は、そのテクニカルな外見のために、哲学のなかのごく特殊な分野にしか、かかわりをもたないかのように思われがちである。しかしながら、それはまちがいである。過去100年にわたる哲学のうちの重要な部分、また、現在主に英語圏を中心に国際的な規模で展開されている哲学の大部分は、意識的にせよ、あるいは、無意識的にせよ、現代の論理学を、議論の明晰さの基準に取っている。そう考えるならば、現代の論理学をある程度知っていることが、現在の哲学を理解するのに大きく役に立つことが納得できよう。
本書は、そのタイトル『論理と哲学の世界』が示すように、哲学の現在の営みにおいて、現代の論理学がどのようにはたらいているかを教えてくれる、哲学への入門書である。40年近く昔に出版されたものでありながら、その内容は少しも古くなっていない。ここでは、現在標準とされている論理的枠組みが過不足なく紹介されているだけでなく、さらに進んで、一方で不完全性定理に至るメタ数学、他方でコウエンの結果や巨大基数に至る集合論といった、「入門書でそこまで?」と思わせる事柄まで扱われている。もちろん、著者も断っているように、標準であるということは、唯一であるということではない。論理学は、哲学的に中立な道具なのではなく、現代の論理学も、いくつかの哲学的前提に基づいている。その前提を問題にしようとすれば問題にできるし、実際、問題にされてきた。しかしながら、現在でも、ここで紹介されている枠組みが標準的なものであることに変わりはないし、何事においても、まずは何が標準であるかを知っていることは大事なことである。
19世紀以来の論理学の発展に促されて生じた哲学のあり方は、現在では「分析哲学」という名称のもとに包摂されているが、それを単に紹介するのではなく、自身の責任で展開するということが行われ、その成果が一般の読者の眼にも触れるようになったのは、わが国では、1960年代のことである。まず、市井三郎の『哲学的分析』(1963年)と沢田允茂の『現代における哲学と論理』(1964年)が、「分析」と「論理」というキーワードを印象づけた。さらに、哲学者だけでなく、さまざまな分野の科学者も参加して作られた、全3巻から成る『科学時代の哲学』(1964年)は、哲学が孤立した個人による営みではなく、哲学以外の分野の研究者も加わった議論を通じてなされるべき共同作業でありうることを示した。
こうした傾向の哲学は、それが出てきた当時は「哲学ではない」などと言われたりもしたが、1970年代に入ってからも、着々と成果を生み出した。たとえば、現在に至るまで読み継がれている、黒田亘の『経験と言語』(1975年)や大森荘蔵の『物と心』(1976年)などは、そうした成果の一部である。そして、「入門書」でありながら、著者独自の体系的な哲学が展開されている本書もまた、そうである。本書がカバーする論理の範囲がきわめて広いことを先に述べたが、それがカバーする哲学的問題の範囲の広さにも驚くべきものがある。
分析哲学についてもたれているイメージのなかには、それが、論理や言語といった「専門的な」領域のなかで、ごく特殊な話題を取り上げて、こまごまと論じる種類の活動だというものがある。こうしたイメージは、専門化が進行している現在の分析哲学の状況のなかでは、あたっているところもないわけではない。しかし、他方で、分析哲学が論理や言語といった領域に属する事柄しか取り上げないということは正しくない。「分析哲学」が「哲学」の別名でもありうることは、本書の第一章をみるだけでわかる。そこでは、形而上学と認識論から、倫理や神や美の問題に至るまでが、哲学のさまざまな問題群のなかでどのような位置をもつかが説明されている。そして、広い意味での論理学を紹介したあとで、そうした問題のすべてが論理学の観点から考察されている。論理学への入門でありながら、哲学全般への入門書である本書のような書物は、他に類をみない。
また、いま本書を読み返して改めて強く感じるのは、その文体の新鮮さである。日本語の哲学用語の多くは、明治から大正にかけて作られたのだろうが、哲学の言葉として使うのに不自由しないだけの日本語が作られたのは、一般に考えられているよりもずっと遅く、第2次大戦後、1960年代のことではないかと私は考えている。そして、この日本語を作るのに大きく貢献したのは、本書の著者を含む、先に名前を挙げたひとたちである。私と同じ世代の哲学者は多かれ少なかれ、このひとたちから、文体も含めて、哲学のスタイルを習ったのである。
本書が最初1977年に新潮選書の1冊として刊行された際、小松左京氏が推薦の文を寄せている。その最初にはこうある。
19世紀後半から、20世紀の前半にかけて、論理学の分野で、主として「数学の基礎」との結びつきにおいて起った発展は、真に驚くべきものがあり、その社会的結果の一端は、コンピューターでもって、「論理」が「演算」できるという形で、すでに私たちは享受しているのだが、一方で、この分野の発展が、少なくとも日本の高等教育を受けた人々の教養と常識にならなかった、という点も驚くべき事である。
40年後の現在、状況は改善されていると思いたいのは山々だが、ひょっとすると期待されたほどには改善されていないのかもしれない。最初に引いた私の知人の言葉は、こうした危惧に根拠があることを示している。本書の使命はまだまだ終わっていない。