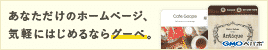インフォメーション(日々更新中)
2022-07-04 07:19:00
五念門と五果門(復習)‼️
156ページから。
「五念門」というのは、浄土論にある、「礼拝、讃嘆、作願、観察、回向発願」のことで、これらに対象する「果」を「五果門」といい「近門、大会衆門、宅門、屋門、薗林遊戯地門」をいいます。
これらを法蔵菩薩を含めた「菩薩の行」として、「浄土論註」によって説明記述されます。
156ページからこの「五念門」を詳しく説明されます。
まず、
「無碍光如来を念じて安楽に生ぜんと願ず」と
ここでの名号は「帰命尽十方無碍光如来」であり、
「帰命」は礼拝門で「尽十方無碍光如来」は讃嘆門と定義されます。
ここから「礼拝」について説明されます。
156ページの9行目に、一般的に「礼拝」といっても「恭敬」もあって、必ずしも「帰命」ではない。
しかしここの礼拝は「帰命」であるといわれます。
ここに「彼此あひ成ず」とあるように、仏とわたしがひとつになることであると帰命礼は「五体投地」のように、自らを放棄して投げ出すことであると、礼拝は「無我」と同じであると記述されます。
そして、「尽十方無碍光如来」を浄土論の偈文の後の論説(長行じょうごう)から、「讃嘆門」だと定義して、まず「称名」について(詳説)される中で、(称の字は《軽重を知る》《秤と同じ》として、「唱」との違いを明確にされています。)
ですから真宗の《しょうみょう》は[称名]と書くのです。
157ページに「光明智相」のごとく、かの「名義」のごとく、「実」のごとく、修行し相応せんと欲うがゆえに、
とあり、ここにある「名義」を「南无阿弥陀仏のいわれ」と解説されることも多いのです。
しかし、教行証文類において、この段階では、名号は「帰命尽十方無碍光如来」ですので、光明智相、名義、実を通して讃嘆門と定義されるのは、「大経の十二光」なかでも「無碍光」であるとするのが適切です。
ですから3行目に「尽十方無碍光如来」とのたまへり。
と記述され、「如来の光明智相の如く」讃嘆する。
と定義されます。
この「光明智相」こそ、さとりの智慧を光明で表されている【重要】な文言です。
そして「願生安楽国」を「作願門」として、天親菩薩の「帰命」の意であると抑えられていることも【重要】です。
「願生」が「如来の願を受けてわたしの願」となる意が内在されるからです。
【この次に重要な問答があります】
《親鸞が「浄土教は仏教であるという論拠」を記述されているからです》
157ページの中ほどに「問うていわく」とあり、仏教経典のさまざまなところに「衆生畢竟無生にして虚空のごとし」という、根本仏教も中観派も、その他すべて仏教は「無我、空、真如無分別」を説いているのに、「生まれるという表現はおかしいのではないか」という問いがあります。
この答えとして、「衆生畢竟無生にして虚空のごとし」と説かれているのに、「2通りある」として、
1つ目に「凡夫が、衆生(存在)を実存と思うように、凡夫が生死があると錯覚している観点からの《生まれる》ということである、しかしこれは亀に藻がついているのを亀毛といっているような、「所有なけん」つまり「あるはずのない間違った見方」であるといわれています。
ですから、このような見方は「亀毛のようであり、虚空のようなもの」であると定義され、ここでいう「願生」の「往生」は、「凡夫のいう《生まれる》」ではないと明言されます。
2つ目には、「諸法」は「因縁生」であるから、生まれるとか生まれないということではなく、「不生」であって、「あらゆることは無いというのは、虚空と同じである」と記述されます。
だから、天親菩薩の「願生」は、「因縁生」の意味でいわれていて、仮に「生まれる」と名づけているのであり、一つ目の凡夫がいう「生まれる」とは違うと明確にされています。
そしてつぎの問答で、「じゃあなぜ往生というのか」と問いを立てられます。
答えとして、
実存しない「仮の名で存在としている《仮名人》」であるわれわれが五念門を修行すると、
修行する前念と後念で変化するので、
煩悩界を生きていた「仮名人」が
浄土を生きる「仮名人」になった
という因果において一つ(同じ)であるというポイントを明確にするため「往生」という文言を使っているのであり、「行」が一つの流れで相続されることを明確にするためであると明言されます。
(ポイント)
この部分の原典(158ページの2行から3行目)に、「前念と後念と因となる」とありますが、脚注にもあるように、本来なら「前念は後念のために因となる」と読むべきなのになぜ、「前後ともに因」にされているのか。
ここに縁信心が、因信心になって「因果同時である」ということをあらわしてあると推論できます。
つまり、【親鸞の読み方は、往生は現世とか来世というものではない】という、重要ポイントがあるのです。
このような、親鸞の独特な読み方に内在される【重要ポイント】を「無視して」さらっと流しては重要な内容が抜けて「ありきたりな浄土教」になってしまいます。
30/11/03[2–5]
《浄土教が仏教である根拠》
158ページの6行目に、第一行の三念門を釈しおわったと区切られて、次の文言に入られます。
ここに「我依修多羅、。。。」と浄土論の偈文「世尊我一心、帰命尽十方無碍光如来、願生安楽国」について根拠を述べられます。
この根拠を「修多羅」によると記述されます。
これは「経典をよりどころ」にするということですが、
仏教の教えは「経典」などを「十二部経」といわれる分類に仕分けていますが、
その最も重要な「修多羅」によるとしています。
しかも、その修多羅のなかでも「四阿含」という、いわゆる「小乗の経典」やその他の『経、律、論の三蔵』までも差し置いて、「三蔵(経、律、論)」に該当しない「大乗の経典」であるというところまで絞っています。
その理由が、このあとの《真実功徳相》の記述になります。
158ページの終わりあたりから、この説明になります。
まず「功徳に2種類ある」という論調で、何度も出てくる「《凡夫》と《さとり》の2種について」功徳を解説しています。
凡夫の功徳は「顚倒(転倒)し、虚偽(うそいつわり)」であるから「不実功徳」である。
そして、菩薩の功徳は、「智慧清浄の業より。。仏事を荘厳す」として
「法性によりて清浄の相に入れり」とあり、
これがなぜ「顚倒(転倒)せずに虚偽(うそいつわりでもない」のかというポイントを
「二諦」によって、究極の結果として衆生を「浄」にいれるからであると解明しています。
ここの「二諦」については「法性(真諦)と言説(俗諦)」という前提で、
脚注のように「浄土の荘厳」というイメージは、衆生のイメージにあわせて「真如に導く方便」として「さとりの智慧を内在させて荘厳されたもの」だから、衆生が真如法性の真諦を体得するための《適切な言説によるイメージ》であるから、つまりは俗諦(方便)である
と、わかりやすく【浄土教が仏教である理由】を定義されています。
これは、「唯識派」の天親菩薩が、中観はもちろんのこと、さらに認識論から浄土を論じていることが明確になっているポイントでもあります。
現実の中で、浄土の荘厳を経典にあるように認識できるようになるための行が「五念門行」であるということです。
これが「唯識論」による【観察門】であるといっているのです。
これを石泉学系では「現実の中に浄土が現映する」などと表現されて、現生と死後を分断しない「一如」に相応した「仏教としての浄土教」を解明しています。
このように、159ページの中ほどに至って、なぜ「浄土教」が「仏教」と相応するかという課題を解析して、解明されている重要な部分です。
《十二部経》
https://r.goope.jp/sainenji/free/hodoku
30/11/04[2–6]
159ページの中ごろに至って五念門中の四門まで解説されました。
そして、「いかんが回向する」から第五回向門の解釈です。
ここに「苦悩の衆生を捨てず〜回向を首として大悲心を成就することを得たまへるがゆえ」
と記述されたうえで、わたしたち衆生に「大悲心をもって与えるのは往相還相の回向」であるという大悲の内容を「さとりへのベクトル」であると定義しています。
そのうえでなおかつ、「作願して《ともに》阿弥陀如来の安楽浄土に往生せしめたまへるなり」と、《ともに》さとりに向かう[往生]という方向へ進むという状態が「回向(発願)」であると明確にされています。
ここでよく使われる「回向を首としたまひて、大悲心をば成就せり」という和讃の定義が、法蔵菩薩とともに「さとりに向かう」ということであると定義されていることを見逃してはいけません。
30/11/05[2–7]
150ページの【20】からは道綽の安楽集の引用ですが、これはここまでの論拠のうえから、ほぼ「念仏を勧める」譬え話ですので、さらっと飛ばします。
ここでいう「念仏三昧」は「五念門、五果門」の集約とみてよいでしょう。
わたしはあくまでもこの時点での念仏三昧は「帰命尽十方無碍光如来」と見ますが、
「南无阿弥陀仏」が一般的でしょう。
そもそもここの安楽集の出だしが、「観仏三昧経」の引用ですから、
そういう点では「南无阿弥陀仏」の方が適しているのでしょうが、
演繹的推論では、ここも「帰命尽十方無碍光如来」で抑える方がスムーズですし、
いきなり「阿弥陀仏」にチェンジする必要もありません。
いずれにせよ、この引用で注目すべきポイントは【21】に現在の障を除いて〜念仏三昧を行ずれば、「現在、過去、未来の一切諸障を問ふことなくみなのぞくなり」の部分にも、仏教の時間論にまつわる記述があることです。
つまり、「現在の障(煩悩など)がさとりへと転じると、過去法も未来法も変化する」という内容です。
これを具体的にいえば、「現在の現実を念仏三昧によって観察」していると今までと「現実の解釈定義」が変わります。
わたしたちは、念仏三昧を生きるまでは、「むさぼり、怒り、愚痴」などの煩悩によって現実をみて、俗にどっぷり浸かっています。
すると、いろいろな物事が「障りや苦」だと思ってしまいます。
しかし、そんなわたしが「念仏三昧に生きる」と同じ現実が「浄土に見えてくる」のです。
もっと具体的に言えば「色々な出来事から自分の煩悩の愚かさを知らされて、そういう現実がさとりへの糧だ」と思えるようになるわけです。
そして「悔いていた過去やこれから訪れる未来の出来事も同じようにさとりへの糧だ」と思えるようになるので、「現在、過去、未来の一切の諸障が除かれる」という状態になるという念仏三昧による具体的な状態を明らかに表現しています。
【22】には「たとひ大千世界に〜。」など、よく使われる文言が出ています。
【23】には「無量寿仏国往き易くとり易いのに、外道に迷ってつかえてしまう」と外道に迷うことへの警告をされています。
次に、善導の引用に移ります。
2022-07-02 08:20:00
罪は深いか?
浄土の教えでよく言われる「罪業深重」ということについて、なぜ仏教でそんな表現がされるのかといえば、そもそもこの言葉が、善導という中国の僧侶の書物に由来していて、
その僧侶が大切にしていた「観無量寿経」が、中国で「キリスト教ネストリウス派(景教)」の影響を受けて作られたと思われるということが、まず第一にあります。
そして、第二には、「なんでこんなに苦しまなきゃいけないんですか?」という、論理のわからない、抽象論もわからない、文字も書けない読めない人たちに、「あなたは前世から罪をたくさん作ってきたからなんですよ」と納得させて、
その事例として「韋堤希(いだいけ)」っていう罪人の救いについての物語を教えて、そこに「南無阿弥陀仏」をとなえたら来世は極楽にいけるって教えられていますよ!
と納得させる教えにおいて「罪業重深」という前提が必要だったのでしょう。
しかし初期仏教における「罪」は「戒律を破ること」ですから、何でもかんでも「罪」ではなかったはずなのです。
そこで、平安時代というコンピュータもない、論理的な学問もかなり少ない時代に、このストーリーに意味があったのでしょう。
しかし、親鸞さんは、論理的かつ精神的なポイントを重視するひとだったので、このストーリーを単純には受け入れられなかったのでしょう。
そこで、善導さん以前の、曇鸞さんという僧侶が書いた「浄土論註」という理論書によって、阿弥陀如来というよりも、無碍光如来という観点で、この教えを解釈されたといえます。
それが教行証文類なのですが、これとて、のちの僧侶は、今に至るまで、「信文類」ばかりを重視して、引文をただの「証拠書類」のようにあつかっているために、本来の親鸞さんの理解は広まっていないといえます。
たとえば、親鸞会さんという宗教もありますが、結局「本願寺」と同じで内容は、親鸞さんの血統にあたる蓮如さんの教えになっているのです。
これがまた、善導さんに戻っているのです。
だから、現代人に、浄土の教えがわからないのです。
親鸞さんはいち早く、現代のような時代を迎えることを予測していたのか、現代でも理解できる論を教行証文類に書かれているんです。
まぁ基本的に、前世らしきものからの「罪業深重」ということは、およそ仏教ではないと言えるでしょう。
2022-07-02 07:22:00
ホントの仏教をみなわかっているか?
仏教というのは、元来「人間の根本的な苦」を解決するために、「悟る」ことを目指す教えなんです。
まぁこんなことは仏教を知ってる人にすれば「当然」だと言えるんでしょう。
ただ、ここで問題なのは、お釈迦さんの出家の動機です。
お釈迦さんは、なんの不自由もなく、「快楽は好き放題」という王子だった時に、人間の「老病死」を垣間見て、「快楽の虚しさ」や生きることの悲しさに心打たれたということなんでしょう。
また、鳥が虫を啄む(ついばむ)ところをみて、「生類は互いに喰みあっている」ということに心を痛めたとも言われています。
こういう点から、そもそもお釈迦さんは、快楽にも贅沢にも満足できない「精神的なポイントを重視するひと」だったのでしょう。
しかし、普通の人間は、こういうことを「当たり前」だとして、「安心安全、命の保障」を求め、さらに「快楽」をも求めている「肉体的ポイントを重視するひと」だと言えるでしょう。
そして、お釈迦さんはそのような人間を「ダメなひと」「罪びと」とはいっていないのです。
単純に「悟ったら」この現世の肉体に意味がないことを知って、「滅度」に入ろうとするということだったんです。
なので、お釈迦さんは「悟った時」に、そのまま涅槃(炎が消える)に入ろうとされたのでしょう。
しかし、5人の修行者に請われて教えを説くようになられ、教化が始まったんです。(初転法輪)
けれど、初期仏教というのは、あくまでも苦悩の解決であり、精神世界の問題への示唆であり、いのちが尊いとか、死んだらどうなるとかいうようなことは説かれていないというよりも、そんなことは「戯論」だ、わからないことを論じることは無意味だとまでいっておられます。
そういうポイントからいうと、初期仏教は、極めて明確な論理だったといえます。
「信じる信じない」というような性質の教えではありません。
当然の「苦悩と苦悩からの解放の論理」だからです。
こういった「苦の解決」と「その方法」という明確な仏教が、大乗仏教になって、「阿弥陀仏」「観音菩薩」「薬師如来」「お不動さん」だのといった、「神的な存在が説かれる」ようになって、現代人には意味不明な教えになってしまったのです。
文字を知らない書けない、抽象概念がわからない、例えば、引力の法則がわからないから、「引っ張る仏様」がいる、といった偶像を設定しなくてはいけなくなったのでしょう。
「引っ張る仏様」はここで私が創作したのですが、こういう創作が多くなされたため、その時代の苦悩に応じた偶像仏や菩薩が生み出されたのでしょう。
しかし、もはや現代において「偶像仏」は必要ないというよりも、「それがあるからわからない」となっているのです。
そして、宗派のセクトにこだわって、ムリクリ説明をしようとするので、余計に意味不明になっているのです。
その点、バイブルは事実が書かれていて、「苦の解決」や「いのちは尊い」といったことが書かれてあるのではありません。
そういう点で、現代の「量子物理学」をも超えた存在や精神的なポイントが説かれているのですから、学べば学ぶほど、その真実に驚きを禁じ得ないのです。
2022-07-01 04:50:00
アーメン‼️
アーメンは、基本的に「その通り」と言う意味だというのは、どこを調べても出てくる内容です。
つまり「神の言葉の通り」という意味が大前提です。
また、祈りの言葉を発した人に「同意する意味のその通り」ということもあるんです。
ただ、伝統的に「アーメン」は、言葉の節目に唱えたり、いつ唱えると決まったものではないと言われます。
そこで、これを「祈った、その通りになるように…」と祈りの成就を願う言葉というのは、微妙に悩ましいんです。
祈った人への同意をもって「アーメン(その通り)」というニュアンスがあって、その延長上に、「その通りになったらいいね」という、このニュアンスもなくはないということですが…
その祈りが、全く祈っている人の「自我丸出しだったり、それはあかんやろ」っていうような場合には、「その通りになってもらっては困る」ということになりますから、全ての祈りに「その通りになるように」とは言い難いと思うんです。
とはいえ、その人の祈りへの同意の意味であるかどうかに関わらず、「アーメン」は使えるんです。
あくまでも、イエスキリストをアーメン(その通り)と受け入れている人間の命は、「神の言葉や教えを伝道するために…健康でありますように!」といった祈りはしても、「自我を自分勝手に元気で生きたいから健康を祈る」というようなことは、その通りではないはずなのです。
とはいえど、その人が、「自我で祈ったことを、その通りと同意すること」で、主(神)と聖霊の力で、その人の生き方が修正されたり、そもそも、その人がそう祈っている理由を理解することができたりすることもあるのですから、あながち「目一杯わがままな自我の祈り」を「その通り」と同意することは間違いではないのでしょう。
主の祈りの深さが感じられる「アーメン」です。